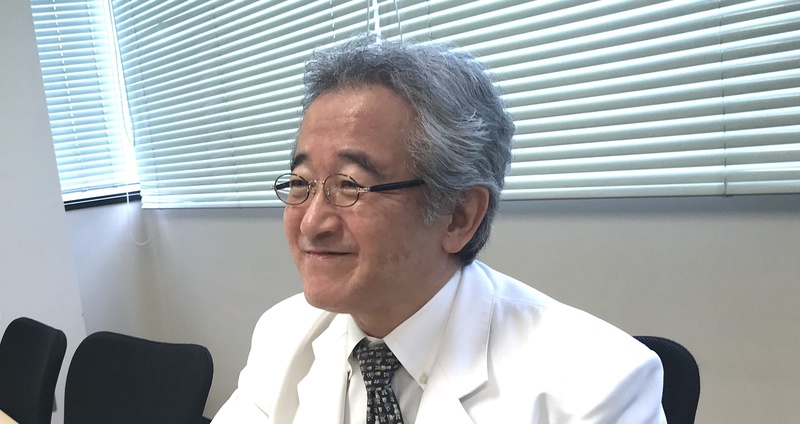佐賀県鹿島市で100年以上に渡り地域を支えてきた社会医療法人 祐愛会織田病院は、地域の救急医療を中心として、急性期医療を担ってきました。一般病棟111床と規模は大きくありませんが、稼働率は100%に近い水準で推移しています。また、地域密着型病院として貢献できるよう、2004年より開放型病床としてベッドの一部を地域のクリニックに開放しています。超高齢社会に突入し、後期高齢者の人口が急増するなか、時代の変化に応じ織田病院のあり方も変わってきています。祐愛会理事長の織田正道先生にお話を伺いました。
85歳以上が急増する地域で病院の役割とは何か
当院の医療圏である佐賀県南部は3市4町からなり、人口約16万人、高齢化率は約30%、75歳以上が約16.5%です。この10年で後期高齢者の中でも85歳以上人口が急激に増えています。当院の一般病棟は111床ですが、2016年には年間3,200人を超える新規入院患者さんを受け入れました。しかし、人口構成に並行し新規入院患者のおよそ3割が85歳以上の高齢者が占めるようになりました。
病院が在宅支援に力を入れる

10年程前までは、75才前後の患者さんが多かったのですが、この頃は要介護の患者さんは全体の1割にも満たず、パートナーも健在ですので、比較的家に帰りやすい(退院しやすい)状況でした。しかし、85歳以上になりますと認知症や運動機能障害を併せ持つ患者さんが多くなり要介護率が急激に上がります。また、パートナーもご高齢で治療が終わったからといって簡単には家に帰すことができません。超高齢社会がさらに進展する時代にあってこのような問題は当地方だけではなく全国的な問題として捉えなくてはなりません。
厚生労働省が発表した2017年1月の中央社会保険医療協議会総会での統計資料でも、全国で在宅医療を受けている人口は2008年約13万人、2015年約42万人であり、この7年間で在宅医療を受けるようになった患者さんが約29万人も増えているのです。この数字は今後も増え続けることが予想されます。
自宅で過ごしてもらうためには、院内の仕組みづくりから始める必要がある
どれだけ一生懸命病気の治療をしても、生活の場へ帰れなければよい医療の質が向上したとはいえません。つまり、病気を治すことと、生活の場に戻ってもらうことは同じぐらい重要になっています。そこで、入院から退院、さらに在宅での安心した生活に戻られるまでを3つの支援に分けて取り組みました。
退院準備から在宅ケアまで橋渡しするリエゾンナース
患者さんが入院し退院するまでには医師、病棟の看護師、薬剤師、リハビリ担当スタッフなどさまざまな専門職が関わります。退院時にはケアマネージャーや訪問看護師など地域とつながる専門職が関わります。しかし従来の業務の流れは、各専門職が専門分野でのみ患者さんに関わり、入院から退院、さらに退院後のケアまで継続的な関わりをもつ機能がありませんでした。
そこで病棟の看護師とは別に、退院準備から在宅ケアを結ぶ支援(リエゾンシステム)を行う専属の看護師を配置しました。この看護師のことを当院ではリエゾンナースと呼んでいます。入院早期から在宅復帰支援が必要な患者さんをスクリーニングし、その患者さんにはリエゾンナースが中心となって院内の各専門職と連携して退院支援を進めます。そして医療や看護の視点で地域の診療所や介護、在宅支援部門と退院後必要なケアを継続するために調整を行い、橋渡しします。患者さんの情報がすべてこのリエゾンナースに集まることで、退院後の在宅ケアや地域との連携もスムーズに進むようになりました。
多職種協働のフラット型医療支援体制-多職種の総力戦で退院支援に臨む

さらに退院支援が円滑に進むようになったのは多職種協働のフラット型医療支援体制の構築です。これは、薬剤師、管理栄養士、セラピスト、メディカルソーシャルワーカーなど多職種を各病棟に専従で配置し、医師や看護師だけではなく、多職種が常にステーションに集っている体制です。医師からの指示を待つのではなく、多職種全員が専門性を活かし積極的に患者さんに関わり、情報を共有します。
朝の申し送りから多職種協働で前日に入院した患者さんについて把握します。その結果、退院前の会議においても、すでに全員が患者さんのことを把握している状況となり、話がスムーズに進みます。在宅や介護支援を進めるとき、ケアマネージャーにとって医師が忙しく連携を取りにくいということが課題の一つでした。この支援体制構築後は多職種間で患者さんの情報が共有されているので、医師がいなくても薬のことはすぐに薬剤師に、リハビリに関することは理学療法士にきけるというように連携が円滑に進むようになりました。
認知症患者さんの環境を整える

4年前までは点滴を抜いたり、転倒したりするなど目が離せない認知症の患者さんはスタッフステーションに連れてきて見守っていました。それは、不穏な行動などにすぐに対応するためでしたが、スタッフの出入りが多く動き回るため、患者さんにとっては不安であり、けしてよい環境とはいえませんでした。そこで認知症の患者さんにとって、環境を整えることが大切であるという視点から、2014年よりDCU(ディメンティアケアユニット)を開設しました。病床8床を完全ユニット化、ユマニチュード(ケアの技法)を導入し、スタッフの認知症への理解やケアの向上に努めました。特にこのケアチームは認知症の認定看護師を中心に、多職種で編成しています。この効果はとても大きく表れました。利用者は精神的に落ち着き、穏やかな時間が増え、睡眠・覚醒リズムが整いやすくなり、目が離せない患者さんもDCUに集めることで効率よく見守れるようになりました。
退院後のケアを継続するMBC(メディカルベースキャンプ)

地域の先生方が在宅医療を行うとき、緊急時の対応が一番大変です。特に高齢者は退院直後に悪化することが多く、これをクリアしないと在宅医療に踏み込めません。そこで退院直後から在宅医療を支援するMBC(メディカルベースキャンプ)を立ち上げました。スタッフは現在約30名、医師、訪問看護師、訪問リハ、ケアマネージャー、ヘルパーなど多職種です。情報共有をスムーズにするため、部屋の壁をなくして全員が顔の見える位置で仕事をしています。退院直後2週間はこのスタッフで在宅医療を行います。原則的に2週間が過ぎ、症状が安定していると判断した段階で地域の先生にバトンタッチする仕組みにしています。
今後はIoT、AIを使って24時間見守り体制へ
今後も需要が増え続ける在宅医療ですから、スタッフも人海戦術では足りなくなります。そこでIoT、AIを活用できるのではないかと考えています。この取り組みは現在実証実験中ですが、タブレットを使っての声かけ機能、スマートウォッチを使ってのナースコール機能やバイタルデータ収集。さらには、AIカメラを使って在宅での転倒転落検知などさまざまです。ことに在宅はプライバシーの問題がありますので、人が見るのではなくAIが探知して、おかしいと判断した場合はこちらがアラートを鳴らす。事前にご家族の承諾を得ている場合のみ、カメラが作動しこちらに状況を確認できる仕組みになっています。このIoTやAIを活用した在宅支援の取り組みは、新たな在宅医療ということでさまざまなメディアでも取り上げていただいています。
「住み慣れた地域で自分らしく最後まで」を支える
認知症になっても安心して退院しその後も在宅で暮らすために、鹿島市を7つのゾーンに分け、すべてに認知症デイサービスを作りました。このデイサービスはすべて幹線道路沿いにあり、家で何かあったときはすぐここに相談できるようにしています。
また、当グループは地域で暮らし続ける仕組みとして、1997年より鹿島市内約8000坪の敷地に「ゆうあいビレッジ」を開設し整備を進めてきました。このビレッジには小規模多機能ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、デイサービス、訪問看護、訪問介護、通所リハビリセンターなどがあり、さまざまなステージ(状態)に対応したサービスメニューがそろっています。「住み慣れた地域で自分らしく最後まで」をサポートすることが目的です。
織田正道先生からのメッセージ
これまで情勢や地域環境にあわせてさまざまな施設をつくってきましたが、85歳以上が急増し、認知症の方も増えるなか、施設だけでは限度があります。そこで当院は病院の役割を見直し、在宅支援を充実させる方向にモデルチェンジしました。治療と並行して退院支援を多職種で進め、退院直後はMBC(メディカルベースキャンプ)で在宅医療を支援し、それから地域へ返す。今後MBC(メディカルベースキャンプ)が医療と介護を結ぶ大きな役割を担っていくものと思います。そして将来的には、このMBCが病院の行なう在宅医療の全国モデルになれるよう学会や研究会で情報を発信していきたいと思います。
織田 正道 先生の所属医療機関