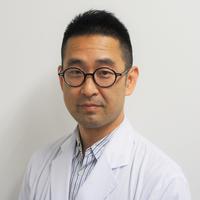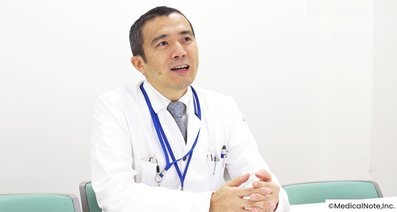
間質性肺炎は原因によっていくつかの種類に分けられますが、その大半は原因不明の特発性間質性肺炎と呼ばれるものが占めています。かつては有効な治療法がないとされていた病気ですが、その分類によって治療に対する反応性がそれぞれ異なることがわかってきました。国際医療福祉大学成田病院 副院長の津島健司先生に、間質性肺炎の全体像とその分類ごとの治療戦略についてうかがいました。
間質性肺炎とは-肺を支える間質に炎症や線維化が起こる病気
肺の組織を構成する「肺胞(はいほう)」というひとつの単位があります。これはブドウの房のようなイメージで、そのブドウの房のようなものひとつが小葉(しょうよう)などの呼び名で表されます。
その小葉などブドウの房同士の間を「間質(かんしつ)」といいます。間質性肺炎ではその部分が病変の主体となり、炎症と線維化が起こります。線維化とは、膠原線維と呼ばれるものができてくることで、そのために肺胞が膨らみにくくなり硬くなってしまいます。それが肺の実質まで進展してきて肺実質そのものをつぶし、肺組織の構築が変わってしまいます。

つまり、間質から始まった炎症が肺の実質に及び、胞隔炎(ほうかくえん)といって肺の中まで壊れていくため、最終的にその部分が膠原線維などで置き換わり、構造改築を来した状態です。その壊れた部分が修復されていくときにも、余計に膠原線維が出てきて過剰な修復が進行するため、間質性肺炎という病態ができるのだろうと考えられています。
間質性肺炎の原因-膠原病や喫煙などさまざまな原因があるが6割近くは原因不明
間質性肺炎の原因として以下が挙げられます。
- 膠原病
- 粉塵(アスベスト・羽毛・カビなど)
- 薬剤性(漢方薬・風邪薬・抗がん剤)
- 喫煙
- 原因不明(特発性間質性肺炎)
間質性肺炎の原因にはさまざまなものがありますが、ほとんどの原因はわかっていません。この原因が明らかでないものを特発性間質性肺炎といいます。最近では遺伝的な要因についても指摘されていますが、間質性肺炎全体の6割近くは原因不明であるとされています。
間質性肺炎という大きなくくりの中には、原因不明の特発性間質性肺炎もあれば、薬剤の影響や環境要因による曝露など、さまざまなものにさらされることによるびまん性の間質性肺疾患もあります。そういったものをひとつの大きなくくりとしてとらえ、間質性肺炎として考える必要があります。
特発性間質性肺炎の分類-それぞれのタイプによって治療に対する反応は異なる
間質性肺炎の中で原因がわからないものを特発性間質性肺炎(IIPs:Idiopathic interstitial pneumonias)といいます。特発性間質性肺炎はさらに次のように分類されます。
- 特発性肺線維症(IPF)
- 特発性非特異性間質性肺炎(特発性NSIP)
- 特発性器質化肺炎(COP)
- 剥離性間質性肺炎(DIP)
- 呼吸細気管支炎関連性間質性肺疾患(RB-ILD)
- 急性間質性肺炎(AIP)
我々のところへ紹介されてくる患者さんの中には、インターネットなどで調べて予後が悪い病気なのではないかと心配されている方も少なくありません。しかしそういった方々は、間質性肺炎という大きなくくりの中にもいろいろな種類があるということまでは理解しておられません。
私はまずその部分を誤解していただきたくないと考えています。特発性肺線維症(IPF)と呼ばれるタイプのものなのか、それともそれ以外の分類なのかということによって、治療に対する反応もまったく違いますので、そこはしっかりと分けて考えるべきです。

たとえば膠原病は治療が困難な病気ですが、その膠原病にともなう間質性肺炎の中にも、肺線維症のようなパターンになるのか、それとも非特異性の間質性肺炎のようなパターンになるのかという違いがあります。それだけでも治療反応性が大きく異なりますので、そういったものを混同しないようにしていただきたいと考えています。
間質性肺炎の症状-痰の絡まない咳や息切れなどが特徴的な所見のひとつ
間質性肺炎の患者さんにみられる咳(せき)は、痰がらみのない乾性咳嗽(かんせいがいそう)と呼ばれるもので、風邪をひいたときの痰(たん)が絡むような咳とは異なります。
間質性肺炎が進行した方の場合、肺が硬くなっているために思い切り息を吸ったときに肺がうまく膨らみません。そうすると肺のストレッチが原因で咳が誘発されます。そのような場合に出る咳はいわゆる空咳(からせき)、つまり乾性咳嗽(かんせいがいそう)という所見を呈します。
もうひとつの症状は息切れです。特に体を動かしたとき、たとえば階段を上ったときや駆け足をしたときなどに負荷がかかると息切れがします。また、動くと呼吸も荒くなるため咳が誘発されやすくなります。そういった一連の症状が間質性肺炎に特徴的な所見のひとつであるといえます。
間質性肺炎の検査と診断
間質性肺炎を診断するには、下記のような検査を行います。
- 問診
- 診察
- 血液検査(KL-6, SP-D:間質性肺炎マーカー)
- 胸部X線
- 胸部CT
- 気管支鏡検査
- 肺機能検査、6分歩行検査
- 外科的肺生検(クライオバイオプシー)
【問診】
「間質性肺炎の症状」でご説明したような咳(乾性咳嗽)と息切れの状態をみるために、問診では「咳がありますか」「動いた際に息切れが出ますか」「痰が出ますか」という3つの質問を必ずして、それがいつからどういった状況で出ているかということから間質性肺炎の有無を判断しています。また、その症状が悪くなっているかも問診します。
【診察】
開業医やかかりつけの一般内科などでは、間質性肺炎の最終的な細かい分類まで診断をつけることは難しいと思われますが、少なくともその患者さんが間質性肺炎かどうかということは、聴診(ちょうしん)で胸の音を聴くことによってある程度判断できます。聴診をすればその方の肺の状態に相当する呼吸音が聞こえます。一般的には、両側背部下側のあたりに聴くことができます。もちろん間質性肺炎であっても異常な音が聞こえない方もいらっしゃいますが、特に肺線維症の方の場合は特有の音が入ってくるため、それがまずひとつの所見となります。背中側の聴診音でバリバリ、パリパリという音がする際は、この病気が隠れている可能性があり、胸部X線よりも早く間質性肺炎を発見できるツールにもなります。
【血液検査】
まず血液検査のマーカーとしてはLDHという、ごく一般的な検査項目においても値の上昇がみられますし、KL-6、SP-D、SP-Aなども上がるとされています。KL-6、SP-D、SP-Aについてはすべて同時に検査することはできませんが、そのうちの2つまでであれば保険適用で検査ができますので、月1回程度はこれらの項目を確認し、その変動を把握しておくことが望ましいと考えます。
特にKL-6は間質性肺炎が存在することやその活動性などを示すマーカーになるといわれていますので、開業医の先生方も患者さんを紹介する際にKL-6を測定してくださることが多くなっています。
【胸部X線】
胸部X線写真では網状影(もうじょうえい・肺の間質が厚くなることによって見える網の目状の陰影)などの所見がみられます。
開業医の先生方が間質性肺炎を見つけるのはX線画像による場合が多いため、これも重要な所見です。また、間質性肺炎は特定疾患であるため、国から補助を受けるための認定手続きをすることがあります。その際にはX線画像で下肺野優位、つまり肺の下側とその外側がどうなっているか、あるいは肺が縮んでいるかどうかといったことを参考所見にしています。
【胸部CT】
最近では検診の際に胸部X線撮影だけでなくCT検診を受ける方も多くなっているため、X線撮影では判断が微妙な軽症例も見つけることができるようになってきています。実際のところ、我々専門医からみると経過観察でよいと判断するような段階の患者さんも見つかっています。さらに細かい分類まで確定して診断するためには、HRCT(high-resolution CT)という高い分解能を持つCT画像を作って判断するようにしています。定期的なフォローもこの胸部CTを施行しながら観察を行います。
【気管支鏡検査】
間質性肺炎の分類を決め、治療反応性をみるために、気管支鏡を用いて肺の中に150ccの生理食塩水を50ccずつにわけて3回入れ、その液を回収する気管支肺胞洗浄(BAL)という検査を行います。これは肺の一部から回収した液の中の細胞分画などを調べる検査です。
正常な場合は肺胞マクロファージがおよそ9割を占めています。肺胞マクロファージは細菌など外部からの異物を貪食(どんしょく)して免疫反応を起こすものですが、それ以外にたとえばリンパ球が増えている場合、あるいは好中球や好酸球が増えている場合など、それぞれの状況によって分類することができます。
この検査で得た情報によって、それぞれ治療法も異なってくるため、間質性肺炎の患者さんに対してはできるだけBALを受けていただくようにしています。ただし、それなりに侵襲のある検査ですので、施設によっては入院して行うこともあります。
BALと同様に気管支鏡を用いて行う検査としては、経気管支的肺生検(TBLB)というものがあります。これは米粒以下のごく小さな組織を採取してくる検査で、間質性肺炎かどうか、あるいは肺がんではないかどうかといった大まかな鑑別しかできないため、診断を確定するためには胸腔鏡下肺生検(VATS)と呼ばれる検査が必要になります。施設によっては、外科的生検をせずに気管支鏡検査の一環としてクライオバイオプシーを施行し、正確な病理診断を得ている施設もあります。
【外科的肺生検】
胸腔鏡下肺生検(VATS)は全身麻酔下で外科的に皮膚に小さな切開を行い、胸腔鏡と呼ばれるスコープを挿入して3cmほどの大きさの組織を採取します。採取した組織を病理医が診断するので、細かい分類を確定するには一番確実な検査です。
ただし、特発性肺線維症(IPF)に関しては、典型例では画像の所見だけでIPFであることが判断できるため、その場合にはVATSを行わなくてもよいと考えられています。

間質性肺炎の治療はいつ始めるか-線維化の進行に抑制をかける薬剤とは
我々は特発性肺線維症(IPF)の患者さんの状態が安定して動きがない場合には、治療は行いません。しかし病状がゆっくりと進行している場合には、6分歩行検査などの負荷をかけると重症度のステージが上がる、つまりより悪い状態になることがあります。
重症度のステージはIからIVまで4段階になっていますが、たとえばステージIIの患者さんが6分間歩行をしてSpO2と呼ばれる酸素飽和度が90%未満に下がった場合には、重症度のステージをIIIに上げることになっています。私はこのような重症度IIレベルの患者さんには治療を始めるべきであると考えます。
また、重症度Iの患者さんの中にも、6分間歩行で酸素飽和度の低下を認める患者さんがいるため、画像所見、臨床経過と併せて治療検討をすべきであるとも考えています。
このような患者さんに対しては、肺がだんだん硬くなって呼吸機能が低下していくことを抑制するために、さまざまな薬物治療が行われます。比較的高額なお薬もありますが、「軽症高額」に該当する患者さんが1年間のうち3か月、規定以上の高額な医療費を負担した月があった場合、その後は国から医療費の助成が受けられる制度があります。
薬物治療のポイント
間質性肺炎に対して薬物治療を行うポイントは、その背景にある疾患や間質性肺炎の状態によって変わってきます。たとえば膠原病であったり、画像所見で非特異的な間質性肺炎(NSIP)に分類されるようなもの、急性増悪を起こした場合や肺に線維化が起きている場合など、背景疾患や状態はさまざまです。
これらに対し、あらゆる薬剤を状況に合わせて導入し、症状およびQOL(生活の質)などの現状の改善、運動耐容能(体を動かした際の負荷に耐えるための呼吸や心臓などの機能)と身体活動性の向上、将来的な治療目標として病気の進行・再燃・急性増悪の抑制、併発症・合併症の予防・治療、さらには生命予後の改善を目指していこうという考え方へと変わりつつあるのです。
新たに誕生した疾患概念、進行性線維化を伴う間質性肺疾患とは
加えて、近年、進行性線維化を伴う間質性肺疾患(PF-ILD)という概念が出てきています。これは、さまざまな間質性肺炎のうち、肺に進行性の線維化が見られるものを指します。特発性肺線維症(IPF)はこの進行性の線維化を伴う代表的な疾患ですが、そのほか、特発性間質性肺炎や自己免疫性の間質性肺炎などでも進行性の線維化を伴う場合があります。
このような疾患に対しては、背景となる疾患の治療を適切に行ったうえで、線維化の抑制や患者さんの予後の改善を目的とした次なる治療へと移していく必要があります。そのためにも、疾患の経時的変化を追うことは重要です。
間質性肺炎は正しい診断と分類によってできることがまだまだある疾患
かつては有効な薬剤がなかったため、患者さんが低酸素の状態になったときに在宅酸素療法(HOT)を導入して、少しでもQOLを上げることぐらいしかできませんでした。実際に間質性肺炎には治療の手立てがないと思っている医師もたくさんいます。
しかし現在はそうではありません。病気の進行を遅らせる薬剤が使えるようになった今、正しい診断をつけて分類することによって、まだまだできることがある疾患であるということを皆さんに知っていただきたいと考えています。
関連記事
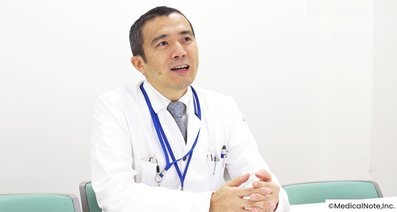

間質性肺炎の診断と治療―確かな診断と治療で治すことも可能

間質性肺炎は病名ではない!間質性肺炎の分類や原因
関連の医療相談が10件あります
騒音性難聴と耳鳴り
1年くらい前から耳鳴りがきになり耳鼻科を受診したら騒音性難聴とのことでした。その後テレビがついていたり雑音があると会話が聞き取りにくく、仕事中どうしてもなんかしら雑音があるため聞き取りにくく聞き返すことが増えてこまっています。時々耳抜きができないような詰まった感じがすることも増えました… 加味帰脾湯という薬を処方されましたが改善しません… ほかの病院を受診してみるべきですか? あと、耳の感じはとても説明しにくいです。症状を伝えるのになにかアドバイスあったらおしえてほしいです…
お腹の張り 脈をうつ
ふとお腹に手を当てるとへその左上が 少しかたく脈を打ってます 仰向けに寝るとかたいのは無くなるんですが 脈は少し感じられます かたいのをマッサージするように撫でると 無くなったり場所が変わったりするんですが これは何かの病気ですか? 心配性なので調べると腹部動脈瘤て出てきて とても不安です 病院に行きたいですが子供が濃厚接触者なので すぐには行けません その間に破裂しないか不安でたまりません 20代女子でも大動脈瘤になることありますか? ちなみにタバコは吸わないしお酒全く飲みません
三日前から、のどの痛み、せき
妻は現在抗がん剤治療中です。 三日前から37~38度の熱とのどの痛み、せきがあります。 市販の風邪薬を服用しても良いでしょうか?
肺に影あり
風邪気味だった為に、病院へ行って、レントゲンをとったら、肺に影あり。その場でCT検査実施。肺がんとの指摘受けた。レントゲンとCTで特定できるのでしょうか?。症状は特にありません。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「間質性肺疾患」を登録すると、新着の情報をお知らせします