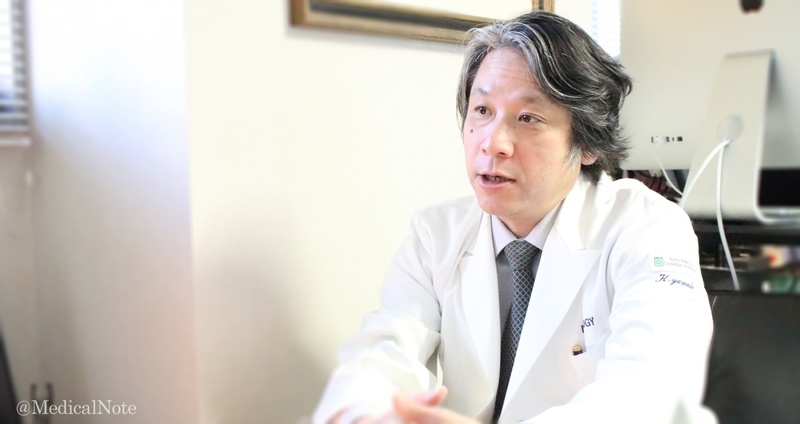CTやMRI、PETをはじめとする画像診断領域は今最も発展が著しい分野の一つといえます。画像診断の過去、現在、未来を展望していただきながら、脳疾患領域において画像診断がどれほど活用され、その中でも認知症についてどのような診断が可能になっているのかについて、京都府立医科大学放射線医学教室教授の山田惠先生にお話を伺いました。
画像診断の世界は日進月歩。CTから MRI 、核医学へ。
画像診断の歴史は、1895年にレントゲンがX線透視法を発明したことから始まります。その後、CT、MRI、核医学へと進歩を遂げ、現在、画像診断分野はすべての医学領域の中で今最も発展が著しい分野の一つといえるでしょう。
レントゲンがX線透視法及びX線撮影法を発明したのは今から120年前にさかのぼります。その後X線は胸部や腹部、骨などの異常を画像化する目的で普及していきました。1960年代にはX線CT(コンピュータ断層撮影法)の構想が確立され、人体を輪切りの横断像として見ることができるようになりました。
CTと同様に2次元画像を得る方法にMRI(磁気共鳴画像診断)があります。磁気共鳴現象を利用して体内の水素原子の量と分布を検査する方法で、1980年代以降に普及が進みました。現在はCT、MRIともに機器、ソフトウエア共に格段の進歩を遂げ、より広い範囲をより速く、より詳細に画像化できるようになっています。
核医学も画像診断の領域に含まれます。1980年代にPET(陽電子放出断層撮影法)装置が臨床で使われるようになり、普及していきました。病変の形状を見るCT、MRIと異なり、放射性同位元素の特性を利用して体内の細胞の機能や灌流状態を断層画像として捉えることができます。
現在は多くの疾患で画像診断が診療方針の決定に欠かせなくなっており、放射線科医は「ドクターオブドクター」と呼ばれることもあります。医療機器、解析ソフトの急速な進歩に加え、ゲノム解析結果と画像情報を組み合わせた手法の研究も進んでおり、画像診断学はすべての医学領域の中で今最も発展が著しい分野の一つといえるでしょう。
画像診断でできることは?
画像診断は体の外からでは見ることのできない体内の様子を可視化するもので、体を傷つけることなく臓器や血管、骨、細胞などの状態を調べることができます。
CT は短時間で広い範囲の検査ができるため、特に救急医療の現場での診断に適しているほか、MRIでは画像化の難しい骨や肺の評価にも適しています。一方、放射線を体に当てて検査するため、少なからず被ばくの危険性があります。あるイギリスの研究ではCTの撮影回数と脳腫瘍、白血病の発症頻度の相関性を示すデータが報告されています。放射線に対する感受性が高い小児や思春期の間は、検査の必要性をよく考えて適応決定をする必要があります。
一方でMRIは放射線の被ばくがないため、繰り返しが必要な検査に適しています。病変部と正常組織のコントラストが付きやすく、断面も横断像(輪切り)だけでなく冠状断像(頭頂部から考えた横切り)や矢状断面(頭頂部から考えた縦切り)など、様々な画像を得ることができます。CTとの比較では、検査できる範囲が狭い、検査に時間を要することが難点です。
PETは、形態でなく機能を見ることができる特性を生かし、病気のステージや治療効果判定、再発・転移診断などに有効です。
画像診断は進歩を遂げ、健康診断からがんの診断に至るまで一般的に使われる診断法となっています。近年は機器や薬剤の開発が進んで、より鮮明に細部を得られるようになり、病気の早期発見に役立てられています。一方で、疾患の特性や患者さんの状態により機器を使い分けたり、組み合わせたりする必要があり、どのような機器を使って画像診断を行うかの判断はより専門性が求められるようになっています。
当院では、画像診断は専ら集中読影室で行われます。広い読影室に17台の読影端末を設置してあり、トレーニング中の医師は、常に上級医の指導を受けることが可能となっており、この仕組みは各大学や関連病院からも高い評価を受けています。
*本記事は京都府立医科大学放射線医学教室教授の山田惠先生に取材させていただき、それに基づいて作成されました。掲載された内容についてはご確認いただいていますが、文責の所在はメディカルノート編集部とさせていただきます。
山田 惠 先生の所属医療機関