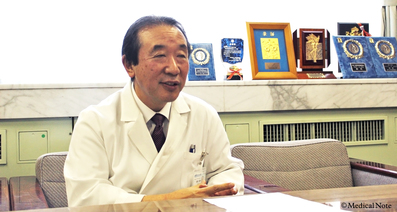HBs抗体
- 2019/08/16
- 更新しました
- 2019/08/14
- 掲載しました
目次
HBs抗体とは
HBs抗体とは、B型肝炎ウイルスの感染の有無を調べる検査項目のひとつです。
B型肝炎ウイルスの表面には、HBs抗原と呼ばれるタンパク質が存在しています。このHBs抗原に対して特異的に結合してB型肝炎ウイルスを攻撃するものがHBs抗体です。B型肝炎に感染すると体内ではHBs抗体がつくられるようになり、攻撃相手となるHBs抗原が消失すると消費量が減少するため、血液中に検出されるようになります。
一般的にはB型肝炎ウイルスに感染して5か月ほど経過すると検出されるようになると考えられています。このため、HBs抗体の検出は、B型肝炎ウイルスに感染した後治癒し、B型肝炎ウイルスに対する免疫があることを意味します。また、B型肝炎ウイルスにはワクチンが存在しますが、ワクチン接種後にもHBs抗体が検出されるようになります。
B型肝炎ウイルス感染の有無を調べる他の検査項目にはHBs抗原、HBe抗原、HBe抗体などさまざまなものがあります。それぞれB型肝炎ウイルスに感染後、どの時期に検出されるか異なっているため、感染が継続した状態か否かを判断する指標です。
検査が行われるタイミング
HBs抗体は、血液検査で肝機能障害が発見されたり、倦怠感や黄疸(肝臓や血液の異常で皮膚や粘膜が黄色くなること)など、肝機能障害が疑われる症状がみられるような場合に検査が行われます。
また、B型肝炎ウイルスのワクチンを接種したあとに抗体が形成されたか否かを調べるために、ワクチン接種後半年ほどの期間をおいて検査されることもあります。さらに近年では、医療従事者への感染や院内感染を防ぐため、入院時や手術時にC型肝炎ウイルスや梅毒、ヒト免疫不全ウイルスなどとともに感染の有無を調べる目的で広く検査が行われることが一般的です。
一方、治療が終了したあとにも、治療効果の判定や経過観察をする目的で検査されることもあります。
検査を受ける前のポイント
検査前に注意すること
HBs抗体は血液検査によって測定されます。検査結果は食事や服薬、運動などに影響を受けないため、検査前に注意すべきことは特にありません。
しかし、健康診断や人間ドックなどの一環として検査を行う場合は、血糖値や尿酸値など食事の影響を受けやすい検査項目も含まれている可能性があるため、早朝の空腹時に検査を受けることが望ましいと考えられます。
検査前の注意点については、検査を実施する機関の指示に従うようにしましょう。
検査前に心がけるとよいこと
検査では採血が行われるため、検査当日は腕が露出しやすく、袖にゆとりのある服装を心がけましょう。また、この検査を受ける方は肝機能の低下によって血小板数が減少し、血液が止まりにくい場合があるため、検査後はしっかりと止血を行いましょう。
検査にかかる時間と痛みの有無
検査に使用する血液は、一般的な静脈血採血によって採取されます。このため、検査自体は採血さえ滞りなく終了すれば、ごく短時間で終えることが可能です。
また、採血時は注射針を皮膚に刺すため、軽度な痛みは生じますが、注射針が抜去されて検査が終了すれば自然と治まるため、過度な心配は必要ありません。
検査を受けたあとのポイント
検査結果の見方
HBs抗体の基準値は10.0mIU/mL未満です。検査結果は数値ではなく、(-)・(+)や陽性・陰性で表記されることもあります。
もし異常が見つかったら
HBs抗体は、B型肝炎ウイルスに感染したあとに治癒した場合に検出されます。このため、HBs抗体が検出されても特に問題となることはありません。
しかし、感染が継続している場合もHBs抗原とともにHBs抗体も陽性となることがあります。B型肝炎ウイルスは、感染しても多くは治癒し、慢性化することはほとんどありません。しかし、なかには慢性肝炎に移行して肝硬変や肝臓がんを引き起こすケースもあるため、感染が継続している場合は適切な治療を行う必要があります。
このため、HBs抗体が陽性の場合には、現在も感染が続いているのか、治癒したあとなのかを明確にする必要があります。そのためには、HBs抗体単独の結果だけでなく、HBs抗原やB型肝炎ウイルスが増殖する際につくられるタンパク質のHBe抗原と、それに対する抗体であるHBe抗体などの結果を総合して判断することが大切です。
自分自身で注意できること
HBs抗体は、一般的にはB型肝炎ウイルス感染の治癒後やワクチン接種後に陽性となります。しかし、特にワクチン接種によってHBs抗体が形成された場合には、時間の経過とともに効果が減弱することがあります。また、免疫力が極端に低下する病気になった場合には、HBs抗体が陽性であってもうまく作用せず、微量に潜んでいたB型肝炎ウイルスが再活性化して肝炎を発症するケースもあります。
このため、HBs抗体が陽性であっても感染には十分に注意し、感染機会の多い医療従事者などは定期的に検査を受けるようにしましょう。また、肝機能障害が疑われる症状がみられる場合には、なるべく早く病院を受診することも大切です。
本記事で採用している検査名称はより一般的な表現を採用しておりますが、医療機関や検査機関によって異なる場合があります。また名称が異なる場合、検査内容も一部異なっている場合があります。