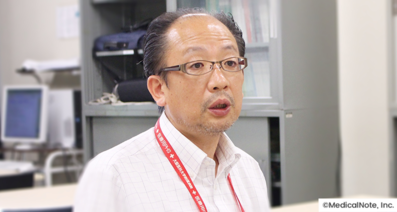
自分が男性なのか女性なのか、多くの人が生まれた時から意識することなくごく当たり前に過ごしています。しかし、近年広く社会に認識されるようになった性同一性障害やトランスジェンダーの方は、幼少期から非常に強い葛藤を抱えながら成長しています。
生まれつき体の性と自分が認識する性が違い、その違和感に苦しむ性同一性障害、男女という2つの概念にとらわれることなく自分を表現するトランスジェンダーを、私たちはどのように理解すればいいのでしょうか。大阪医科大学の康純先生にお話をうかがいました。
性同一性障害とは
性同一性障害は従来、「自分の性別はどちらであるのか、自分で自覚している性別(ジェンダー・アイデンティティー)と戸籍上の性別(身体的性別)との間にずれがある状態」と定義づけられていました。「男女」という二つの性別の原理に基づけば、体は男性だけど自分は女性、あるいは体は女性だけど自分は男性という認識を持つことが、医学的な概念として性同一性障害といわれていました。
しかし最近では、自分の性別が男女どちらでもない、どちらだと決められない、自分は男女の中間だと本人が認識しているケースが見られることもあります。それを、『クエスチョニング』『Xジェンダー』と呼ぶこともあります。そこまで踏み込んでいくと、身体的性別と自分が思う性別がどうかということは、男女という二つの概念を基にした性同一性障害からは少しはずれます。
ジェンダーという言葉は「社会的性」などと訳されますが、「自分が生きていくうえで自己をどういう性であると表現したいのか」をジェンダーと考えると、それが社会から認識される性と一致せず、自分らしい性を表現する人々をトランスジェンダーと呼んでもいいのかもしれません。
ジェンダーを考えるとき、アメリカのジョン・マネーによる3つの分類をもとにします。
ジェンダーアイデンティティ=性自認自分はどちらの性別に属するのか
ジェンダーロール=性役割自分はどういう役割を担うのか
セクシャルオリエンテーション=性指向恋愛対象がどちらなのか
3番目の要素は、性同一性障害の診断においてはまったく関係ありません。恋愛対象が男女どちらなのか、これが典型的でない人はゲイやレズビアン、バイセクシュアルなどと表現されます。そうではなく、性同一性障害を考えるうえでは「自分が認識する性役割がどちらなのか」ということが重要なのです。
「性役割」について考えてみましょう。たとえば明治時代と現代を比較すると、男女の性役割はまったく同一ではありません。時代によって、文化によって、さらに国によっても異なります。
このように、「男性」「女性」という言葉が何を意味するのかということは非常に流動的です。明治時代の男性が見れば「あんなの絶対男じゃない!」というような「男性」も現代にはいるでしょう。このように性役割を考えていけば、「では自分はどういう役割を表現していくのか」と考えたときに、古典的な男性・女性に属さない、そのように表現できない、という状態の方がたくさん存在することは理解できるのではないでしょうか。
康 純 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
不整脈が何年も続いている
小3から不整脈(頻脈)をもっている 今までに計3回の手術をしている。 一回目は全身麻酔 二回目は局所麻酔 三回目は全身麻酔 でした 一回目と二回目は同じ回路でしたが三回目のは違う場所に出来ていましたが 手術で取り除きました ですが激しい運動をしていて飛んだりすると脈が飛んでなかなか治りません。(脈は安静にしていても150以上 目眩や倒れるなどの症状なし) また4回目の手術をした方がいいのか
洞不整脈について
早朝勤務や夜勤が積み重なっているからか、心臓の音が大きく聞こえるような動悸が止まらなくなることがあります。息が浅くなり、仕事場にいるのが辛くなることもあります。緊張を強いられる仕事、さらに仕事への大きな不安も根底にあるせいかとは思うのですが。1ヶ月前の心電図の健康診断で洞不整脈と出ていますが、現段階では心配はないとのことでした。 今後、どのようにしたら良いでしょうか?
先天性弁膜症の大動脈狭窄症症候群大動脈弁不全閉鎖症
3年前から心電図にQT延長雑音エコー心電図脈が飛びました。胸部のレントゲンでは以上なしでした。この場合手術薬とかなるでしょうか?毎年引っ掛かかってて参ってます。血液検査は異常なしです。どうしてなんでしょうか?教えて頂けますか?動機息切れ胸がチクチク痛む。めまいもします。
何回か脈が飛ぶ
ここ2、3日、10回に一度くらいドクンと、脈が飛ぶことがあります、他の症状はありません、走ったりしてもしんどくないです
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「性別不合」を登録すると、新着の情報をお知らせします





