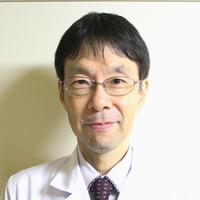提供:Meiji Seika ファルマ株式会社
新型コロナワクチンの全額公費負担による接種は2023年度で終了し、2024年10月から65歳以上の方や60~64歳で重度の基礎疾患がある方などを対象とした定期接種が始まりました。2024年10月から2025年3月の定期接種に使われたワクチンには、2023年に承認された“次世代mRNAワクチン”を含め、5種類のワクチンがありました。今回は川崎医科大学小児科学 特任教授の中野 貴司先生に、ワクチンの種類ごとの特徴や、ワクチン接種を正しく理解することの重要性、新型コロナウイルス感染症の流行に関する見解などについて伺いました。
新型コロナウイルス感染症を予防するために――ワクチン接種の意義とは?
新型コロナウイルス感染症にかかると、後遺症が残って生活の質が大幅に低下することや、命に関わる場合があります1)。特に、高齢の方や基礎疾患がある方などはそうでない方よりも重症化するリスクが高いとされています。自分自身の感染を防ぐだけでなく、周囲の方を守るためにも適切な感染対策が重要です。
予防の基本は、手洗いやマスクの着用など一般的な感染対策
手洗いやマスクの着用をはじめとした一般的な感染対策は、新型コロナウイルス感染症に限らず感染症の予防のための大切な手段です。日本国内では新型コロナウイルスの流行以前から、特にインフルエンザなどの感染症が流行しやすい冬の時期にはマスクをして、咳やくしゃみをした際にウイルスが飛び散らないようにする対策を励行されている方が多かったように感じます。常日頃から、感染症の流行状況などを考慮しつつ、一人ひとりが日常生活とのバランスを取りながら、それぞれの考えに基づいて対策を行うとよいでしょう。
ワクチンは、病原体への免疫をつけ重症化などを防ぐ手段
私たちの体を守る免疫には、一度侵入してきた病原体(病気を引き起こす細菌やウイルスなど)を記憶し、次に入ってきた際により早く対処する機能が備わっています。ワクチンはこの仕組みを利用し、ある病原体に対して特異的にはたらく機能(免疫)を獲得させます。つまり、新型コロナワクチンは新型コロナウイルスへの免疫をつけ、感染や発症、重症化に対して能動的に予防を図る方法なのです。

現在、国内の定期接種で使われている新型コロナワクチンには、“mRNAワクチン”が3剤、“次世代mRNAワクチン”と“組換えタンパクワクチン”が各1剤あります(2025年3月時点)2)。
新型コロナワクチン接種開始時から使用されてきた“mRNAワクチン”
mRNAワクチンはmRNA(メッセンジャーRNA)を使ったワクチンのことです。mRNAが遺伝情報(生物を形づくる設計図となる情報)を伝達し、細胞がその遺伝情報に基づいてタンパク質をつくるという仕組みを応用したワクチンです。
新型コロナワクチンの接種が始まった2021年から使われ、広く普及してきました。病原体の遺伝情報が分かればそれに基づいてワクチンを製造できるため、新たに出現した病原体や変異した病原体にも対応しやすいという利点があります。
mRNAワクチンは新型コロナウイルスの遺伝情報の一部を記録したmRNAを脂質の膜で包み、細胞に送り込みやすくした構造で、接種するとその遺伝情報をもとに体内で新型コロナウイルスのタンパク質の一部がつくられます。すると体内に新型コロナウイルスが侵入したような状態になり、それに反応して抗体ができることなどによって免疫を獲得し、新型コロナウイルス感染症の予防ができると考えられています3)。
次なる選択肢として登場した“次世代mRNAワクチン”
感染症予防のメカニズムと期待されるメリットとは?
次世代mRNAワクチンは2023年11月に承認*され、定期接種で使われているワクチンです。免疫ができる仕組みは従来のmRNAワクチンと同じですが、接種されたmRNAが体内で増幅する点が異なります。この性質により、従来のmRNAワクチンよりも少ないmRNAの接種で効果が期待できます。また、mRNAの増幅によって体内で病原体のタンパク質がつくられる時間が長くなり、免疫がより強く誘導され持続することが望めます3)。承認されてから長い年月の経っているワクチンではないので、実臨床の使用下における利点や副反応**について確認するとともに、今後公表される情報を注視していきたいと考えています。
*承認取得日 日本:2023年11月28日、欧州:2025年2月12日
**副反応:ワクチン接種後に生じた有害事象(好ましくない事象)のうち、ワクチン接種と因果関係があるものを指す。
厚生労働省と学会が“シェディング”を否定
次世代mRNAワクチンについては、“シェディング”という言葉を「接種後に感染性病原体が体外に出る」という意味で使い、ワクチンを接種した人から周囲の人への感染を心配する声が上がっています。これに対して厚生労働省は『新型コロナワクチンQ&A』3)の中で、「次世代mRNAワクチンを受けた方からほかの方にワクチンの成分が伝播するという科学的知見はない」と述べています。また2024年10月、日本感染症学会、日本呼吸器学会、日本ワクチン学会は合同で「被接種者が周囲の⼈に感染させるリスク(シェディング)はない」とのコメントを発表しました4)。ワクチンについて考える際には、科学的根拠の乏しい憶測に惑わされず、信頼度の高い情報を見きわめる冷静な姿勢が求められるでしょう。
承認時から継続的に安全性をチェック
インターネット上でやりとりされる情報の中には、「ベトナムで実施された次世代mRNAワクチンの治験で、多くの死亡者が出ている」といった安全性を不安視する声が見受けられました。これに対して厚生労働省は、2024年度第2回予防接種に関する自治体説明会で、「ベトナムの臨床試験で確認された死亡例については、本剤承認後速やかに審査報告書等において情報が公表されている」としたうえで、「いずれの死亡例についても、治験薬接種と死亡との因果関係は否定されている」と述べています5)。
製薬会社が薬事承認*を申請する際には、審査資料として有効性や安全性の根拠となる臨床試験データの提出が求められます。当然ながら、ワクチンや医薬品は安全性についても厳しいチェックを受けて世に出ているのです。さらに、薬事承認後も臨床現場での使用例が増えていくなかで継続的にモニタリングされ、データが蓄積されています。安全性についても、こうした確かな資料を確認されるとよいと思います。
*薬事承認:医薬品などの有効性や安全性に関する審査に基づく、厚生労働大臣による製造販売の承認。

ほかの疾患でも用いられている“組換えタンパクワクチン”
組換えタンパクワクチンは、病原体のタンパク質の遺伝子情報をもとに細胞などを用いて遺伝子組換え*の病原体タンパク質をつくり、そこにアジュバント**を加えたものです。病原体のタンパク質が体内に入ると免疫が異物の侵入を認識し、さらに免疫増強剤によって免疫反応が高まり、新型コロナウイルス感染症の予防ができると考えられています3)。
組換えタンパクワクチンとしては、新型コロナワクチンのほかにB型肝炎ウイルスワクチンなども承認されています。
*遺伝子組換え:ある生物の遺伝子の一部をほかの生物の細胞に組み込み、新たな性質を加えること。
**アジュバント:免疫の獲得を助け、ワクチンの効果を高めるために使われる物質。
新型コロナウイルス感染症の流行状況と今後の可能性
日本国内における新型コロナウイルス感染症の流行は、オミクロン株に置き換わった直後の2022年から2023年初めにかけて3回ほどピークがみられました。その後、2023年5月に患者報告数データが全数把握*から定点把握**に切り替わって以降の推移を見ると、夏と冬の年2回の流行となり、流行の間隔が少し長くなってきている印象を受けます6)。
定点報告数はどのくらいの患者さんが医療機関を受診するか、どのくらいの報告があるかによって数値が異なるため、全数把握だったシーズンとの単純な比較は難しくなっています。しかし、定点報告数の推移を見る限り、流行のピークの高さは下がってきている印象です。
これまで新たな変異株が出現すると流行の規模が大きくなるという状況が何度かありましたが、現時点ではウイルス変異の速度が鈍くなってきており、患者さんの爆発的な増加に至らずに経過しているのではないかと推測されます。
*全数把握:全ての医師が届出を行う感染症。
**定点把握:指定した医療機関のみが届出を行う感染症。
新型コロナワクチンをどう選択する? 信頼できる情報を判断材料に
ワクチン接種による副反応の可能性も
ワクチンはある病原体に対して特異的にはたらく免疫をつけるための手段であり、言い換えれば体内で免疫反応を起こすわけです。したがって、免疫反応に伴う副反応をゼロにはできません。発熱や倦怠感、頭痛といった全身反応、注射した部位の痛みや腫れ、赤みなどの局所反応が生じる可能性があります。
新型コロナワクチンの接種によって起こり得る副反応について、詳しくは厚生労働省ウェブサイトの『新型コロナワクチンQ&A』ページ3)や、ウェブ上で公開されているワクチンの電子添文(電子化された添付文書)*などで確認できます。厚生労働省が発信する情報はもちろん、電子添文は薬剤の承認時に国に届け出た文書であり、どちらも中立的かつ科学的で分かりやすい資料だと思っています。また、各種ワクチン接種後の健康状況の調査も実施されており、資料はインターネットで閲覧可能です7)。
*電子添文:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページに掲載される医薬品などの用法、用量や注意点などを記載した文書。
ワクチンを正しく理解することが重要
新型コロナワクチンの全額公費負担による接種は2023年度で終了し、2024年度から65歳以上の方や60~64歳で重度の基礎疾患がある方*などを対象とした定期接種が始まりました。原則として有料で、自己負担額は自治体によって異なります。
接種の際には、一人ひとりが個別の観点でどのワクチンを打つかを決定されていると思います。実際に、接種を希望して医療機関を受診される方は事前によく調べていらっしゃると感じることが多いです。信頼できる情報をもとにワクチンについて正しく理解し、ご不明な点があれば医師にご相談ください。
*重度の基礎疾患がある方:心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障害があり、日常生活が極端に制限されている方を指す。

最後に――ワクチン接種は感染症予防の大切な選択肢
感染症にはさまざまな予防手段があります。中でも新型コロナワクチンは新型コロナウイルスに対して特異的にはたらく免疫を獲得するためのもので、重要な感染症対策といえます。ただし、ワクチン接種にあたっては副反応が起こる可能性があり、副反応を許容できる範囲や接種せずに感染したときの重症化リスクは人によって異なります。年齢や流行状況によってもその度合いは変わってくるでしょう。だからこそ、正確な情報を知ったうえで選択していただきたいのです。
新型コロナは定期接種のB類疾病*であり、ワクチンは一人ひとりの意思に基づいて接種するものです。ワクチンの接種率は低下していますが、今後も正しい知識をもって適切に接種を判断していただきたいと思っています。
*B類疾病:予防接種法で接種が定められているワクチンのうち、努力義務や国の積極的勧奨がないもの。新型コロナのほか季節性インフルエンザや高齢者の肺炎球菌感染症が該当する。
参考文献
- 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
- 厚生労働省 新型コロナワクチンについて https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
- 厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html
- ⼀般社団法⼈⽇本感染症学会、⼀般社団法⼈⽇本呼吸器学会、⽇本ワクチン学会「2024 年度の新型コロナワクチン定期接種に関する⾒解」https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/news/gakkai/gakkai_covid19_241021.pdf
- 厚生労働省 令和6年度第2回予防接種に関する自治体説明会 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001316061.pdf
- 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の国内発生状況等について https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html
- 厚生労働省 第105回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和6年度第10回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催) 資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00125.html
本ページにおける情報は、医師本人の申告に基づいて掲載しております。内容については弊社においても可能な限り配慮しておりますが、最新の情報については公開情報等をご確認いただき、またご自身でお問い合わせいただきますようお願いします。
なお、弊社はいかなる場合にも、掲載された情報の誤り、不正確等にもとづく損害に対して責任を負わないものとします。