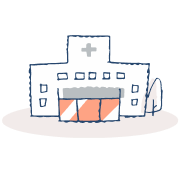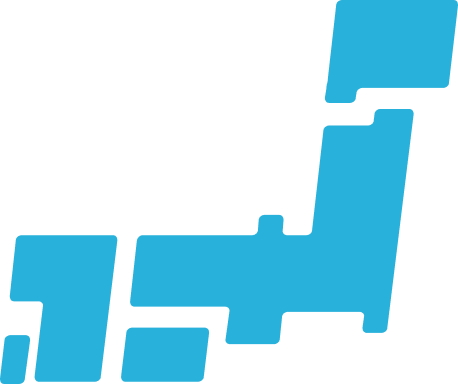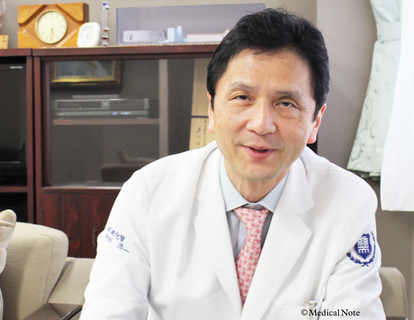概要
機能性ディスペプシアとは、検査で明らかな異常がないにもかかわらず、慢性的なみぞおち辺りの痛みや胃もたれなどの上腹部症状を現す病気を指します。
慢性的な上腹部症状は、胃や十二指腸の炎症、潰瘍、がんなどの病変(器質的異常)によって引き起こされることが多いですが、病変が認められない場合もあります。この場合には、胃や十二指腸の機能的な問題によって症状が引き起こされていると考えられます。
機能性ディスペプシアの罹患率は約15%であると報告され、頻度の高い身近な病気です。命に関わることはありませんが、QOL(生活の質)に影響するため、我慢せずに適切な治療を受けることが大切です。
原因
機能性ディスペプシアの原因はまだはっきりと分かっていませんが、胃・十二指腸の運動異常や知覚過敏、胃酸分泌、心理的なストレスなどが原因の1つと考えられています。
また、最近ではサルモネラ感染などによる感染性胃腸炎が治った後に、機能性ディスペプシアを発症する例も報告されています。
そのほか、アルコールや喫煙、不眠といった生活習慣の乱れも関わっているとされ、これらの原因が1つ、もしくは複数が組み合わさって発症すると考えられています。
なお、ヘリコバクター・ピロリ菌を除菌することで症状が軽快することがあります。この場合には機能性ディスペプシアではなく、ピロリ菌関連ディスペプシアとして区別されるようになってきています。
症状
機能性ディスペプシアでは、みぞおち辺りの痛みや灼熱感、食後の胃もたれ、早期飽満感(少し食べるだけでお腹がいっぱいになる)などの症状がみられます。
胃もたれは、前日に脂っこいものを食べたりお酒を飲みすぎたりしたときなどによくみられる症状で、暴飲暴食であれば胃を休めると自然に軽快していきます。
しかし、機能性ディスペプシアの場合には暴飲暴食などの明らかな原因がないにもかかわらず、このような症状が慢性的に持続し、毎日あるいは週に数回程度現れます。
症状の種類や程度は人によってさまざまで、みぞおち辺りの痛みと灼熱感のどちらかがある場合を心窩部痛症候群、食後の胃もたれと早期飽満感のどちらかがある場合を食後愁訴症候群と呼び、2つの病型に分類されています。この2つが重複することもあります。
検査・診断
機能性ディスペプシアの診断には、症状の原因となり得る病気を否定することが重要です。
そのために、詳細な問診(症状の種類・発症時期・食事との関連・体重減少の有無など)によって病態を確認します。そのうえで、多くの場合は上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)やピロリ菌検査が行われます。
必要に応じて、血液検査や腹部CT検査、超音波検査などが行われることもあります。このような検査の結果から、明らかな異常がない場合に機能性ディスペプシアと診断されます。
治療
機能性ディスペプシアでは症状に応じた薬を用いて治療します。第一選択薬として推奨されているのが、胃酸の分泌を抑える酸分泌抑制薬(プロトンポンプ阻害薬やヒスタミンH2受容体拮抗薬など)と、胃のはたらきをよくする消化管運動機能改善薬(ドパミンD2受容体拮抗薬やコリンエステラーゼ阻害薬など)です。
一般的には、みぞおち辺りの痛みや灼熱感がある心窩部痛症候群には酸分泌抑制薬、食後の胃もたれや早期飽満感がある食後愁訴症候群に対しては消化管運動機能改善薬が用いられます。
また、考えられる原因に応じて、抗不安薬や抗うつ薬、漢方薬(六君子湯など)が使われることもあります。ピロリ菌に感染している場合にはピロリ菌の除去療法が検討されます。
漢方薬の相談ができる医療機関を調べる
エリアから探す
予防
機能性ディスペプシアは、約5人に1人が数か月以内に再発するといわれています。しかし、原因を特定することが難しい病気であり、発症・再発予防の方法はまだ明らかになっていません。
とはいえ、胃酸分泌や感染症、心理的ストレスなど、考えられる原因を防ぐことで機能性ディスペプシアの予防につなげられる可能性も考えられます。
十分な睡眠を取る、食事を腹八分目にして過度な飲酒を避ける、ストレス対策をするなどの基本的な心がけは、ほかのさまざまな病気の発症予防にもつながるため、意識的に予防策をとるとよいでしょう。
「機能性ディスペプシア」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください