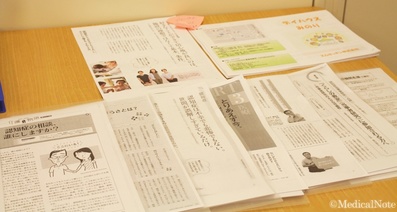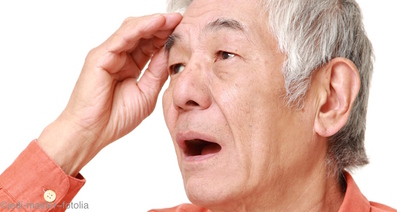認知症とともに、軽度認知障害(MCI)という言葉を耳にする機会が増えました。MCIとは、認知症のハイリスクグループ(将来認知症になる可能性がより高いグループ)のことをいいます。のぞみメモリークリニックの院長である木之下徹先生は、多くの認知症の人を訪問診療で診てこられました。本記事では、MCIの概念がうまれた背景とその診断についてお話しいただきました。
MCIとは
MCI(mild cognitive impairment)は、直訳すると「軽度認知障害」となり、認知症のハイリスクグループのことを指します。MCIを理解しやすくするために、ここでは、アメリカ精神医学会が作成しているDSM-5(精神障害の統計・診断マニュアル)の考え方を紹介します。ただし、DSM−5では、MCIという呼称ではなく、神経認知障害(Minor Neurocognitive Disorders)という呼称が使われています。MCIという概念の歴史は、1962年頃から、「認知症にならない良性の物忘れとは何か」といった議論に端を発します。詳細な歴史の流れは省略しますが、それから歴史を経て、現在は他の集団よりも「より将来認知症になる可能性の高い」集団として軽度認知障害という概念が規定されています。
DSM-5でMCIを診断するときの手順は次のようなものです。まずは区別すべき重大な疾患や状態の人を除外します。それから認知機能検査の結果に従って、一般集団の平均と標準偏差から、相対的に結果が低い人を統計的にはじき出す方法を提示しています。具体的な手順は後述します。
ところでDSM-5の特徴は、認知症もMCIと同じ原理で診断するといった極めて合理的、かつ理解しやすい方法を提案していることです。つまり、「正常—MCI—認知症」という連続的な現象として捉えていることが特徴です。これまでは、MCIは認知症のハイリスクグループである、という考えが前面に据えられており、あまり認知症との関係を論じてこなかった歴史があります。認知症の定義は、「正常に発達した認知機能が、後天的な脳の変化に従って低下し、生活に支障をきたす状態」です。
一方で、1990年代くらいからMCIという概念に似たもの(例えば、AAMI、AACDなど詳述は省略します)が提示され、MCIはその当時から神経心理検査などの結果から統計的に規定する概念でした。つまり、実践的かつ定量的なMCIの概念と定性的な認知症の定義は、完全に連続的な概念ではありませんでした。極端に言えば、視点を転ずることで、MCIを経ないで認知症に移行する人がいることにもなります。このような混沌としていた状況がありました。
「DSM-5では認知症、MCIの概念が理解しやすい」と前述した理由は、この2つの状態を連続的なものと定義したこと、さらに実践的に評価できる見通し(認知機能検査)をDSM-5がつけたからです。このような優れた点がある一方で、果たしてこのような捉え方で良いのか否かは別問題です。また横断的な(一時点での)診断のMCIの概念と、縦断的な(経時的な)認知症の定義を同一の文脈で述べて良いのかという問題もあります。明らかに、認知症の診断において、MCIの診断方法のような横断的な方法を用いてしまうことには懸念があります。なぜなら、認知症は時間の経過とともに進行していくためです。この点に留意することは大切です。
DSM-5におけるMCIの診断
DSM-5におけるMCIの診断は、年齢と教育歴で階級分けされた6つのスケール(物さし)を用いて行われます。なぜなら年齢や教育歴によってテスト点数の平均が異なると考えられているからです。逆に同じ年齢や教育歴による層別の各集団の有病率は、各国でその数値が変わらないと信じられている背景もあります。ただし日本では、2012年、筑波大学の朝田教授が班長を務める厚労省研究班の発表によって状況が変わりました。この発表は、病院の受診者ではなく地域の住人の視点で研究されたもので、MCIの人数もおそらく、世界で初めて統計的に示しました。そこで示された階層別有病率は、今まで疫学で示されていた世界各国の有病率よりも大きいものでした。
6つのスケールは、以下のような主要な神経認知領域をあらわします。
- 複合的注意(complex attention)
- 実行機能(executive function)
- 学習と記憶(learning and memory)
- 言語(language)
- 知覚‐運動(perceptual-motor)
- 社会認知(social cognition)
※現在、臨床の実践に十分対応できるような6つのスケールが全て完備されているわけではありません。
このスケール(物さし)は健常者をもとに作成されており、MCI・認知症の区域を設定しています。ご本人の認知機能のテスト結果を各スケールに当てはめ、どこに位置しているのかをあらわします。これら6つのスケールのうち、ひとつでもMCIの区域に入っていれば、他は健常者の区域に位置していても、その方はMCIと診断されます。認知症の場合も、たとえば「実行機能」のスケールのみが認知症の区域に入っていれば、他は健常者の区域であったとしても、認知症と診断されます。
とはいえ、前述したようにこのテストを一度受けて、その点数だけで認知症と診断してしまうことには懸念があります。ここでのテストは神経心理検査のことですので、実際は一定の揺らぎ(ばらつき)があります。あくまで、DSM-5で定義された概念の「理解のしやすさ」をここでは利用している、ということをここで再度強調しておきます。認知症であれば、認知機能の低下は時間の経過とともに進行します。実際の臨床では、検査結果の経時的変化を確認することが必須であるのは言うまでもありません。
木之下 徹 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
健康診断で血圧が
昨日健康診断を受けて、血圧をはかったら上が150で下が88でした。昨年は上が110で下が85ぐらいだったのにいきなり上がり出して怖いです。何か病気のサインでしょうか?自分では疲れやすいぐらいで前とあまり変わらないと思うのですが?病院に行った方が良いですか?ちなみに143cm体重79キロです。体重落とさないと駄目ですよね?塩辛いおつまみやお酒、スナック菓子大好きです。これはやめないとまずいですね。
いびき対策として、どのような施術があるのか
いびきがうるさく、睡眠時無呼吸ことなっていることを指摘されました。 いびきを小さくしたいのですが、どのような施術があり、特徴があるのでしょうか。 できれば、一度の施術で終えられるようなものがよく、かつ、保険が使えると助かります。 よろしくお願いいたします。
ぎっくり腰の処置方法
12月11日タイヤ交換している時にぎっくり腰になりました。椅子から立ち上がったりする時に強く痛みを感じます。 あを向けに寝ることはできます。 どのような処置をしたら良いでしょうか。
突然のボケ
今日夕方、実家の弟から母が出先で急に訳が分からなくなり帰れなくなり先方から電話があった。 話の途中で急にわからなくなり、誰と話しているか、自分がどこにいるかもわからなくなったようです。 私が県外で暮らしている事も忘れているとの事です。現在も状態変わらず。 以前、転んで頭を打った際にかかった病院に電話すると検査が明後日、診断は来週の予約しか取れないと言われたそうですが、すぐに病院に行かなくても良いのでしょうか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「軽度認知障害」を登録すると、新着の情報をお知らせします