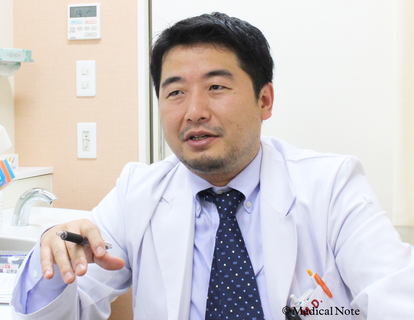概要
先天性股関節脱臼(発育性股関節形成不全)とは、生後3~4か月ごろに生じることがある、股関節が不安定になっている状態を指します。状態により、脱臼していることもあれば、不完全な脱臼(亜脱臼)が生じていることもあります。脱臼や亜脱臼が生じていない、股関節の骨の形成不全により関節が不安定になっている状態(臼蓋形成不全)も含みます。
従来は乳幼児期の股関節脱臼を“先天性股関節脱臼”と呼んでいました。“先天性”とは、“生まれつきのもの”であることを意味します。しかし、成長の過程で脱臼が生じることも多くあり、その要因も多岐にわたるため、脱臼、亜脱臼、臼蓋形成不全を全て含めた状態として、“発育性股関節形成不全”と呼ばれるようになりました。
以前と比較すると発症頻度は大幅に減少していますが、現在でも1,000人に1~3人程度の発症がみられるとされています。発症頻度は減少した一方で、発見が遅れ、歩行開始後に脱臼や股関節の不安定性がみつかることが増加しているともいわれています。
先天性股関節脱臼の原因は多岐にわたります。たとえば、女児は股関節が柔らかいために脱臼を生じやすいといわれています。血縁者に股関節の変形などがみられる場合や、股関節に負担がかかる姿勢をとっている場合にも発症しやすくなります。
治療としては、年齢や股関節の状態などにより行われる内容が異なります。治療開始が遅くなると手術が必要になり、また、早期に治療を開始した方が経過が良好であるといわれています。早期発見・早期治療が重要であり、脱臼を起こさないために赤ちゃんの姿勢に注意することも大切です。
原因
先天性股関節脱臼の原因は多岐にわたります。発症に関わる患者の性質や特徴としては、女児であること、血縁者に股関節の変形などがみられることが挙げられます。女児は関節が柔らかいために男児よりも脱臼しやすく、発症頻度としても女児のほうが高いとされています。また、詳細は分かってはいないものの、股関節の変形と先天性股関節脱臼との間に、遺伝的な関連があると考えられています。
一方で、患者の性質などによらず、外部的な原因で発症することもあります。主に、股関節に負担がかかる姿勢をとることで発症しやすくなります。乳児にとっては脚を“M”の字のように曲げた姿勢が自然ですが、脚を伸ばすような姿勢では股関節に負担がかかります。生まれる前には、骨盤位(逆子)の場合は脚が伸びた状態となり脱臼の原因になります。生まれてからの原因としては、抱っこの仕方、衣服、おむつなどにより脚を伸ばした状態で固定されることや、寝ているときの左右への“向き癖”が挙げられます。
症状
先天性股関節脱臼では、脱臼していても痛みが生じません。そのため、歩くことができない年齢の乳児では脱臼していると分かりづらいことがあります。現れる特徴としては、股関節が開きにくい、太ももや鼠径部のシワが左右対称でない、寝ているときの脚の位置が左右対称でない、などが挙げられます。
歩き始めるまでに脱臼に気付かれないと、歩き方の異常がみられることがあります。歩行することは可能ですが、片方の股関節を脱臼している場合は歩行の異常が現れ、両方の股関節を脱臼している場合は腰やお尻を突き出したような歩き方がみられます。
検査・診断
乳児検診では、股関節の状態について確認されます。前述のような、股関節が開きにくいなどの特徴がみられたり、股関節脱臼のリスク(女児、血縁者の股関節の変形、骨盤位)が高かったりする場合には、追加での検査を行います。
追加の検査としては、X線、超音波などを用いた画像検査が行われます。超音波検査では、X線検査では見分けられない脱臼の兆候を発見することが可能といわれています。股関節の動きなどの身体的な検査の結果、画像検査の結果を総合的に判断して、診断が行われます。
治療
先天性股関節脱臼の治療法は大きく分けて、装具による治療、牽引による治療、手術による治療の3つあります。脱臼が生じている場合、年齢や股関節の状態に応じて治療方法が選択されます。一般的に、早期に治療を開始した方が、治療後に臼蓋形成不全などの合併症を生じにくくなるといわれています。
装具による治療
生後6か月ごろまで、多くは乳児検診がきっかけで診断された場合などに、まず選択される治療法です。この治療法では、リーメンビューゲルと呼ばれる装具が用いられます。装具のベルトにより体幹や脚を固定し、股関節を正しい位置に戻します。
入院の必要はなく外来での治療が可能で、多くの場合で2週間以内に股関節を正しい位置に戻すことができます。その後も装具の装着は数か月ほど継続されますが、装着期間などの詳細は医療機関により異なることがあります。
股関節の変形が残りにくい治療法とされており、約80%はこの方法で治療することができるといわれています。
牽引による治療
生後6か月以降で、装具による治療で改善がみられない場合などに選択されます。脚を引っ張り、股関節周辺の筋肉をほぐしながら、股関節を正しい位置に戻します。牽引による治療も、医療機関により詳細に違いがみられることがあります。
入院のうえで行われる治療法であり、全身麻酔も必要になります。股関節が正しい位置に戻った後も、ギプスや装具による固定を行う必要があり、数か月間を要します。
手術による治療
リーメンビューゲルや牽引による治療で改善がみられない場合や、2~3歳を過ぎてから診断された場合などに選択されます。入院のうえ、全身麻酔が必要になります。
予防
先天性股関節脱臼では、脱臼のリスク(女児、血縁者の股関節の変形、骨盤位)については予防することができません。一方で、脱臼が生じやすくなる外部的な要因を知っておくことで、発症を予防したり悪化を防いだりすることが可能です。
予防として、乳児が歩き始めるまでは、股関節に負担がかからないよう注意が必要です。具体的には以下の事項に注意しましょう。
- 乳児が寝ているときは、脚を“M”の字のように曲げた姿勢で、脚を自由に動かせるようにする
- 衣服やおむつによって、脚を伸ばした状態にならないようにする
- 左右への“向き癖”がある場合は、向いている方向と逆の膝が、まっすぐになった状態(立て膝)や、内側に倒れこんだ状態にならないようにする
- 抱っこをする際も、脚を伸ばさせず、脚が“M”の字に曲がる形(コアラ抱っこ)になるようにする
早期発見・早期治療により、治療の負担を軽くすることが可能で、経過も良好といわれています。日常生活での対策を行ったうえで、股関節が開きにくい、太ももや鼠径部のシワが左右対称でない、寝ているときの脚の位置が左右対称でないなどの特徴がみられた際は、よく観察して医療機関の受診を検討するとよいでしょう。
「先天性股関節脱臼」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください