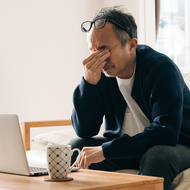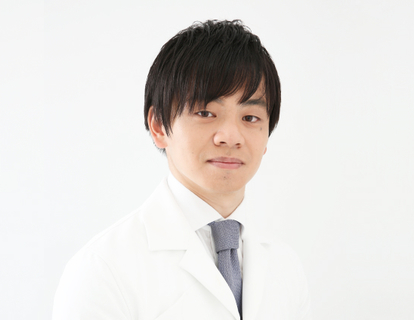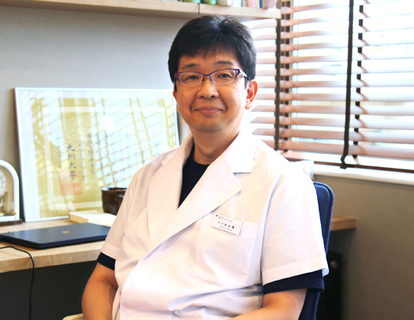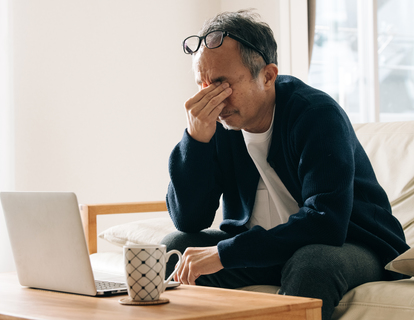概要
不眠症とは、良質な夜間の睡眠を十分に取ることができず、仕事や学業に支障をきたすなど日中の機能障害が生じた状態を指します。不眠症状には寝付きが悪い(入眠困難)、夜間に目覚めてその後眠れない(睡眠維持困難)、朝早くに目覚めてしまう(早朝覚醒)などのタイプがあります。
不眠症を引き起こす原因はさまざまであり、心理的なストレス、飲酒、薬物、身体の不調など多くのものがあります。不眠に関しての問題を抱える人の割合は高く、成人の30%以上が一過性の不眠症状を経験し、10%ほどが不眠症に罹患していると報告されています。すなわち、現在の日本においては誰であっても不眠症に陥る可能性があるといえます。
不眠症の診断や治療の必要性は、睡眠時間のみでは判断できません。不眠症状が存在していることに起因して、昼間のパフォーマンスに悪影響を及ぼしているかどうかを判断することがとても重要です。
原因
不眠症の原因としては、不適切な生活習慣、心理的なストレス、アルコールなどの嗜好品や薬物、心身の病気などが挙げられます。
不適切な生活習慣には、現在の日本社会の様相が大きく影響しています。本来ヒトの体内時計は、1日平均24.18時間でリズムを刻んでいます。1日24時間の枠組みの中で決まった時間に寝起きし規則正しい生活を送るには、日中の活動時間に光を浴びて体内時計をリセットすることが必要不可欠です。しかし、深夜営業・終夜営業のコンビニの存在、就寝前のスマートフォンの利用、24時間稼働の工場勤務や夜勤労働など、不適切なタイミングで光を浴びることでヒトの体内時計に狂いが生じます。
そのほか、家族や親しい友人の死去、仕事の過度なストレスなどの心理的なストレスも不眠症の原因になります。また寝付きをよくするためにアルコールを飲む方もいますが、むしろアルコールは夜間の睡眠の質を悪化させるため、結果として不眠症を引き起こす要因になります。
症状
不眠症では、夜間の不眠症状が基盤にあります。不眠症状のタイプとしては入眠困難、睡眠維持困難、早朝困難があります。
“入眠困難”はなかなか寝付けないことです。寝るまでに30分から1時間かかる場合がこれにあたります。不眠症の中でももっとも訴えの多いものです。
“睡眠維持困難”はいったん眠りについても何度も目が覚めてしまう、目が覚めた後に眠れない場合がこれにあたります。年齢を重ねるとともに眠りが浅くなり目が覚めやすくなります。お年寄りに多くみられるタイプです。
“早朝覚醒”は朝早く目が覚めてしまい、そのまま眠れない場合です。年齢を重ねるとともに体内時計のリズムが前にずれやすく、この症状が出やすくなります。
不眠症では、こうした不眠症状により日中の機能障害が生じることが特徴です。具体的には、仕事や学業に支障をきたすなどのパフォーマンスの低下、集中力や記憶力の低下、やる気が出ない、情緒の不安定さ(気分がすぐれない・イライラしやすいなど)がみられます。
検査・診断
不眠症の診断においては、どのようなタイプの不眠症状があるのか、またそれによる日中の機能障害があるのかを判断することが重要です。さらに睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群など、ほかの睡眠障害を除外できる場合に不眠症と診断することになります。
基本的には、不眠症状や日中の機能障害は問診による主観的な評価をもとに判断しますが、夜間睡眠の状態をより詳細に評価するために“睡眠ポリグラフ検査”という検査が行われることがあります。また、腕時計型の加速度センサーを手首に取り付け、連続的に活動量を計測する“アクチグラフィ”という検査が行われることもあります。
治療
不眠症の治療においては、不眠症状の原因に対してのアプローチ、薬物療法、認知行動療法が検討されます。
原因の項目で記載したとおり、不眠症は不適切な生活習慣、心理的ストレス、アルコールや薬物などさまざまなものが原因となりえます。そのため、良質な睡眠を保つことができるような睡眠衛生指導が行われます。たとえば、毎日なるべく決まった時刻に寝起きする、日中に光を浴びる、寝る前のカフェインやブルーライトを避けるなどが挙げられます。
こうしたアプローチに加えて、薬物療法や認知行動療法を用いることもあります。薬物療法は安全性の高いオレキシン受容体拮抗薬やメラトニン受容体作動薬が優先されますが、場合によってはベンゾジアゼピン受容体作動薬なども使われます。薬物は漫然と継続するのではなく、定期的に症状を評価し、可能であれば減薬・休薬も試みます。認知行動療法は単独でも薬物療法との併用でも行われることがあります。適切なスケジュールで睡眠をとるトレーニングとリラクゼーション法を組み合わせる方法が一般的です。
「不眠症」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください