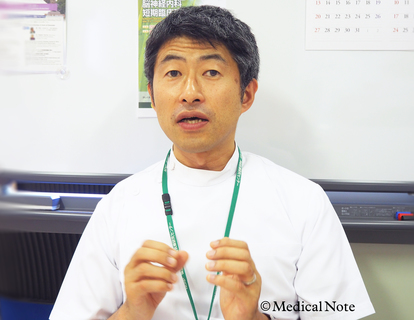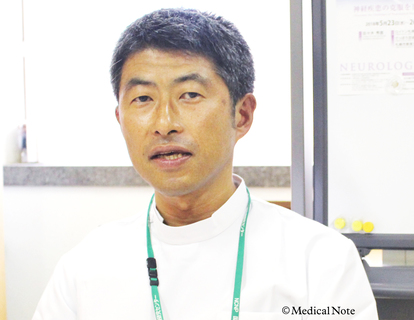概要
多系統萎縮症とは、大脳、小脳、脳幹、脊髄といった脳のさまざまな部位が障害を受けることで発症する病気です。
脊髄小脳変性症と呼ばれる疾患の一部を構成しており、特に孤発性(遺伝性でないもの)脊髄小脳変性症の大部分を占めています。以前は以下の3つに分類されて考えられていました。
- 線条体黒質変性症
- オリーブ橋小脳萎縮症
- シャイドレーガー症候群
しかし、いずれも病理学的な特徴を共有することから現在では一つの疾患概念として捉えられています。
多系統萎縮症では、病気を根本的に治療する方法は確立されていません。さまざまな症状が現れるため、薬物や周囲の環境整備を含めて各種症状に応じた支持療法を行います。
原因
多系統萎縮症では、αシヌクレインと呼ばれる異常構造物が脳内に蓄積します。小脳や脳幹、脊髄に蓄積することが多く、同部位の障害を受けることから病気が発症すると考えられています。
神経細胞が障害を受けると細胞は変性と呼ばれる変化を受けて、最終的には神経細胞がなくなり脳が萎縮していきます。神経変性疾患のひとつに脊髄小脳変性症と呼ばれる病気が存在しますが、遺伝性の有無に応じて大きく分類されています。
このなかでも遺伝性のない脊髄小脳変性症は70%ほどを占めています。遺伝性のない脊髄小脳変性症のことを孤発性脊髄小脳変性症と呼びます。このなかの多くを多系統萎縮症が占めています。
多系統の名前が示唆する通り、脳神経のなかでもどの部位が障害を受けるかに応じてそれぞれ出現する症状は異なります。たとえば大脳の一部(線条体と呼ばれるところ)が障害を受けるとパーキンソン病のような症状が現れます。小脳が障害を受けるとバランス調整に障害を受けます。脊髄に関連して自律神経障害が現れることもあります。
症状
大脳、小脳、脳幹、脊髄の障害に応じた症状があらわれます。なかでも多系統萎縮症では、小脳の障害に起因した歩行障害から発症することが多いです。
小脳に障害を受けると体幹のバランスをとるのが難しくなるため、千鳥足のようなふらふらとした歩行をみます。両足をそろえた形で起立するのも難しくなります。そのため、体幹のバランスをとりやすくするために足を広げて歩くようになります。
また、しゃべり方にも影響が生じ、ろれつが回りにくくなります。手の障害もみられ、震える、字が書けないなどの症状があらわれます。
脊髄に障害が生じると、自律神経系の症状がみられるようになります。具体的には、尿失禁や頻尿、立ちくらみ、汗をかきにくいなどの症状が挙げられます。
さらに大脳(線条体)・脳幹(黒質)に関連して、パーキンソニズムと呼ばれる症状があらわれます。歩幅が狭くなり、動作が遅くなります。表情も乏しくなり、方向転換時に転倒をしやすくなります。多系統萎縮症では、手足の突っ張りや嚥下障害がみられるようになり、数年かけて悪化していくとされます。
検査・診断
多系統萎縮症では、頭部MRIを行い病変部位の萎縮性変化を含めた病変をみます。特徴的なMRIの所見が診断に重要です。
また脳の血流を確認するためにSPECTと呼ばれる検査が行われます。PETと呼ばれる検査を通して、脳細胞の代謝機能を確認することができます。多系統萎縮症ではSPECTで血流低下が、PETで代謝の低下がそれぞれ確認されます。
そのほかにも、神経系の働きを確認するために、聴覚誘発電位、視覚誘発電位などの検査が行われる場合もまれにあります。
多系統萎縮症では自律神経機能異常が生じることがあります。ヘッドアップチルト検査を通して、体位に応じた血圧の調整がうまくいかないことを確認します。
また、心電図検査、膀胱自律神経検査、サーモグラフィーなども同じく自律機能を確認することを目的として実施されることがあります。睡眠時無呼吸を生じることもあるため、ポリソムノグラフィ検査が行われることもあります。
治療
多系統萎縮症では、病気を根本的に治療する方法は残念ながら存在していません。そのため、症状にあわせた支持療法を組み合わせて行います。
たとえばパーキンソニズム症状に対しては、初期であればパーキンソン病で使用される薬剤も有効なことがあります。ただし、時間経過と共に無効となることが多いです。
小脳性の運動障害に対してはタルチレリン、尿障害には抗コリン薬や間欠的自己導尿*、睡眠時無呼吸症ではCPAPなどがそれぞれ行われます。
多系統萎縮症では、薬物治療による治療効果よりも、リハビリテーションによる治療効果が期待されています。残存している筋力を保持することで、転倒のリスクが減り、最終的に寝たきりの予防にもつながると考えられています。生活の質を長い時間維持するためにも、リハビリテーションはとても重要です。
*間欠的自己導尿:患者さん自身が尿道から膀胱へカテーテルを入れ、尿を体外へ排出する方法
「多系統萎縮症」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「多系統萎縮症」に関連する記事
 自律神経障害が現れるシャイ・ドレーガー症候群とは? 多系統萎縮症の病型を解説国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生
自律神経障害が現れるシャイ・ドレーガー症候群とは? 多系統萎縮症の病型を解説国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生 歩行時のふらつきなどが現れるオリーブ橋小脳萎縮症とは? 多系統萎縮症の病型を解説国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生
歩行時のふらつきなどが現れるオリーブ橋小脳萎縮症とは? 多系統萎縮症の病型を解説国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生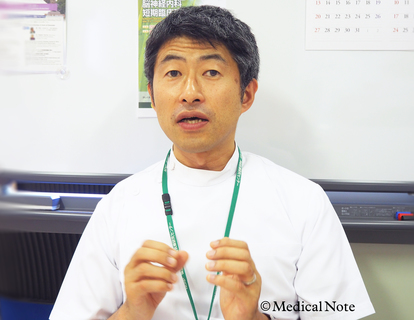 パーキンソン病に似た症状が特徴の線条体黒質変性症とは? 多系統萎縮症の病型を解説国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生
パーキンソン病に似た症状が特徴の線条体黒質変性症とは? 多系統萎縮症の病型を解説国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生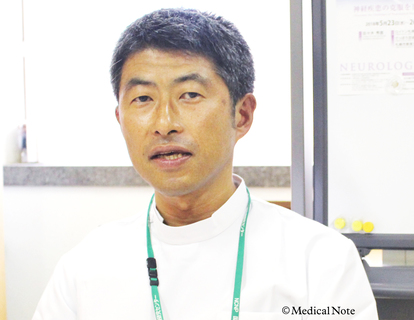 多系統萎縮症の治療 多職種チーム医療の早期介入が大切国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生
多系統萎縮症の治療 多職種チーム医療の早期介入が大切国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生 多系統萎縮症(MSA)とは 原因と症状、検査方法について詳しく解説国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生
多系統萎縮症(MSA)とは 原因と症状、検査方法について詳しく解説国立精神・神経医療研究センター病院 脳...髙橋 祐二 先生