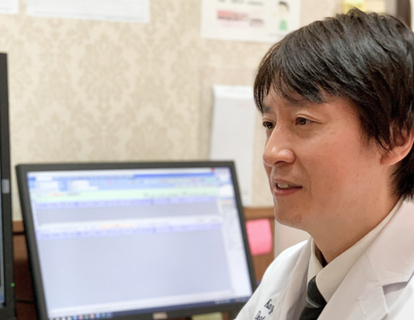概要
腟がんとは、子宮の入り口である子宮頚部と外陰をつなぐ筒状の”腟”にできる悪性腫瘍です。高齢の方に多く、女性生殖器がんの約1%、外陰にできる腫瘍と合わせて罹患率が10万人に0.7人と発症することはまれです。腟の上部(子宮側) 1/3での発生が最も多く (56%)、ついで下部(入り口付近)1/3 (31%)、中間部1/3 (13%)です。
原因
腟がんの大部分(80-90%)は扁平上皮がんで、ついで約5~10%が腺がんです。この他まれではありますが、原発性腟がんとして悪性黒色腫、肉腫、小細胞がんなどが知られています。
扁平上皮がんの主な危険因子としては、高年齢(60歳以上)、子宮頸部の扁平上皮がんと同じくヒトパピローマウイルス(HPV)への感染が挙げられます。腟の扁平上皮がんには子宮頚部の扁平上皮がんと同様に前癌病変があり、腟上皮内腫瘍(vaginal intraepithelial neoplasia; VAIN)と呼ばれます。異型の程度によってVAIN1〜VAIN 3の3段階に分類され、VAINの大部分は持続的な HPV 感染が要因であることが知られています。
一方、腺がんは腟の表面にある腺細胞より発生します。多くは高齢女性にみられ、扁平上皮がんと比べて、肺やリンパ節への転移の可能性が高くなります。海外において胎児期に母親がジエチルスチルベストロール(DES)という薬物を使用した場合(現在は国際的に使用が禁止されています)に特殊な型の腺がんが発生するという報告がなされていますが日本ではDESの使用は少なく非常にまれです。
症状
腟がんの初期症状として最も多いのは、月経と無関係、あるいは閉経後の出血やおりものの異常です。しかし、初期症状がみられない場合も多く、子宮頸がんの検診や内診等で偶然みつかる場合も多くみられます。その他の症状として性交痛、下腹部の痛み、排尿時の痛み、腟内のしこり、便秘などが挙げられますが、いずれも腟がんに特有な症状ではありません。
検査・診断
がん検診の際は、通常細胞診を行いますが、細胞診でがんが疑われたときには、さらに詳しい検査として内診や直腸診、コルポスコープ診、組織診を行います。また、がんの広がりについて超音波検査、CTやMRIなどの画像検査により確認を行います。
コルポスコープ診(コルポ診)は腟と子宮腟部について拡大鏡(コルポスコープ)を用いて観察し、異常な領域がないか調べる検査です。コルポスコープないし肉眼で異常を認めた部位より小さな組織片を切り取り、病理医が顕微鏡で観察しがんの兆候がないか調べます。がんの兆候を認めた場合には超音波検査を行い、腟の中から超音波をあてて、腫瘍と周囲の臓器(子宮、卵巣、膀胱、直腸など)との位置関係やリンパ節への転移の有無について調べます。 また、CTやMRIなどの画像検査では、リンパ節転移 (リンパ節の腫れがみられます)、遠隔転移の有無、周辺臓器への広がりを調べます。一般にCTは全身のリンパ節や転移の有無を調べるのに適するのに対し、MRIは腫瘍と周囲の臓器との関係といった骨盤内の病変の広がりの評価に適しています。
上記の検査に基づいて腟がんの病期 (ステージ; がんの広がり具合を指します)を判定します。病期は下記の通りI期からIV期に分類されます。
I期:がんが腟壁に限局するもの II期:がんが傍腟結合織まで浸潤するが、骨盤壁には達していないもの III期:がんが骨盤壁にまで達するもの IV期:がんが小骨盤腔をこえて広がるか、膀胱、直腸粘膜を侵すもの IVA 期: 膀胱 および/または 直腸粘膜への浸潤があるもの および/または 小骨盤腔をこえて直接進展のあるもの IV B 期:遠隔転移を認めるもの
治療
治療方法は、がんの病期や組織型、腫瘍の位置 (腟の上部、中央、下部いずれにあるか)に加え、年齢、全身状態などの個々の患者さんの状況に応じて選択されます。腟がんの治療の原則は放射線療法であり、病変の広がり具合や位置によって手術療法が選択されます。また、放射線療法に化学療法 (抗がん剤)を併用する場合があります。
放射線治療では腟を通して腟がんのある部分(内部)に照射する方法(腔内照射)と体外からの放射線照射(外照射)、あるいは両者の併用による治療が病巣の状況に応じて行われます。放射線治療はがんの根治を目的とした治療の他、手術後に再発の危険性を減らす目的で補助的に行われたり、再発した場合や手術ができない場合に行われたりします。
手術療法ではがんがごく表面にとどまる場合にはレーザー蒸散術、部分腟壁切除術、腟切除術などが選択されますが、病変が進展している場合には広範囲の切除術が必要となります。腟中央部や下部1/3の病変を完全に摘出する場合には外陰部の広範囲な切除や骨盤除臓術 (腟腫瘍に加え膀胱や直腸を合わせて切除する)が必要となり、著しく生活の質を下げる可能性があるため、放射線治療が選択される傾向にあります。一方、腟上部1/3に病変があり、Ⅰ、Ⅱ期の場合には子宮頸癌と同様に広汎/準広汎子宮全摘術に加え、腟摘出術が選択されることが多い傾向にあります。
いずれも、腫瘍への治療効果や合併症について担当医と十分に話し合った上で、自身の状況に最も適した治療を選択することが重要です。
「腟がん」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください