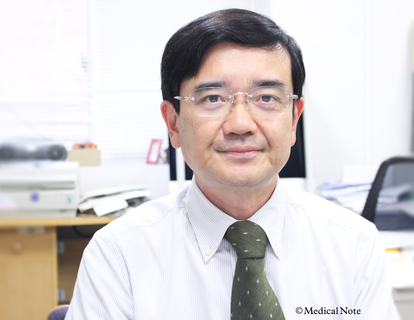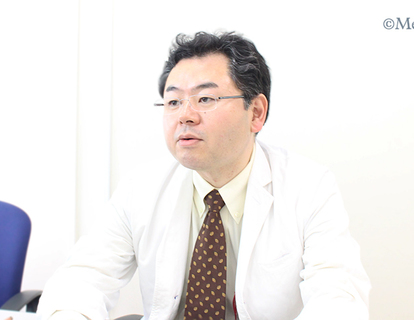概要
けいれん重積型(二相性)急性脳症とは、感染症の発症をきっかけとして脳の障害やけいれんを呈する病気です。特に生後6か月から1歳代に好発するとされ、国内の小児における感染症が誘因となる急性脳症のうち、もっとも多くの割合を占めるといわれています1)。
発症した場合、典型的には発熱に伴う長いけいれんを生じた後、意識状態が低下します。その後、数日にわたり一時的に意識状態は改善するものの、再度けいれんを起こすと共に悪化するのが特徴です。治癒した後も、約70%の患者さんには後遺症が残るといわれています。
明確な発症メカニズムは不明であるものの、遺伝子の型によって発症のしやすさに違いがあることが分かっています。
発症を認めた場合には、全身状態の管理やけいれんに対する薬物療法が行われるほか、回復期には後遺症に対するリハビリテーションが行われます。
原因
けいれん重積型(二相性)急性脳症の明確な原因は解明されていません。しかし、突発性発疹やインフルエンザなど、小児に好発する感染症(主にウイルスによるもの)をきっかけに発症することが分かっています。また近年では、けいれん重積型(二相性)急性脳症を発症しやすい遺伝子の型があることが分かり、複数の原因遺伝子が特定されています。さらに、気管支拡張薬のテオフィリンなど特定の薬がけいれん重積型(二相性)急性脳症の状態を悪化させる可能性があることも指摘されています2)。
症状
けいれん重積型(二相性)急性脳症では、発症して間もない急性期から、ある程度時間が経過した慢性期にかけて段階的に症状が変化します。
急性期(発症初日)
急性期には、突発性発疹やインフルエンザなどの感染症の発症初期に発熱に伴うけいれん発作を認めます。けいれん発作は多くの場合15分~1時間以上持続します(長時間続くけいれんのことをけいれん重積というので、けいれん重積型の急性脳症と呼ばれます)。一方、まれに短時間で消失することもあります。
また、けいれん発作に続き、多くの場合意識状態が悪化します。
一過性回復期(発症から2〜5日)
発症後2〜5日間は一時的に意識状態が軽快することがあります。しかし、完全に通常どおりの意識状態になるケースは少ない傾向にあります。また、患者によっては一過性回復期を認めないケースもあります。
けいれん反復期(発症から3〜6日)
多くの場合、発症から3〜6日程度たった時期に、体に部分的にけいれんを生じる焦点発作を認めます(急性期のけいれんから間隔をあけてまたけいれんが出現することから、二相性の急性脳症と呼ばれます)。焦点発作の程度は軽微で気付かないケースもあるものの、数日にわたって繰り返されます。
また、けいれん発作の再発と共に再び意識状態が悪化します。
回復期(発症から7日〜2か月)
けいれんの反復期を過ぎると、けいれん発作が消失して意識状態が徐々に改善します。しかし、手足、肩など体の一部が、本人の意思とは無関係に動く不随意運動などを認めることがあります。
慢性期(発症から3か月以降)
慢性期には、不随意運動などはほとんど認められなくなります。しかし、多くの場合、軽度から重度の知的障害や四肢の運動麻痺が残ります。また、意識がもうろうとして全身がガクガクと動いたり、突然手足がビクッと動いたりするてんかん発作を認めることも多い傾向にあります。
検査・診断
診断上特に重要なのはMRIなどの画像検査であり、けいれん重積型(二相性)急性脳症では、発症からの経過に応じて特徴的な所見が確認されます。頭部MRI検査では、急性期には画像異常を認めず、けいれん反復期になると大脳の白質に腫れが出現することが特徴です。
そのほか、ほかの病気との鑑別や身体状態を把握する目的で、血液検査や髄液検査*を行うことがあります。
また、脳波検査は診断に有用ではないものの、けいれんや意識障害を呈する大脳の機能をリアルタイムに確認することができるので、状態を評価するために行われることがあります。
*髄液検査:背骨の間に針を刺し、脊髄腔に流れる脳脊髄液を採取する検査。
治療
けいれん重積型(二相性)急性脳症に有効性が確立された治療法はなく、その時の症状に応じた処置や、けいれんを抑えるための薬物療法などが行われます。
薬物療法としては副腎皮質ステロイド薬を3日間大量に投与するステロイドパルス療法を行いますが、有効性は確立されていません。また、一部の患者さんに対しては脳の温度を平温(36℃程度)に保つ体温管理療法が有効とされる意見があるものの、十分な医学的根拠は得られていません1)。
回復期や慢性期には、てんかん発作に対する治療に加え、運動障害や認知障害に対するリハビリテーションが行われます。呼吸機能や飲み込み(嚥下)の機能が低下している場合には、必要に応じて食事介助や経管栄養が行われます。
参考文献
- 難病情報センター. ”痙攣重積型(二相性)急性脳症(指定難病129)”. 厚生労働省. 2023-10. https://www.nanbyou.or.jp/entry/4513. (参照 2024-02-29)
- 小児慢性特定疾病情報センター. “73 痙攣重積型(二相性)急性脳症”. 日本小児神経学会. 2018-01-31.https://www.shouman.jp/disease/html/detail/11_32_073.html. (参照 2024-02-29)
「けいれん重積型(二相性)急性脳症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「けいれん重積型(二相性)急性脳症」に関連する記事
 けいれん重積型(二相性)急性脳症の診断・予防・治療東京大学医学部大学院医学系研究科 国際保...水口 雅 先生
けいれん重積型(二相性)急性脳症の診断・予防・治療東京大学医学部大学院医学系研究科 国際保...水口 雅 先生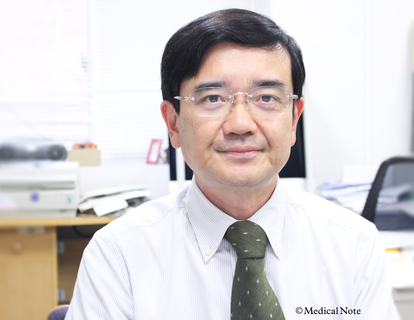 幼児の感染症に伴うけいれん重積型(二相性)急性脳症—原因・症状・後遺症東京大学医学部大学院医学系研究科 国際保...水口 雅 先生
幼児の感染症に伴うけいれん重積型(二相性)急性脳症—原因・症状・後遺症東京大学医学部大学院医学系研究科 国際保...水口 雅 先生 急性脳症とは? 突発性発疹による急性脳症の症状、予後、治療うさぴょんこどもクリニック 院長、千葉市...橋本 祐至 先生
急性脳症とは? 突発性発疹による急性脳症の症状、予後、治療うさぴょんこどもクリニック 院長、千葉市...橋本 祐至 先生 子どもの急性脳症の種類と症状ーけいれんに潜む重大な病気とは?神奈川県立こども医療センター 神経内科科長後藤 知英 先生
子どもの急性脳症の種類と症状ーけいれんに潜む重大な病気とは?神奈川県立こども医療センター 神経内科科長後藤 知英 先生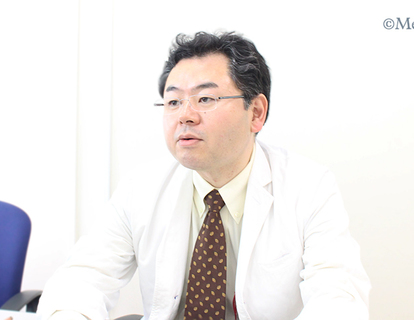 子どもがけいれん、ひきつけを起こしたらどう対応する?救急車は呼ぶべき?神奈川県立こども医療センター 神経内科科長後藤 知英 先生
子どもがけいれん、ひきつけを起こしたらどう対応する?救急車は呼ぶべき?神奈川県立こども医療センター 神経内科科長後藤 知英 先生