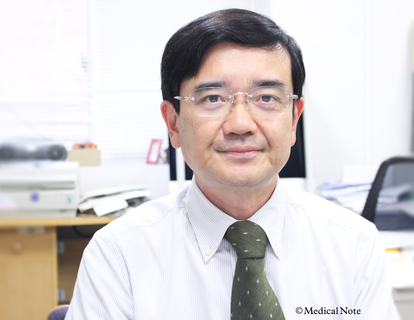概要
急性脳症とは、脳の炎症や脳出血、脳梗塞などの原因がないにもかかわらず、浮腫(むくみ)が生じて脳の機能に異常を引き起こす病気の総称です。乳幼児期に発症する頻度がもっとも高く、発症すると、意識状態が悪くなったりけいれんを起こしたりします。CT検査などでは大きな異常がみられないことも多いため、診断が難しいのがこの病気の特徴です。
急性脳症にはさまざまな原因があるものの、多くはインフルエンザなどの発熱を伴うウイルス感染症をきっかけに発症するものとされています。また、糖尿病や電解質バランスの異常、薬剤の影響、手術後の合併症として発症するケースも報告されています。
なお、急性脳症は発症すると約6%が死に至り、30%以上の割合で神経系に後遺症が残るとされています。発症した場合は脳のむくみやけいれんを改善するための投薬治療などを行い、原因となる病気が分かっている場合はそれらに対する治療を並行して行っていく必要があります。
原因
急性脳症は、脳に炎症、出血、梗塞などを認めないにもかかわらず、脳の広い範囲にむくみが生じる病気の総称です。
発熱性の感染症に伴う急性脳症では、インフルエンザや突発性発疹、マイコプラズマなどの感染症にかかった際に発症するとされています。感染症からどのようなメカニズムで急性脳症を発症するのかは解明されていませんが、炎症を引き起こすサイトカインと呼ばれる物質が多く生じることなどが原因と考えられています。
また、急性脳症は、糖尿病や尿毒症、肝機能異常などによって体に不要な老廃物が多くたまる代謝の異常、低ナトリウム血症などの電解質異常、薬剤の影響、心臓の手術による合併症などによって引き起こされることもあります。
症状
急性脳症を発症すると、脳の機能に異常が生じて意識障害やけいれん発作、幻覚や幻聴などの“せん妄症状”がみられる場合もあります。また、脳のむくみによって頭の中の圧が高まることで、吐き気や嘔吐、頭痛などの症状が生じるほか、生命の維持を担う脳幹と呼ばれる部位に影響が及んだ場合には、呼吸の異常などの症状を引き起こすこともあります。
検査・診断
急性脳症が疑われる場合は、以下のような検査が必要となります。
画像検査
脳の状態を評価するために頭部CTや頭部MRIなどによる画像検査が行われます。これらの画像検査では脳のむくみの状態を調べることができます。
血液検査
急性脳症はさまざまな原因によって引き起こされるため、炎症や代謝異常の有無などを調べたり、全身状態を把握したりするために血液検査を行うのが一般的です。また、感染症の関与が疑われる場合は、抗体などを調べることで原因となっているウイルスや細菌の特定の手助けとなることもあります。
髄液検査
髄膜炎の有無や頭の中の圧を調べたりする目的で髄液検査を行うことがあります。ただし、脳腫瘍などが原因で脳の圧が著しく高まっている場合は、髄液検査を行うことで脳の一部に重大なダメージが生じる脳ヘルニアを誘発することがあります。行う前には画像検査で脳の状態を確認することがすすめられます。
脳波検査
急性脳症ではけいれん発作が生じることがあるため、てんかんを引き起こすほかの病気と区別するために脳波検査を行うことがあります。脳波検査とは、大脳の表面に発生しているわずかな電気を、頭皮に貼り付けた電極で記録する検査です。
治療
急性脳症と診断された場合は、原因となる病気の治療と脳のむくみやそれに伴う症状を改善するための対症療法が必要となります。
原因となる病気の治療としては、インフルエンザウイルス感染症の場合は抗インフルエンザ薬の投与、アンモニアなど体内にたまった老廃物の排泄を促す治療、電解質バランスを改善する治療などが挙げられます。また、効果は確かではないものの、感染症など過剰な免疫のはたらきが原因と考えられる場合は、免疫のはたらきを抑えるステロイドの投与が行われることもあります。
一方、脳のむくみやこれに伴う症状への対症療法としては、利尿薬や抗けいれん薬の投与のほか、重症の場合は人工呼吸器による全身の管理などが必要です。また、一部の施設では脳低温/平温療法などを試みることもありますが、急性脳症の確立した治療法はないのが現状です。
予防
急性脳症の多くは感染症が関与していると考えられています。そのため、インフルエンザや麻疹などのようにワクチンがあるものは予防接種を受けることが推奨されています。なお、解熱薬(非ステロイド性抗炎症薬)の種類によっては、急性脳症を悪化させる可能性があるとされているため、発熱があっても自己判断での服薬はしないようにしましょう。
そのほか、急性脳症は糖尿病、肝機能障害、電解質異常などによって引き起こされることもあるため、これらの病気がある場合は適切な治療を継続していくことも大切です。
「急性脳症」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「急性脳症」に関連する記事