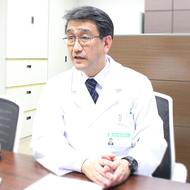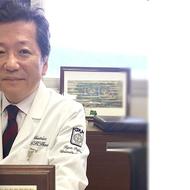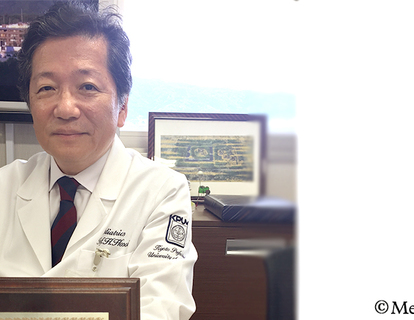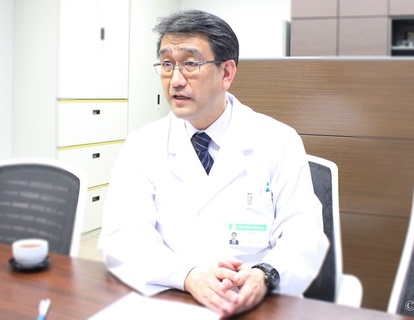概要
神経芽腫とは、自律神経の1つである交感神経から発生する腫瘍です。1歳までの乳児に発生することが多く、日本では毎年約150~200名が神経芽腫と診断されています。
交感神経細胞が存在する交感神経節や、腎臓の上に位置する副腎に発生する頻度が高いと報告されており、お腹が大きく膨れるなどの腹部症状のほか、進行状況によって発熱や貧血などの症状が現れることがあります。
神経芽腫は、良性のものから転移しやすい予後不良のものまであり、治療方法は腫瘍の悪性度などによって異なります。診断時の年齢が1歳未満の場合、予後は良好であるといわれています。
原因
神経芽腫を発症する原因は多くが不明とされています。
しかし、MYCNという遺伝子の増幅や染色体数の異常が予後を左右する重要な因子であるとの報告があります。
症状
発生初期の段階ではほとんどが無症状ですが、進行するとお腹が異常に大きい、お腹に硬いしこりがあるといった症状がみられる場合があります。
転移している場合は、発熱や貧血、頻繁にぐずる、歩かない、まぶたが腫れる、骨の痛みなど転移した部位によってさまざまな症状がみられます。
検査・診断
神経芽腫が疑われる場合には、まず尿検査と血液検査を実施します。
神経芽腫では、カテコールアミンという物質を産生する腫瘍細胞が増殖します。カテコールアミンは、体内で代謝されたのち、尿中にHVA(ホモバニリン酸)やVMA(バニリルマンデル酸)として排出されるため、一部の神経芽腫を除いて、尿検査で濃度を確認できます。血液検査では、NSE(神経特異エノラーゼ)、LDH、フェリチンなどが高値を示すことがあります。
血液検査や尿検査で神経芽腫が疑われる場合は、超音波検査や単純エックス線検査、CT、MRIなどの画像検査を行って腫瘍の発生部位を特定します。また、放射性同位体(ラジオアイソトープ)を利用したMIBGシンチグラフィ検査で、腫瘍の発生部位や全身への転移の有無を調べるほか、必要に応じて骨髄検査を行って骨や骨髄に転移していないか確認することもあります。
確定診断にあたっては、摘出した腫瘍や生検で一部採取した腫瘍組織を顕微鏡で確認する病理診断が必要です。また、治療方法を決定するために、採取した組織を使ってMYCN遺伝子の数を確認する遺伝子検査も併せて行います。
治療
神経芽腫には、自然と小さくなる良性のものから、転移を起こしやすい予後不良のものまであり、腫瘍の悪性度や進行具合によって治療方法は大きく異なります。
日本では、神経芽腫国際病期分類(INSS分類)による臨床病期*、年齢、腫瘍の遺伝子診断(MYCN遺伝子増幅や染色体数の異常など)、国際病理分類に基づいて、低リスク、中間リスク、高リスクの3つに分類されます。このリスク分類に応じて、治療方法が決定されます。
低リスク群の場合、通常は腫瘍摘出手術のみの治療となります。周囲の臓器との関係で診断時に腫瘍全摘出が難しい場合などは、手術に先立って抗がん薬を用いた比較的軽度の化学療法を行う場合もあります。
中間リスク群の場合、中等度~強度の化学療法を行い、腫瘍を小さくした後に手術を行います。
高リスク群の場合、原発腫瘍が周囲の臓器や血管を巻き込んでいたり、転移していたりすることが多いため、抗がん薬による化学療法や手術による外科療法、放射線療法の組み合わせによる集学的治療が必要です。まずは強力な化学療法を行い、原発巣ならびに転移巣の腫瘍を小さくした後、手術での全摘出を目指します。術後は、化学療法の継続や自家造血幹細胞移植を併用した抗がん薬治療**を行い、原発腫瘍を切除した部位には放射線照射が行われます。近年は化学療法と自家造血幹細胞移植後に、手術と放射線照射を行う方法(遅延局所療法)も行われており、2021年からは神経芽腫表面に存在するジシアロガングリオシド(GD2)を標的とした抗GD2抗体療法が保険認可されています。
*近年さらに新しい分類として、治療前の画像診断を加えた国際神経芽腫リスクグループ病期(INRGSS)も利用されている。
**患者自身の造血幹細胞を前もって採取しておき、強力な抗がん薬治療を行ったのちに移植を行い、正常な造血機能を回復させる治療方法。
「神経芽腫」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください