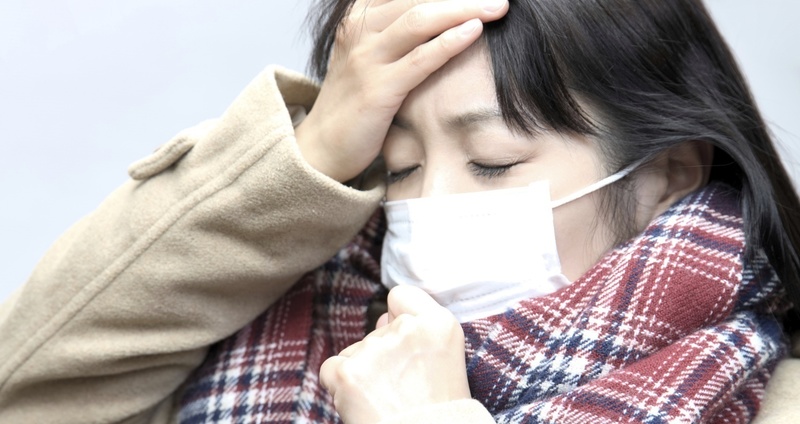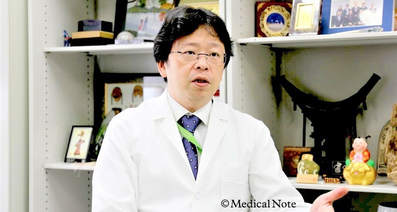
体調が優れないとき、私たちはしばしば「かぜだと思う」と、病院や薬局で伝えることがあります。果たして、その症状は本当にかぜによるものなのでしょうか。一般社団法人Sapporo Medical Academy代表理事で感染症コンサルタントの岸田直樹先生は、医療者もまた、かぜという用語を誤って使用することがあるとおっしゃいます。この記事では、かぜの定義と、定義づけをする必要性についてお話しいただきました。
かぜの定義-自然によくなる上気道のウイルス感染症
かぜは私たちが最も日常的にかかりやすい病気であり、体調が優れないと「かぜをひいた」と考えがちです。しかしそれは本当にかぜなのでしょうか? かぜとはどのような病気なのでしょうか。どのような症状があれば、かぜと言うことができるのでしょうか。ここでは、まずはかぜとはどのようなものであるのかという定義について述べていきます。
かぜの定義は、「自然によくなる上気道のウイルス感染症」のことをいいます。臨床的な上気道とは、喉と鼻、肺の手前にある気管支のことを指します。そして感染症とは、菌やウイルスといった微生物が体内に侵入し、感染し増殖することで発症する病気のことです。つまり、かぜとは上気道のウイルス感染症であり、下痢だけなどではかぜとはいわないということになります。
主な症状としては、鼻水・のどの痛み・咳・発熱・くしゃみなどがあげられます。しかし、逆にこれらの症状が見られたからといってかぜとはいえず、他の病気の可能性もあります。かぜに似た症状を出す病気は、ウイルス以外の呼吸器の感染症やそれ以外にもあり、この鑑別を行うのは医療者の重要な役割となります。また、かぜは自然によくなるという特徴を持っているので、症状が長引く場合は、かぜではない可能性があると考えられます。
かぜの定義は、他の疾患との鑑別のために重要
先ほど、下痢はかぜではないと述べましたが、実際に医療者の中には「お腹のかぜ」というような表現を用いて説明する人もいます。確かに、下痢はウイルス性胃腸炎、つまり自然によくなる腸のウイルス感染症のひとつの症状ですから完全に間違いとはいえませんが、ここでは「ウイルス性胃腸炎」と診断するのが正しいといえます。なぜなら、医療者は「どこまでがかぜか?」ということを明確にすることで、先に述べたように、かぜ以外の疾患との鑑別をする必要があるからです。下痢までかぜに含めてしまうと、かぜというカテゴリーが広くなってしまい鑑別が難しくなります。
例えば、咳とのどの痛みと鼻水が出ていればかぜ(ウイルス性上気道炎)とし、嘔気・嘔吐や腹痛、下痢がある場合には、診断はウイルス性胃腸炎であるとします。この場合は、症状もわかりやすいですが、実際には頭痛や倦怠感、関節痛などそのほかの症状もあり、複雑になります。このとき医療者は、「どこまでがかぜか?」を見極め、症状や検査から鑑別をしていきます。そうすることによりスムーズに適切な治療が進み、早く治ることにつながります。ですから、かぜの定義はできるだけ曖昧にせず、「自然によくなる上気道のウイルス感染症」のみを指すこととし、重要なのはウイルス感染の部位を広げすぎずに、上気道のみに絞り、その症状がきちんとあるかどうかと考えることです。
*本記事は岸田直樹先生の著書「総合診療医が教える よくある気になるその症状 レッドフラッグサインを見逃すな!」を参考にしています。
感染症コンサルタント 、北海道科学大学 薬学部客員教授、一般社団法人Sapporo Medical Academy(SMA) 代表理事
岸田 直樹 先生日本感染症学会 感染症専門医・指導医日本内科学会 総合内科専門医日本化学療法学会 抗菌化学療法指導医 ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター
“良き医学生・研修医教育が最も効率的な医療安全”をモットーに総合内科をベースに感染症のスペシャリティを生かして活動中。感染症のサブスペシャリティは最もコモンな免疫不全である“がん患者の感染症”。「自分が実感し体験した臨床の面白さをわかりやすく伝えたい」の一心でやっています。趣味は温泉めぐり、サッカー観戦(インテルファン)、物理学、村上春樹作品を読むこと。 医療におけるエンパワメントを推進する法人を立ち上げ活動している。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
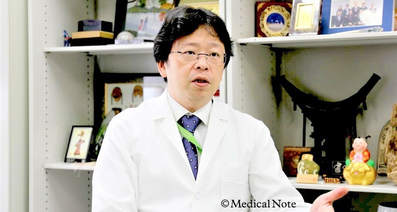

かぜだと思ったのに-かぜに似た別の病気には何がある?
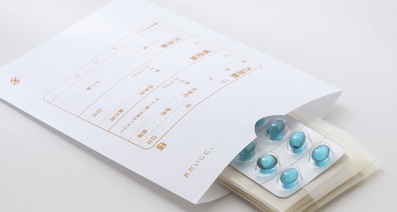
典型的なかぜに罹ったとき、病院や薬局ではどのような薬が処方される?
関連の医療相談が10件あります
キライディティ症候群とはどのような病気ですか。
人間ドックで、胸部CTで、キライディティ症候群疑いとの診断が出ました。(毎年受診していて今年初めて診断されました。) どのような病気でしょうか。診断には、「高血圧、胸痛などの症状があるときは、循環器内科を受診してください」とありましたが、高血圧は10年以上前から服薬で治療中です。胸痛の場合、どのような痛み(鈍い、鋭い、刺すような、胸のどの辺り等)になりますでしょうか。 体の倦怠感はあるのですが、関連する可能性がありますでしょうか。
血圧が高い
病院で血圧を測定したら 上140 下92 心拍数114 とかなり高い数値になりました。 乳児を抱いていたので、子がボタンを押さないよう抑えたりしながらではありました。 また妊娠中から白衣症候群で病院だと緊張していつも高かったです。 ただ、今までにない高さだったので心配です。 正しく計測ていない可能性はありますか?
チック症は治りますか?
突然、しゃっくりのような変な声が出たり身体が痙攣したりするようになってしまいました。 病名はまだわかっていませんが、病院ではもしかしたら「チック」かもと言われました。 もう3ヶ月近くずっと治っていなくて、薬もあまり効いていません。 声が出てしまうので職場でひどく目立ってしまい、周りから心配されます。 今後症状が治らない場合は仕事を続けるにしても周りに迷惑がかかるし、リモートワークも可能になってはいますが永久にそれだけでは今の仕事を続けるわけにいかないのでは…独身なので人と関わらないのは辛いし… と不安です。。 薬が効かない場合は治療法はないのでしょうか…?
生理前の貧血や不整脈
生理前に貧血のような症状(立ちくらみ)が起こります。目の下は白いです。 しかし生理不順なので2週間以上続いたりします。 また、不整脈の自覚症状も増え不快なのですが、これは仕方のないことなのでしょうか? 原因や対策など教えていただきたいです。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「かぜ症候群」を登録すると、新着の情報をお知らせします