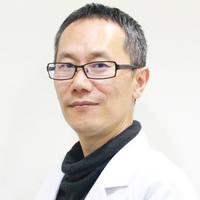がんなどの深刻な疾患に罹患すると、その病気自体が苦痛を引き起こすだけでなく、治療の副作用による吐き気や、不安による精神症状など、様々な原因による「いたみ」が現れることがあります。これらの苦痛を最小限に抑えるためには、主治医だけでなく、症状緩和を専門とする医師の手が必要になります。「いたみ」の種類によっては、精神科医の要請が必要なときもあります。そのため、聖隷三方原病院の緩和支持治療科では、患者さんを最も近くでみる看護師が、様々な職種に役割を振る「看護師中心のチーム医療」を実践しています。具体的な治療の流れと関わるスタッフの役割について、聖隷三方原病院副院長の森田達也先生にお話しいただきました。
看護師中心の医療と多職種連携-緩和支持治療の実際

聖隷三方原病院の緩和支持治療科では、「看護師中心」の治療が行われています。本項では、初診時からの具体的な流れと、いつ誰がどのように患者さんに関わっていくのかを解説していきます。
※以下はあくまで一例です。
主治医の先生などから患者さんを診てほしいと要請があったとき、つまり初診の際には、私たち専門医と看護師の2名が患者さんのもとに診察に行き、アセスメントを立ててその場で薬剤等を処方します。薬剤の処方は主治医の先生にお願いすることもあります。
翌日からは看護師が1人でフォローアップを行い、医師は週1回ほどのペースで定期的な診察を行います。(※ここでいう医師とは緩和支持治療科医のことで、主治医ではありません。)
症状緩和がうまくいっておらず、アセスメントの立て直しが必要な場合は、看護師が医師に連絡を入れます。
つまり、基本的には患者さんの主治医と、緩和支持治療科の看護師の2人体制で治療が進んでいくということです。
患者さんを最も近くでみている看護師が様々な職種に役割を振る
緩和支持治療を進めていくなかで、患者さんの身体症状は落ち着いてきたものの、新たに精神症状が出てきたときは、看護師が精神科医を呼ぶこととなります。
このように、当科では看護師が様々な職種に役割を振る「看護師中心の緩和支持治療」が実践されており、患者さんのケアの8割程度を看護師が行っています。そのため、当院で緩和支持治療科に配属される看護師は、10年以上のキャリアを持ち、医療チームを回せるだけの能力を有している優秀な方が多いという特徴があります。
日本では看護師に処方権はありませんが、私たち専門医が看護師からの連絡を受けて駆けつけたときには、既に薬の想定等が終わっており、患者さんやそのご家族の価値観に寄り添った提案ができる状態にあるということがほとんどです。
私たち専門医の役割とは、その提案や患者さんの訴えを聞くだけでなく、専門的な検査をして、対応法が適切かどうか、また、他の侵襲処置の必要性はないかどうかを見極め、医学的なアセスメントを立てることです。
緩和支持治療=集学的治療

また、薬剤師も大いに活躍しており、彼ら彼女らの服薬指導も、患者さんから高い評価を得ています。服薬の方法を記した用紙を渡すのではなく、朝昼晩と服薬のタイミングをわかりやすく記すなどの工夫をしており、飲み間違いや飲み忘れを防ぐ一助となっています。
また、当科はペインクリニックとも連携しているため、神経ブロックが必要なときにはすぐに対応することも可能です。年に数件しかない稀な例ですが、オピオイド鎮痛剤の副作用が強く出てしまう患者さんには、くも膜下投与を行うこともできます。
以上のように、多職種が連携して患者さんを支える土壌があることは、患者さんの苦痛を最小限にとどめ、QOLを向上させるために極めて重要です。真に患者さんにとって包括的な緩和支持治療とは、様々な専門家の叡智を結集させた集学的治療であると考えます。

緩和支持治療を専門とする医療スタッフに求められる資質
コミュニケーション力とは価値観に対する幅の広さである
緩和支持治療を専門とする医療スタッフに求められるものは、コミュニケーション力であると考えます。コミュニケーション力というと漠然としてしまいますが、私はこれを「価値観に対するキャパシティの広さ」であると考えています。
たとえば、鎮痛剤に焦点をあてて考えてみましょう。教科書的には、即効性の高いレスキュー・ドーズを1日に4回や5回も服用しなければならないような場合であれば、症状がよくないと判断し、他の薬剤を増やすことが正しいとされます。
しかし、患者さんの中には、「この薬を1日○回飲むペースを崩したくない」「この薬を気に入っており、○回飲んでいると症状がよくなるように感じる」という方もおられます。
このとき、患者さんの説得に入るチームと、「それでもよいね」と許容するチームがあり、前者は患者さんとの関係がもつれてしまう傾向があります。専門的な視点からみて健康に害がないようであれば、教科書通りの処方にこだわりすぎる必要はありません。患者さんの多様な価値観を受容して効果的な治療を進められるチーム、それこそが、この領域においてはコミュニケーション能力の高い医療チームといえます。
主治医としての緩和ケアと、緩和支持治療科医のケアの違い
記事1「抗がん剤の副作用など、治療による痛みや吐き気の緩和や告知直後の不安をケアするために」でも触れましたが、緩和支持治療科の医師には「引き出しの多さ」が求められます。患者さんの主治医として緩和ケアを行うときには、使用する薬剤も限定されますし、自分が得意とする処方の仕方を選ぶこともできます。
しかし、緩和支持治療科の医師は、主治医から相談を受ける側の医師です。緩和支持治療科の医師が、「私はモルヒネ以外を用いた緩和法については詳しくない」というようでは、主治医の先生たちからの信頼も得られません。
引き出しを増やすには、長期にわたり経験を積むことが大切です。
私は医師となってから長らくホスピス、緩和支持治療科の医師としての経験を蓄積してきましたが、それでも過去に4~5件しかみたことがない稀な症例についてコンサルテーションを受けることもあります。たとえば、上位頚椎に腫瘍の転移が生じており、患者さんを動かすと横隔神経麻痺になりかねない症例について相談を受けたこともあります。
患者さんをどの程度動かしてもよいのかと主治医の先生から聞かれたとき、答える側の医師も「わからない」といっていては、コンサルタントとしての意味がありません。主治医の先生も、自分たちとは異なるスペシャリティを持った「プロ」相手でなければ、相談しようと思わないでしょう。
このような経験から、実務経験に基づく知識の蓄積は非常に重要であると考えます。
緩和支持治療の今後の課題と展望
森田達也先生自身の課題-緩和ケアの臨床研究をできる人材育成を

私はこれまで緩和ケアの臨床研究を続けてきましたが、今、続々と研究に取り組みたいという後輩たちが出てきています。そこで、私自身の課題として、全国的なネットワークを作りたいと考えています。施設にとどまることなくより広い規模で、緩和ケアの臨床研究をできる人材を育てていくことが、個人としての当面の目標です。
慢性心不全の患者さんに対する緩和ケアの確立
また、病院単位での緩和支持治療に関する課題もあります。
本記事では、主に「がん患者の緩和支持治療」について記してきました。今、がん領域の緩和支持治療体系はほとんど確立されているといってよく、今後は現状+αの改良が加えられていくことでしょう。そのようななかで、症例数も多く循環器科の先生方からも解消が必要な課題として提言されているのは、慢性心不全の患者さんの緩和ケアです。
慢性心不全の場合、症状自体はオピオイドの投与などで緩和できるため、治療の内容は比較的シンプルです。
しかし、慢性心不全の患者さんのなかには、突然容態が急変してしまい、ご家族がお別れをいえないまま亡くなってしまう方などが多々いらっしゃいます。
循環器系の疾患がみつかった際に、患者さんと医師が「最期」に関する話まですることは、全国的にみてもほとんどありません。しかし、患者さんやご家族にとって満足のいく終末期を送るためには、外来診療のなかに、症状が悪化してきたときのことをお話しできる体制を組み込んでいくことが必要です。病院全体で対応を進め、後悔が残ってしまう慢性心不全の患者さんとご家族を減らすことが、現在私たちに求められている課題であると考えます。
聖隷三方原病院 副院長、聖隷三方原病院 緩和支持治療科部長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。