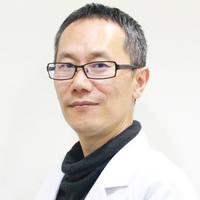「緩和ケア」と聞くと、がんが進行し、根治的な治療が難しくなった場合に行われるものとイメージされる方も多いかもしれません。しかし、深刻な病気に伴う苦痛は必ずしも病期が進んだときだけに起こるものではありません。告知直後に大きな不安に襲われ眠れなくなる方や、抗がん剤治療を開始する前に嘔気を訴える方などもいらっしゃいます。聖隷三方原病院緩和支持治療科部長の森田達也先生は、「症状を和らげるための治療は、時期を問わず、必要とされたタイミングで行うものである」とおっしゃいます。病気に伴って生じる苦痛を最小限に抑えるための治療の在り方と工夫について、森田先生にお話いただきました。
緩和ケアと緩和支持治療の違い-支持治療とは何か?
聖隷三方原病院の「緩和支持治療科」という名称は、緩和治療と支持治療を組み合わせて作ったものです。末期がんの患者さんなどに対して行われる「緩和治療(緩和ケア)」という概念は、この数年で一般の方にも広く浸透し始めています。しかし、「支持治療」という言葉については、耳馴染みがないという方も多いでしょう。
本項目では、この2つの概念について整理して解説します。
緩和治療(パリアティブケア)
緩和治療とは、「深刻な疾患に直面した患者さんとご家族のQOLを向上させる治療」であると、WHOにより定義されています。つまり緩和治療とは、患者さんが生命を脅かす病気に現在進行系で対峙しており、それにより生じる苦痛を和らげるために行われるものなのです。英語では緩和治療をパリアティブケア(palliative care)といいます。
支持治療(サポーティブケア)
一方、支持治療は、抗がん剤治療など、病気の治療によって生じる副作用などを取り除く目的で行う治療が主となります。このほかに、栄養治療やリハビリテーションなども、支持治療に含まれます。世界では、支持治療はサポーティブケア(supportive care)と呼ばれ、パリアティブケアと明確に区別されています。ヨーロッパ腫瘍内科学会では、支持治療を「全ての患者さんのQOLを向上させる治療」と定義しています。
日本ではこれまで両者の概念を明瞭に区別しておらず、緩和治療の中に支持治療も含まれるといった、やや曖昧な形で言葉を使用していました。
サポーティブケアの必要性が日本でも広がり始めている
近年、緩和治療の概念が日本で急速に広まり、「診断時早期からの症状緩和治療を」という声が上がり始めました。これを受け、日本にもサポーティブケアという概念が必要だと考えた専門家たちが増えました。最近では、「がんサポーティブケア学会」が立ち上げられるなど、少しずつ支持治療の概念も広がりつつあります。そのため、他の大学に新たに設けられた講座では、「緩和支持治療科」といった名称が用いられるようになっています。
当科では、もともと緩和治療と支持治療の双方をチームとしてまとめて行っており、そのコンセプトを明瞭化するために「緩和支持治療科」という名称を使っています。
患者さんへの自己紹介の工夫-患者さんが困っていることを治す医師であると名乗る

しかしながら、支持治療と緩和治療を区分することは、患者さんにとってはあまり意味をなさないため、私自身はこの名称に特別なこだわりは持っていません。
病期や苦痛の原因に関わらず、主治医だけでは除去できない苦しみや痛みが生じたときには、常に当科が要請されます。そのときに、「緩和支持治療科の医師です」と名乗っても、名称が漠然としているため、患者さんは困惑してしまうでしょう。
ですから、私は患者さんが「今現在困っていること」について、アプローチするために来た医師であると名乗るよう、日頃から心がけています。
たとえば、
「主治医の○○先生に痛みが取り切れないといわれて来た、痛み担当の医師です。」
「主治医の△△先生から要請を受けた、吐き気止めを調整する医師です。」
といったように自己紹介すると、患者さんにも私たちがどのような立ち位置の医師であるかイメージしやすいようです。主治医が変わるわけではないことや転科するわけではないことも伝わるため、患者さんに不用意に不安を抱かせてしまうことも防げます。
緩和支持治療は時期を問わずいつでも受けられる-早期にこだわる必要はない
2010年、アメリカの医師たちによる論文、『早期からの緩和ケアによって患者の生存期間が延長する可能性がある』が、医学雑誌New England Journal of Medicineに掲載されました。この研究はステージ4の肺がん患者を対象に行われたものです。研究の結果、転移の診断後に標準治療のみ受けたグループよりも、緩和治療を併せて受けたグループのほうが、生存期間が有意に長くなるということが明らかになりました。これを機に、緩和治療は診断後早期に行うことが望ましいと盛んにいわれるようになったのです。
緩和支持治療を必要とする時期は、人それぞれ異なる
しかし、患者さんの病状や価値観、病気の捉え方は個々人により異なるため、「診断後すぐ」といった画一化はしないほうがよいと考えます。
私たちは、患者さんが苦しい、あるいはしんどいと感じる症状が出たら、「その時期を問わず」治療にあたります。
たとえば、がんだと告知された直後、身体症状は出ていなくとも、不安で夜眠れないという訴えがあれば、当科が対応します。
また、抗がん剤治療を行う前から、予期せぬ嘔吐や吐き気に悩まされる方もいます。「告知を受けたことを子どもにどのように伝えればよいのか」、「民間療法に関して質問がある」、このような悩みや疑問にも、私たちは対応しています。
画一的な「早期治療」は患者さんの不安を煽ることにも繋がりかねない

一方で、診断を受けた直後には、治療や助言が必要な心身症状が出ない方もおられます。そのような患者さんに対し、医師が良かれと思って「これから具合が悪くなることもあるので」と緩和支持治療科の医師を紹介してしまうと、患者さんは「これから自分は非常に辛い体験をするのではないか」と不要な恐怖心を抱いてしまうこともあります。
ですから、診断後早期の治療は、学問上では重要な概念ですが、臨床の場においてはこだわりすぎないほうがよいといえます。
がんの告知を受けた直後から心身に症状が現れる方は多くはない
告知直後に緩和が必要な症状が現れる患者さんの割合は、全体の1~2割程度です。たとえば、身内の方が過去にがんを患っており、激しい痛みなどを訴える様をみてこられた「がん恐怖」のある患者さんなどが、この1~2割に該当します。病気が進行すると、緩和支持治療を必要とする方は増え、最終的には全患者さんの半数ほどが治療を受けられます。しかし、どのタイミングで私たちの手が必要となるかは、病期など、画一化された時期で決められるものではありません。
緩和支持治療科ではどのような症状を和らげられる?
聖隷三方原病院では、疼痛や消化器症状、呼吸器症状など、治療対象となる症状と治療法をまとめた「症状緩和ガイド」を作成し、これをもとに緩和支持治療を行っています。電子カルテにも症状緩和ガイドが連携されているため、基本的なこと(医療用麻薬の処方など)は主治医の先生でも対応でき、また人的なミスを防ぐこともできています。
(詳細:聖隷三方原病院 症状緩和ガイド)
そのため、当院の緩和支持治療科が力を発揮するのは、一般的な症状緩和法では苦痛が除去できず、アセスメントを立て直す必要がある時など、他科の先生では対応できない難しい苦痛が生じたときが多くなっています。
また、患者さんに医学的な問題ではない「不安」や「不満」があるとき、お話を聞くのも私たちの役割です。
患者さんが今何をしてほしいのかを聞き出し、その症状にピンポイントで対応する

緩和支持治療科で対応することが多い代表的なケースは、患者さんの痛みや苦しみが、1日のうち一時的に強く生じるという場合です。
たとえば、常に小さな痛みがあり、明け方になると強い痛みが現れる場合、より細かなアセスメントが必要になり、主治医のチームのみでは対応できないことがあります。
患者さんの痛みの訴えのみに基づき、ベースとなる鎮痛剤の処方量を増やしてしまうと、副作用により眠気が増してしまったり、うまく喋ることができなくなることがあります。
しかし、患者さんご自身が「どの時間帯が最も痛い」と自発的に訴えることは、ほとんどありません。
ですから、いつ疼痛が最も強くなるのかを聞き出し、最も効率的な緩和法を考え、患者さんの苦痛に「ピンポイント」で対応するのが私たちの役目となります。
使用する薬は全て保険診療で使えるものですので、何か特別な武器を持っているわけではありません。しかし、このようなピンポイントでの対応を行うためには、多くの引き出しを持っておらねばならず、緩和支持治療科の医師には豊富な経験の蓄積が求められます。また、緩和支持治療の現場においては、専門医だけでなく看護師や薬剤師の活躍とチームワークも不可欠です。
次の記事では、当科が実際に行っている治療の流れや、各医療スタッフの役割についてお話します。
聖隷三方原病院 副院長、聖隷三方原病院 緩和支持治療科部長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。