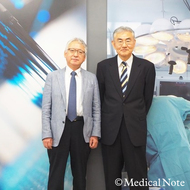概要
老人性難聴とは、加齢以外に特別な原因がない難聴を指します。加齢による組織変化のうち、主に音の信号を感知する耳の中の細胞減少により引き起こされる聴力低下を、“老人性難聴”または“加齢性難聴”などと呼びます。聴力低下には左右差がなく、特に高い音から聞こえにくくなるのが特徴です。60歳代後半頃から症状が現れる人が多く、80歳になると男性では8割以上、女性では7割以上の人が老人性難聴を示すとされています。
老人性難聴は進行すると日常生活に支障をきたすことも少なくありません。しかし、進行を止める方法や明確な治療法は解明されておらず、聞こえの不足を補う“補聴器”の装着が主な対処法です。
原因
老人性難聴の主な原因は、耳の奥にある“蝸牛”と呼ばれる器官の中の感覚細胞が、年齢を重ねるごとに減少するためと考えられています。感覚細胞は、耳の穴から入ってきた音の刺激を感知する役割をしています。そのほかに蝸牛から脳まで音の信号を伝える神経細胞の減少や変性、脳そのものの加齢変化も、老人性難聴の“聞こえにくさ”に関与しています。
加齢によって感覚細胞や神経細胞が減少する明確なメカニズムは解明されていませんが、遺伝的な背景、高血圧症・糖尿病・動脈硬化などの健康要因、音響曝露(大きな音にさらされること)や喫煙習慣などの生活習慣などが関与していると考えられています。特に長期間にわたって大きな音を耳にする機会が多いと、早期に老人性難聴が現れたり進行したりしやすいとも考えられています。
症状
老人性難聴は、特に高い音から聴き取りにくくなるのが特徴です。高い音域の成分を含む“さ行”と“か行”が聞き取りにくくなることが多く、雑音の中での音の聞き分けも苦手になります。このため、日常会話に支障をきたすことも少なくありません。音を聞き取って理解しながら会話をする能力は、単純な聴力だけでなく、さまざまな脳の機能も必要です。一般的に年齢を重ねると、会話に必要なことばを聞き取って理解する能力も低下していくため、音そのものの聞こえの低下と、ことばを正確に聞き取る力の低下が相まって会話が困難になるのも老人性難聴の特徴であると考えられています。
また、老人性難聴は進行すると高い音だけではなく日常的な会話に必要な高さの音も聞こえにくくなります。さらに慢性的な耳鳴りを自覚する人も多いとされています。
検査・診断
老人性難聴が疑われるときは、次のような検査を行います。
聴力検査
ヘッドホンを耳に当て、高さが異なる音の聞こえの程度を評価する検査です。老人性難聴は初期段階では高い音が聞こえにくくなりますが、進行すると低い音も聞こえにくくなります。
併せて耳の後ろの骨に音の振動を当てる“骨導検査”を行い、外耳、中耳、内耳または内耳より奥のいずれの領域に問題がある聴力低下なのかを評価します。
画像検査
聴力の低下は脳梗塞などの加齢によって発症率が高くなる病気によって引き起こされることがあります。そのため、老人性難聴以外の病気が疑われる場合は頭部CTや頭部MRIなどによる画像検査が必要となります。
治療
老人性難聴は音信号を伝える感覚細胞や神経細胞の加齢変化によって引き起こされる状態です。そのため、聴力を回復させる方法は明確には確立されていません。
しかし、老人性難聴は進行すると日常会話などに支障をきたすこともあるため、聴力低下が著しい人や日常生活が困難な人は聴力を補うための“補聴器”を装着して対処する必要があります。
補聴器にはさまざまな形状があり、近年では環境音を抑えて会話の音を大きくするといった機能が備わったタイプのものもあります。補聴器は聴力の程度や使用する場面など個人に合ったものを選択することが大切です。
一方で、近年ではES細胞やiPS細胞を用いて加齢によって失われた音の感覚細胞を再生させる治療の開発が進められており、今後の発展が期待されています。
予防
老人性難聴は加齢による生理的な変化による症状であるため、完全に予防する方法は今のところありません。
しかし、老人性難聴は動脈硬化や騒音への長期的な曝露によって発症リスクが高まるとの報告もあるので、体全体の健康状態を良好に保つことが予防に有用で、動脈硬化の原因となる暴飲暴食、運動不足、禁煙などの生活習慣を改め、環境を整えることが大切と考えられています。
「加齢性難聴」を登録すると、新着の情報をお知らせします