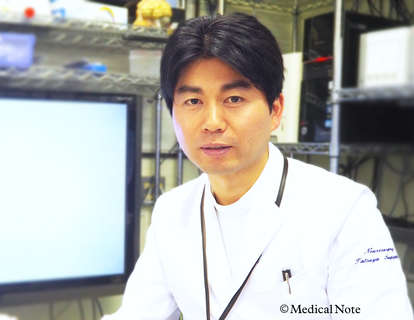概要
もやもや病とは、首から脳へ血液を送るための内頚動脈が脳内に入ったところで狭くなっていき、やがて閉塞していく病気です。閉塞していく血管の通り道を補うように周囲の細い血管が網目状に発達し(側副血行路の1つ)、それが画像検査で“もやもや”した塊に見えるため、もやもや病と呼ばれています。通常は左右両側にみられ、発症年齢は10歳以下の子どもと40歳前後の成人が多いとされています。この病気は進行性で、原因ははっきり分かっておらず、厚生労働省の指定難病の1つになっています。
血管の狭窄や閉塞の進行に対して側副血行路の発達が追い付かない場合は、脳の血流が低下します。特に小児では、楽器演奏や熱い物を食べるときに息を吹きかける動作によって脳の血流低下が強くなり手足の麻痺や言語障害が生じ、一定時間経過すると回復するという症状がみられます。
脳の血流が不足した状態がさらに進行すると、やがて脳梗塞を引き起こします。成人の場合は、発達した側副血行路への負担が増して破綻することで脳出血を起こすケースが多いといわれています。慢性的な頭痛に悩まされて学業や日常生活に支障が出ることや、高次機能障害を併発して就労が困難になることもあります。
根本的な治療には、バイパス手術を行って血流の改善を図る必要があります。もやもや病は日常的な動作をきっかけに症状が現れるため、日常生活にさまざまな制限が必要となりますが、手術を行うことで制限のない生活も可能になり、もやもや病の進行による脳梗塞や脳出血の発症を防止できると考えられています。
原因
もやもや病は脳の血管の一部が徐々に狭くなっていき、やがて閉塞していく病気です。このような血管の変化は脳内のウィリス動脈輪に引き起こされます。ウィリス動脈輪とは、心臓から脳へ血液を送る左右の内頚動脈と後大脳動脈が頭蓋内で互いに交通する輪を形成したものを指します。もやもや病で血管が閉塞していくのは、ウィリス動脈輪で起こる現象であることから“ウィリス動脈輪閉塞症”とも呼ばれます。
もやもや病は、脳の血流低下を補うために狭くなった血管の周囲に網目状の細かい血管が発達します。これは、もやもや血管と呼ばれますが、こうした現象はもやもや病の患者にだけ認められる特徴的なものです。はっきりした原因は現在のところ明確には解明されていません。しかし、もやもや病は同じ家系の中で発症しやすいとのデータもあり、何らかの遺伝が関与しているのではないかと考えられています。
症状
もやもや病はウィリス動脈輪が進行性に狭窄・閉塞する病気であるため、脳への血流が低下していきます。
小児の場合
特徴的な症状の現れ方として、楽器演奏や、食べ物を冷ますために息を吹きかけるといった動作を行うことが引き金となることが挙げられます。こうした過呼吸と呼ばれる動作によって一時的に脳内の二酸化炭素が少なくなり、その反応で脳の血管がさらに収縮するために脳への血流が低下して、手足の麻痺、呂律が回らない・言葉が出てこないなどの言語障害、意識消失などの神経症状が現れます。
多くは一時的な症状のみで自然に改善するため、病院を受診せずに発見が遅れるケースも少なくありません。しかし、脳の血流不足の度合いが強いと脳梗塞を発症する恐れがあり、場合によっては重い後遺症につながることもあります。
成人の場合
成人も小児と同じように、脳の血流不足による一時的な症状や脳梗塞を発症する場合があります。そのほか、発達した側副血行路への負担が増していき、それが破綻することで脳出血を起こすこともあります。死亡率は小児よりも高いのが特徴です。
なお、もやもや病であっても神経症状がみられず、慢性的な頭痛や知的な発達障害、高次機能障害などの症状のみが現れることもあります。このようなケースでは病気が発見されず、さまざまな社会生活上の不便さを抱えながら過ごしている人も少なくないと考えられています。
検査・診断
もやもや病が疑われる場合は、以下のような検査が必要になります。基本的には、ウィリス動脈輪の狭窄・閉塞が両側にあること(片側例もあり)、その近くにもやもや血管が認められることが診断の基準になります。
画像検査
脳出血や脳梗塞の有無を調べるにはCTやMRIを用いた画像検査が必要です。
MRI検査では、脳の血管の走行などを調べるMRAという方法も併せて行うと、もやもや病の診断に役立ちます。
このほか、脳シンチグラフィ検査も行います。脳の血流の状態を詳しく調べることができる画像検査の1つで、もやもや病の診断だけでなく治療方針を決めるうえでも大切な検査です。
血管造影検査
脚の付け根や手首などの太い動脈からカテーテルと呼ばれる医療用の細いチューブを挿入して頚部の血管まで到達させ、そこから造影剤を注入して血管の走行や血流の状態を調べる検査です。通常は入院して行う検査ですが、もやもや病の確定診断や治療方針の決定に必要となります。
治療
もやもや病の根本的な治療は手術治療です。通常は以下の直接血行再建と間接血行再建を組み合わせて手術を行います。
- 直接血行再建術……頭皮の裏を走行する正常な血管を脳の表面の血管に直接つなげるバイパスを作り、脳の血流を増加させる手法です。
- 間接血行再建術……頭皮の裏にある筋肉や脳を包む硬膜の表面を、脳の表面に折り返して接触させる手法です。一定期間経過すると脳の表面に細かい新しい血管が生えてきます。
脳梗塞や脳出血を発症している場合は、それぞれ脳の血流を少しでも保つ薬や脳を保護する薬を使用したり、血腫を取る手術をしたりするなどの対症的な治療を行い、その後に根本的な治療を行うのが一般的です。
予防
もやもや病は明確な発症メカニズムが解明されておらず、有効な予防法はないのが現状です。しかし、治療が遅れると重篤な脳梗塞や脳出血を起こす可能性があるだけでなく、小児の場合は知能の低下などの後遺症を残すことも少なくありません。一時的な脱力などの神経症状が繰り返させる場合はできるだけ早めに医療機関に相談しましょう。
「もやもや病」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください