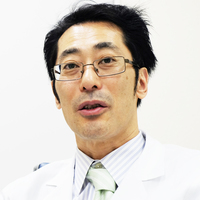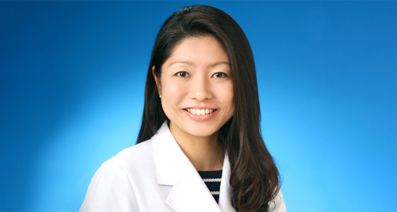周産期心筋症は、もともと心臓病のなかった方が周産期に心不全を発症する疾患です。記事1『周産期心筋症とはどんな病気? 原因・症状・合併症について』では、周産期心筋症の原因や症状についてご説明しました。本記事では、周産期心筋症の検査と治療、患者さんの予後について、熊本大学医学部附属病院の河野宏明先生にお話を伺います。
周産期心筋症の検査
心臓超音波検査(エコー)・心電図・血液検査・胸部レントゲン撮影を行う
周産期心筋症を疑うときには、基本的に心臓超音波検査(エコー)、心電図、血液検査を行います。加えて、多くのケースでは産科の主治医と相談のうえ胸部レントゲン撮影を行います。また心臓カテーテル検査を行うケースもありますが、これは母体が放射線を浴びるため、胎児への影響を考慮し、出産後に限り検査が検討されます。
【周産期心筋症の検査】
- 心臓超音波検査(エコー)
- 心電図
- 血液検査
- 胸部レントゲン撮影
- 心臓カテーテル検査(出産後に限り検討する)
周産期心筋症の治療—慢性的な症状への治療
基本方針:最終的には薬なしで過ごせる状態を目指す
周産期心筋症の患者さんの多くは、慢性的な症状に対する薬物治療を行い(詳しくは後述します)、心臓の収縮力の回復を試みて、最終的には薬なしで生活できる状態を目指します。
(1)利尿剤による治療
周産期心筋症の治療では基本的に、まず利尿剤を使います。周産期心筋症は記事1『周産期心筋症とはどんな病気? 原因・症状・合併症について』でお話したように、心臓の収縮力が低下して起こります。心臓のなかで最も重要な役割を果たしているのが、左室です。左室は大動脈に血液を送り出す、つまり血圧を作り出している部分です。心臓はこの左室を中心に収縮と拡張を交互に繰り返しています。
心臓の収縮力が低下すると、左室から大動脈に血液が出て行かなくなります。一方、左室には左房から血液が流入します。左室から血液が出て行けないということは、左室に血液が残っていることを意味し、左房に血液が停滞することになります。左房には酸素をたくさん溶かした血液が肺から流入します。しかし、左房に血液が停滞すると肺から左房に血液が流れなくなり、肺に血液が溜まることになります。これが心不全の状態です。空気が入るべき肺の中に液体の血液成分があふれてしまうのです。このことを肺水腫と呼びます。結果として呼吸困難が出現します。このような場合、利尿剤によって体内の水分量を減らし、心臓の負担を軽減します。
利尿剤の副作用:腎障害と胎児への影響
利尿剤は腎臓への負担が大きく、副作用として腎障害を起こすことがあります。
また胎児に栄養を送るためには、子宮や羊水の量を十分に確保しなければなりません。しかし母体に利尿剤を使うと、体内の水分量・血液量が減ってしまいます。胎児に十分な栄養を送るという視点では、利尿剤の使用は好ましくないのです。さらに、利尿剤は子宮内の羊水の量を減少させます。
周産期心筋症の患者さんは水分摂取量、塩分摂取量に注意
利尿剤には副作用があるため、使用を必要最低限に抑えることが理想です。そのためには、水分摂取量について留意すべきでしょう。夏にはテレビなどで水分をこまめにとるよう注意喚起がされますが、周産期心筋症の患者さんは心臓の収縮力低下によって体内の水分を排出しにくい状態ですから、一概に水分を摂取するのがよいとはいえません。ましてや利尿剤による治療をしている場合には、その効果を半減させることにもなります。周産期心筋症の患者さんは、主治医とよく相談し、自身の適切な水分摂取量を理解しておくことが大切です。また、塩分は体内に水分貯留を引きおこします。塩分の摂取にも十分にご注意ください。
(2)降圧剤や塩分制限による血圧のコントロール
血圧が高い場合には、降圧剤や塩分制限、利尿剤(血圧を下げる効果があります)によって血圧のコントロールを行います。入院中に塩分制限をする際には、1日7gを目安に食事内容を調整します。
(3)患者さんに合わせた薬剤治療を継続的に行う
先に述べたように、慢性的な症状に対しては体内水分量の調節や血圧のコントロールを行います。夏には水分摂取量が増え、冬には塩分摂取量が多くなるといった季節的な生活の変化を考慮しながら、患者さんの状態や食事内容を加味して、オーダーメイド的に薬物治療を継続します。最終的に、薬なしで生活できる状態を目指します。
周産期心筋症の治療—重篤な心不全への治療
前項で述べた内服薬での治療が効果を示さない場合は、心臓機能の補助装置や人工心臓装置を埋め込み、心臓移植待機となります。しかしながら、ここまで重篤な状態であることは非常にまれです。
(1)心臓機能の補助装置IABP・PCPSを使用する
周産期心筋症により重篤な心不全に陥った場合、IABP(大動脈内バルーンパンピング)や、PCPS(経皮的心肺補助装置)を使用し、心臓の機能を補助します。IABP(大動脈内バルーンパンピング)はバルーン付きカテーテルを心臓に近い大動脈に留置し、心臓の動きに合わせてバルーンを拡張・収縮させる方法です。一方、PCPS(経皮的心肺補助装置)は、人工心肺装置で心臓と肺の循環機能を代行し、生命を維持する方法です。

(2)IABP・PCPSで回復を認めない場合に人工心臓を埋め込む
IABP(大動脈内バルーンパンピング)や、PCPS(経皮的心肺補助装置)でも心臓の機能が回復しない場合には、LVAS(左心補助人工心臓)の埋め込みを検討します。LVAS(左心補助人工心臓)は、外付けのポンプで心臓に血液を送ることができます。しかしLVASは血管内部に人工の装置を付けるため、機械のなかで血液が固まりやすくなります。そのため血栓症の危険性が高くなります。したがって、血液凝固を抑える薬を投与する必要があります。この凝固を押さえる薬剤は、一方で、脳内出血など全身の出血のリスクを上昇させます。また皮膚を介してLVASを装着することで、感染症のリスクが上がります。そこで感染症予防のために抗生剤を使用しますが、抗生剤の副作用として腎障害・肝障害が起こりえます。
このような重篤なケースはまれではありますが、患者さんの状況や要望を把握し、主治医とよく相談のうえ慎重に治療方針を決定することが重要です。

周産期心筋症の予後
軽快退院できる患者さんのうち3分の1の方は治療薬を飲み続ける
周産期心筋症の患者さんは、出産後に病院でさまざまな心臓の検査を行う必要があるため、子どもさんと同時に退院できないケースもあります。患者さんの状況次第で入院期間は変わりますが、2〜3週間の入院が必要なケースが多く、長くても1か月ほどで退院できることがほとんどです。
周産期心筋症では大部分の患者さんが回復し、9割の患者さんが軽快退院できます。しかしながら、退院した患者さんのうち3分の1ほどの患者さんは心臓の収縮力がもとに戻らず、心不全の治療薬を飲み続ける必要があります。

出産後の授乳や次の妊娠・出産について考慮する必要がある
周産期心筋症の治療薬を飲み続けている場合、子どもを母乳で育てることは難しくなります。
出産後1〜2年といった時間を経て患者さんの心臓の収縮力が回復すれば、次の妊娠・出産も可能ですが、妊娠中に再び周産期心筋症を発症するリスクがあります。一方、心臓の収縮力が戻らなかった場合には、次の妊娠・出産について慎重に考える必要があります。いずれにせよ患者さんのケースによって予後は異なりますので、次の出産や日常生活における注意点などを主治医とよく相談することが大切です。
周産期心筋症の患者さんやご家族へのメッセージ

医学は日々、進歩しています。現在、心不全に対する新しい薬がいくつか実用化の準備段階にあり、近い将来には周産期心筋症の治療に活用できるようになるでしょう。周産期心筋症の患者さんやそのご家族には、ぜひ希望を持って前向きに生活していただけたら嬉しいです。今は苦しい状態だとしても、新しい薬や治療法が開発されていることに期待して、ご自身の生活を存分に楽しんでいただきたいと考えています。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が12件あります
心筋症疑いについて
前回鎖骨の下左右辺りの痛みと強烈な吐き気、 冷や汗で救急車で運ばれ、その時は心房細動あり、でも発作の原因ではないだろう… 詳しく検査しますとの事で、後日24時間ホルダー、新エコー、造影剤CTの検査をし、 今日結果を聞きにいきました… 冠動脈は問題なし。 心房細動はずっとあり。 期外収縮は正常範囲内。 私の年齢では、こんなにずっと心房細動があるのは珍しいと言われました… 頻脈ではなく除脈と言われました。 発作性ではなく、前から心房細動はあったんではないかとのこと。最後に受けた健康診断は2年前で、それまでは問題なしと先生に伝えました。 今回の検査で、筋肉の数値が規定範囲内ではあるが、下の方の数値の為、心筋症疑いありのため、又検査必要と言われました。 造影剤MRIと、心筋シンチグラフィです… 筋肉がよわっているから、心房細動が絶え間なくでるのか詳しく検査した方がいいとの事だったんですが、 私は心筋症疑いと言われた事がショックだし、 発作の原因がはっきりしてないのも不安です… カテーテル検査はしなくていいんじゃないかと言われました。 筋肉が弱い→数値が規定範囲内で低いと 言うことは心筋症の可能性大という事なんでしょうか?
服用中の薬について
カルベジロール錠10㎎、ミカルディス錠40㎎、ニフェジピンCR錠20㎎を服用していました。前回の診察でニフェジピンを中止しました。その日から次の診察までの日数を誤認したらしく、ミカルディスが無くなってしまいました。代用でニフェジピンを服用しても良いでしょうか。それともカルベジロールのみの服用で良いでしょうか。 よろしくお願いします。
胃腸炎の後の腹鳴・ガス
11/28(金)の夕方から胃の不快感(ムカムカ)があり、市販の胃腸薬を飲んで様子をみるとおさまったのですが、食欲はまったく無し。 11/29(土)はお粥を少量食べる程度(食欲がない) 11/30(日)のam2時ぐらいから急な水便が朝まで続く(10回以上)。 腹痛はなし。便意があるので急いで行くと水便。 日中は排便なし。 胃の不快感も無し 12/1(月)am4時頃からまたもや水便4~5回 消化器内科クリニックを受診。 迅速血液検査で、炎症反応も白血球も異常なし(正常範囲内)といういうことで、消化不良による胃腸炎と診断 リーダイ配合錠とミヤBM錠が4日分でました。 下痢はおさまったのですが、やたら腹鳴とガスがでます。 まだ、腸の状態がよくないのでしょうか?もう一度受診して別のお薬をいただくのがいいでしょうか? また、別の事も考えられるでしょうか? 消化不良でそんな激しい水便症状はでますか? 現在は胃の症状も下痢もおさまりましたが、やたら腹鳴(特に左腹部)とガスが多くて困っています。 消化不良による胃腸炎に関係しますか?
健康診断で尿たんぱくが出ました。
健康診断で、尿たんぱくの反応が出ました。昨年に続き2年連続ででたのでとても心配です。最近疲れがたまっているのもあるのかもですが。健康診断では「要経過観察」とはなっていましたが、近日中に内科の検診とか精密検査が必要だと思われますか?今のところ特に自覚症状はありません。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「心筋症」を登録すると、新着の情報をお知らせします