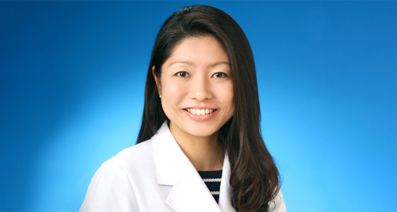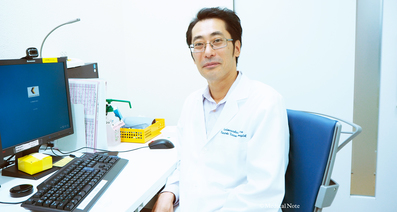
周産期心筋症の検査と診断基準
周産期心筋症の診断基準は
- 周産期である分娩前1か月から分娩後5か月以内であること
- もともと心臓病の既往がないこと
- 心臓の機能が低下していること
の3つに当てはまることです。そのため、検査としてはまず、心臓超音波検査(心エコー検査)や胸部のレントゲン撮影を行い、心臓の機能低下について詳しく調べます。
また、心不全になると血中のBNPと呼ばれるホルモンの値が高くなります。そのため、血液検査を行い、BNPの値を測ります。
周産期心筋症の治療法 薬物療法や機械を用いた治療法

周産期心筋症の症状は、一般的な心筋症と同様です(周産期心筋症の詳しい症状については、記事1『周産期心筋症とは 原因・症状について詳しく解説』をご参照ください)。そのため、治療も心不全に対する処置を行います。妊娠中に周産期心筋症を発症した場合は、分娩後に治療を行うケースが一般的です。
薬物療法
心不全の症状を和らげ、進行を抑えるための治療としては、ACE阻害薬やARBといった薬を使用します。また、心臓の負担を軽くするβ遮断薬という薬や、心機能低下に伴い発生した腎臓機能の低下によって、体のなかに溜まった水分を排出するために、利尿薬を使用することもあります。
経皮的心肺補助装置(PCPS)
薬物治療だけでは症状の改善が不十分な場合、経皮的心肺補助装置(PCPS)といった機械を用いて治療を行います。経皮的心肺補助装置は、血液内の酸素の量を増加させ、全身へ送る補助をする装置です。
周産期心筋症の予後 多くの患者さんは1年以内に回復

病院を退院した後も、心臓の働きが元通りになるまでには、一定の期間が必要であり、周産期心筋症の治療をされた日本の患者さんの6割から7割は、1年以内に心臓の働きがもとに戻っています。しかし、頻度はまれですが死亡するケースもあります。予後をよくするためには、早期発見と治療が大切です。
周産期心筋症の日常生活での注意点
過労や睡眠不足などを避け、身体的・精神的なストレスを溜めないように心がけてください。
そして、軽い運動での息切れや、咳、急激な体重の増加といった症状が悪化していると感じた場合は、早急に医療機関を受診しましょう。
そして、心臓の機能が回復しないうちの妊娠は非常にリスクが高くなります。きちんと避妊を行いましょう。周産期心筋症の既往歴のある患者さんの妊娠については以下でご説明します。
周産期心筋症発症後に2人目を妊娠・出産するリスクとは
周産期心筋症の既往歴(過去の病歴)のある患者さんが、再び妊娠をされたときのリスクは、心機能がどこまで回復したかに深く関係しています。
回復している方と回復途中の方のリスクの差
周産期心筋症は再現性のある疾患のため、心機能が回復した患者さんの場合でも、再度妊娠された方のなかの3割は、再び周産期心筋症を発症すると報告されています。一方、心機能が十分回復していないまま次の妊娠をした方では、5割が再発し、早産や心不全の重症化、最悪の場合、死亡するというケースもありました。
妊娠する前に病院へ
上記のような危険性があるため、周産期心筋症を患ったことのある方は、必ず次の妊娠をする前に、医師に相談して検査を受け、心機能が回復していることを確認してください。その際に重要なことは、妊娠後ではなく、妊娠をする前に検査を受けるという点です。
妊娠に伴う心臓の動きの変化は、妊娠直後から始まっています。そのため、妊娠がわかってから病院に行っても、その患者さんの心臓がどれほど回復した状態であったのかは、既にわからない状態になっています。ですので、そろそろ次の妊娠をしたいと考えた時点で、検査を受ける必要があるのです。
前回の記録が役立つ
周産期心筋症発症以降の分娩を安全に行うためには、前回周産期心筋症を患ったときの症状や心臓の経過情報が非常に重要となります。そのため、病院で前回の経過を詳細に記録してもらっておくことが大切です。
周産期心筋症に対して現在行われている研究
周産期心筋症に関して、2017年現在は以下のような研究が行われています。
プロラクチンの発生を抑える抗プロラクチン療法
周産期心筋症の発生には、プロラクチンというホルモンが関係していると考えられます(周産期心筋症の原因についての詳しい説明は、記事1『周産期心筋症とは 原因・症状について詳しく解説』をご参照ください)。そこで、プロラクチンの発生を抑える薬を使用した、抗プロラクチン療法の大規模な研究がヨーロッパで行われています。
また、日本でも少しずつですが、抗プロラクチン療法の症例の集積が進められています。しかし、目覚ましい効果がまだみられていません。そのため、ヨーロッパで行われている大規模な研究ではどのような結果が出るのかが期待されています。
妊娠中に心エコーを実施しスクリーニングを行う
現在の妊婦健診では、心臓の検査は、何か症状が発生しない限り行いません。しかし、拡張型心筋症の原因遺伝子を保有している方や、妊娠高血圧症候群の方など、周産期心筋症になりやすい素因を持った方を対象に、妊娠中から心エコーの検査をし、心機能の変化を観察するという研究が行われています。
検査をすることで、周産期心筋症の発症をある程度予測することが可能です。そして、妊娠中から既に心機能に異変が起こっている妊婦さんは、循環器内科の専門医がいる病院で出産する選択ができるなど、発症したにしっかりとした対応が可能となるのです。
周産期心筋症の治療には家族の支えが大切

周産期心筋症を患ってから、心臓を元の状態まで治すためには、一定の期間が必要となります。その間は、通院が必要な状態ですし、身体だけではなく、精神的な負担もかかるため、治療するためには家族でサポートすることも大切です。
また、次の妊娠を望む場合、心臓の回復状態を把握せずに闇雲に妊娠してしまうことは非常に危険です。妊娠をしたいと考えた時点で医療機関を受診し、医師と相談をしながら妊娠の準備をしてください。
国立循環器病研究センター病院 周産期・婦人科部 部長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
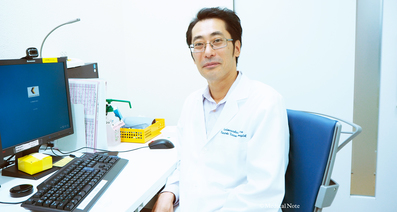

周産期心筋症とはどんな病気? 原因・症状・合併症について

特発性拡張型心筋症の治療法確立を目指して
関連の医療相談が12件あります
心筋症疑いについて
前回鎖骨の下左右辺りの痛みと強烈な吐き気、 冷や汗で救急車で運ばれ、その時は心房細動あり、でも発作の原因ではないだろう… 詳しく検査しますとの事で、後日24時間ホルダー、新エコー、造影剤CTの検査をし、 今日結果を聞きにいきました… 冠動脈は問題なし。 心房細動はずっとあり。 期外収縮は正常範囲内。 私の年齢では、こんなにずっと心房細動があるのは珍しいと言われました… 頻脈ではなく除脈と言われました。 発作性ではなく、前から心房細動はあったんではないかとのこと。最後に受けた健康診断は2年前で、それまでは問題なしと先生に伝えました。 今回の検査で、筋肉の数値が規定範囲内ではあるが、下の方の数値の為、心筋症疑いありのため、又検査必要と言われました。 造影剤MRIと、心筋シンチグラフィです… 筋肉がよわっているから、心房細動が絶え間なくでるのか詳しく検査した方がいいとの事だったんですが、 私は心筋症疑いと言われた事がショックだし、 発作の原因がはっきりしてないのも不安です… カテーテル検査はしなくていいんじゃないかと言われました。 筋肉が弱い→数値が規定範囲内で低いと 言うことは心筋症の可能性大という事なんでしょうか?
服用中の薬について
カルベジロール錠10㎎、ミカルディス錠40㎎、ニフェジピンCR錠20㎎を服用していました。前回の診察でニフェジピンを中止しました。その日から次の診察までの日数を誤認したらしく、ミカルディスが無くなってしまいました。代用でニフェジピンを服用しても良いでしょうか。それともカルベジロールのみの服用で良いでしょうか。 よろしくお願いします。
胃腸炎の後の腹鳴・ガス
11/28(金)の夕方から胃の不快感(ムカムカ)があり、市販の胃腸薬を飲んで様子をみるとおさまったのですが、食欲はまったく無し。 11/29(土)はお粥を少量食べる程度(食欲がない) 11/30(日)のam2時ぐらいから急な水便が朝まで続く(10回以上)。 腹痛はなし。便意があるので急いで行くと水便。 日中は排便なし。 胃の不快感も無し 12/1(月)am4時頃からまたもや水便4~5回 消化器内科クリニックを受診。 迅速血液検査で、炎症反応も白血球も異常なし(正常範囲内)といういうことで、消化不良による胃腸炎と診断 リーダイ配合錠とミヤBM錠が4日分でました。 下痢はおさまったのですが、やたら腹鳴とガスがでます。 まだ、腸の状態がよくないのでしょうか?もう一度受診して別のお薬をいただくのがいいでしょうか? また、別の事も考えられるでしょうか? 消化不良でそんな激しい水便症状はでますか? 現在は胃の症状も下痢もおさまりましたが、やたら腹鳴(特に左腹部)とガスが多くて困っています。 消化不良による胃腸炎に関係しますか?
健康診断で尿たんぱくが出ました。
健康診断で、尿たんぱくの反応が出ました。昨年に続き2年連続ででたのでとても心配です。最近疲れがたまっているのもあるのかもですが。健康診断では「要経過観察」とはなっていましたが、近日中に内科の検診とか精密検査が必要だと思われますか?今のところ特に自覚症状はありません。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「心筋症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。