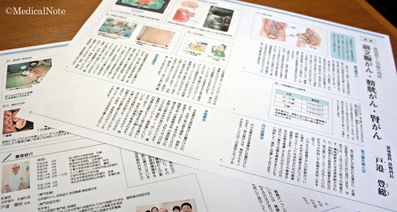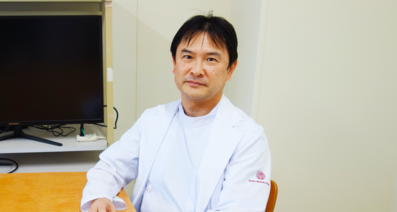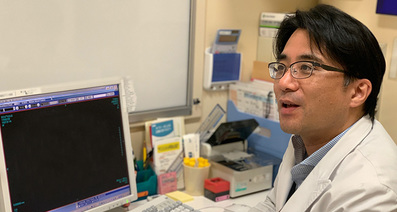膀胱がんは膀胱の粘膜(膀胱内部を覆う上皮)から発生するがんで、進行すると膀胱の筋層(膀胱を形成する筋肉の壁)にまで浸潤(広がること)し、周辺のリンパ節や肺、肝臓、骨などにも転移を生じます。比較的早い段階で血尿などの症状が認められることが多いため、早く発見できるケースが多いがんの1つとされ、比較的予後がよいがんともいえます。膀胱がんの治療方法はがんの進行度によって異なり、膀胱の摘出が必要な場合には術後の生活にも大きな影響を与えます。
本記事では、膀胱がんのステージ別の治療方法や治療後の注意点などについて詳しく解説します。
膀胱がんの治療
膀胱がんの治療は進行の程度によって異なります。一般的に、早期の段階ほど体への負担が少ない治療を行うことができ、進行すると膀胱を摘出する必要がある場合や、治療を行うのが困難なケースも少なくありません。治療の方法を決定する指標としては、ほかのがんと同じように進行度合いによって分類される“ステージ”が用いられます。
膀胱がんのステージ
膀胱がんは膀胱の粘膜から発生し、進行するにしたがって上皮の下層にある粘膜下層、さらにその下の筋肉の層に浸潤していきます。
がんが上皮内のみにとどまり、筋肉の層へ広がっていないものは“ステージ0”“ステージI”に分類され、いわゆる“早期がん”の段階にあたります。一方、筋肉の層にまでがんが広がったものは“ステージII”“ステージIII”で、いわゆる“進行がん”です。また、リンパ節やほかの臓器に転移を生じているものは“ステージIV”となり、一般的には“末期がん”と呼ばれるものです。
ステージ別に選択される治療
ステージ0、ステージI(早期がん)
この段階で主に行われるのは“経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)”です。
これは、尿道から膀胱内に内視鏡を挿入し、内部の状態を観察しながら腫瘍を切除する治療です。ごく早期のがんであれば、この治療のみでがんを取り除くことができます。
そのうえで、切除後の再発を予防するために膀胱内にがんの発生を抑える作用のある抗がん薬やBCGを注入する“膀胱内注入療法”を行うのが一般的です。
一方、がんが筋肉の層にまで達していなくても、悪性度の高いがんが上皮に広範囲に広がっている場合はTUR-Btのみでがんを取り切るのが困難なため、膀胱を摘出しなければならないケースもあります。
ステージII、III(進行がん)
筋肉の層まで、あるいはそれを超えて浸潤したがんはTUR-Btのみで完全に切除することができないため、膀胱を摘出する必要があります。多くはCTやMRIなどでは描出できない微小な転移を生じている可能性を考慮して、手術の前に抗がん薬治療(術前補助化学療法:NAC, neoadjuvant chemotherapy)が推奨されています。
膀胱は腎臓で産生された尿をためるための臓器です。このため、膀胱を摘出した場合は、尿の排泄路を新たに作る“尿路変向術”を同時に行わなければなりません。尿路変向術には、尿の出口(いわゆるストーマ)を新たに造設する非禁制型尿路変向術と、腸の一部で膀胱のような臓器を新たに作る禁制型尿路変向術とがあります。
非禁制型尿路変向術で代表的な術式としては、尿管を直接皮膚に開口させる“尿管皮膚瘻造設術”と、小腸の一部に尿管をつなげて反対側の皮膚に開口させる“回腸導管造設術”があります。
一方、禁制型尿路変向術はさらに細かくみると“自己導尿型代用膀胱形成術”と“自排尿型代用膀胱形成術”があります。“自己導尿型代用膀胱形成術”は形成した膀胱を臍などの皮膚に開口させる術式ですが、最近ではほとんど行われていません。近年は、回腸で形成した膀胱を尿道につなげる“回腸利用新膀胱造設術”を行うことが一般的です。
また、手術後にも再発を予防するために抗がん薬治療や免疫チェックポイント阻害薬(ニボルマブ)による治療を行うことがあります。
ステージIV(末期がん)
転移があったり、全身の状態が悪く手術できなかったりするような場合には、積極的に手術を行わず、プラチナ製剤を含む抗がん薬治療、免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ*、アベルマブ**)、抗体薬物複合体(エンホルツマブ ベドチン***)などが用いられます。これらの治療はがんを小さくすることを目的としていますが、十分な効果が得られない場合などでは、がんによる痛みを取ることを目的として放射線治療が行われることもあります。さらに、痛みが強く生活に支障が出ているようなケースでは、医療用麻薬などを用いた緩和治療が行われます。
*ペムブロリズマブ(免疫チェックポイント阻害薬:ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体):プラチナ製剤を含む抗がん薬治療後に増悪した場合の治療として推奨されています。
**アベルマブ(免疫チェックポイント阻害薬:ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体):プラチナ製剤を含む抗がん薬治療が奏功した場合の維持療法として推奨されています。
***エンホルツマブ ベドチン(抗体薬物複合体:抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体):プラチナ製剤を含む抗がん薬治療およびPD-1/PD-L1阻害薬治療後に増悪した場合の治療に用いられます。
ステージ別の生存率
膀胱がんは、発見された段階で適切な治療を受けたとしても、発見時のステージによって生存率は大きく変化します。膀胱がんのステージ別の5年生存率*は、ステージIでは86.4%、ステージIIでは58.5%、ステージIIIでは43.3%、ステージIVでは19.1%となります。
また、膀胱を摘出した場合でも尿管などにがんが再発することもあるため、定期的な検査を続けていくことが大切です。
*国立がん研究センター:がん診療連携拠点病院等院内がん登録 2012-2013年5年生存率集計 報告書, 2021, p53, 61
膀胱を摘出した場合に行われる治療
膀胱を摘出した場合は、新たな尿の排泄経路を作る“尿路変向術“が行われます。前項でも述べたとおり主に3つの方法があり、それぞれ排尿の仕方や注意点が異なるので、術後は医師の指示に従った排尿習慣を心がける必要があります。
回腸導管造設術
皮膚に開口させた小腸の一部で作成した導管から自然に尿が排出されるので、適宜開口部に装着したバッグを交換することが必要です。自身のペースで行うことができるため、排尿にかかる手間は比較的少ないといえます。
回腸利用新膀胱造設術
小腸で作った新たな膀胱と尿管・尿道をつなぐため、手術前と同じく尿道から排尿することが可能です。
尿をためるバッグを装着しなくてよいため、QOL(生活の質)は大きく向上するといえます。しかし、新たに作った膀胱は尿がたまっても尿意が生じず、尿をためられる容量も少ないため、夜間も含めて2~3時間おきに意識的に排尿しなければなりません。
また、尿を出すにはある程度訓練しなければならないため、患者自身の努力も求められます。
尿管皮膚瘻造設術
この方法は、腸を使わずに尿管をそのまま皮膚に出す方法ですが、回腸導管造設術と同じく尿管を開口させた部位から自然に尿が排出されるため、尿がたまるバッグを交換することとなります。腸を用いないため手術時間も短く済むメリットがありますが、尿管開口部が狭窄(狭くなること)をきたしやすいことから、狭窄を予防する目的で尿管ステントを留置する必要があります。そのため、定期的にステントを交換しなければならないことや、尿管が直接皮膚に開口しているため細菌が侵入して腎盂腎炎などを発症するリスクが高くなることから、長期的に腎機能が低下しやすいとされており、慎重な清潔管理を行わなければならない点がデメリットとなります。
患者自身も治療について十分に理解することが重要
膀胱がんは予後のよいがんの1つです。しかし、発見されたときのステージによっては膀胱を摘出する必要があり、術後の生活にも大きな影響をもたらします。
そのため、まずは自身のがんの状態を十分に理解したうえで、今後の治療について不安や疑問がある場合は躊躇せずに医師に相談するようにしましょう。
国際医療福祉大学病院腎泌尿器外科 部長 教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
内田 克紀 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事


膀胱全摘除術とは? 尿路変向術や手術後の生活についても解説

膀胱がんの症状・検査・治療――血尿が一度でも出たら受診を
関連の医療相談が22件あります
再発リスクの評価
表在性膀胱癌の手術を6月に行い、単発抗がん剤注入を受けました。 その後、先9月の膀胱鏡検査では、再発をしていませんでした。 比較的簡易な処置で済む癌ですが、1年以内の再発率60%程度と高く、一度再発すると2度目は70%、3度目80%、とさらに上がるそうです。 よって近場の泌尿器科のクリニックでがん細胞診の尿検査を毎月受け、3ヶ月毎に膀胱鏡検査をすることにしています。 しかし、その確率の高さを考えると憂鬱です。先手を打ち再発リスクを下げる方法はないのでしょうか? また、よしんば再発が免れたとしても、いったいあと何年再発への注意をしなければいけないのか?見通しが欲しいです。
治療方法など
2018.6に非浸潤型膀胱がん発症、2ヶ所Ta、ローグレード 2019.5再発2ヶ所、2020.5再発2.5ヶ所手術は実施予定 (2018.11、2019.12は再発せず) いずれもTURBT手術を実施 手術後、抗がん剤注入せず 抗がん剤注入しないのは効果が変わらない 又同病院ではやっていない とのこと (病院は、がんを診察したクリニックからの紹介) 質問 1.抗がん剤の効果は無いのか 2.再発時の手術後、抗がん剤は注入しないのか 3.将来、BCG注入必要になった際、BCGは副作用があり、その代替で抗がん剤注入しないのか 4.転院しても抗がん剤注入した方が良いのか 5.転院は簡単に出来るのか 6.転院の手続きはどうするのか 7.BCG注入で萎縮の副作用があれば、膀胱を切除するしかないのか 以上
86歳、膀胱癌で手術後のBCG注入治療は必要か教えてください。
86歳で膀胱癌と診断され手術後BCG注入治療を勧められたのですが、介護施設の主治医に副作用が大変だから勧められないと言われ治療をお断りしたら再発・再発で1年間に3度の手術を受ける結果となりました。3月3日に手術をしましたのでまた1ヶ月後に治療を勧められると思います。癌は再発、転移するので治療が絶対必要だとおっしゃる先生と、高齢で進行がゆっくりなのに副作用が大変な治療をする必要はないとおっしゃる介護施設の主治医、知識や経験が全くない私はどちらを選択すれば良いのか悩んでおります。良きアドバイスをどうぞよろしくお願い致します。
膀胱がんでのBCGについて
来月からBCGを開始するのですが 1.BCGはやるべきか 2.一般に生じる副作用はどのようなものか 3.BCGは恐ろしい気がするのですが
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「膀胱がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。