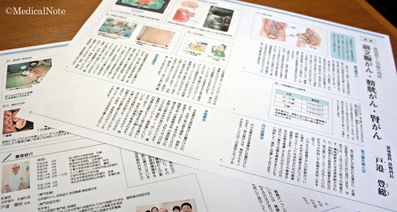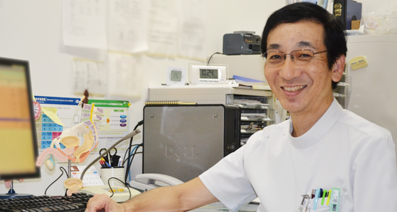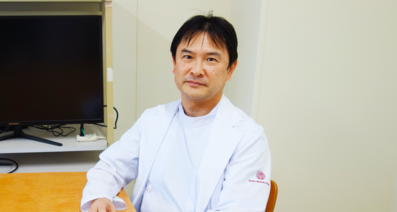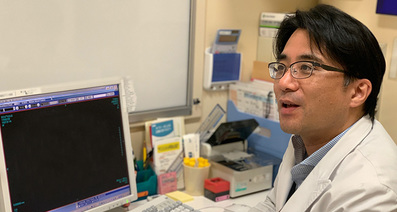膀胱がんの治療のために膀胱全摘除術を受けた後、回腸導管とStuder法による代用膀胱造設術(ネオブラダー)では術後の経過や日常生活にどのような違いがあるのでしょうか。長期的な予後や患者さんとご家族のQOL(生活の質)などについて済生会宇都宮病院泌尿器科主任診療科長の戸邉豊総先生にお話をうかがいました。
ストマのない骨盤内臓全摘術とは
骨盤内臓全摘術とは、直腸がんが進行して膀胱側など他の臓器に浸潤してしまったときに、骨盤内にある臓器をすべて摘出する手術です。その場合、患者さんは回腸導管と人工肛門の2つのストマを造設して生活しなければなりませんでした。
そこで、私が済生会宇都宮病院の前にいた千葉大学医学部附属病院では、「ストマのない骨盤内臓全摘術」という術式を行っていました。これは排尿・排便機能を再建した骨盤内臓全摘術です。直腸がんの患者さんは比較的若い方も多いので、非常に喜ばれていました。
長期予後はどうなっているのか
私が実際にStuder法によるネオブラダー(新膀胱)の第1例目の手術を行ったのは1998年のことですが、それ以来、今でもずっと年賀状やお手紙をくださる患者さんがいらっしゃいます。ちょうど2000年に「ストマのない骨盤内臓全摘術」を受けた患者さんで、16年経った今でも排尿・膀胱に問題がなくお元気な方がいらっしゃいます。
気になる長期予後について、腎機能や排尿ができるかどうかなど、術後10年で区切ってみたデータがありますが、術後10年でも日中は尿がもれることもなく排尿ができています。ただし夜間に関しては少し失禁が見られます。これは就寝中に起きてトイレに行けば回避できることなのですが、慣れてくると尿もれパッドなどで対策をして睡眠を優先するという方も増えてくるので、そういったケースも含まれます。術後3年で見ると6〜7割の方は夜間ももれはありませんし、日中は尿もれのない方が95%以上になっています。
また、残尿もほとんどみられません。ただし10年経過するとカテーテル導尿をする方が出てきますが、それは術後の後遺症というよりも加齢性の変化という部分が大きいとみられます。
患者さんと家族のQOL(生活の質)
Studer法によるネオブラダーは腹圧をかけることによって排尿をします。そのため、ご高齢で寝たきりになったときに回腸導管のほうがむしろ管理が楽なのではないかと考える方もいるのですが、実際にはバルーンカテーテルを尿道から入れておけば何ら問題はありません。
我々はQOL(Quality of life:生活の質)について研究をしたことがありますが、そこでは患者さんとご家族のQOLについて調べました。膀胱がんの患者さんご本人だけでなく、ご家族も忘れてはならない存在です。もちろん患者さんがストマの管理を自分自身でされる場合もありますが、尿をためるパウチの交換などをご家族にやってもらうことも少なくありません。我々はその点に着目して研究を行いました。健康関連のQOL(HRQOL: Health Related Quality of Life)を測定するための尺度にSF-36®というものがあります。身体機能や全体的健康感、心の健康など、それぞれの項目の得点をレーダーチャートで表したものが下記の画像です。

すべての項目においてネオブラダーが回腸導管より上回っている

社会生活機能、日常役割機能、全体的健康感でネオブラダーの方が回腸導管より上回っている
このようなデータで比較すると、回腸導管よりもネオブラダー(新膀胱)のほうがよい結果が出ています。それは患者さんのご家族で見ても同様です。しかも時間を追って見ていくと、回腸導管ではストマのケアで疲弊してしまってスコアが落ちてくるのに対して、ネオブラダーのほうは変わらないかむしろ向上しています。
膀胱がんは高齢の患者さんが多いため、面倒を看るご家族、特に配偶者の方も一緒に高齢化しています。ご高齢であってもストマのケアに慣れてきて十分続けられる方もおられるでしょうが、データから見てもやはり高齢のご家族が疲弊してQOLが低下しているという面が伺えます。そういった意味でもこのネオブラダーは、適応可能な方にはさまざまな面でおすすめできる術式であると考えます。
済生会宇都宮病院 泌尿器科 主任診療科長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事


膀胱全摘除術とは? 尿路変向術や手術後の生活についても解説

膀胱がんの症状・検査・治療――血尿が一度でも出たら受診を
関連の医療相談が22件あります
再発リスクの評価
表在性膀胱癌の手術を6月に行い、単発抗がん剤注入を受けました。 その後、先9月の膀胱鏡検査では、再発をしていませんでした。 比較的簡易な処置で済む癌ですが、1年以内の再発率60%程度と高く、一度再発すると2度目は70%、3度目80%、とさらに上がるそうです。 よって近場の泌尿器科のクリニックでがん細胞診の尿検査を毎月受け、3ヶ月毎に膀胱鏡検査をすることにしています。 しかし、その確率の高さを考えると憂鬱です。先手を打ち再発リスクを下げる方法はないのでしょうか? また、よしんば再発が免れたとしても、いったいあと何年再発への注意をしなければいけないのか?見通しが欲しいです。
治療方法など
2018.6に非浸潤型膀胱がん発症、2ヶ所Ta、ローグレード 2019.5再発2ヶ所、2020.5再発2.5ヶ所手術は実施予定 (2018.11、2019.12は再発せず) いずれもTURBT手術を実施 手術後、抗がん剤注入せず 抗がん剤注入しないのは効果が変わらない 又同病院ではやっていない とのこと (病院は、がんを診察したクリニックからの紹介) 質問 1.抗がん剤の効果は無いのか 2.再発時の手術後、抗がん剤は注入しないのか 3.将来、BCG注入必要になった際、BCGは副作用があり、その代替で抗がん剤注入しないのか 4.転院しても抗がん剤注入した方が良いのか 5.転院は簡単に出来るのか 6.転院の手続きはどうするのか 7.BCG注入で萎縮の副作用があれば、膀胱を切除するしかないのか 以上
86歳、膀胱癌で手術後のBCG注入治療は必要か教えてください。
86歳で膀胱癌と診断され手術後BCG注入治療を勧められたのですが、介護施設の主治医に副作用が大変だから勧められないと言われ治療をお断りしたら再発・再発で1年間に3度の手術を受ける結果となりました。3月3日に手術をしましたのでまた1ヶ月後に治療を勧められると思います。癌は再発、転移するので治療が絶対必要だとおっしゃる先生と、高齢で進行がゆっくりなのに副作用が大変な治療をする必要はないとおっしゃる介護施設の主治医、知識や経験が全くない私はどちらを選択すれば良いのか悩んでおります。良きアドバイスをどうぞよろしくお願い致します。
膀胱がんでのBCGについて
来月からBCGを開始するのですが 1.BCGはやるべきか 2.一般に生じる副作用はどのようなものか 3.BCGは恐ろしい気がするのですが
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「膀胱がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。