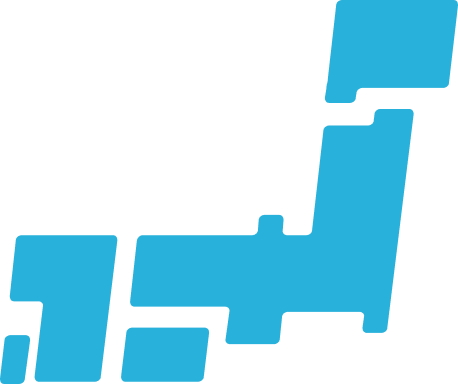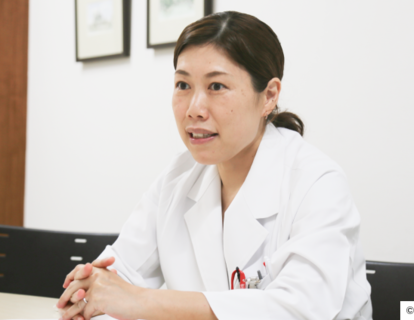概要
バセドウ病とは、甲状腺のはたらきが異常に活発になることで甲状腺ホルモンが過剰に産生される病気のことです。甲状腺ホルモンは、全身の臓器に作用して新陳代謝を促すホルモンであるため、バセドウ病を発症すると動悸・体重減少・手の震え・発汗などの身体的症状やイライラ感や落ち着きのなさといった精神的な症状が現れるようになります。
発症頻度は1,000人に0.2~3.2人とされていますが、若い女性に発症しやすいのが特徴です。発症原因は甲状腺を刺激する抗体(特定の組織や細胞を攻撃するタンパク質)が産生されるようになることであり、免疫機能の異常によって発症する”自己免疫疾患”の1つとされています。
バセドウ病は適切な治療をしないまま放置すると心不全や骨粗しょう症などを引き起こすリスクが高くなるため、早期発見・早期治療が重要です。また、日常生活でのストレスなどにより症状が急激に悪化する”甲状腺クリーゼ”に陥ることもあり、場合によっては命を落とすケースもありますのでバセドウ病と診断された場合は日常生活にも注意が必要となります。
原因
バセドウ病の原因は、甲状腺を刺激する”TSH受容体抗体”が体内で産生されるようになることです。
甲状腺ホルモンは、脳の下垂体から分泌される”甲状腺刺激ホルモン(TSH)”が甲状腺を作る細胞表面に存在する”TSH受容体”に結合することによって甲状腺を刺激し、分泌が促されます。バセドウ病では、TSH受容体抗体がTSH受容体に結合し、甲状腺を過剰に刺激することで甲状腺ホルモンの過度な分泌が生じるのです。
どのようなメカニズムでTSH受容体抗体が産生されるようになるのか、明確なメカニズムは解明されていません。しかし、バセドウ病は遺伝の関与も指摘されているほか、もともとバセドウ病になりやすい体質の人が過度なストレス・過労・重度な感染症・妊娠・出産などを契機に発症するケースも多いと考えられています。
症状
バセドウ病を発症すると甲状腺ホルモンの過剰分泌が引き起こされます。甲状腺ホルモンは全身の臓器に作用して新陳代謝を促す作用があります。また、バセドウ病は自律神経の一種である交感神経のはたらきを活性化するカテコールアミンの分泌量も過剰になることが知られています。
その結果、動悸・体重減少・手の震え・過剰な発汗・下痢などの身体的症状、イライラ感・不眠・落ち着きのなさ・疲労感などといった精神的症状が見られるようになります。
また、過度に刺激されることによって甲状腺は大きく腫れ、喉の違和感を自覚することも少なくありません。さらに、目を動かす筋肉や脂肪に炎症を引き起こすことで腫れを生じ、目が内側から押し出されるように見える”眼球突出”が現れるのもバセドウ病の典型的な症状の1つです。悪化するとまぶたや結膜に充血・目の動きの異常、ドライアイなどを引き起こします。
さらに、バセドウ病は適切な治療をしないままの状態が続くと、心臓に過度な負担がかかって不整脈を引き起こしたり、心不全に至ったりするケースも少なくありません。また、骨の代謝が活発になることで骨が脆くなり、些細な刺激で骨折しやすくなる可能性があります。
検査・診断
症状や甲状腺の腫れなどからバセドウ病が疑われる場合は、次のような検査が行われます。
血液検査
バセドウ病の確定診断のためには血液検査が必要です。血液検査では、甲状腺ホルモン値、TSH値の測定、TSH受容体抗体の有無の判定が行われます。
また、一般的な血液検査項目を調べて全身の状態を評価する必要もあります。
超音波検査
超音波を出す機械を喉に当てて甲状腺の状態を調べる検査です。甲状腺の大きさ、しこり、血流などを確認することができます。
アイソトープ検査
甲状腺はヨウ素やテクネチウムを取り込みやすいという性質があります。これを利用して放射線を放出するヨウ素やテクネチウム薬剤を服用して、甲状腺にどれくらい取り込まれるかを計測します。この検査では甲状腺ホルモンの上昇が甲状腺の機能に問題がないかどうかを調べます。
治療
バセドウ病と診断された場合は、重症度などによって次のような治療が行われます。
薬物療法
基本的に、バセドウ病の治療は甲状腺ホルモンの分泌を抑える”抗甲状腺薬”を用いた薬物療法から行います。服用を続けると1~2か月ほどで甲状腺ホルモンは正常値となることが多いとされていますが、治療はTSH受容体抗体の産生がストップするまで続ける必要があるといわれています。
放射性ヨウ素内用療法
甲状腺はヨウ素が蓄積しやすい臓器です。その性質を利用したのが放射性物質を含むヨウ素を内服し、甲状腺に蓄積した放射性物質によって甲状腺組織の破壊を促す放射性ヨウ素内用療法です。甲状腺ホルモンを分泌する細胞が減少するため、バセドウ病の根本的な治療が望めます。
しかし、この治療法は実施できる施設や年齢が限られており、治療効果が高すぎると甲状腺ホルモン分泌量が過度に少なくなってしまうことがあります。
手術
バセドウ病のもっとも効果が高い治療法は、手術によって甲状腺自体を摘出することです。薬物療法などほかの治療法で十分な効果が見られない場合、副作用で薬物療法が行えない場合などに実施されます。
バセドウ病に伴う“甲状腺眼症”を知っていますか
提供:アムジェン株式会社
監修:オリンピア眼科病院 神前あい先生
目を守るためには早期に適切な治療を受けることが大切
主にバセドウ病(甲状腺機能亢進症)やまれに橋本病(慢性甲状腺炎)に合併する症状の1つに“甲状腺眼症”があります。これは目の自己免疫疾患で、目の周りにある脂肪や目を動かす筋肉に炎症が起こる病気です。これにより、瞼が腫れたり、眼が飛び出してきたり、眼が動かしにくくなり、ものが二重に見えたりするようになることがあります。
“甲状腺”という名前がついていますが、甲状腺眼症に対してはバセドウ病とは異なる治療が必要となります。バセドウ病が悪化すると甲状腺眼症も悪くなることが知られているため、まずは甲状腺機能を安定させることが重要です。一方で、甲状腺機能が安定していても、甲状腺自己抗体が陽性の症例では甲状腺眼症が悪くなる場合があることから、バセドウ病の治療中は目の症状に注意しましょう。また、バセドウ病と診断される前に甲状腺眼症が発症することもあります。

また、頻度は数%と少ないですが、重症化すると視神経障害などによる失明の恐れもあるため、早期に見つけて、適切な治療を受けることが重要です。少しでも気になることがあれば、一度チェックシートを使って確認してみましょう。
 Q1. 過去にバセドウ病や橋本病(慢性甲状腺炎)の診断を受けたことがありますか?
Q1. 過去にバセドウ病や橋本病(慢性甲状腺炎)の診断を受けたことがありますか? Q2. 次のうち最近当てはまる症状があれば選択してください(複数回答可
Q2. 次のうち最近当てはまる症状があれば選択してください(複数回答可 Q3. 次のうち、朝起きた時に感じる症状について当てはまるものを選択してください(複数回答可)
Q3. 次のうち、朝起きた時に感じる症状について当てはまるものを選択してください(複数回答可)*近くではなく少し遠くを見てください(ドアの端やカレンダーなど)
作成年月:2024年11月
予防
バセドウ病ははっきりした発症メカニズムが解明されていないため、確立した予防方法はありません。しかし、バセドウ病は、薬物療法などを行っても強いストレスや疲れなどが生じると、急激に症状が悪化して甲状腺ホルモン量が激増する”甲状腺クリーゼ”を引き起こすことがあります。命に関わることも多いため、バセドウ病と診断された場合は適切な治療を続けるとともに、日ごろからリズムを整えてストレスや疲れがたまりにくい生活を心がけるようにしましょう。
「バセドウ病」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください