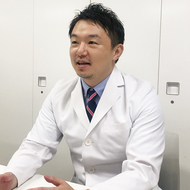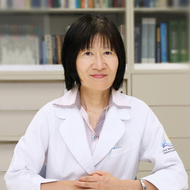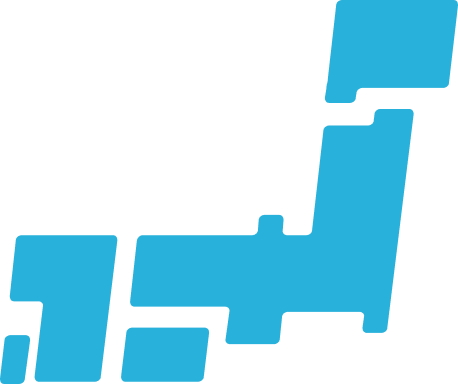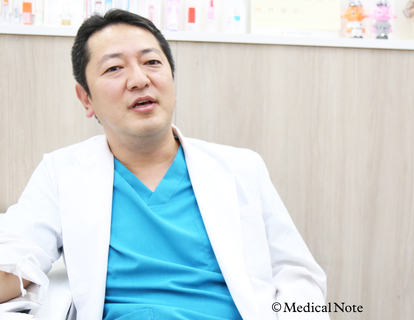概要
乾癬とは、皮膚の表面の細胞が過剰に増殖することで銀白色の皮膚の粉(鱗屑)が付着した赤い皮疹(紅斑)が全身に生じる病気のことです。
乾癬は併発する症状に応じていくつかのタイプに分かれています。尋常性乾癬とは乾癬の中でももっとも多い病気であり、乾癬患者の約90%を占めます。
尋常性乾癬では、乾癬特有の皮膚症状が全身にみられます。皮膚症状の大きさ・数・形はさまざまで、皮疹同士がくっついて大きな病変をつくることもあります。尋常性乾癬は青壮年期に発症することが多く、発症により生活の質が低下し、精神的な影響が生じることがあります。
尋常性乾癬は、重症度に応じて外用治療、光線治療、内服治療、生物学的製剤で治療します。
原因
乾癬発症には、遺伝的素因、環境因子、免疫学的要因が関わっていると推定されています。
遺伝的素因
乾癬は家族内発症する割合が高いことから、遺伝的な素因が関与していると考えられています。欧米では家族内発症が20〜40%、日本では4〜5%に見られると報告されています。
環境因子
環境要因として考えられているものは、外傷などの外からの刺激、感染症や薬剤、食事内容、ストレスなどです。
免疫学的要因
乾癬では、ヘルパーT細胞と呼ばれる白血球の一種が病変部位で免疫反応を起こすことが分かっています。TNF-α、IL-17、IL-23という炎症性物質を産生する細胞が炎症に関与していることも知られており、近年それらを抑制する治療法が開発され、実際に効果を示しています。
症状
皮膚症状
尋常性乾癬では、全身にくっきりと盛り上がった赤い皮疹のような症状が現れます。皮膚は赤く盛り上がり、まわりには銀白色で皮膚に粉がふいたような状態(鱗屑)が見られます。
好発部位は、刺激を受けやすい頭・肘・膝・お尻です。約50%の患者で皮膚症状にかゆみを伴います。また、爪が粗く研がれたように変形したり、へこんだりする症状も高頻度でみられます。
そのほかの症状
皮膚などの症状は精神的なストレスとなり、生活の質を低下させます。また、尋常性乾癬ではTNF-αと呼ばれる物質が体内で増加し、これに関連して糖尿病の悪化、心血管病変の形成などを引き起こすことも知られています。
検査・診断
尋常性乾癬は症状の出る部位によって、ほかの皮膚疾患と区別がつきにくい場合があります。この場合は、皮膚を少し採取して顕微鏡で確認する病理検査を行います。また、尋常性乾癬では糖尿病や心血管系イベントのリスクが高いため、血圧測定、血液検査(血糖やHbA1c、脂質など)を行うことも大切です。
尋常性乾癬に使用される薬剤に関連して副作用を生じることもあるため、副作用の有無を適宜検索するための検査も重要です。
治療
尋常性乾癬の治療では、症状に応じて薬物療法(外用薬や内服薬、生物学的製剤)や紫外線療法を行います。
外用薬・内服薬
尋常性乾癬の治療は、通常は外用薬(塗り薬)から開始します。使用されることのある外用薬としては、ステロイド外用薬や活性型ビタミンD3外用薬および、これらの配合外用薬が挙げられます。また内服薬としては、ビタミンA誘導体、免疫抑制剤(シクロスポリン、メトトレキサート)、PDE4阻害薬などが挙げられます。
紫外線療法
尋常性乾癬では紫外線を全身に当てる紫外線療法が選択されることがあります。紫外線療法は、薬を外用(または内服)後、波長の長い紫外線を照射する治療です。近年では311nm前後の紫外線(ナローバンドUVB)が乾癬に有効であることが示されています。
ナローバンドUVBの照射が可能になってからは薬外用(内服)も必要なく、照射時間も短くなり、現在はこのナローバンドUVB照射が急速に普及しています。また、難治の部位にはターゲット型のエキシマライト(308nm)による部分照射を行うことで全身の総紫外線照射量を減らすことが可能です。
生物学的製剤
重症の尋常性乾癬に対しては、生物学的製剤を使用することを検討します。生物学的製剤の治療効果や奏功率はとても高く、ほとんどの患者において効果を期待することができるといわれています。
2010年に認可された抗TNFα製剤に加え、3か月毎投与で効果を維持する抗IL-12/23p40抗体、さらにはIL-17関連抗体や抗IL23p19抗体などが続々と登場し、皮疹が完全に消失する患者さんも出現してきています。
乾癬の相談ができる医療機関を探す
エリアから探す
「尋常性乾癬」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください