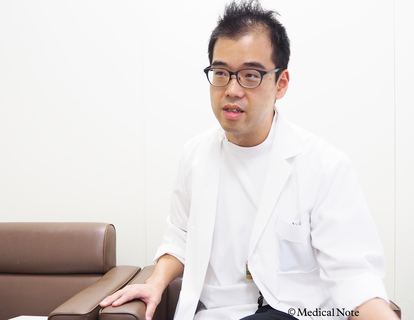概要
水痘とは、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)に感染することによって、発熱や倦怠感とともに特徴的な発疹が全身に生じる病気です。一般的には“水ぼうそう”とも呼ばれています。
9歳以下の子どもがかかることが多く、発症すると強いかゆみを伴う発疹が全身に広がっていきます。発熱やかゆみを伴うこともありますが、発疹以外の症状は比較的軽いことが多く、発疹も一週間前後で水疱(水ぶくれ)から痂皮(かさぶた)となって剥がれ落ち、自然に回復します。一方、成人がかかると重症化することもあり、肺炎や髄膜炎、脳炎などの合併症を発症することがあります。
水痘は小児を中心に年間で100万人以上がかかっていましたが、水痘・帯状疱疹ウイルスに対するワクチンが2014年から乳児期の定期接種に定められたため、患者数は減少していくことが期待されています。
原因
水痘の原因は水痘・帯状疱疹ウイルスに感染することです。水痘・帯状疱疹ウイルスは感染力が非常に強く、感染者の唾液や発疹から出た浸出液などに含まれるウイルスは、容易に他者へと感染します。水痘・帯状疱疹ウイルスは一般的な感染症に多い飛沫感染や接触感染だけでなく、空気感染も起こし得るのが特徴です。このため、感染者の唾液や浸出液に触れたり、それらが付着したものを触れたりしなくとも、感染者と同じ空間にいるだけで感染してしまうのです。このため、保育施設や学校などの集団生活の場で感染が広がりやすく、子どもがかかりやすい感染症のひとつとなっています。
通常、水痘は一度感染すると免疫が形成されるので再び感染することはない終生免疫とされているため、成人がかかることは少ないとされています。しかし、子どもの頃に水痘にかかっていない、もしくは予防接種を受けていない成人は免疫がないため、水痘・帯状疱疹ウイルスに感染する機会があればかかってしまうことがあるのです。
症状
水痘は、ウイルスに感染すると10~21日ほどの長い潜伏期間を経て発熱、頭皮を含む全身の発疹、倦怠感などの症状が引き起こされます。
子どもの場合は、症状が強いかゆみを伴う発疹から現れることが多いというのが特徴です。頭皮や顔に現れた発疹は、胴体、手足へと全身に広がって次々と新しい発疹が出現します。水痘の発疹は、紅斑(赤いできもの)から丘疹(やや尖った膨らみのある皮疹)、水疱(みずぶくれ)、痂皮(かさぶた)と変化していくのが特徴で、発症中はさまざまな形態の発疹が見られます。発疹は通常1週間前後で全てが痂皮となって剥がれ落ち、発症中は38℃前後の発熱や倦怠感が2~3日続くこともありますが、症状は比較的軽度なことがほとんどです。
一方、成人の場合は重症化することが多く、高熱が続いたり、発疹に細菌感染を引き起こしたりすることもあります。また、肺炎や髄膜炎、脳炎などの重篤な合併症を起こしやすく、死亡率も子供に比べて10~20倍にも上るとされています。
検査・診断
水痘は特徴的な発疹が見られるため、その症状から検査をせずに診断が下されることが多いのが現状です。しかし、確定診断のためには、水痘・帯状疱疹ウイルスに対する抗体の有無を調べたり、発疹内部に溜まった液体や喉を拭った液体にウイルスの遺伝子が含まれているか、などの検査をしたりする必要があります。
多くは症状のみで診断されますが、予防接種を受けた後にかかった場合などは特徴的な症状が現れにくいこともあり、症状のみで診断することができない場合にこれらの検査が行われるのが一般的です。
治療
水痘に対する治療は薬物療法が主体ですが、基本的には発疹のかゆみを抑える石炭酸亜鉛華リニメント、細菌感染を防ぐための抗菌薬などの塗り薬のみが用いられます。発熱などに対して解熱剤が使用されるケースもありますが、子どもの場合に起こる症状は、発疹以外の多くが軽度であるため治療が必要になることはほとんどありません。
一方、成人がかかった場合など重症化したケースや重症化が予想されるようなケースでは、水痘・帯状疱疹ウイルスに対する抗ウイルス薬“アシクロビル”の点滴が行われます。
「水痘」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください