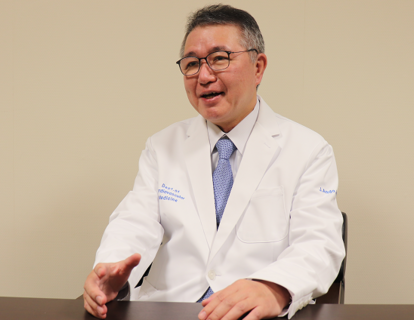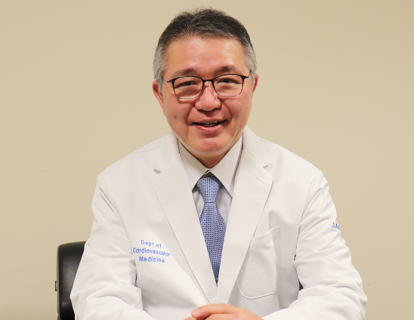概要
狭心症とは、心筋(心臓を構成する筋肉)に血液を行き渡らせる“冠動脈”が狭くなることにより、一時的に心筋が酸素不足に陥って胸の痛みや圧迫感を引き起こす病気のことです。
狭心症による症状は通常数分以内に収まりますが、放置すると冠動脈が完全に詰まる“心筋梗塞”を引き起こす可能性があるため、危険な病気の1つと考えられています。
主な発症原因は動脈硬化によって冠動脈が狭くなることですが、冠動脈自体に異常がないにもかかわらずけいれんを起こしたように収縮することで発症するケースや、大動脈弁狭窄症などの病気が原因で引き起こされるケースもあります。
また、狭心症は運動後に胸痛発作が生じることが多いものの、夜間就寝時や安静時に発症することも多く、さらに頻回に発作が生じる場合もあります。発作の回数が頻回になり、痛みが強くなると危険な兆候の可能性があるので病院の受診が必要です。
治療法は発症の原因や症状の強さ、発作の頻度などによって異なり、基本は薬物療法が行われますが、その後にカテーテル治療やバイパス手術が必要になることも少なくありません。
原因
狭心症は、冠動脈に狭窄が生じることによって心筋に十分な酸素が行き渡らなくなることによって生じる病気です。
冠動脈に狭窄が生じる原因としてもっとも多いのは、“動脈硬化”です。動脈硬化は高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病によって引き起こされる血管の変化のことであり、血管の内側の壁にコレステロールなどが沈着することで血管が狭くなります。冠動脈に動脈硬化が生じると、当然ながら心筋へ流れる血液が減少します。そして、運動後など心臓の拍動が増えて心筋により多くの酸素が必要になったときに、いわゆる“酸欠状態”となって胸の痛みや圧迫感などを引き起こすのです。
一方、狭心症は冠動脈が一時的にけいれんを起こして強く収縮することによって発症することもあります。このようなタイプの狭心症は、血管を広げる作用のある“一酸化窒素(NO)”と呼ばれる物質の合成が加齢とともに低下していくことが主な原因と考えられており、安静時にも発症することが特徴です。
そのほか、狭心症は大動脈弁狭窄症や大動脈弁逆流症、肥大型心筋症などの病気によって冠動脈の血流が低下することを原因として発症することもあります。
症状
狭心症の特徴的な症状は、胸の痛みや圧迫感が引き起こされる“発作”が生じることです。
特に胸の痛みは、1か所にとどまらず、左肩、左腕、顎、歯、背中、腹部などに響くように放散することが特徴で、なかには胸の痛みを感じずに別の部位のみに痛みが生じるケースもあります。また、冷や汗や吐き気、めまいなどの症状を伴うことも少なくありません。
通常、運動後に発作が生じる“労作性狭心症”では、安静にしていれば数分以内に発作が治まりますが、冠動脈がけいれんを起こすタイプの“冠攣縮性狭心症”では症状が30分近く続くことがあります。
また、発作が頻回に生じる“不安定狭心症”は冠動脈が完全に閉塞してしまう前触れの症状であると考えられています。
検査・診断
症状などから狭心症が疑われるときには、次のような検査が行われます。
心電図検査
心臓の電気的な動きを体に取り付けた電極が感知して波形として記録する検査です。
心筋が酸素不足に陥ると特徴的な波形が見られるため、診断の重要な手がかりとなります。しかし、発作が生じているときにしか特徴的な波形が見られないため、労作性狭心症が疑われるときは踏み台昇降やトレッドミルなどを用いて運動を行い、運動前後の心電図波形の変化を見る“運動負荷心電図検査”を行うことが一般的です。
血液検査
心筋のダメージの有無や程度などを調べるために行う検査です。通常、狭心症は心筋の酸素不足がごく短時間に限られているため血液検査で異常が見られることはありませんが、心筋の状態を確認するために行われます。
心臓超音波検査
心臓の動きや機能を調べるための検査です。外来などでも簡便に行うことができるため、狭心症の経過を観察する際にも用いられます。
心臓CT検査
造影剤(血管が映りやすくなる薬剤)を投与しながらCT撮影を行うことで、冠動脈の状態を三次元に描出することができる検査です。冠動脈が狭くなっている部位や位置などを詳しく調べることができるため、最近は確定診断に用いられます。
冠動脈造影検査
足の付け根や腕などからカテーテル(医療用の細い管)を動脈に挿入して心臓まで至らせ、そこから造影剤を流し込むことで冠動脈の状態を調べる検査です。
心臓CT検査と同じく、冠動脈の病変を詳しく調べることができ、冠攣縮性狭心症が疑われる場合は冠動脈の収縮を促すアセチルコリンと呼ばれる薬剤をカテーテルから注入して発作が生じるか調べる“アセチルコリン負荷試験”を行うことができます。
治療
狭心症の治療は原因・重症度・発作の頻度などによって、次のようなものが行われます。
薬物療法
狭心症の治療には基本的に薬物療法が行われます。
使用される薬剤は、冠動脈を広げる“血管拡張薬”や心臓の活動を抑えて必要な酸素量を減らす“β遮断薬”などです。また、冠動脈の動脈硬化が強い場合には、心筋梗塞を予防するため血栓(血の塊)ができにくくなる抗血小板薬などの内服が必要になることも少なくありません。
一方、発作が生じたときには冠動脈を速やかに広げる作用のある硝酸剤が使用されます。
カテーテル治療
カテーテルを用いて狭くなった冠動脈を風船で広げたり、冠動脈にステント(網目状の筒)を挿入したりする治療のことです。
“冠動脈形成術”とも呼ばれ、薬物療法では発作が抑えられないケースや、心筋梗塞に移行するリスクが高いケースなどで行われますが、ときに症状がないケースでも、虚血があれば治療を考慮することがあります。
手術
足や胸、腕、胃などの動脈を採取し、狭くなった冠動脈にバイパス(迂回路)を作成する治療が行われることがあります。“冠動脈バイパス術”と呼ばれ、カテーテル治療が困難な場合や冠動脈が狭くなっている部位が複数ある場合などに手術が行われることがあります。
予防
狭心症の多くは高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が発症の引き金となっています。このため、狭心症を予防するには、食事や運動習慣、睡眠など生活習慣を整えることが大切です。また、そのほかにも喫煙や過剰な飲酒、ストレス、急激な寒冷環境なども発症の原因となるため注意しましょう。
さらに、狭心症を発症した場合はできるだけ早い段階で治療を開始し、発作が起きないよう医師の指示に従って適切な治療を続けていくことが大切です。
狭心症でお悩みの方へ
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
「狭心症」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「狭心症」に関連する記事