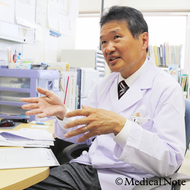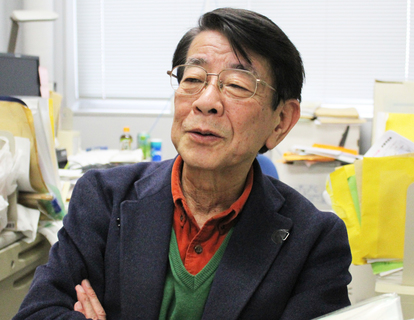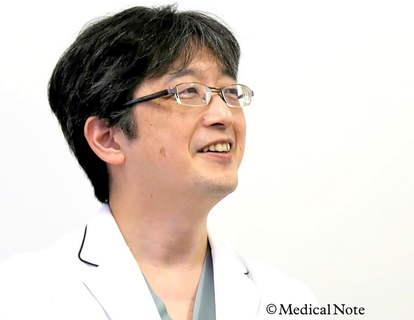概要
生活習慣病とは、食事・運動・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に関与する病気のことを指します。生活習慣病には、主に以下のような病気があり、日本人の健康に大きく影響するものが多いです。
生活習慣病には予後不良のものも多いため、予防が重要といえます。
 人生100年時代を健やかに–健康寿命を長く生きるために社会福祉法人 大阪暁明館病院 特別顧問、...児玉 和久 先生
人生100年時代を健やかに–健康寿命を長く生きるために社会福祉法人 大阪暁明館病院 特別顧問、...児玉 和久 先生近年、「人生100年時代」という言葉を耳にすることが多くなってきました。寿命は伸びてきていますが、できるだけ健康を保ちながら長く生きることは誰...続きを読む
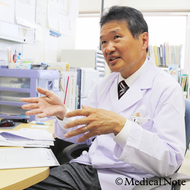 将来の生活習慣病を予防する-食生活を見直し、赤ちゃんの低体重化を防ぐ河内友絋会 河内総合病院 副院長高屋 淳二 先生
将来の生活習慣病を予防する-食生活を見直し、赤ちゃんの低体重化を防ぐ河内友絋会 河内総合病院 副院長高屋 淳二 先生日本では10人に1人の赤ちゃんが、2,500gに達しない低出生体重で生まれてくるといわれています。赤ちゃんの低体重には、妊娠中のお母さんの食生...続きを読む
 健康診断・人間ドックの詳細――がん検診や脳ドックについても解説財団法人同友会 ライフメディカル健診プラ...高橋 大介 先生
健康診断・人間ドックの詳細――がん検診や脳ドックについても解説財団法人同友会 ライフメディカル健診プラ...高橋 大介 先生健康診断・人間ドックではさまざまな検査がパッケージとなっていることが多いですが、はたして過不足はないのでしょうか。これは年齢や持病の有無、ま...続きを読む
原因
生活習慣病の発症は、その名前からも示唆されるように「日々の生活習慣」が深く関係しています。具体的には、食習慣や運動習慣・休養・喫煙・飲酒などです。たとえば、カロリーの過剰摂取は糖尿病につながります。また、睡眠が十分に取れていない状況では高血圧につながる可能性があります。
しかし、これらの要因が一対一対応で糖尿病や高血圧などの病気につながるわけでなく、生活習慣が複合的に組み合わさり生活習慣病が発症します。また、家系に糖尿病、高血圧の方がいらっしゃると、生活習慣病になるリスクが高くなると考えられています。
症状
生活習慣病の糖尿病や高血圧などが発症した初期の段階では、特に大きな自覚症状はありません。しかし、生活習慣病が長年持続すると、重篤な症状が生じるようになります。
たとえば、糖尿病では、目が見えなくなる・腎臓を悪くして透析が必要になる・手足の感覚がなくなるなどの状態となることがあります。また、糖尿病や高血圧などは動脈硬化を促進し、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こします。脳卒中では突然の意識障害や手足の麻痺、言語障害などが生じることがあります。急性期に治療がうまくいった場合でも、手足の麻痺が残る・嚥下機能が障害を受け誤嚥性肺炎を繰り返す・寝たきりになってしまうなどの状況になることがあります。急性心筋梗塞を起こすと胸痛や意識消失などが生じます。治療が奏功せずに亡くなることや、心臓の機能が低下して心不全症状を発症しやすくなる場合もあります。
また、生活習慣病では、肺がんや大腸がんなどの悪性疾患をみることもあります。このように、生活習慣病では身体の機能を著しく低下させるものが多く、自立した健康な生活を送ることができなくなるケースもあります。
検査・診断
予防に重点が置かれる一方、早期発見も重視されています。健康診断における体重測定や血圧測定は、肥満や高血圧の発見に役立ちます。また、血液検査を通して糖尿病や高脂血症を疑われることもあります。
さらに尿検査も加えることで、腎臓の病気が指摘されることもあります。必要に応じて眼底検査が追加されることもあり、糖尿病関連の網膜疾患の早期発見に役立てられています。がんの早期発見を目的とした検査も行われます。大腸がんであれば、便検査にて便潜血の有無を確認します。胸部単純レントゲン写真を行うことで、肺がんの有無のスクリーニングがおこなわれることもあります。
 健康診断・人間ドックの特徴や違いとは財団法人同友会 ライフメディカル健診プラ...高橋 大介 先生
健康診断・人間ドックの特徴や違いとは財団法人同友会 ライフメディカル健診プラ...高橋 大介 先生「健診」や「人間ドック」という言葉を聞いたことはあるでしょうし、少なくとも健診は受けたことがある方が多いかもしれません。しかし、具体的な違いを...続きを読む
 健康維持のために活用したい、人間ドック、健康診断、検診の特徴[医師監修]
健康維持のために活用したい、人間ドック、健康診断、検診の特徴[医師監修]健診、検診、人間ドックはそれぞれ特徴や目的が異なるものです。定期的に健康診断を受けたり、症状が出ていなくても検診を受けたりすることで、自身の健...続きを読む
 人間ドックとは――国立国際医療研究センター病院 人間ドックセンターを例に国立健康危機管理研究機構 国立国際医療セ...梶尾 裕 先生
人間ドックとは――国立国際医療研究センター病院 人間ドックセンターを例に国立健康危機管理研究機構 国立国際医療セ...梶尾 裕 先生人間ドックとは、日帰りまたは短期間の入院によって全身の状態を詳しく調べる精密検査のことで、病気の早期発見と健康増進を図ることを目的に行われます...続きを読む
治療
治療では、以下のような取り組みが重要です。
- 禁煙する
- 食生活を見直す
- 運動量を増やす など
糖尿病や高血圧と診断された場合には医療機関を受診し、血糖値・血圧値をコントロールすることが求められます。
運動面からの改善という意味では、インターバル速歩と呼ばれる方法の有効性も指摘されています。筋肉に負荷をかける「さっさか歩き」と、負荷の少ない「ゆっくり歩き」を交互に行うことで、筋力や持久力を向上させることができる新たなトレーニング法です。また、特別な運動器具を必要とせず、全体を通してトータル15分から取り組むことができる気軽さも大きなメリットです。
厚生労働省は、運動という考え方以外に「生活活動」という考え方を提唱し、日々の生活で積極的に取り組むことを推奨しています。生活活動とは、階段の上り下り、掃除をする、買い物に行く、重い荷物を持つなどの動きのことです。これらは日常で意識せず行っている動きですが、このような動きも健康づくりにつながります。
また、動物性脂肪の取り過ぎも生活習慣病につながります。食塩やマグネシウムなどの摂取に気をつけた食事を心がけることも重要です。
「生活習慣病」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「生活習慣病」に関連する記事