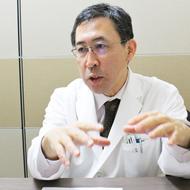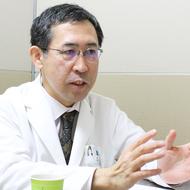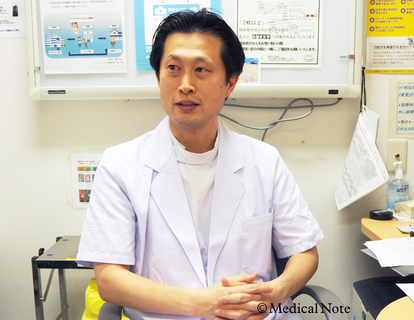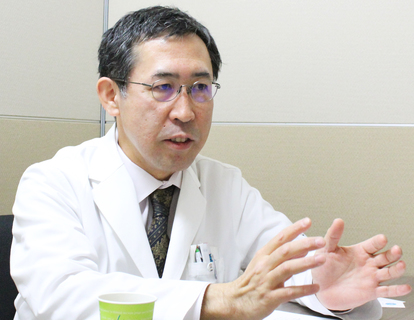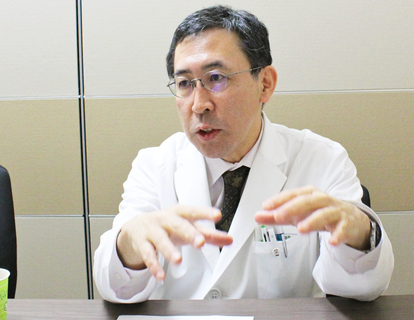概要
誤嚥性肺炎とは、食事時の誤嚥(飲食物や唾液、逆流した胃液が気管に入ってしまうこと)によって生じる肺炎のことを指します。
喉の奥は、空気を肺に送る“気管”と、飲食物などを胃に送る“食道”の2つの道に分かれていて、食べ物や水、唾液を飲み込むと脳が指令を出して気管の入り口を塞ぎ、食道に流れて胃に送られるようになっています。
しかし、加齢などで飲み込む機能が弱くなると、飲食物や唾液、胃液などが気管に入ってしまうことがあります。これを誤嚥といい、誤嚥したものと一緒に細菌が肺に入って炎症が起こったものが誤嚥性肺炎です。
特に高齢の方に多く、高齢の肺炎患者さんのうち7割以上が誤嚥による誤嚥性肺炎とされています。肺炎は日本人の病気による死者数の上位を占める病気で、死亡率が高いことから、誤嚥性肺炎を起こさないよう、また悪化を防ぐために早めの対策が必要です。
原因
誤嚥性肺炎はその名のとおり、誤嚥によって引き起こされる肺炎です。誤嚥は、病気によって嚥下反射(飲み込む力)が障害されたり、食道が狭くなったり、加齢によって飲み込む力が弱くなったりすることで起こります。
病気としてはパーキンソン病やアルツハイマー病といった神経疾患、筋疾患、脳梗塞の後遺症、喉の腫瘍(食道がんや咽頭がん)などが挙げられ、中でも認知症や脳梗塞による発症率が高いとされています。
このように何らかの原因によって誤嚥を起こし、誤嚥したものと一緒に細菌が肺に入ることで肺炎を発症します。原因となる菌は肺炎球菌や口の中の常在菌である嫌気性菌が多いため、口の中の状態が清潔ではない場合には肺炎の原因となる菌が増殖しやすく、肺炎を起こすリスクが高まります。
また、寝たきりの方も咳反射が弱くなって嚥下機能が低下するため、肺炎を発症しやすくなります。そのほか、栄養状態が悪いことや免疫機能の低下も発症に関係し、このような状態にある高齢の方では死に至るケースも少なくありません。
症状
肺炎の典型的な症状は、発熱、咳、濃い色の痰です。しかし、誤嚥性肺炎においてはこのような症状が出にくく、普段よりなんとなく元気がない、ぼんやりとしている、食欲がないなどの症状しか現れないことが多いのが特徴です。
なお、誤嚥については食事中にむせる、咳き込むといった症状が出現します。ただし、気道防御反応(気道を守る反応)が低下している場合には、誤嚥をしてもむせたりしないことがあり、高齢の方に多くみられます。
また、誤嚥は就寝中に生じることもありますが、不顕性誤嚥といって気管に入る唾液や胃液などが少量なら誤嚥を自覚しないため、多くの場合、誤嚥性肺炎は繰り返し発症します。
検査・診断
明らかに誤嚥がある人や、すでに嚥下機能の低下が確認されている人では胸部X線検査が行われ、この検査で肺炎像を認めると誤嚥性肺炎と診断されます。
また、肺炎を起こすと血液中に白血球が増えたり、炎症性物質が出たりすることがあるため、血液検査で白血球増多やCRP(C反応性タンパク)上昇が認められた場合にも診断されます。
治療
誤嚥性肺炎では、原因菌に対する抗菌薬を用いた薬物療法が基本となります。全身状態や呼吸状態が悪い場合には入院して治療をします。
抗菌薬は肺炎の原因となる菌に効果があり、炎症を鎮めることができますが、誤嚥を防ぐ効果はなく、治療後に誤嚥を起こすと再び発症する可能性があります。したがって、誤嚥性肺炎では日々の口腔ケアによって口の中を常に清潔に保つことや誤嚥防止のリハビリテーションを行うことも大切です。また、低栄養は飲み込む力や免疫機能を低下させるため、誤嚥のある人では難しい問題ですが、十分な栄養を取ることが求められます。
喫煙は、気道の粘膜の浄化を抑制して細菌が付きやすくなるといわれているため禁煙も重要です。肺炎球菌ワクチンの接種も肺炎の予防に有効とされています。
「誤嚥性肺炎」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください