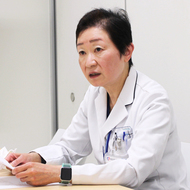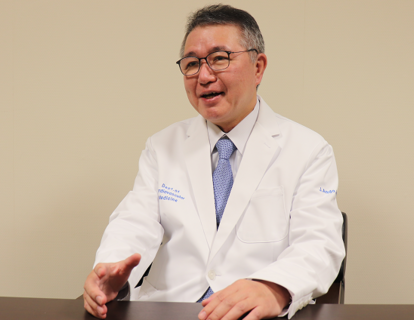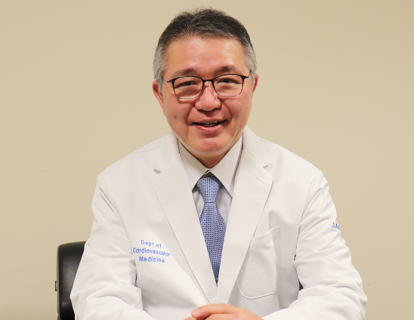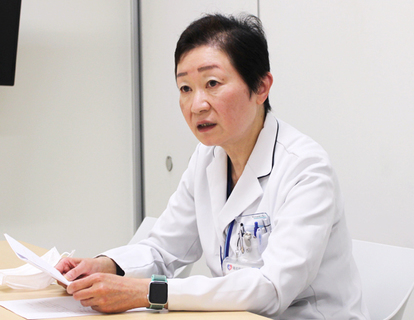概要
心筋梗塞とは、心筋(心臓を構成する筋肉)に血流を送る“冠動脈”が閉塞することによって血流が途絶えることで、心筋が酸素不足の状態に陥る病気のことです。
発症すると冷や汗や吐き気などを伴う強い胸の痛みや圧迫感が生じ、やがて心筋の細胞が壊死して死に至る可能性も少なくありません。また、冠動脈が閉塞する部位によっては広範囲な心筋の酸素不足が生じることで突然死に至るケースもあります。
心筋梗塞の原因は冠動脈の動脈硬化であり、狭くなった血管に血栓(血液の固まり)が詰まることで完全な閉塞が生じると考えられています。突然発症する場合も多いですが、一般的には動脈硬化によって心筋への血流が低下することで、運動後など心筋が必要とする酸素が増えるときにのみ酸素不足の状態となって胸の痛みなどを引き起こす“狭心症”から進行することが多いとされています。
 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の種類と症状――みぞおちの上の痛みは受診を国立国際医療センター 心臓血管外科 医長...田村 智紀 先生
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の種類と症状――みぞおちの上の痛みは受診を国立国際医療センター 心臓血管外科 医長...田村 智紀 先生虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん)とは、心臓の筋肉に十分な血液が行き渡らなくなり、胸部の痛みなどの症状が起こる病気の総称です。具体的な病...続きを読む
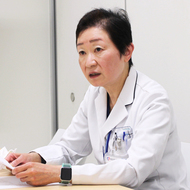 心筋梗塞とは? 発症する前に早めの対策が重要――狭心症との違いやリハビリテーションについて菊名記念病院 循環器センター センター長本江 純子 先生
心筋梗塞とは? 発症する前に早めの対策が重要――狭心症との違いやリハビリテーションについて菊名記念病院 循環器センター センター長本江 純子 先生日本人の死亡原因で2番目に多い心筋梗塞(しんきんこうそく)。発症すると心臓の筋肉が時間とともに壊死(えし)して命に関わる恐れがあるため、できる...続きを読む
 心筋梗塞に前兆はあるのか? 心筋梗塞の原因や症状について解説医療法人 札幌ハートセンター 名誉会長藤田 勉 先生
心筋梗塞に前兆はあるのか? 心筋梗塞の原因や症状について解説医療法人 札幌ハートセンター 名誉会長藤田 勉 先生心筋梗塞とは、何らかの原因で冠動脈が塞がれてしまい、心筋が壊死を起こした状態です。心筋梗塞を発症する前には、胸痛や圧迫感、背中の痛み、歯の痛み...続きを読む
原因
心筋梗塞の原因は冠動脈の動脈硬化です。
動脈硬化とは、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病や喫煙習慣によって引き起こされる血管の変性であり、血管の内側の壁が傷ついてそこにコレステロールなどが沈着することで血管が硬く狭くなります。その動脈硬化が破綻(破裂)することにより血栓ができて、急激な血流低下から血管の閉塞を生じます。
このため、心筋梗塞は好ましくない生活習慣の積み重ねによって生じると考えられています。
症状
心筋梗塞は、突然の胸の痛みや圧迫感を生じることが特徴です。
痛みの程度は非常に強く、冷や汗や吐き気・嘔吐を伴うことも少なくありません。また、痛みは胸の一部分だけでなく、左肩、左腕、顎、歯、背中、上腹部など広い範囲に響くように放散します。
なかには胸以外の部位にのみ痛みを感じることもあり、発見が遅れるケースも見られます。腹部痛で発症する心筋梗塞も多くみられ、見逃されるケースも多くみられます。また、まれですが、無症状もしくは極めて軽症の症状の人もいます。症状が軽いから軽症とは限りません。
このような症状は長時間続き、酸素不足に陥った心筋が徐々に壊死し、心臓のポンプ機能は低下していきます。そして、全身への血流が滞ることでむくみや呼吸困難、意識消失などの症状を引き起こし、心室細動などの不整脈や心臓破裂を引き起こして最終的には死に至ることもあります。心筋梗塞の三大合併症は心不全、不整脈、心臓破裂です。
検査・診断
心筋梗塞が疑われる場合は早急な治療が必要になるため、次のような検査が迅速に行われます。
心電図検査
心臓の電気的な動きを、体表面に装着した電極が読み取って波形として記録する検査です。心筋梗塞による心筋へのダメージが生じると、特徴的な波形の心電図となるため心筋梗塞の可能性も迅速かつ簡便に調べるのに適した検査といえます。
また、心電図検査の結果からは、冠動脈が閉塞した部位を大まかに予測することも可能です。
血液検査
心筋のダメージの程度などを調べるために行う検査です。心筋梗塞が疑われた場合はほぼ全ての例で行われ、治療後も経過を評価するために繰り返し実施されます。
心臓超音波検査
心臓の動きや心臓が血液を送り出す機能の程度などを調べることができる検査です。体に負担をかけずに簡便に行うことができるため、救急搬送時などに迅速に行うことが多々あります。
心筋梗塞では冠動脈が閉塞した部位によって心筋にダメージが生じる部位が異なるため、超音波検査で心臓の動きを観察すればどの部位に閉塞が生じているか予測することが可能です。
冠動脈造影検査
足の付け根や腕などの太い動脈からカテーテル(医療用の細い管)を挿入して心臓まで至らせ、カテーテルから血管を描出しやすくする造影剤を流し込むことで冠動脈の状態を詳しく調べる検査です。閉塞が生じている部位や程度などが分かるため、治療方針を決めるうえでも役立ちます。
また、心筋梗塞の多くはカテーテル治療を行うため検査と治療を同時に行うのが一般的です。
治療
心筋梗塞と診断された場合には次のような治療が行われます。
薬物療法
心筋梗塞を強く疑う症状が見られる場合や心筋梗塞と診断された場合は、できるだけ早急に冠動脈を広げる作用のある硝酸剤、さらなる血栓の形成を防ぐための抗血小板薬の投与が行われます。また、痛みや呼吸苦を和らげて心臓の負担を軽減するため、酸素や医療用麻薬(モルヒネ塩酸塩水和物)の投与を実施するケースも少なくありません。
再灌流療法
心筋梗塞発症からの時間が大切であり、12時間以内であれば、基本は再灌流療法が第一選択になります。
再灌流療法は2つあり、カテーテルによるものと薬によるものがあります。基本は、カテーテルによる治療が選ばれますが、ケースにより薬物により試みることもあります。カテーテルによる治療は通常のカテーテル治療と一緒です。薬物による治療では、血栓を溶かす薬を点滴もしくは、直接冠動脈にカテーテルで注入する血栓溶解療法を行います。
カテーテル治療
冠動脈内まで至らせたカテーテルを用いて、閉塞している部位を“バルーン(風船)”で膨らませて拡張し、血管の広がりを維持する効果のある“ステント(網目状の筒)”を挿入する治療を行います。再灌流療法といわれている方法で、発症から12時間以内に血流が回復することが大切だといわれています。
約9割のケースはこのような“経皮的冠動脈形成術”を行えば、冠動脈の血流が回復するとされていますが、時間が経過すると再び狭窄や閉塞を引き起こすリスクもあるのがデメリットの1つです。
手術
カテーテル治療が困難な場合には、脚や腕、胃などから採取した血管で閉塞した冠動脈に迂回路を作る“バイパス手術”が行われます。
緊急性を問われる冠動脈治療のおいては、選択されることは少ないです。合併症(心臓破裂など)のときに行うことがあります。
予防
心筋梗塞は上でも述べたとおり、高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病や喫煙習慣などが積み重なることで発症すると考えられています。そのため、心筋梗塞を予防するには食事や運動などの生活習慣を整え、喫煙者は禁煙を目指すことが大切です。
また、定期的に数分間の胸の痛みなどがある場合は心筋梗塞の前段階である狭心症を発症している可能性があります。病院を受診して検査を受け、適切な治療を続けることで心筋梗塞への進行を予防しましょう。
心筋梗塞でお悩みの方へ
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
「心筋梗塞」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「心筋梗塞」に関連する記事
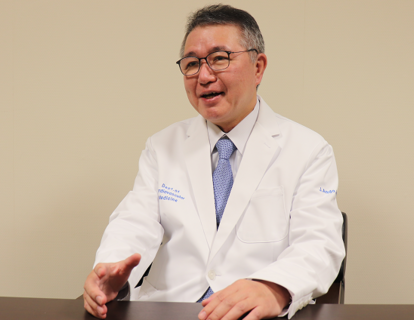 虚血性心疾患が疑われたら――診断の流れと治療の選択肢NTT東日本関東病院 循環器内科 部長安東 治郎 先生
虚血性心疾患が疑われたら――診断の流れと治療の選択肢NTT東日本関東病院 循環器内科 部長安東 治郎 先生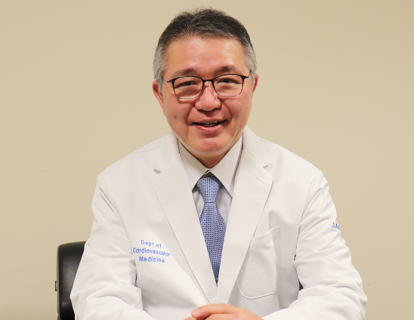 虚血性心疾患の原因と注意すべき症状――自覚症状があればすぐに受診をNTT東日本関東病院 循環器内科 部長安東 治郎 先生
虚血性心疾患の原因と注意すべき症状――自覚症状があればすぐに受診をNTT東日本関東病院 循環器内科 部長安東 治郎 先生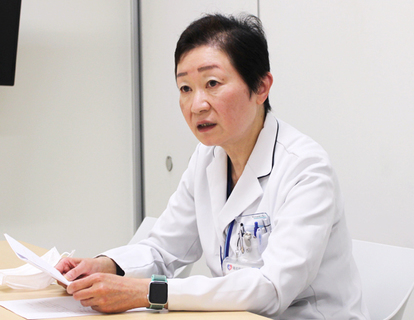 心筋梗塞とは? 発症する前に早めの対策が重要――狭心症との違いやリハビリテーションについて菊名記念病院 循環器センター センター長本江 純子 先生
心筋梗塞とは? 発症する前に早めの対策が重要――狭心症との違いやリハビリテーションについて菊名記念病院 循環器センター センター長本江 純子 先生 心筋梗塞の症状~症状別の起こりやすさや注意すべき前兆について~慶應義塾大学 循環器内科 共同研究員、日...福田 芽森 先生
心筋梗塞の症状~症状別の起こりやすさや注意すべき前兆について~慶應義塾大学 循環器内科 共同研究員、日...福田 芽森 先生 突然発症する心筋梗塞は予防が重要~起こしやすい人の特徴や気を付けるべき生活のポイント~国際医療福祉大学 大学院医学研究科(循環...岸 拓弥 先生
突然発症する心筋梗塞は予防が重要~起こしやすい人の特徴や気を付けるべき生活のポイント~国際医療福祉大学 大学院医学研究科(循環...岸 拓弥 先生