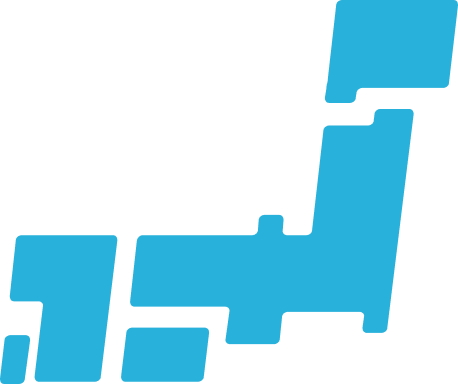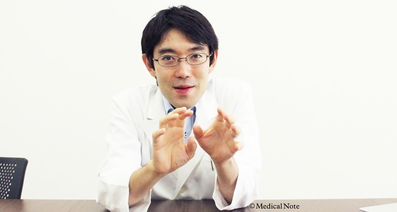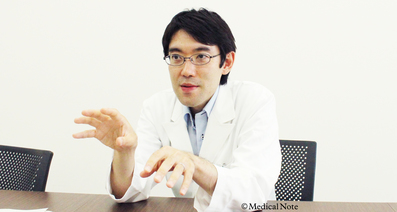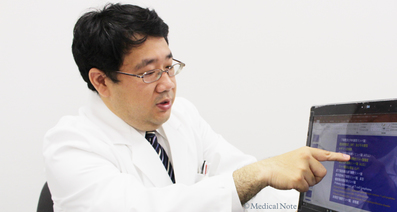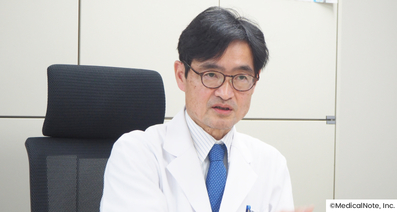びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)は、血液細胞のリンパ球に由来するがんである悪性リンパ腫の一種です。DLBCLでは最初の治療(初回治療)として抗がん剤治療が行われますが、中には効果が得られない場合や治療後短期間で再発する場合があります。主にそのような患者さんに対する治療法として高い効果が期待されているものが、CAR T(カーティー)細胞療法です。
治療に尽力されている国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科の蒔田 真一先生は「CAR T細胞療法は早い時期から検討することが大切」とおっしゃいます。今回は蒔田先生に、DLBCLの特徴や治療選択肢について、特にCAR T細胞療法に焦点を当ててお話を伺いました。
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)の特徴
悪性リンパ腫の中でも、もっとも発生する頻度が高いのが“びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)”です。DLBCLは、悪性度が高く進行が速いという特徴があり、基本的に診断されたらすぐに治療する必要があります。

初回治療の中心となるのは全身への効果が期待できる抗がん剤治療です。DLBCLにおいても、最初にR-CHOP療法*をベースとした抗がん剤治療をしっかりと受けておくことが非常に重要です。この初回の抗がん剤治療によって、約半数の方で治癒(治療終了後、一生リンパ腫が再発しない状態)が得られます。
*R-CHOP療法:3種類の抗がん剤と副腎皮質ホルモン剤を組み合わせたCHOP療法に、抗体薬を加えた治療法。
再発・治療抵抗性のDLBCLとは?
DLBCLは、お話ししたとおり初回治療によって約半数の方で治癒が期待できます。しかし中には、初回治療を受けても、がんが一度も消失しない“治療抵抗性”、初回治療後1年以内に再発する“早期再発”の患者さんが15%ほどいらっしゃいます。
DLBCLと診断されて最初に行う抗がん剤治療は、もっとも効果が期待できるからこそ初回に選択されています。それでも効果がみられない、あるいはすぐに再発するのは、抗がん剤が効きにくい病状であるからであって、ほかの治療法で対抗するべき相手と認識しなければなりません。
一方、初回治療後1年以上が経過してから再発する“晩期再発”においては、若年の患者さんであれば依然として抗がん剤治療と引き続く自家末梢血幹細胞移植が標準治療と考えてよいでしょう。
再発・治療抵抗性のDLBCLに対する治療
主な治療の選択肢――3種類の治療法について
再発もしくは治療抵抗性のDLBCLの2回目以降の治療選択肢には、主にCAR T細胞療法、救援化学療法、自家造血幹細胞移植があります。
CAR T細胞療法は、患者さんの血液からT細胞(がん細胞を攻撃するリンパ球)を取り出し、CARという遺伝子を組み入れて攻撃力を強めた“CAR T細胞”をつくって増やしたうえで、その細胞を体内に戻す治療法です。CAR T細胞が長期間体内にとどまり、増殖しながらがん細胞を攻撃します。

また、救援化学療法は初回治療とは異なる抗がん剤を使って行う薬物療法です。これによって効果が現れれば、自家造血幹細胞移植を検討します。自家造血幹細胞移植は、事前に患者さん自身の造血幹細胞(赤血球、白血球、血小板のもとになる細胞)を採取しておき、強力な抗がん剤治療や放射線治療を行った後に移植して機能を回復させる治療法です。
適切な治療を迅速に選ぶことが大切――CAR T細胞療法の積極的な検討を
DLBCLは、基本的に根絶やしにしなければ再発してきてしまうがんのため、2回目の治療を選択する際には治癒を期待できるかどうかが鍵となります。
治療抵抗性、もしくは初回治療後1年以内に再発した早期再発の患者さんには抗がん剤が効きにくいことから、当院ではCAR T細胞療法を積極的に検討するようにしています。治療抵抗性、早期再発の患者さんの半数程度がCAR T細胞療法によって治癒が得られ、生存期間などの治療成績がかつての標準治療であった抗がん剤治療と比較して優れていることが、複数のランダム化比較試験で示されています。
一方、初回治療後1年以上が経過してから再発した場合(晩期再発)には、抗がん剤治療により効果が得られる可能性が残っています。そのため、年齢が比較的若い方の選択肢としては、救援化学療法と自家造血幹細胞移植を組み合わせた治療を行うことがあります。ただし、自家造血幹細胞移植は体への負担が大きいため、当院では65歳までの患者さんに限定しています。より高齢の方には、晩期再発であってもCAR T細胞療法が検討されます。
CAR T細胞療法の治療の流れ――従来の治療法との違いは?
CAR T細胞療法は、早い段階で受けたほうがよい治療
CAR T細胞療法は高い効果が期待できることに加えて、投与したCAR T細胞が一定期間体内に残り持続的にはたらき続けるというのも、この治療のよい点です。

私は、できる限り早い段階でCAR T細胞療法を検討することが大切だと考えています。その理由は次のとおりです。
1つは、患者さんの血液から採取するT細胞の質がよいほうが、より高い治療効果が期待できるからです。抗がん剤は正常な細胞にも影響を及ぼすため、抗がん剤治療を繰り返し受けているとT細胞の質が低下しやすくなります。たとえば抗がん剤治療を3回受けた後よりも、1回しか受けていない時点のほうがT細胞の質が維持されている可能性が高いのです。
また、CAR T細胞を投与した後には約1か月の入院を必要とするため、入院治療に対応できる体力がなかったり、心機能や腎機能が治療に耐えられる状態でなかったりするとCAR T細胞療法を受けるのは難しくなります。
さらに、患者さんの血液からT細胞を採取して製造施設に送り、できあがったCAR T細胞が届くまで数週間の待機期間があります。そのため、T細胞を採取してからCAR T細胞が届き投与するまでの間、病気をコントロールしておくための治療選択肢が残っていることも重要です。
このように、CAR T細胞療法を受けるには全身状態が安定しており、病気をある程度コントロールしながらCAR T細胞が届くのを待てる状態で、T細胞の質が保たれている必要があります。だからこそ、なるべく早い段階で治療を受けることが大切なのです。
CAR T細胞療法の治療経過
CAR T細胞療法は、私たちの体に本来備わっている免疫の力を利用した治療法なので、がんへのアプローチの仕方が抗がん剤治療とはまったく異なります。そのため、吐き気や脱毛といった抗がん剤治療にみられる副作用はないものの、免疫反応に伴ってサイトカイン放出症候群*や神経毒性**などの副作用が現れる可能性があります。いずれも投与後の入院期間中に起こりやすいことを念頭に置き、慎重に対応しながら実施すべきといえます。
患者さんには、退院後も経過観察のため継続的に通院をお願いしています。CAR T細胞を投与してから数か月は血球減少***などの副作用が懸念されるため、定期的に通院いただき、特に慎重に経過を確認していかなければなりません。通院頻度は血球減少の程度によって判断され、退院当初は当院では週1~2回程度となる方が多いでしょう。血球減少がみられれば、必要に応じて治療薬の投与や輸血により対処します。そのほか、病原体から体を守るB細胞のはたらきが治療によって抑えられるため、感染症にかかったときに重症化しやすくなります。感染症の症状が現れたときには、迅速に適切な治療を受けていただくことが大切です。
また、患者さんやご家族から、この治療の効果はどの時点で判断するのかというご質問をよく受けます。当院では投与後3か月、6か月の時点でPET-CT検査を実施し、効果を判断しています。患者さんには「まずはこの2つのポイントで病気を抑えられている状態を目指しましょう」とお話ししています。

CAR T細胞療法に限った話ではありませんが、治療を受ける患者さんやご家族は、ほかにもさまざまな疑問や不安を抱えていらっしゃると思います。当院では、状況に応じて看護師がサポートにあたるなど、多職種で連携しながら疑問を解消し、不安を和らげていただけるよう努めています。
*サイトカイン放出症候群:大量のサイトカイン(免疫細胞を活性化させるタンパク質)が放出され、高熱や血圧低下、呼吸不全などの症状が現れること。
**神経毒性:サイトカイン放出症候群で放出されたサイトカインが脳に作用することなどにより、震えやけいれん、認知機能低下などの症状が現れること。
***血球減少:血球(赤血球、血小板、白血球)が減ること。CAR T細胞投与後、約1~2週間で起こり、1週間ほどで改善するものの、その後再び低下するケースもある。
CAR T細胞療法で大切なこと――治療後は好きなことをしてほしい
適切なタイミングで治療を始められるように
DLBCLは悪性度が高く進行が速いため、CAR T細胞療法を選択したらできる限り早くT細胞を採取するために必要な検査などのスケジュールを組んでいきます。
当院では、セカンドオピニオン*で来られた患者さんであっても、必要だと判断すれば「すぐにでもCAR T細胞療法を行ったほうがいいですよ」とお伝えすることがあります。また、病気は待ってくれませんので場合によっては「明日診察に来てください」「明後日から入院してください」といったスピード感で治療に向かわざるを得ないことも多いです。これまでも、当院にお越しいただいたときにはすでに病気が進行しすぎておりCAR T細胞療法にたどりつけないことも少なからず経験しました。「1週間前にきてくれればリンパ球採取が間に合ってCAR T細胞療法を受けられたのに」と思うこともあります。
CAR T細胞療法を受けるためには、タイミングを逃さないことがもっとも大切です。
*国立がん研究センター中央病院におけるセカンドオピニオンは自由診療であり、対面は44,000円(税込)、オンラインは49,940円(税込)。
安全に配慮しながら治療を進めている
CAR T細胞を投与した後の入院期間中は、免疫反応に伴う副作用を適切に管理することが大切です。さらに、血球減少や感染症などの副作用にも注意してみていく必要があります。初めのうちは通院の回数が多くなるため患者さんの負担が大きくなりますが、安全性を担保しながらより高い治療効果を得るためにご協力いただければと思います。
なお、CAR T細胞療法を行っても一定程度再発する可能性があります。そのため、当院では特に治療後3か月、6か月のポイントを超えるまでは経過観察をしっかりと行い、血球減少、感染症に加えて再発の有無をみていきます。
感染症には注意が必要
日常生活では感染症には十分注意が必要です。患者さんには「最低でも1日1回は検温をしましょうね」とお伝えしています。ただし、心配だからといって外出を完全に我慢する必要はないと思います。体調がよければ行きたいところに行き、好きなことをしてリフレッシュされてはいかがでしょうか。ただし、感染症の兆候がみられたらすぐに適切に対処することが大切です。
蒔田先生からのメッセージ「安心して早めの相談を」
現状ではCAR T細胞療法を実施する医療施設が限られており、この治療にアクセスしづらい患者さんもいらっしゃるかもしれません。しかし、お話ししたようにCAR T細胞療法はタイミングが重要な治療法です。抗がん剤治療をひととおり受けた後に検討したいという患者さんもいらっしゃるかもしれませんが、適した時期を逸してしまう可能性があります。“最後の手段”と捉えるのではなく、早い時期から抗がん剤治療以外の治療法にも目を向けておくことが大切です。
ためらわず、安心して医師へ相談してほしいと思います。特に、再発してしまった場合には、なるべく早い段階でCAR T細胞療法を実施している医療施設に話を聞くのがよいでしょう。主治医の先生でも、対応している医療施設でも構いません。まずは相談のアクションをしてもらえたらと思います*。治療のタイミングについてアドバイスをもらえるかもしれませんし、実際にCAR T細胞療法を行っている医師から話を聞くと、リスクも含めて治療についてより具体的なイメージを持てるのではないでしょうか。再発が1回目という方は躊躇される気持ちがあるかもしれませんが、ぜひ早めに検討を始めていただければと思っています。
*治療中の医療機関がCAR T細胞療法の実施施設ではない場合、セカンドオピニオンに該当します。
DLBCL「CAR T細胞療法」「自家造血幹細胞移植」に対応している病院を探す
絞り込み条件
※条件なしで検索する場合はチェックを外してください。
エリアから探す
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が10件あります
騒音性難聴と耳鳴り
1年くらい前から耳鳴りがきになり耳鼻科を受診したら騒音性難聴とのことでした。その後テレビがついていたり雑音があると会話が聞き取りにくく、仕事中どうしてもなんかしら雑音があるため聞き取りにくく聞き返すことが増えてこまっています。時々耳抜きができないような詰まった感じがすることも増えました… 加味帰脾湯という薬を処方されましたが改善しません… ほかの病院を受診してみるべきですか? あと、耳の感じはとても説明しにくいです。症状を伝えるのになにかアドバイスあったらおしえてほしいです…
潰瘍性大腸炎20年経過、異形性疑い
こんばんは、初めまして 潰瘍性大腸炎を20年患い、ここ5年は落ちついていましたが、今年の夏前後に血便がでたりしました。 先月からは、またよくなりましたが、 内視鏡検査で、新しい病変がみつかり細胞診になりました。結果は3週間かかるそうです。昨年はコロナで検査はなしで、一昨年はそこには何もありませんでした。 異形性かしらべるようです。 とて不安です。今後どうなるか気になっています。
逆流性食道炎について
今年になって、生まれて初めて逆流性食道炎になりました。 原因は不明ですが、仕事や対人関係のストレスかもしれません。 ですが、月日を追う毎にメンタルも強くなっていってるのが自分でも分かります。 ただ、逆流性食道炎の症状(悪心・嘔吐)が治りません。 薬を服用すれば治りますが、飲むのをやめると症状が出てしまいます。 逆流性食道炎って完治するのですか?? どうやったら完治するのでしょうか??
鉄欠乏性貧血
鉄欠乏性貧血の治療してから1年以上経過してますが改善されてません、値もギリギリでかかりつけの病院で何で改善しないのか確認してもわかりませんと言われて不安です
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」を登録すると、新着の情報をお知らせします