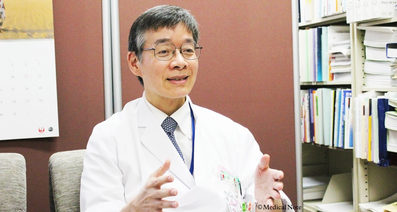筋萎縮性側索硬化症(以下、ALS:Amyotrophic Lateral Sclerosis)は、運動神経細胞がダメージを受けることで全身の筋肉が動かせなくなっていく病気です。できるだけ早く治療を開始することで病気の進行を抑えられることが分かっているため、ALSを疑う症状がある場合は早期に神経内科を受診し、診断・治療を受けることが重要です。近年は新薬の開発が進んでおり、今使われている治療薬との併用でより効果が期待できる可能性が出てきています。
今回は、ALS治療薬の薬事承認に尽力された吉野内科・神経内科医院 院長の吉野 英先生に、ALSの症状や治療法、新薬に期待することなど幅広くお話を伺いました。
ALSとは? 体の筋肉が徐々に動かせなくなっていく病気
薬の服用で病気の進行を抑える
ALSとは、運動神経細胞が徐々に破壊され、全身の筋肉が動かせなくなっていく病気です。手足を動かす力や話したり飲み込んだりする力が衰えていき、最終的に呼吸をする筋肉が動かせなくなると呼吸不全を起こします。60〜70歳代で発症する方が多く、男女比は3:2で男性にやや多いことが特徴です。日本では10万人あたり年間約2人が新たにALSを発症するといわれており、近年患者さんの数は増えてきています。その背景には高齢化が進んでいること、ALSの認知度が高まって神経内科で適切な診断を受ける方が増えていることがあると考えています。
過去には原因不明で治療方法はないとされていましたが、現在は病気の進行を遅らせる薬としてリルゾールとエダラボンの2種類があります。これにより治療に希望を持てるようになってきていることを、私は普段の診療で患者さんにお伝えしています。さらに最近ではメコバラミンが承認され、治療手段がまた広がりました。
病気の原因が徐々に明らかに
ALSの発症原因の1つと考えられているのが、フリーラジカル*による酸化ストレスです。治療薬の1つであるエダラボンは、このフリーラジカルを消去するメカニズムを持っています。
また、日本におけるALSの約5%は遺伝性(家族内での発症)で、そのうち3分の1の方でSOD1という遺伝子に異常がみられることが知られています。そのほか、FUSという遺伝子の変異もALSの原因として割合が大きいことが分かっています。
*フリーラジカル:通常はペアとなって分子の中に安定した状態で存在するものが、対をなさず不安定な状態で存在している分子のこと。酸化ストレス(酸化反応により生じる生体への有害な作用)を引き起こす活性酸素の中にもフリーラジカルを含むものがある。
ALSの症状・診断のきっかけ
他科で様子を見ている間に進行するケースも
ALSは手足の脱力(四肢麻痺)から症状が始まる患者さんが最も多く、その次に話しにくさや飲み込みにくさ(球麻痺)によって発症する方が多いといわれています。また一部で、呼吸の苦しさ(呼吸障害)を自覚してALSの診断に至る方もいらっしゃいます。
四肢麻痺から始まる場合では、肩の力が低下して重いものを持ち上げられない、または指先に力が入らずペットボトルの蓋を開けられないといった症状がみられます。足の症状としては、何かにつかまらないと歩きにくくなったり、座った状態から立ち上がるのが難しくなったりします。手足の症状があると整形外科を受診される方が多く、X線検査で何らかの異常(頚椎の変形など)が見つかると、本当はALSが原因であるにもかかわらず、そのままリハビリテーション(以下、リハビリ)をしながら経過観察とされてしまうケースがあります。そのうちに症状が進行し、ようやく神経の病気が疑われて神経内科に紹介されて受診する患者さんは少なくありません。
また、球麻痺では耳鼻咽喉科を受診される方が多く、いずれも初期に神経内科を受診される方は少ないのが現状です。適切な治療を受けないまま時間がたち、他科の医師から紹介されて神経内科にたどり着く方が多く、診断が遅れてしまう場合もあります。ALSは早期に治療を開始したほうが効果を得られることが分かっているため、早い段階で神経内科を受診していただきたいと思います。

診断のための検査――似た症状がみられる病気の除外も重要
ALSの診断においては、運動神経細胞がどの程度ダメージを受けているかを確認するための針筋電図検査が欠かせません。針筋電図検査では、手足の筋肉に針を刺して安静時と力を入れたときの筋線維の電気活動を記録し、ALSに特徴的な波形の有無を調べます。
そのほか、ALSと似たような症状をきたすほかの病気を除外するための検査も重要です。頚椎、腰椎、頭部のMRI検査で異常の有無を調べるほか、ギラン・バレー症候群など末梢神経の病気の可能性を考慮し、神経伝導検査*や髄液検査**を行います。
*神経伝導検査:皮膚の上から電気刺激を送り、末梢神経の異常の有無を調べる検査。
**髄液検査:腰に針を刺して脳脊髄液を採取し、成分を調べて異常の有無を確認する検査。
ALSの治療――さまざまな側面からの治療・ケアを行う
薬物療法――今ある薬と新薬との併用効果にも期待
薬物療法では、主にリルゾールとエダラボンという薬が使われます。
リルゾールは神経伝達物質として作用する興奮性アミノ酸の1つ、グルタミン酸のはたらきを阻害するといわれています。肝機能障害や間質性肺疾患*などの副作用が起こる可能性があるため、血液検査や呼吸検査などで状態をチェックしながら使用します。一方、エダラボンはフリーラジカルを消去して神経細胞を守る薬で、使用の際には腎機能障害や肝機能障害などの副作用に注意が必要です。
この2つの薬の併用によって、治療薬がまったくなかった時代と比べてよい状態を長く保てるようになったと感じています。エダラボンが2015年にALSに承認されて以降の長期予後の改善状況を調査した結果が間もなく発表されるようですが、私としてはよい結果が出てくることを期待しています。
また2024年11月末からはメコバラミンがALSに対して使用可能になりました。高濃度のビタミンB12溶液を筋肉内に注入する治療方法で、リルゾールやエダラボンとは異なる機序で運動神経細胞を保護する効果があると考えられています。さらに、今ある薬と組み合わせて使用することで、より高い効果が得られることも期待されています。
*間質性肺疾患:肺を支える間質という組織に炎症が起こり、肺全体が硬くなって機能が低下する病気。
リハビリテーション
リハビリは、特に呼吸に欠かせない胸郭の可動域を保つために非常に重要です。また、患者さんの治療へのモチベーションを引き出すうえでも重視しています。リハビリによってどの程度病気の進行を抑制できるかを示す科学的根拠は今のところありません。ただし呼吸機能については、早期にリハビリを開始することで、気管切開をせずに過ごせる期間や呼吸機能を維持できる期間を延長できるという報告があります。
栄養摂取
ALSでは、食事によって十分な栄養を摂取し、体重を維持することがとても重要です。特に、通常は取りすぎるとよくないとされる高脂肪食の摂取がALSの進行を遅らせることが分かっています。そのため、患者さんには「脂質が多くても構わないので、好きなもの、おいしいものをしっかり食べてください。それが大切な治療の1つになります」とお伝えしています。
なお、筋力が低下して食べるのに疲れてしまい、十分な栄養を取れず体重が落ちてしまっている方には“胃ろう*”の造設を提案する場合もあります。胃ろうと聞くと延命治療のように感じてマイナスイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、ALSの治療においては、しっかり栄養を取って病気に立ち向かっていくための積極的な治療手段です。
*胃ろう:胃に開けた穴にチューブを挿入して、直接栄養補給をする方法。
メンタルケア
病気の特性もあって、ALSと診断されると心を閉ざしてしまう方も多いため、メンタル面でのサポート・ケアも欠かせません。患者さんには「病気について周囲に積極的に相談して、1人で抱え込まずに助けを借りながら過ごしていきましょう」と声をかけています。
呼吸管理
筋力が低下して呼吸が難しくなった場合には、呼吸補助具を使ったり、気管を切開して人工呼吸器を装着したりするケースもあります。
進歩するALS治療――新薬が登場、さらなる進展も

ALSに対しては新たな治療薬の開発が進んでおり、多くの治験(人に使用して有効性や安全性などを確認するための臨床試験)が行われています。そうしたなか、2024年11月からメコバラミンが使用できるようになったほか、2024年5月にはトフェルセンが承認申請されました。トフェルセンは、SOD1遺伝子に異常があるALSの方への効果が期待されている薬で、アメリカでは2023年に迅速承認、欧州でも2024年5月に販売承認されて、すでに使用されています。
トフェルセンに続いてFUS遺伝子の変異をターゲットにした治療薬の開発も進んでおり、現在治験が実施されています。遺伝性ALSの治療にも明るい展望がひらけてきているといえるでしょう。また、ALSではフリーラジカルが発生して障害を起こしている部分にTDP-43という変異したタンパク質が固まって沈着を起こしていることが明らかになっています。このTDP-43を取り除く治療薬の開発も進行中です。今後、さらに病気の根本に迫るような本質的な治療薬が登場してくることを期待しています。
ALS診療にかける吉野先生の思い
治療薬承認に向けた14年の奮闘
エダラボンは、急性期脳梗塞の治療薬として、2001年に承認された薬です。当時、国立精神・神経センター国府台病院(現:国立国際医療研究センター国府台病院)に勤務していた私は、エダラボンの“フリーラジカルを消去する”というメカニズムに着目しました。「脳梗塞とはまったく違う病気だけれど、ALSの発症にもフリーラジカルが関与していると考えられているから、もしかしたらエダラボンはALSにも効果があるかもしれない」と思い立ったのです。そのため、病院の倫理委員会に申請し、当時持っていた研究費をほぼ全てつぎ込んで自主試験を開始しました。最初の自主試験で大きな手応えを感じたため、その後も自主試験を続け、承認申請のための第II相試験*、第III相試験**を経て、2015年にエダラボンがALS治療薬として承認されました。私が自主試験を開始してから14年目のことでした。ここにたどり着くまで紆余曲折がありましたが、患者さんからいただいた励ましと期待の声があったからこそ、長年力を尽くしてこられたのだと思っています。
*第II相試験:同意を得た少数の患者に使用して薬の有効性や投与量、投与法などを確認するための試験。
**第III相試験:同意を得た多数の患者に使用して薬の有効性や安全性などを確認するための試験。
前向きに病気に立ち向かえるよう患者さんとご家族をサポート

現在は、クリニックでALSの方を含めた神経疾患の患者さんの外来診療や訪問診療に携わっています。当院にはご夫婦で連れ添って通院されているALS患者さんが多く、ご家族の固い絆を感じます。また、在宅療養されている患者さんを支えるご家族の姿にふれるたびに、病気の治療にとどまらず、何とかこのご家族を守っていきたいという思いが湧き上がってきます。
患者さんやご家族が孤立せず、訪問看護など必要なケアを受けながら治療を継続できる状況をつくるため、当院では介護保険の申請をお手伝いしたり、場合によっては重度訪問介護が利用できるようはたらきかけたりするなど、できる限りのサポートをしています。医師、看護師、リハビリスタッフら全てのスタッフが、クリニックへの通院や訪問診療によって患者さんやご家族に前向きな気持ちになっていただけるような診療を心がけています。
吉野先生からのメッセージ――治療が大きく進歩。気になったら早めに神経内科へ
ALSの治療法がほとんどなかったかつての時代には、病名を告知されて自ら命を落としてしまう方も少なくありませんでした。しかし近年は治療法が進歩してきており、今後は病気の根本に迫るような本質的な治療薬の登場も期待されています。今ある薬では完全に進行を止められるわけではなくいまだ難しい病気ではありますが、深く絶望される患者さんは昔に比べて少なくなったように感じています。
今はインターネットなどで情報を得やすくなっており、当院にはALSを疑って自ら来院される方が増えています。早期に治療を開始して病気の進行抑制につなげるためにも、少しでも気になる症状があれば早めに神経内科を受診していただきたいと思います。
吉野 英 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が14件あります
ギランバレー、ALSについて
3月末から4月頭まで風邪。 4/15〜外傷がないのに肌がヒリヒリする。腕、背中顔など色々な場所、同時に皮膚の冷感、スースーするような感覚 4/30〜手指に力が入りにくい、動かしにくい感覚 5/5〜肩こり、筋肉痛 5/7〜筋肉のピクつき、腕の疲れ、体の疲れ、足の脱力感、つっぱる感じ があります。 明日脳神経外科でMRIとCTを取ることになっていますが、ネットで検索してALSを見つけてからノイローゼ気味で全くやる気も起きず、吐き気や喉の渇き、頭痛、食欲もなくなって、毎日泣いております。 明日検査してもすぐわかるわけではないですし、時間はかかると思いますがとにかく不安が解消されず、どう過ごしていいかわかりません。 上記のの症状があればかなり可能性は高くなるのでしょうか?
脱力感、痺れ。ALSかギランバレーへの不安
1月13日、左腕の違和感(筋肉痛のような)その後、左半身に痺れ発生。炭酸風呂に入っているようなシュワシュワした痺れと冷感。そして、脱力感。17日、個人病院の神経内科受診、脳CTでは異常なし。翌日、紹介状を持って大きな総合病院へ。脳MRIを撮り異常なし。1週間後に頚椎MRIを撮るも痺れにあたる異常なし。その間に左半身だった痺れが顔全体(顔面も含め)、右側にも広がりました。救急外来へ電話をするも脳MRIなども異常ないし、呂律がしっかりしているので緊急性はなさそう。平日、専門科で受診した方が良いと言われ1週間我慢。頚椎MRIも異常ないので、原因がはっきりせず。 ここで気になる病名です 1→ギランバレー症候群 12月21日にインフルエンザワクチン接種 顔面の痺れも含めた全身の痺れ、脱力感 力の入りにくさ 2→ALS 私自身、一番これを疑ってしまっています。 痺れ、脱力感、力の入りにくさ、手首の動かしにくさ、筋肉のピクつきなどが当てはまります。 来週、神経伝達速度検査をします。どうやったら、この不安が消えますか? この2週間、これらの病気のことを調べすぎて吐き気がおこるくらい精神的に追い込まれています。毎日、涙、涙しながら見なければいいのにALSばかり調べています。 あと、舌を見るとわかるとありますが舌を出すと小刻みに震えています。これは健常者でもあることなんでしょうか?
左腕細くなり手が上がりません
一年ほど前から左手が上がらなくなり、自分は、昔の左足の骨折が原因で筋肉が引っ張られて上がらんようになったとおもってたんですが、妻が半年ほど前だと思うんですが、お父さん左腕が細くなって来てるでと言われ自分も左腕が、正面側に上がらないので肩が横から見てたら左の肩だけ、重いものを持つと体が傾いておかしな姿勢になってると言われて、近くの整形外科に行きました。そこで三角筋とかその辺が筋肉落ちてるし、首のレントゲン撮影してもらったら頚椎が神経を圧迫してるしMRI取りに行って来なさいと言われて診察受けました。MRIの写真でも神経を圧迫してるから症状と合致はするがここからは僕では見きれないから大学病院の、脊柱外来紹介するからと言うことで大学病院の順番を待っていますが、腕が細くなってるのが、自分も気になります。神経のややこしい、病気もよく似た症状みたいなので何か、他にアドバイスがあればと思います。痺れは、たまにエアコンに入ってると手足に感じるんですが、それより筋肉のピクピクするのが気になります神経の病気を見てるとALSと言うのが初期症状でぴくつくと書いてあるのが多いのでどうなもんかなぁ怖いなぁと思っているのですが、あと現状では握力は落ちてはいません手先も普通に動きます左腰左足の外側の筋肉は歩くと重痛い感じで常に少しかばっているような状態で筋肉も引っ張られている感じです炎天下の中仕事してるせいもあると思うんですが、体重も春の健康診断より6キロほど前落ちています暑さの何かアドバイスがあれば教えて下さい
左半身不随意運動
5年ほど前から左手に違和感を感じ始め、少しずつ思い通りに動かなくなっております。 プルプルと震えて動かそうとしても動かないといった症状です。具体的には「パソコンの キーボードを押した後に指があがらない」「頭が洗えない」等です。2年前に某総合病院の 神経内科で脳のMRIとCTの検査をしていただきましたが異常なく、「手が動かなくなるのは 体質。その程度で病院に来るな。物が呑み込めなくなったらまたおいで」と言われました。 ただ、ここ1年くらい左足も思うように動かずバランス感覚がいちじるしく低下しており、また 右手も違和感を感じ始め、日常生活が一人で行えなくなってきたため、相談させていただき ました。薬でも治療でも少しでも改善できればと思っております。 下記にてその他の違和感のある症状をあげておきます。原因が違うもの等も含まれて いるのかもしれませんが、思いつくことあればアドバイスいただけたら幸いです。 ・頻尿になった(いきたくなると我慢できなくなった) ・声がかすれたように出ない時がある ・力が抜けない(常に手足に力が入っている) ・手足、わき腹等がつりやすくなった ・精神的にも異常(違和感)を感じている せめて、何科に相談すればいいかわかればいいのですがわからずのままです。 糸口でもよいので助けていただけないでしょうか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「筋萎縮性側索硬化症」を登録すると、新着の情報をお知らせします