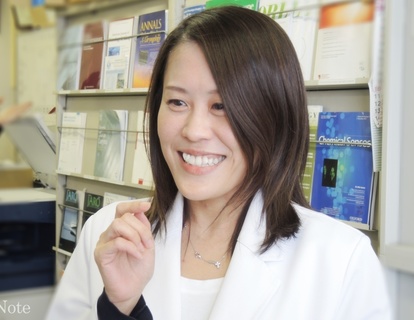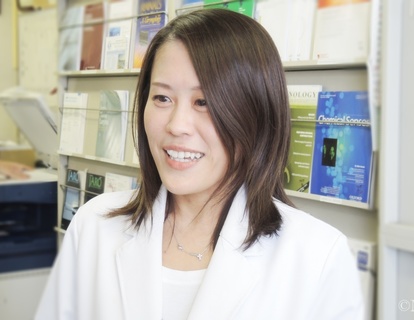概要
味覚障害とは「味をまったく感じない」「味を感じにくい」「異常な味がする」といった味覚の異常がある状態のことです。味覚障害には全ての味覚を感じにくくなるものや、特定の味覚のみが障害されるもの、変な味を感じるものなどがあります。
2019年に報告された日本口腔・咽頭科学会の調査によれば、現在日本では1年間に推計27万人*が味覚異常を自覚して医療機関を受診するといわれており、患者数は年々増加傾向にあることが指摘されています。幅広い年代の人に起こり得ることが分かっていますが、特に高齢の患者が多く、その理由として長期にわたって病気にかかっていることや心身の活力の低下を示す“フレイル”など、加齢に伴うさまざまなトラブルが関与している可能性が高いと考えられます。また、味覚障害で医療機関を受診する方の多くが女性であることも特徴です。これは日常生活において女性のほうが調理をする機会が多く、味付けの際に異変に気付いたり調理した食事を食べる家族から異変を指摘されたりするなど、気付くきっかけが多いためと考えられています。
*Nin T, Tanaka M, Nishida K, Yamamoto J, Miwa T. A clinical survey on patients with taste disorders in Japan: A comparative study. Auris Nasus Larynx. 2022 Jan 27;S0385-8146(22)00021-9. doi: 10.1016/j.anl.2022.01.002.より引用
味覚障害と深く関係する“風味”と“脂肪味”
味覚障害と似た症状に“風味障害”があります。
味覚は5大基本味(苦味・酸味・甘味・塩味・うま味)を指すのに対し、風味はイチゴ味やチョコレート味といった嗅覚が関与するものです。嗅覚は味に大きく関与しており、味覚が正常でも嗅覚に異常が生じて味が分かりにくくなっているケースがあります。味覚と嗅覚を完全に区別することは困難ですが、さまざまな検査を行うことで味覚と嗅覚のどちらに異常が生じているのかを確認することが大切です。
また、近年では第6基本味として“脂肪味”の存在が立証されつつあります。脂肪味とは食べ物に含まれる油脂を認識できる味のことで、脂肪酸が甘味やうま味に深く関係している可能性があるといわれています。脂肪味の存在が明らかになることで、摂食行動などの関係が明らかになる可能性があると期待されています。
原因
ほとんどの味覚障害は、舌に存在して味の伝達に関わる“味蕾”に次のような異常が生じて起こると考えられています。
- 味蕾に存在する味細胞の代謝遅延
- 味覚神経の反応に関わる酵素の活性低下
- 味蕾に食べ物の味物質を届ける唾液が減って、味蕾が働きにくくなる
など
また、近年はストレスの蓄積などによって味覚を脳に伝える神経や、味覚を判断する脳そのものに何らかの異常が起こるために生じる“心因性の味覚障害”も多く確認されています。
味覚障害は上記2つ以外にもさまざまな原因で引き起こされることがあり、たとえば以下の要因が挙げられます。
- 亜鉛、ビタミン、鉄などの栄養素の不足
- 加齢
- かぜ、新型コロナウイルス感染症 など
- 病気(消化器疾患、肝疾患、腎疾患、口腔疾患、精神疾患、貧血疾患、内分泌疾患、自己免疫疾患、脳疾患、認知症など)
- 手術や放射線照射などの医療による合併症や薬剤の副作用
- 外傷
など
味覚障害は、これらの特定の原因によって引き起こされることもあるほか、複数の要因が影響し合うことで発症することもあると考えられています。
症状
味蕾には苦味・酸味・甘味・塩味・うま味を代表として、さまざまな味を感じるはたらきがあります。
味覚障害には、これらの全てを感じなくなるものや、特定の味のみを感じなくなるもの、口の中に何もないのに不快な味を感じる症状などがあります。
味覚低下・脱失
味覚が減退し、味を感じにくくなったりまったく感じなくなったりします。全ての味覚が減退することが多いですが、“甘味だけ感じない”など、特定の味覚のみが障害されることもあります。
異味症
異常な味を感じる症状です。口の中に何もないのに味を感じる“自発性異常味覚”と呼ばれるものなどがあります。
検査・診断
味覚障害で行われる検査には味覚検査、唾液検査、血液検査、舌の観察などがあります。中でも味覚検査は重要で、濾紙ディスク法や電気味覚検査と呼ばれる検査があります。
また、味覚障害は精神的なストレスで発症することがあるため、アンケートなどで精神状態をチェックすることもあります。必要に応じて、唾液腺の異常を確かめる検査や嗅覚検査、CT検査、MRI検査などを行うこともあります。
治療
味覚障害の原因が明らかな場合は、原因に応じた治療を行います。
たとえば、亜鉛や鉄、ビタミンなどの栄養素が不足している場合は薬を服用するなどして補充します。唾液分泌量が減っている場合は、唾液の分泌を促進する治療薬を使用します。また前述のとおり、味覚障害は消化器疾患、肝疾患、腎疾患など幅広い病気が原因となって生じることも少なくないため、原因と考えられる病気が明らかな場合は、原因疾患の治療を行います。
そのほか薬剤の副作用で味覚障害を生じている場合は、原因薬剤を中止します。ストレスが原因の場合は、心療内科での治療が必要になることもあります。
予防
味覚障害は栄養不足で発症することがあるため、バランスのよい食事を規則正しく取り入れて味覚障害を予防しましょう。特に味覚に重要な味蕾の代謝に関わる亜鉛が多く含まれる食品を積極的に摂取することが大切です。亜鉛が多く含まれる食品には、かき、うなぎ、牛の赤身、豚レバーなどがあります。また、鉄分やたんぱく質、ビタミンなども必要です。
なお心因性の味覚障害も存在するため、日頃から十分な睡眠を取り、ストレスをできる限りためないよう心がけるとよいでしょう。
「味覚障害」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください