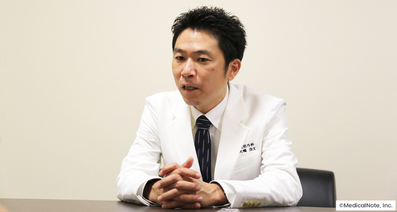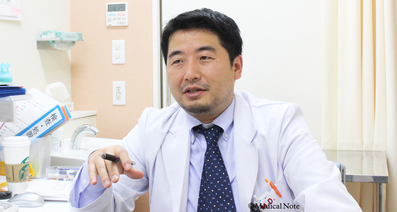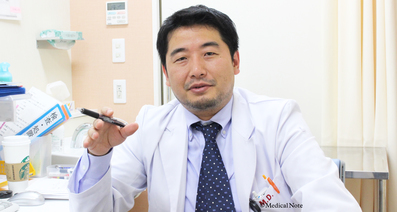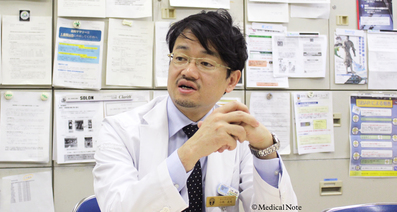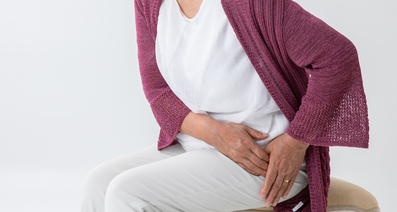記事2『自分の股関節を利用する関節温存術 - 骨切り手術と関節鏡下手術』記事3『股関節置換術-人工股関節手術の術式発展』では、進行した股関節症の手術として「骨切り手術」と「人工関節手術」を説明いただきました。実際に術式を選ぶときにはどのようなことに留意すればよいのでしょうか。骨切り手術と人工関節手術、それぞれの適応について引き続き北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科および大学院医療系研究科整形外科学教授の高平尚伸先生に伺いました。
この記事で書かれていること
- 進行した股関節症の手術として「骨切り手術」と「人工関節手術」がある
- 術式を選択する際、患者さんの病期や年齢・希望によって判断する必要がある
- 自分に適した医師・治療方法に出会うには、日本股関節学会の評議員を調べることをおすすめ
脚長差について-仰向け手術の有用性
「骨きり手術」でも「人工関節手術」でも課題に上がる問題として「脚長差」があります。脚長差とはその名の通り左右の足の長さの差を指します。手術を行う際に医師の技術や術式によってこの差が大きく開いてしまうことがあり、術後の歩き方に跛行(=はこう・足をひきづって歩くこと)が出たり、反対側の足にまで痛みが出てしまうことがあります。
私は「骨きり手術」でも「人工関節手術」でも限界はあるにしろ脚長差をある程度揃えることができると自負していますが、特に人工関節手術では、仰向けに手術を行い、術中にきちんと両下肢の長さの確認をしているからです。手術をしない方の足もきちんと消毒をし、術中に足の長さを確認します。伸ばした状態でかかとの位置を確認したのち、膝を曲げ、膝の位置も確認します。
逆に言うと、横向きの手術ではこのような脚長差の確認をすることができないので、横向き手術で脚長差を合わせることは難しいと言わざるを得ません。というのも手術をしない方の足にはシーツがかかっており、手術中に見ることができないからです。もちろん、仰向けの手術でも手術をしない方の足にシーツがかかっていれば不正確になりやすいです。
やはり手術中に足の長さを実際に確認することによって、患者さんの今後の日常生活に大きな効果が見込めることは言うまでもありません。仰向け手術の恩恵は回復の早さや手術の正確さだけでなく、患者さんの今後の生活にももたらされるのです。
関節温存手術・人工関節手術の選択-患者さんにとって最良の選択は?
「ステージ・病期」と「年齢」から正確な判断を

「骨きり手術」をはじめとする関節温存手術と「人工関節手術」は、患者さんの病期や年齢、希望によってどちらを行うべきか判断をする必要があります。とりわけ関節温存手術は適応が限られており、向き不向きがありますが、合っている方には非常に有効な手術です。
一方で、適応が絞られるため年間の症例数も少なく、医師としてもやり慣れている人工関節手術のほうが安心でやりやすいと考える傾向にあります。股関節手術において、この辺りのせめぎ合いは意見が医師によっても異なるためひとつの課題となっています。
Timesaving(タイムセービング)という考え方
股関節手術の選択肢には「タイムセービング」という考え方が重要視されています。一生をタイムスパンとしてみたときに、骨きり手術で時間を稼ぎ、人工関節手術の回数をなるべく少なく済ませるという考え方です。
近年は人工関節の精度が上がり、必ずしも再置換が必要とは限らなくなってきましたが、それでも現状での人工関節の寿命は30年といわれていますので、若いうちの手術であれば自分の骨をつかった骨きり手術を視野に入れて考えるべきだと考えています。また、タイムセービングをしている間には、次の手術である人工関節やその手術手技がさらに進歩している可能性も期待されます。
関節手術を行う病院は、自分たちが行った手術に責任を持ち、次に手術する場合には何ができるかというアフターケアの技術を持っていなければいけません。
骨きり手術の技術を守る
骨きり手術が普及しない理由は欧米的な考え方の流入にあります。欧米では長期入院をよしとせず、なるべく早く社会復帰できるような医療が求められています。骨きり手術は「骨を切る手術」というだけあり入院期間が長く、人工関節が2週間以内、若い人なら1週間以内で退院できるのに対し、およそ6週間の入院期間を要します。働き盛りの20〜40代の患者さんにとって、1ヶ月以上の入院は家庭や仕事の都合でなかなか難しい場合もありますし、病院側も長期入院の受け入れが制度的に難しくなってきています。
そのため、この手術はアメリカではほとんど行われていません。以前私も国際学会で「骨きり手術」の有用性に関する発表をしたことがありましたが、座長の先生に「人工関節があるのに、なぜまだこの手術をやっているのか」と問われることもありました。
骨きり手術の有用性

とはいえ、骨きり手術は「自分の骨を残したい」と思う日本人の特有の観点から見れば確実にニーズが高く、今後も守られていくべき技術であると私は思っています。日本股関節学会でも同じように骨きり手術を残していこうという動きがあり、骨切り手術の有用性について私が講演することもしばしばあります。この手術ができる医師がどんどん少なくなってきているので、若い医師に骨きり手術の有効性を伝え、技術を伝えていくことも私のひとつの使命です。
また、人工関節には寿命があり、早ければ15〜20年もすると入れ替えのための再置換手術が必要になることがあります。骨きり手術はうまくいけば、生涯人工関節を使わずに過ごせますし、病状が進んだとしても次に人工股関節にする際には難しい再置換術ではなく、初めての人工股関節手術として行うことができます。ただし、これからの骨きり手術には、次の人工股関節手術を妨げないように、うまくバトンリレーができるような手術が求められます。
北里大学のトータルケア
北里大学では関節手術のトータルケアを目指し、ゆりかごから墓場までという形で簡単な手術から難しい人工関節の再置換手術まで全てを網羅したケアを行なっています。患者さんにとって最適な手術を提案し、途中で匙を投げることなくどんな手術でも対応できるように心がけています。
最初の手術がうまくいかなかったり、関節症が進行し再手術が必要になった場合でも、次の治療が提案できるなどアフターケア含め、生涯において患者さんをみていけるような環境作りを心がけています。
自分に合った股関節治療に出会うには
これまで述べてきましたように、人工関節の手術は術式や医師の考え・技術によってその治療方法の選択も大きく異なります。また股関節は専門医という仕組みがないため、整形外科・形成外科などと表記され、本当に股関節専門で治療を行なっている医師を探す難易度がやや高いです。治療に関する選択肢が多い中で、ご自身にあった医師・治療方法に出会うことは簡単なことではありませんが、160名ほどいる日本股関節学会の評議員の方々は知識・技術ともに高いため、検索をして最寄りの評議員の先生あるいはその病院に一度相談されるのもよいかと思います。
北里大学 大学院医療系研究科臨床医療学 整形外科学 教授、北里大学 医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事


変形性股関節症とはどんな病気? 治療方法について

変形性股関節症の手術について――人工股関節置換術とは?
関連の医療相談が10件あります
人工骨頭手術後の注意点
2ヶ月前、主人がテニス中転倒して左大腿骨頭骨折して、人工骨頭置換手術を受けました。その後1ヶ月半かけて日常生活に戻れるようじっくりリハビリしました。 10日経過した今ではキズの痛みあるものの、大分日常生活に戻っています。 そこで、会社に復職するにあたり、会社側から、出来ることと出来ない事を教えてくれと言われました。 退院直後、主治医の診察を受け、言われたことは、重いものを持たないこと、足を内側に曲げない事、の2点くらいです。 主人の仕事は防災関係ですが、今はデスクワークが中心です。重いものと言っても消化器くらいですが、その点も主治医からOKを頂きました。 その他復職するにあたり注意点がありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
血中アルブミンの低下と食事
特別養護老人ホームに入居中の叔母についてアドバイスを頂きたくお願いいたします。叔母は97歳、痩せています。 コロナ禍で面会ができず、叔母の様子がわからないのですが、老人ホームから来た「栄養ケア計画書」に以下のような気になる事が書いてありました。 健康診断の結果、アルブミン値が3.4g/dlと若干低下しているため、低栄養リスクが「低」から「中」リスクとなりました。食事量、体重ともに安定しているため現在ので食事提供を継続して経過を見ていきます (3.5mg/dl以上が低リスクなので問題ありません) 叔母は3月に施設内で転倒し大腿骨私骨折し、現在車椅子生活で、月に1-2回の歩行訓練を受けていると聞いています。 お伺いしたいのは、血中アルブミンが4g/dl以上が正常値、3.5g/dl以下は「低栄養」という基準がありますが、低下傾向にあって3.4mg/dl という数値は問題なしという判断でよろしいのでしょうか? 4mg/dl以上にするためにタンパク質などを増やすようにお願いした方が良いのでしょうか? また、アルブミン値が低いのは肝臓や腎臓が悪くなりはじめているということは考えられないでしょうか?(健康診断ので結果をいただいていないので他の数値は分かりません) (参考) 1ヶ月前に、特別養護老人ホームの介護士さんから「叔母の足のむくみがひどくて、靴下が履きにくい(介助の方が履かせにくい)ので緩い靴下を持って来てほしいという連絡がありました。今年の春に履きやすいようにゴムなしの靴下を持って行きました。足が細い叔母が春に持って行った緩めの靴下が履けないということは相当なむくみが出ているものと推察します。これに関係しているかわかりませんが、「靴下を履く際に足の親指の爪が剥がれた」という連絡もありました。 何かの病気を見逃されていないか心配です。
骨嚢腫の治療
左足親指の骨が痛くて違和感があり整形外科受診。レントゲンで骨に空洞があるのでMRI検査施行。骨嚢腫についてと原因や完治するのか?治療方法やそれに要する日数等詳しく教えてほしいです。
腰がいたい、治療方法について教えてください。
<これまでの経過> 小中学生の頃、運動量の多いスポーツをしている際にも腰痛がありましたが、とくに受診はしませんでした。 20代から大工仕事をはじめまた腰の痛みの症状が増してくるようになりました。 とくに転倒したり、打撲したりはしていません。 <受診結果> 腰痛で受診した結果、腰椎分離症もしくは疲労骨折(の疑い)といわれました。 消炎剤と痛み止めの薬と湿布を処方されて経過観察となっています。 <質問> ・10代の頃から腰痛があるのですが、完治しますか? ・疲労骨折である場合、一般的な治療方法はどういったものが考えられますか? ・通院しつつ、なにか日常生活で症状が改善するためにできることがありますでしょうか?(筋トレやストレッチなど) どうぞ、よろしくおねがいいたします。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「大腿骨頚部骨折」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。