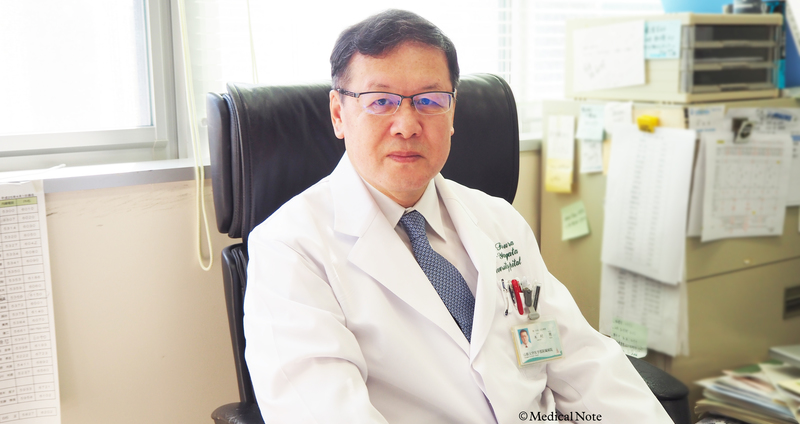IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)とは、膵臓に発生する嚢胞性病変の一つです。IPMNは、難治性で予後が悪いといわれる膵がんに対し、「予後が良好な膵がん」として登場した新たな疾患概念でもあります。
山形大学の教授である木村 理先生は、IPMNの研究とともに、脾臓の温存を実現する脾温存膵体尾部切除術に携わっていらっしゃいます。
今回は、同大学の木村 理先生に、IPMNの原因や症状から、治療法の一つである脾温存膵体尾部切除術の効果までお話しいただきました。
膵嚢胞のひとつ・IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)の特徴
IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)とは、膵臓に発生する嚢胞性病変(液体や半固形状の物質を含む袋状の病変)の一つです。

粘液の産生や膵管の拡張
IPMNの特徴は、ドロドロとした粘液を膵管内部に産生することです。さらに、この粘液のためであるかは定かではありませんが、膵液の通り道である膵管の拡張が認められる点も大きな特徴です。
ファーター乳頭部の開大
また、粘液の産生に伴い、ファーター乳頭部の開大(開いて大きくなること)が認められます。ファーター乳頭部とは、総胆管(肝臓で生成した胆汁の通り道)と主膵管(膵臓で生成された膵液の通り道)が合流し、十二指腸内へと開口する部位を指します。通常、このファーター乳頭部を通して、十二指腸へ膵液と胆汁が送られる仕組みになっています。
IPMNが発生すると、このファーター乳頭部が通常よりも大きく開くことがわかっています。

浸潤するケースが少なく、予後が良好
IPMNは病変が広がる浸潤が起こりにくく、予後も良好であることがわかっています。後ほど詳しくお話ししますが、IPMNのなかには悪性化するケースも報告されています。悪性化した場合であっても、通常の膵がんと比較すると、治療後の予後は良好であるといわれています。
どのようにIPMNの概念はつくられたのか?
予後が良好な膵がんの発見がはじまり
IPMNは、1990年台に、世界的に確立した新たな疾患概念です。1980年台に、日本の研究者が報告した「予後が良好な膵がん」が元となり、IPMNの概念が提唱されるようになったのです。
通常、膵がんは難治性のものが多く、予後が悪い疾患であるといわれてきました。抗がん剤など治療が進歩したことにより予後は改善されてきていますが、近年でも難治性であることに変わりはありません。
一方、1980年台に発表された「予後が良好な膵がん」は、悪性化していないものも含め一括して粘液産生膵腫瘍と呼ばれるようになりました。このように粘液をつくりだし膵管の拡張が認められる膵がんは、通常型膵がんと比較して治療後の経過が非常に良好であることがわかったのです。
これらを通常型膵がんと区別するために、IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)と名付けたことが、新たな疾患概念の形成につながりました。
IPMNの分類
主膵管型、膵管分枝型、混合型に分けられる
IPMNは、主膵管型、膵管分枝型、混合型の3つに分類されます。このうち、膵管分枝型が最も多く、全体の7〜8割程度を占めると考えられています。
主膵管型とは、通常、直径1〜2ミリ程度である主膵管が拡張してしまう病変を指します。一方、分枝型とは、主膵管から細かく広がる分枝が拡張していく病変であり、ぶどうの房のような形をしている点が特徴です。
混合型は、お話しした主膵管型と膵管分枝型の両方が合わさったものを指します。
IPMNの好発年齢や男女比
IPMNの発生がみられる平均年齢は65歳くらいと考えられています。男女比は概ね2対1であり男性のほうが多いといわれていますが、男性が多い理由は定かではありません。

IPMNの原因
原因不明のケースが最も多い
IPMNの原因は明らかになっておらず、原因不明のケースが最も多いでしょう。通常型膵がんが喫煙や家族歴を疾患の発症確率を高めるリスクファクターとしているのに対し、IPMNは生活習慣や家族歴などとの関連は、現状では明らかになっていません。
IPMNの症状
IPMNは無症状のケースが多いですが、膵炎(膵臓の炎症)に伴う症状が現れることもあります。この場合、上腹部の痛みや食欲不振、吐き気、嘔吐、発熱、易疲労感(疲れやすさを感じること)などが現れるでしょう。
IPMNが悪性化したときの症状
IPMNが悪性化すると、黄疸(皮膚などの組織や体液が黄色く染まること)やみぞおちの痛みが発生するケースが多いといわれています。黄疸が発生した場合には、ほぼ悪性化していると考えてよいでしょう。黄疸は、胆管で生成された胆汁が腫瘍によって閉塞されることによって血液中に逆流し、発生するといわれています。
また、黄疸が発生するとともに、便が白くなる点も悪性化の特徴の一つです。
IPMNの悪性化
IPMNがどの段階でがん化するのか,浸潤し始めるのかは定かではありません。IPMNが悪性化し、がんへと変化する割合は、全体の0.24%ほどであるといわれています。
IPMNの悪性化を判断する指標とは?
IPMNの悪性化の指標として有効となるものは、嚢胞壁の結節隆起(もりあがった小さなできもののようなもの)や主膵管の拡張です。たとえば、主膵管径が10ミリ以上に拡張している場合には、旺盛ながんの増殖があるとみなし手術適応となることが多いでしょう。5〜9ミリの場合であると、悪性化の疑いがあるため、さらなる精査や経過観察が求められます。またぶどうの房状の嚢胞性病変の増大率(数年の経過観察で、どのくらい大きくなったか)も悪性の指標となります.
IPMNの治療法-脾温存膵体尾部切除術とは?
脾臓を温存しながら膵臓を切除する手術法
IPMNのなかでも、主膵管型のIPMNは約80%が悪性であるため、その多くは手術が適応となります。一方、膵管分枝型では、嚢胞壁の結節や径3センチ以上になると手術が適応されるケースが多いでしょう。
IPMNに適応される手術法の一つが、脾温存膵体尾部切除法です。脾温存膵体尾部切除法とは、それまでのIPMNの手術では切除されていた脾動静脈および脾臓を温存しながら膵体尾部を切除する治療法を指します。
この脾温存膵体尾部切除術は、IPMNの疑いが強く、腫瘍が嚢胞の外には浸潤していない場合に適応されます。悪性化の可能性が高く、浸潤が認められていないものに対して実施される治療法といえるでしょう。
脾臓を切除することで発生するリスク
ではなぜ、脾臓を温存する治療法が有効なのでしょうか。脾臓がなくなると、白血球や血小板の値が高くなるために、脳梗塞などの危険が高まることがわかっています。この白血球や血小板の値の上昇は、術後年数が経過しても改善されることはありません。
また、脾臓を切除すると、免疫力が低下するために肺炎に罹患しやすくなります。そのため、脾臓を切除した方は、肺炎を予防するために1か月以内に肺炎球菌ワクチンを接種する必要があるといわれています。
治療のタイミングを見極めるため専門医の受診を

IPMNは、お話ししたように、解明されていない部分もまだまだ残されています。疾患の解明とともに、治療法も徐々に変化しています。このため、適切な治療のタイミングを見極めるためには、専門医の受診が有効となるでしょう。
良性の場合であれば経過観察をするケースも多くあります。悪性化の可能性と治療のタイミングを見極めるためには、専門医による診療が重要になります。
私が手術を担当した患者さんのなかには、手術後に状況が大きく改善され、10数年にわたり元気に社会生活を送る方も少なくありません。
適切なタイミングで治療を受ければ、予後も大きく改善されます。専門医とともに治療に取り組むことをおすすめしたいと思います。
医療法人社団全仁会 東都春日部病院 病院長、山形大学 名誉教授、学校法人青淵学園 東都大学 臨床教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医療法人社団全仁会 東都春日部病院 病院長、山形大学 名誉教授、学校法人青淵学園 東都大学 臨床教授
木村 理 先生日本外科学会 特別会員日本消化器病学会 名誉会員・功労会員日本肝胆膵外科学会 名誉会員・肝胆膵外科高度技能指導医日本臨床栄養代謝学会 名誉会員・認定医・終身認定医日本胆道学会 名誉会員・認定指導医日本老年医学会 老年科指導医・老年科専門医・特別会員日本消化器外科学会 名誉会長・名誉会員・消化器外科専門医日本膵臓学会 名誉会員日本外科代謝栄養学会 特別会員・教育指導医日本消化管学会 胃腸科指導医・胃腸科専門医日本成人病(生活習慣病)学会 認定管理指導医日本腹部救急医学会 特別会員・腹部救急教育医・腹部救急認定医日本消化器画像診断研究会 名誉会員手術手技研究会 特別会員日本神経内分泌腫瘍研究会 理事日本外科病理学会 名誉理事長日本高齢消化器病学会 名誉会員
1979年より消化器外科・乳腺甲状腺・一般外科医師としてキャリアをはじめる。1998年には山形大学第一外科学講座 主任教授に就任。膵臓手術のオピニオンリーダーとして、臨床・研究ともに日本をリードしており、2008年からは日本消化器外科学会理事に就任.2019年名誉会長・名誉会員に推戴された。2017年には、著書「木村理 膵臓病の外科学、南江堂、2017年」を上梓した。
木村 理 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。