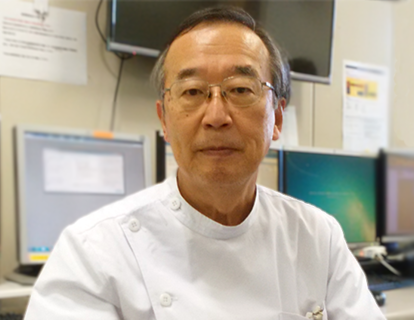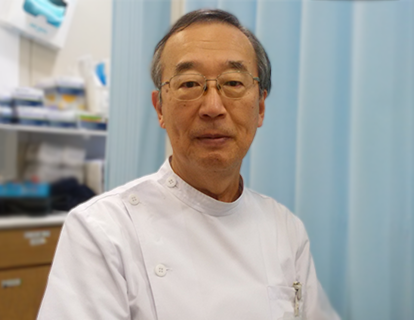概要
外痔核とは、肛門部の血管の壁が腫れあがり、こぶ状に膨らむ病気のことです。
痔核は一般に“いぼ痔”と呼ばれるもので、痔の種類にはほかにも“痔瘻(あな痔)”や“裂肛(切れ痔)”があります。日本人の3人に1人が痔に悩んでいるといわれ、このうち男女ともにもっとも多いのが痔核で、全体のおよそ半数を占めています。
痔核は内痔核と外痔核の2種類に分類され、解剖学的に歯状線(直腸と肛門の境目)の上下で分けて、歯状線よりも内側にできるものが内痔核、外側にできるものが外痔核です。
内痔核が発生する部位には痛覚がないため、通常痛みは感じませんが、外痔核は痛覚がある場所に発生することから、小さくても軽度の痛みから激痛を生じます。また、外痔核の上皮が破れると少量の出血がみられます。
外痔核は軽度であれば自然に治ることもありますが、生活習慣の改善や薬物療法によって早く治すことができます。ひどくなると手術による治療が検討されます。
原因
肛門の周囲には静脈叢があり、小静脈が網目状に集合して肛門をぴったりと閉めるためのクッションの役割を果たしています。
この静脈叢が肛門への外部刺激によってうっ血することや、肛門を構成する筋肉やクッションの部分を支える組織(支持組織)が引き伸ばされて弱くなることで、痔核が発生すると考えられています。
肛門への刺激としては大きなものに、排便時のいきみ、便秘、下痢が挙げられます。排便時にいきむと内圧によって肛門に負担がかかります。便秘では便が硬いこと、下痢では激しい勢いで排便することで肛門が刺激され大きな負担がかかります。重いものを持ち上げたり激しい運動をしたりすることも肛門に刺激を与え、発症につながります。
肛門への刺激以外では、肛門周辺の血流が悪くなることも外痔核の発生・悪化の要因で、たとえば長時間の同一姿勢、妊娠、出産などが挙げられます。
また、お酒の飲みすぎはうっ血を促進するほか、香辛料(唐辛子、こしょうなど)も排便時に肛門に刺激を加えるため、このような嗜好品の取りすぎにも注意が必要です。
症状
外痔核の多くは血まめ(血栓:血の塊)ができる血栓性外痔核です。肛門の周りに生じた血まめがしこりとして触知でき、肛門内に存在する場合には違和感が生じます。
また、発生部位には痛覚があるため、小さくても激しい痛みを伴うことが多く、痔核の上皮が破けると少量の出血がみられます。
血栓が生じた直後に痛みが現れますが、血栓は血の塊であるため時間とともに吸収されていきます。そのため、痛みは発症直後をピークとして1週間くらいで軽快していきます。ただし、腫れは2~3週間残ることがあります。
なお、歯状線よりも内側にできる内痔核が肛門外に脱出する(脱肛)ことや、脱出した内痔核が腫れて戻らなくなる(嵌頓痔核)ことがあります。これらは内痔核が進行したものですが、内痔核に外痔核を伴う内外痔核という状態になる場合もあります。
検査・診断
外痔核の診断は、主に視診や、肛門に指を入れて調べる直腸指診、肛門鏡という器具を用いて肛門内を観察する肛門視診によって行われます。このような検査で外痔核の有無や場所、内痔核との併発の有無が分かります。
下血などで大腸がんが疑われる場合には、大腸内視鏡検査が行われることもあります。大腸内視鏡検査では、先端に小型カメラがついたチューブ(内視鏡)を肛門から挿入し、大腸全体と小腸の一部を観察します。
治療
外痔核の治療は、日常生活で肛門に負担をかけないようにしつつ、薬で症状の緩和を図る保存療法が基本です。痛みに対しては痔の軟膏や坐剤を使用し、必要に応じて血流をよくする薬が用いられます。
外痔核の多くは血栓性外痔核で、保存療法によって時間とともに血栓が溶けて吸収され、次第に小さくなり痛みも引いていきます。
血栓が大きい場合や痛みが続くような場合には、局所麻酔下で血栓を取り除くこともあります。内痔核に外痔核を伴う内外痔核においては、手術による切除やALTA療法(痔核四段階注射法)など内痔核に対する治療も行われます。
予防
痔核の大きな原因が便秘であるため、積極的に水分や果物、食物繊維を摂取する、下剤を使用するなどして、便通をよくして排便時のいきみを避けることが大切です。下痢も同様に早めの改善を心がけ、排便中に新聞を読むなどトイレに長時間いるような習慣がある人はその排便習慣を改善しましょう。
アルコールや香辛料も痔核の発生・悪化に影響します。そのため、このような嗜好品の摂取を控えることも大切です。
痔核は肛門周辺の血行不良も原因の1つです。長時間の座りっぱなしを避けるなどして肛門周辺の血流が悪くならないようにし、入浴やお尻のマッサージで血流を改善するとよいでしょう。
「外痔核」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「外痔核」に関連する病院の紹介記事
特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。