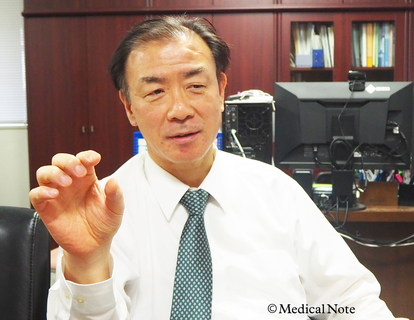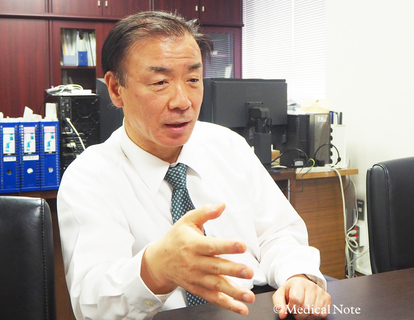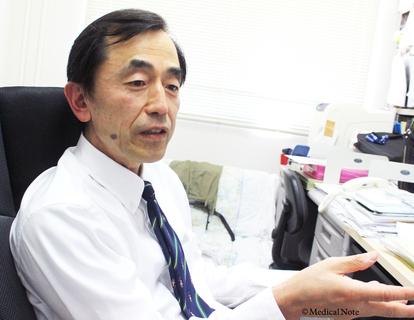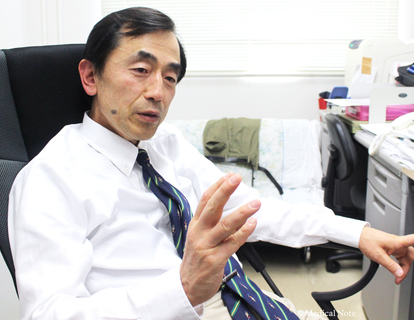概要
消化管間質腫瘍(GIST)とは、消化管の壁に生じる悪性腫瘍(がん)の一種(肉腫)です。いわゆる胃がんや大腸がんが消化管の粘膜から発生するのに対し、消化管間質腫瘍は粘膜より下の層、消化管壁の筋肉の中にある“カハール介在細胞”と呼ばれる細胞が異常に増殖することによって生じます。
消化管間質腫瘍は比較的発生頻度が低く、年間で10万人に1~2人程度が発症するといわれています。好発部位は胃と小腸で、大腸や食道にみられることはまれです。あらゆる年齢層の方にみられますが、特に60歳代をピークとした中高年に多くみられます。なお男女差はありません。
原因
消化管間質腫瘍の発生には、“c-KIT遺伝子”“PDGFRA遺伝子”と呼ばれる遺伝子の機能獲得型の突然変異が原因であることが発見・報告されています。これら遺伝子変異は、腫瘍の特徴や分子標的治療薬の感受性に関連することが知られています。
症状
消化管間質腫瘍は特徴的な症状がなく、初期段階は無症状で経過することも少なくないため、早期発見の難しい病気として知られています。胃がんや大腸がんと比較しても、症状が現れにくいことが特徴です。
進行すると腫瘍が大きくなり潰瘍が形成されることから、血の混じった便が出たり、便の表面に血が付着したり(下血)、口から血を吐いてしまったりする(吐血)ことがあります。また腫瘍からの出血に伴って貧血症状が生じる方もいます。
腫瘍の発生した部位などによっては飲食物を飲み込みにくくなる“嚥下困難”や吐き気、腹痛などがみられることもあるほか、お腹を触った際にしこりを認識できる場合もあります。
検査・診断
消化管間質腫瘍は、健康診断などで行われる画像検査、便潜血検査などをきっかけに疑われ、発見につながることがあります。
具体的な検査方法としては、以下が挙げられます。画像検査などを行ったうえで、病理検査により確定診断を行うことが一般的です。
画像検査
胃のX線造影検査(バリウム検査)や消化管の内視鏡検査(いわゆる胃カメラ・大腸カメラ)、CT検査、MRI検査などの画像検査が検討されます。
胃のX線造影検査
バリウムと呼ばれる造影剤を飲んでX線撮影を行う検査です。胃粘膜の凹凸がはっきりと見えるため、胃の内部の病変の位置を確認できます。
内視鏡検査
内視鏡と呼ばれる小さなカメラを口や肛門から挿入し、消化管の内部を観察する検査です。消化管内部の表面の盛り上がりから病変の発生箇所を確認できます。ただし、消化管間質腫瘍の場合、腫瘍は粘膜ではなくその下層にある筋肉から発生しているため、単純な内視鏡検査では腫瘍の細胞などを採取することはできません。
そのため、消化管間質腫瘍の検査時は“超音波内視鏡”という特殊な内視鏡を用いた検査が検討されます。超音波内視鏡では、粘膜の下にある腫瘍がどの層から発生し、どのくらい広がっているかを確認できるほか、内視鏡に内蔵された針を刺し、粘膜の下にある腫瘍の細胞や組織を採取することもできます。このような病変の採取方法を“超音波内視鏡下穿刺吸引術(EUS-FNA)”といいます。
なお腫瘍が小腸にある場合は通常の内視鏡では観察が難しいため、カプセル内視鏡やバルーン内視鏡などの特殊な内視鏡の使用が検討されます。
CT・MRI検査
体の断面を撮影することによって腫瘍の位置や大きさ、ほかの臓器への広がりや転移の状態などを確認します。
病理検査
超音波内視鏡検査などで採取した腫瘍の細胞や組織を顕微鏡で観察し、腫瘍細胞の形状などを確認します。免疫染色を行い、KIT(c-kit遺伝子から作られるタンパク質)またはDOG1(Discovered on GIST Protein1:消化管間質腫瘍で現れるタンパク質)の陽性が確認された場合に消化管間質腫瘍と確定診断されることが一般的です。
また、手術で切除した組織に対して病理検査を行い、悪性度を調べることで再発リスクなどを評価することもあります。
治療
消化管間質腫瘍と確定診断された場合や強く疑われる場合、一般的に手術治療が検討されます。発見された段階ですでに転移している場合はまず薬物療法を行うこともあります。また、完全に切除することが危ぶまれる腫瘍に対してはまず薬物治療を実施し、縮小させてから手術へと進む“術前療法”が選択されます。
手術治療
消化管間質腫瘍は胃がんや大腸がんと比較すると、周辺に広がりにくく転移しにくいがんのため、臓器の機能を温存できるよう部分切除が行われることが一般的です。ほかの肉腫に対する手術治療と同様、腫瘍を破裂させてがん細胞をばら撒いてしまうことがないよう余裕を持って切除します。腫瘍が大きい場合などには、手術の前に分子標的薬である“イマチニブ”を投与することもあります。
お腹に小さな穴を開けて腹腔鏡と呼ばれるカメラを挿入して行う“腹腔鏡下手術”が検討されることもあります。腹腔鏡下手術は開腹手術と比較して傷が小さく、術後の回復が早いといわれています。
術後の管理
切除した腫瘍に対して病理検査を行い、再発のリスク分類を行います。検査の結果、再発する確率が高いと判断された場合には、再発予防のために薬物療法が検討されます。
薬物療法
診断当初から転移があった場合や腫瘍が大きい場合、術後の再発の危険性が高い場合、実際に再発してしまった場合などに薬物療法が検討されます。具体的にはまず分子標的薬“イマチニブ”が検討されることが一般的で、効果が薄れてきたら“スニチニブ”“レゴラフェニブ”“ピミテスピブ”などの治療薬に切り替えることが一般的です。そのほか、患者の状態に応じて新しい治療薬の臨床試験も数多く実施されています。
薬物療法の大きな注意点は、薬物療法単体での根治治療は難しいということです。副作用をコントロールしながら継続的に服用し、できるだけ長く病気と付き合っていくことが大切です。
「消化管間質腫瘍」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください