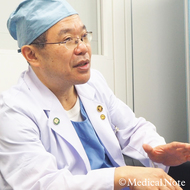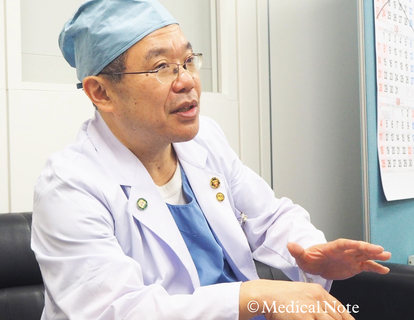概要
聴神経腫瘍とは脳腫瘍の1つで、バランスをつかさどる前庭神経を包む細胞から発生します。前庭神経は、耳で聞いた音から変換された電気信号を脳に伝える“蝸牛神経”とともに聴神経を構成します。そのため、以前は“聴神経腫瘍”と呼ばれていましたが、最近では正確に“前庭神経鞘腫”と呼ばれてきています。
脳腫瘍の7~10%を占めるといわれ、そのほとんどが良性の腫瘍で、ほかの部位に転移することはありません。男女比をみると、やや女性に多いといわれています。一般的に成長の遅い腫瘍ですが、中には急速に大きくなるものもあるため、注意が必要です。腫瘍が増大すると神経の圧迫により聴力の低下や耳鳴り、顔のしびれ、めまいなどのさまざまな症状が現れ、最終的には命に関わることもあります。
原因
聴神経腫瘍が発生する原因は、まだはっきりと明らかになっていませんが、遺伝子異常が関与している可能性が高いといわれています。
特に生まれつきの病気である“神経線維腫症2型”では、左右両側に聴神経腫瘍が発生することが特徴です。この病気は細胞内の染色体に生じる遺伝子異常を原因に発症し、子どもに遺伝する可能性があります。実際、両親のいずれか片方にこの病気があった場合、50%の確率でその子どももこの病気になるといわれています。しかし、時に両親に病気がなくても胎児期に遺伝子変異が生じ、神経線維腫症2型にかかる方もいます。
また神経線維腫症2型の患者でなくとも、後天的に遺伝子変異が起こることで聴神経腫瘍が起こることがあります。
症状
聴神経腫瘍で最初に自覚する症状として、前庭神経と伴走する蝸牛神経が腫瘍で圧迫されることによる聴覚症状が挙げられます。通常、腫瘍は片側に発生するため、片側の耳の聞こえが悪くなるほか、耳が詰まったような感覚(耳閉感)や耳鳴りを自覚します。
たとえば、電話や会話など人の話の内容が聞き取れなくなることで気が付く人もいます。そのほか、前庭神経の症状であるふらつきやめまいで発症する人も多くいます。
進行すると、腫瘍が大きくなり三叉神経(顔面の感覚をつかさどる神経)や小脳をも圧迫するようになります。三叉神経が圧迫されると、顔のしびれや麻痺、あるいは痛み(三叉神経痛)などが生じます。また小脳が圧迫された場合は、ふらつきなどで歩くことが困難になったり、合併症として水頭症が生じて意識障害が現れたりします。
検査・診断
聴神経腫瘍が疑われる場合は、MRI検査やCT検査を検討します。
特に造影剤と呼ばれる薬を注入して行う造影MRI検査は、比較的小さな腫瘍の発見や、腫瘍の正確な位置や形、周囲の神経・血管との位置関係などを確認することにも役立ちます。そのほか、造影剤を用いた脳血管撮影検査なども検討されることがあります。
また、実際の症状の度合いなどを調べるために、聴力検査や平衡感覚の検査、嚥下機能(物を飲み込む機能)の検査などを行う場合もあります。
治療
聴神経腫瘍の治療方法には、経過観察、ガンマナイフ治療に代表される定位的放射線治療、手術(外科治療)の3つの選択肢があり、腫瘍の大きさや大きくなるスピード、症状、患者の年齢、希望などに応じて検討します。できる限り腫瘍が小さいうちに治療を開始したほうが、合併症などが起こりにくいといわれています。また、ガンマナイフ治療と手術は併用されることもあります。
経過観察
腫瘍がかなり小さく、明確な症状などもない場合、特に治療を行わずに経過観察となることもあります。
ただし、腫瘍が大きくなる可能性もあるため、最初のMRI検査から半年~1年の間にMRI検査を行い、腫瘍の状態を確認します。変化がない場合はその後も年に1回を目安に数年経過観察を行い、必要に応じて何らかの治療を検討する場合もあります。腫瘍が大きくなる速度は腫瘍の性質によっても異なりますが、平均して年に1~2mm程度という報告もあります。
また、経過観察中に腫瘍の増大がなくても急に聴力の低下やめまい、顔面神経の麻痺などが起こることがあります。このような場合、ステロイド薬などによる薬物療法を行いますが、治療をしても神経機能が戻らない可能性もあります。
ガンマナイフ治療(代表的な定位的放射線治療)
ガンマナイフと呼ばれる放射線治療装置の1つを用いて、細いγ(ガンマ)線のビームを病巣に複数照射することによって、正常な組織へのダメージを極力抑えて病巣に放射線を当てる治療方法です。主に2cm程度までの比較的小さい聴神経腫瘍に対し検討され、腫瘍を小さくしたり、成長を抑えたりする目的で行います。手術よりも体への負担がかかりにくいため、ほかの病気がある患者や高齢の患者などによく提案されています。ただし、腫瘍が完全に消失するわけではないため、治療後も定期的な経過観察が必要です。
また、治療後一時的に腫瘍が大きくなることがあるほか、水頭症を約3~6%で合併すること、またごくまれに腫瘍が悪性化する可能性が知られているため、医師と相談して治療方法を検討することが大切です。
手術(外科治療)
腫瘍を全摘出することにより、今後起こり得る脳の障害を予防し、現在ある神経の機能を維持することを目的に行われる治療方法です。すでに障害されてしまった神経機能を回復させることは困難ですが、全摘出できれば再発の心配もなく、採取した腫瘍をもとに確定診断も行えることが特徴です。特に、かなり大きくなった腫瘍は定位的放射線治療が困難になるため、命に関わるようであれば必然的に手術が検討されます。
手術は脳幹のすぐ近くで行われるため、特に顔面神経や聴神経に障害が生じやすいと考えられています。できる限り神経機能を温存できるよう、手術中は神経モニタリングを行うなどの必要があり、専門施設で行うことが推奨されています。さまざまな術後合併症が起こり得る可能性があるため、ガンマナイフ同様、医師とよく相談して治療方法を検討しましょう。
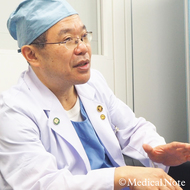 QOLを重視した脳神経外科治療(前編)−髄膜腫、聴神経腫瘍、下垂体腺腫横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳...坂田 勝巳 先生
QOLを重視した脳神経外科治療(前編)−髄膜腫、聴神経腫瘍、下垂体腺腫横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳...坂田 勝巳 先生脳神経外科では、脳や神経にかかわるさまざまな病気を扱っています。横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科では、患者さんのQOL(Qua...続きを読む
 聴神経腫瘍の治療法-大きさや年齢で変わる東京医科大学病院 脳卒中センター長、東...河野 道宏 先生
聴神経腫瘍の治療法-大きさや年齢で変わる東京医科大学病院 脳卒中センター長、東...河野 道宏 先生聴神経腫瘍の治療法には手術と放射線治療があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。そのため、これら治療法の選択は、腫瘍の大きさや患者さん...続きを読む
 聴神経腫瘍の治療と後遺症-手術と放射線治療のメリット・デメリット東京医科大学病院 脳卒中センター長、東...河野 道宏 先生
聴神経腫瘍の治療と後遺症-手術と放射線治療のメリット・デメリット東京医科大学病院 脳卒中センター長、東...河野 道宏 先生小脳橋角部にできる腫瘍のおよそ4分の3を占める聴神経腫瘍。聴神経腫瘍の治療については、現在ガイドラインは存在しておらず、治療方針は施設や医師に...続きを読む
「聴神経腫瘍」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください