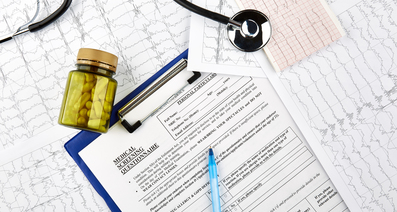自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変(PBC)、原発性硬化性胆管炎は、それぞれ障害される部位や治療法、かかりやすい年齢や性別が異なります。しかし、3つの疾患には共通項も多く、そのひとつとして「合併症」が挙げられます。自己免疫性肝疾患に合併しやすい病気にはどのようなものがあるのでしょうか。患者さんへのメッセージと共に、国際医療福祉大学消化器内科教授の銭谷幹男先生にお話しいただきました。
3つの自己免疫性肝炎に共通して起こりやすい合併症
3種全ての自己免疫性肝疾患に共通して、肝臓以外の自己免疫疾患を合併するケースが多々見られます。
特に多く見受けられる合併症は以下の4つです
胆汁うっ滞により高脂血症を来すことも多い
原発性胆汁性肝硬変(PBC)と原発性硬化性胆管炎では「胆汁うっ滞」が起こることで非常に強い高脂血症を来すため、医学の世界では高脂血症の合併症である黄色腫症を発症しやすいといわれています。(※黄色腫症とは:皮膚に盛り上がりなどができること)
ただし、黄色腫症はコレステロール値が非常に高くなることで現れる病気であり、日本人は欧米人ほどコレステロール値が高くはないので、臨床的にみるとこの病気を合併する方は欧米に比べて少ないのです。
高率で合併するシェーグレン症候群について
黄色腫症とは反対に、高頻度でみられる合併症は涙腺や唾液腺を攻撃する自己免疫性疾患のシェーグレン症候群です
シェーグレン症候群の症状は、目の渇きや口腔内の渇きなど、涙腺や唾液腺の異常により生じるもので、これら分泌物を分泌する管を「導管」と呼びます。上記の症状から、シェーグレン症候群とは導管に対し免疫失調が起こり、あらゆる分泌臓器がうまく働かなくなるものだと考えられます。肝臓もまた胆汁を分泌する臓器であるために、自己免疫性肝疾患にはシェーグレン症候群を合併しやすいのでしょう。
こういったことを医師に教えてくれるのは患者さんにほかなりません。患者さんの症状により、導管に対し免疫失調が起こっていると医師は仮説を立てることができます。患者さんの病態からここまで読み取ることができれば、免疫学的な突破口を発見できる可能性も高くなります。
患者さんにお願いしたいこと
血液検査の重要性
ここまで繰り返し述べてきたように、自己免疫性肝疾患のメカニズムを紐解き、治療法を確立するためには、「患者さんの様子(症状、治療効果など)をみる」ことが最も重要です。私は10年以上にわたり、自己免疫性肝炎の患者さんの会で講演を行っていますが、そこで常にお願いしていることは、「血液検査を厭わず積極的に受けてほしい」ということです。
患者さんの血液をみて検討しなければ、病気の実態を解き明かし、根治療法をみつけることはできません。ただし、この際に問題になるのは、採取した末梢血(通常の血液)の状態だけをみても、それが本当に肝臓内の免疫応答を反映しているのかはわからないということです。
肝生検を頻繁に行うことは容易ではない
現段階では、血液検査が一番よい方法です
肝臓内の免疫応答を調べるには、理想をいえば肝生検で細胞を採取することが一番です。最近では、潰瘍性大腸炎やクローン病など消化管の疾患の解明がめざましく進みました。この理由には、病変が起こっている大腸や胃の生検は比較的簡単にできるということがあります。
しかしながら、肝生検により患者さんの身体や生活にかかる負担は、大腸や胃の生検とは比べものになりません。移植により患者さんから摘出した肝臓をみるという方法もありますが、肝移植を行うほど悪くなってしまった肝臓を調べることは、たとえるならば「大火事の焼け跡をみて火元を探る」ようなもので、原因解明に繋がる可能性が高いとはいえません。しかし、肝臓に炎症が起きた初期の段階で薬の反応などを追うために生検を何度も行うことも、先に述べた理由からできません。ですから、現段階では患者さんに血液検査を受けていただくことが一番よい方法なのです。抹消血をみるということは、病気全体ではなく、病気の頭やしっぽなど、どこか一部だけをみるということですが、私たち医師は断片的な情報を繋ぎ合わせ、病気全体の解明をしていかなければなりません。患者さんからいただいた情報をどのように繋ぎ合わせていくかが、今後の医師の課題といえるでしょう。
国際医療福祉大学大学院 教授、国際医療福祉大学大学院 臨床研究センター 教授、赤坂山王メディカルセンター 院長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
様々な症状の関連性について
5/12帯状疱疹(皮膚科受診)→5/14首の痛みと顔の痺れ(整形外科受診)→5/23風邪(耳鼻科受診)→5/28副鼻腔炎(耳鼻科受診)→5/29膣カンジダ症(婦人科受診)→8/19喘息(内科受診) 立て続けに様々な症状が出ています。 毎日ではないですが、手指や足指の関節が痛むことがあり気になっています。 8/19の血液検査ではCRPは0.5でした。 白血球や貧血などその他は特に問題ありませんでした。 ただの免疫力低下なのかそれとも自己免疫疾患の可能性もあるのでしょうか。 来週、内科の再診があるので5月からの症状の相談もしようと思っているのですが、様々な症状は関連性があるのでしょうか。
お腹が緩く、黒い便が出た
1週間前からお腹の調子が悪く 血が出てた時があり、内科を受診 しかし若いきら痔の可能性として座薬だけで様子を見てと その後4日過ぎましたがお腹不調があり 下痢。 お腹がスッキリせずガスも出ずらい。 黒い便が今日夕方に出た。
三日前から、のどの痛み、せき
妻は現在抗がん剤治療中です。 三日前から37~38度の熱とのどの痛み、せきがあります。 市販の風邪薬を服用しても良いでしょうか?
繰り返す発熱、体の不調
11月12日頃から 微熱、平熱、倦怠を繰り返し カロナールも効かず 大きな病院でPCRして陰性 血液検査(2回行っており、2回目は5本採血してもらいました)、異常なし レントゲン異常なしで 腹部エコーで脾臓が腫れてたため なんらかのウイルス感染症との診断。 来週月曜日に どのウイルスに感染したか検査結果がでます。 今週の火曜日、水曜日、木曜日は とても体調が良く 回復したと思われましたが 昨日の朝から嘔吐、38.9の熱 お腹の不快感で 小さなクリニックを受診 聴診でゴロゴロお腹の音がしたようなので なんらかのウイルスによる腸炎との診断。 カロナールや 整腸剤を処方され いまは熱は下がり お腹だけ不快感。 ここ最近ずっと 熱を繰り返し 体の不調を繰り返し 回復してもいつまた 体が不調になるか不安で 仕事もずっと休んでます。 他に、原因があるのか 他に、病気が隠れてるのではないかと心配で 原因が知りたいです 今回大きな病院で受けた 検査以外に なにか、追加で検査を受けるとしたらどんな検査でしょうか。 考えられる病気があるとしたら どのような病気でしょうか。 今回の腹痛や嘔吐も 最初に診断されたウイルス感染症と関係があるものなんでしょうか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「自己免疫性肝炎」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。