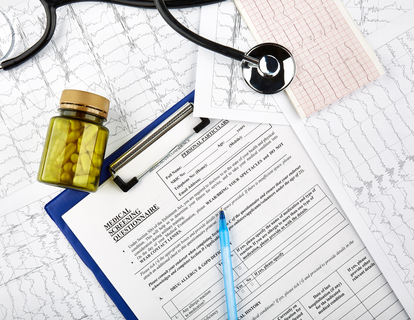概要
自己免疫性肝炎(AIH)とは、ウイルスやアルコールが原因ではなく、免疫の異常によって肝臓の細胞が破壊され、肝炎が生じる自己免疫疾患で、国の指定難病となっています。初期段階では自覚症状がなく、健康診断などをきっかけに発見されるケースが一般的です。
人間は体に入ってきた異物を排除する免疫システムを備えています。しかし、この免疫システムに異常が生じると、自身の臓器を異物と判断して攻撃し、臓器の機能低下が生じる場合があります。このような病気を総称して“自己免疫性疾患”といい、自己免疫性肝炎もその1つです。
難病情報センターによると、2018年の自己免疫性肝炎の患者数は30,000人ほどと推定されており、2004年調査の3倍ほどに増加しています。小児から高齢まで幅広い年齢層の患者が存在しますが、特に50~60歳代の女性に多く発症します。
種類
自己免疫性肝炎は現れる自己抗体の種類によってI型~IV型に分類されます。日本でみられる自己免疫性肝炎のほとんどはI型自己免疫性肝炎です。これは免疫に関わるHLA分子が人種や民族などの集団によって異なる傾向があるためと考えられています。
原因
自己免疫性肝炎の発症原因は不明ですが、近年は発症しやすい遺伝子などが研究によって徐々に解明されており、日本人の場合、患者の約70%が陽性であるHLA-DR4との関連性が報告されています。
患者の家族が同じ病気を発症する例は少なく、自己免疫性肝炎は遺伝しないとされています。しかし、日本人患者にHLA-DR4の陽性例が多いことから、発症しやすい要素が遺伝する可能性はあると考えられます。
また、A型肝炎ウイルスやサイトメガロウイルスなどのウイルス感染をはじめ、薬剤の使用や妊娠、出産を機に発症する人もいるほか、すでに何らかの自己免疫性疾患を発症している人に合併しやすいことも分かっています。
症状
自己免疫性肝炎の自覚症状には、体のだるさや疲れやすさ、食欲の低下などが挙げられますが、一般的に初期症状は軽いため自分では気付きにくく、健康診断での肝機能値の異常をきっかけに発見されるケースが少なくありません。
また病状が進行すると肝硬変に至り、上記の症状の加えて足のむくみや腹水がたまることによるお腹の張り、食道静脈瘤の出血による吐血が生じることがあります。このほか、肝臓がんを合併することもあります。
急性発症例
近年は一部の自己免疫性肝炎で急性肝炎のように急激に症状が進み、肝不全に陥る例があることが分かってきています。このような例では、自覚症状として体のだるさや食欲の低下のほか、肌や白目の部分が黄色くなる黄疸、ぼんやりしたり寝入ったりしてしまう意識レベルの低下(肝性脳症)などの症状が現れます。
主な合併症
自己免疫性肝炎は、ほかの自己免疫性疾患を合併するケースも多くあります。合併する主な病気としては、慢性甲状腺炎、シェーグレン症候群、関節リウマチなどが挙げられます。
検査・診断
自己免疫性肝炎は、血液検査において肝臓の機能を示すAST、ALT(いずれも肝細胞に多く含まれる酵素)の上昇をきっかけに発見されることが一般的です。実際の診断は、肝臓の組織の一部を採取して顕微鏡で調べる肝生検を実施し、2021年に改訂された『自己免疫肝炎(AIH)診療ガイドライン(2021年)』の診断基準に基づいて行われます。しかし、すぐに診断がつかず「自己免疫性肝炎疑い」として診療を続けるうちに、徐々にガイドラインの診断基準を満たすようになり、診断がつく場合もあります。
自己免疫性肝炎の診断基準
肝障害を引き起こす原因がほかにないことを前提条件としたうえで、以下の基準のうち3項目以上を満たすものを典型例*、1項目以上を満たすものを非典型例と診断します。
- 抗核抗体、あるいは抗平滑筋抗体が陽性である
- IgG**の値が高い
- 肝臓の組織に形質細胞浸潤など特徴的な異常がある
- ステロイド薬が効果を示す
*典型例:慢性的な肝炎がみられ、肝動脈や門脈、胆管などで構成される門脈域の線維化と拡大、単核球の浸潤(白血球やリンパ球などが炎症部位に集まる状態。中でも抗体を生産する細胞である形質細胞が多い)、肝細胞のロゼット形成(花冠様の集積)や壊死(えし)がみられることもある。
**IgG:血液中にもっとも多く存在し、免疫に関与するタンパク質(抗体)
治療
自己免疫性肝炎の主な治療方法は薬物療法です。一般的に自己免疫性肝炎は、薬物療法を中止すると肝臓の機能が再び悪化してしまうため、薬の減量や変更することがあっても長期間にわたって治療薬を服用する必要があります。
最初に投与される治療薬は、ステロイド薬である“プレドニゾロン”です。肝臓の機能に応じて量を調節し、機能が改善したら徐々に減薬していきます。また、必要に応じて、肝庇護薬の“ウルソデオキシコール酸”を併用することもあります。
なお、悪化を繰り返す場合や副作用などの事情で十分にプレドニゾロンを使用できない場合は、免疫抑制剤の“アザチオプリン”が使用されることもあります。
急性発症例や重症例
急性発症例や重症例では、多量のステロイドを点滴で投与する“ステロイドパルス療法”や肝臓のはたらきを補助する“血漿交換療法”や“血液濾過透析療法”を含めた“人工肝補助療法”を行います。また肝移植が検討されることもあります。
「自己免疫性肝炎」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください