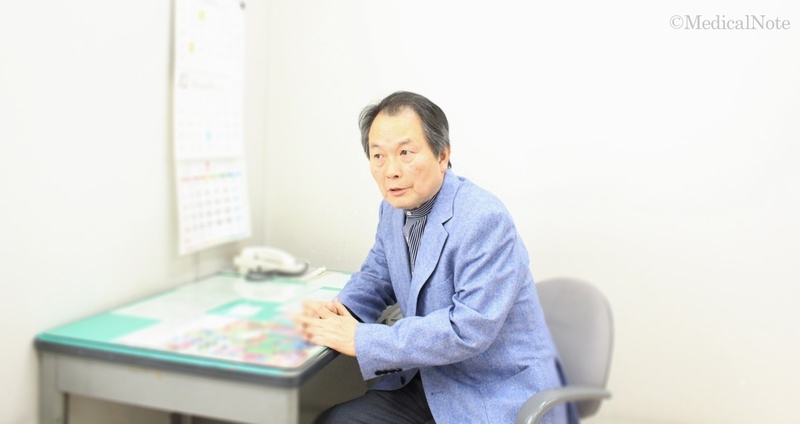子どものメンタルヘルスには精神疾患、不登校、非行など多様な分野があります。その子どもたちをサポートする社会的資源には、医療や心理の他に、行政、福祉、教育、警察、地域、仲間、自助グループ等があり、重層的な関わりが常に求められています。今回は、子どものメンタルヘルスに関する教育や福祉など、社会的な問題を扱う児童精神医学の実際、また児童精神科とその母体である精神科の違いについて、元横浜市立大学附属病院児童精神科診療部長の竹内直樹先生にお伺いしました。
児童精神科医が診る主訴と主症状
児童精神科は乳幼児期から青少年期を対象としており、患者はいわゆる“子どものニュース報道”と重なる主訴で受診してきます。医療に何ができるのかと疑問視されそうですが、患者が受診する具体的な主訴をみると、児童精神科医の扱う問題や存在意義がおわかりいただけるでしょう。
<児童精神科医が診る主訴の例>
- 地域の問題:保育園、幼稚園、学校での不適応、不登校、家庭内暴力、いじめ加害・被害、社会性や衝動性などの「発達障害」関連、学力不振など教育上の不適応の問題など
- 家族問題:養育問題、家族のメンタルヘルス、福祉の問題(被虐待など)など
- 子ども自身の問題:精神障害(心的外傷後ストレス障害、強迫性障害、摂食障害、気分障害、精神病圏前駆)、知的障害、発達障害など
- 福祉(児童相談所)・警察関連の問題:子どもの貧困、非行などの青少年問題、養育相談、性犯罪被害、犯罪加害など
このような子どもの主訴の最終の受け皿を、私たち児童精神科は担っています。
児童精神科の対象は0歳から18歳
私が勤めた横浜市立大学付属病院児童精神科の対象は、乳幼児から思春期(青年期)までの0歳から18歳(高校3年生)です。これは、全員就学にほぼ近い現在の高校進学率を勘案すれば妥当かと考えます。
WHO(世界保健機関)の診断規準でも、パーソナリティ障害の診断、認知障害と知的障害の区分などにおいては、18歳を境界としています。
胎児期から成人、次世代までを連続的に捉える「成育医療」の考え方
現在、小児科医療では「成育医療」が提唱されています。成育医療とは、胎児医療から思春期医療を経て次世代を育成するリプロダクションまでを連続して考える医療です。児童精神科でも知的障害、自閉症、精神病圏などはこの配慮が必要です。実際には高校卒業後から20歳頃までが児童精神科の再診の上限年齢と考えます。また、20歳は精神障害年金診断書交付の年齢でもあり、児童精神科医には「成人期への円滑な移行への配慮」も求められます。そのためには、地域の関係機関、障碍者就労、自助グループなどとの連携はもちろん、その開拓や専門職との交流を増やすことが必要です。上述した諸問題の結果として生じる社会的不利を減らすために、児童精神科医が子どもの権利を守るオンブズパーソンの役割を担うことは重要な課題です。
子どもの症状を診断するために-経過診断の重要性
児童精神科臨床では「症例の経過」を追うことが重要です。というのも、子どもは非特異的症状が多く、内面の言語化がむずかしいため、親の供述に拠ることも多く、横断診断は誤診を伴いやすい傾向があるからです。
乳幼児期、就学年齢だけに関心を留めず、成長や環境の変化などから可塑性のある時期を実感するためにも、個々の転帰から丁寧に学ぶ「経過診断」が診断の確定には欠かせません。また、患者が成人期に精神科を受診しやすくなるように、入口の児童精神科で傷つけないように配慮し、医療にアクセスしやすいよう心がけることも大切です。
15歳から18歳の高校年齢に関する問題-精神科と児童精神科が重複する時期
高校生年齢である15歳から18歳は児童精神科、精神科が重複する時期です。精神病圏での重篤症例は精神科や精神病院へ受診し、発達障害関連や精神病圏が明確ではない前駆期が疑われる症例や学校問題(不登校、いじめ問題、学力の問題など)が主症状のときは児童精神科を選択する傾向があります。
このような棲み分けは、1960年代の横浜市立大学附属病院児童精神科(当時、「小児精神神経科」)開設から半世紀を経て、関係諸機関との連携から生まれたローカルなものですが、それぞれの地域特性を反映させて、メンタルヘルスの連続性を担保することが重要です。
精神医学と児童精神医学の違い
児童精神医学は、精神医学の一分野に位置づけられます。治療においては、子どもだけではなく親や関係者の精神医学的評価を求められることも多く、これらは精神医学におうことが必須であり、子どものみを診るだけでは限界があります。
その一方で、発達精神病理は今後も発展をしていき、子どもだけではなく、精神医学のひとつの柱として寄与できると考えます。以下に、児童精神医学の臨床特徴を記します。
①児童精神科と一括しても、年齢層により病理が異なる。とくに学業や進路などで学年ごとに影響を受けるので、年齢・性別・学年の把握は重要である。
②子どもは家族や地域を含めた環境に影響されやすい。
③子どもの供述は変化しやすいため、病歴聴取は慎重さを要する。
④発達途上である時期には環境の影響を受けやすく、病前性格や社会機能の把握には慎重を要する。
⑤症状は多彩であり、一過性の転帰をたどりやすい。例えば、成人の神経症と似た症状であっても、成人と異なり、その後の経過はよいので、子どもに限定した情緒障害という診断名がある。
⑥薬物治療は子どもにも有効である。薬効により体調や愁訴は改善し、睡眠、消化器愁訴等の生活リズムを良好にするが、これは心理的にも回復に向かわせる。
薬物治療においては親子の意向が重要である。薬物治療に抵抗感がある場合は、環境調整を優先させる。プラシーボ効果やノーシーボ効果のために治療者が焦って処方すると、混乱を招くことに繋がる。
単剤・少量を原則とし、標的症状が軽快したときは休薬を心がける。青年期の過量服薬を防ぐ意味で、残薬の管理は必須である。
⑦精神医学は、社会や時代の医療ニーズに影響を受ける。たとえば、産業革命と知能検査、戦争忌避者と心理検査の出現など、社会の関心や要望により、検査や診断名が新設された歴史が存在する。
このために非行問題、薬物問題、知的障害、発達障害など、国によって児童精神科の関心は異なるが、これは必然ともいえる。
⑧青少年問題は、その時代の抱える不安により捻出される。具体的には、鍵っ子、現代っ子、新人類、肥満児、家庭内暴力、校内暴力、学力低下、不登校、遊び型非行、子どもの自殺、虐待、いじめ問題などが、次々とニュースになっては消える傾向がある。扇情的な報道は子育て不安をあおり、受診動機にもなりやすい。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。