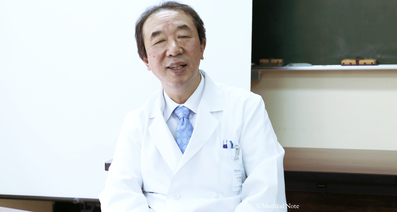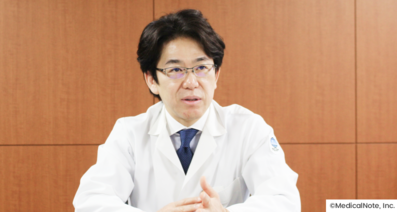
大阪医科大学附属病院消化器内科教授の樋口和秀先生は、日本で初めて逆流性食道炎の内視鏡治療を行われ、2011年に「泳ぐ内視鏡」を開発されました。内視鏡が泳ぐ、とはどのような意味を指すのでしょうか。非常に新しく、画期的な発明でもある泳ぐ内視鏡について、樋口先生にご説明していただきました。
泳ぐ内視鏡を開発するに至った経緯
未だに内視鏡はきつい、つらいという声がよく聞かれます。ですから、できるだけコンパクトなカプセルで内視鏡検査を行えれば、患者さんも検診で受ける際、負担が少なくなります。
また、カプセル内視鏡で胃が診られるようになれば、食道から大腸まですべてひとつのカプセル検査で診られるため、効率的に診察を受けることができます。
現在日本で使われているカプセル内視鏡には小腸用・大腸用のふたつがあります。また、食道用も世界レベルで見れば存在します。しかし、胃専門のカプセルは作成されていません。
それはなぜかというと、胃の構造上の問題があるからです。胃は袋状になっているため、消化管の蠕動の力だけではうまく写真が撮れません。そこで、私は胃カメラの代わりになるカプセル内視鏡を開発しようと考え、「自走式」のカプセルを思い至りました。つまり体外からそのカプセルを操作できるカプセルをつくれば、消化管を一度に診察できると考えたのです。
検査の基本時間は2~3時間で、食道から大腸、肛門まで撮る必要があります。通常、それだけの検査をしようと思うとカメラ検査を3~4回は受けないといけなくなり、非常に大変です。そのような負担をかけることなく、検診で2時間程度の時間ですべて診られるようになれば…というのが、泳ぐ内視鏡の基本のコンセプトです。
体外からカプセルを動かそうと考えたとき、磁場でカプセルを動かそうと思う方も多いはずです。容易に飲み込め、人体に安全で、なおかつ熱が発生しない、ということを考えると、磁場で空気中を動かすというのは難しく、結論として水の中で泳がそうということになりました。水の中なら容易に動かすことができます。
泳ぐ内視鏡のメカニズム
泳ぐ内視鏡の開発メカニズムは以下のとおりです。まず実験段階で水槽の中でカプセルに尾(しっぽ)を付け、泳がせました。これでぴたりと止まることもできるし、頭部のみ左右に振ることもできます。また、3次元にも動かすことができます。
最初に水槽で実験したあとは胃の模型で練習をし、次に犬を使って実際に検査を行いました。それが成功したため、今度は人に対してこの方法を適応しました。胃の中に水を溜めておき、カプセルを飲み込んで、胃の中を泳がせると写真が撮れる仕組みになっています。
泳ぐ内視鏡の課題。写真撮影の精密度の向上がカギとなる
泳ぐ内視鏡を開発する過程で生じた課題は、いかにきれいな写真を、どのような状態の患者さんに対しても撮れるかという点にありました。
はじめは1秒に2~3枚の写真しか撮れず、写真と写真の間にタイムラグが発生していました。カプセルが撮ってきた写真を見ながら操作するため、この枚数だと微妙にズレが生じます。これが大きな課題でした。
しかし、研究を重ねた結果、今のカプセルでは1秒に16枚ほど画像撮影ができるほどに進化を遂げました。それはまるでビデオ撮影のように滑らかな画像を撮ることができます。カプセルが撮った画像を診ながら進むことができるわけですから、医師も非常に検査がやりやすくなりました。
泳ぐ内視鏡のその他の課題
着実に進歩を続ける泳ぐ内視鏡ですが、今後はカプセルを動かす精度およびいかに前処置をうまくきれいにするかが課題となると考えています
前処置とは、具体的にいうと検査を行う前に患者さんのコンディションを整えることです。たとえば胃を撮るとき、胃の中の粘液などが多量に付着してしまいます。そのため、胃カメラの場合でも器具を洗いながら写真を撮るというふうにすることになっています。ところがカプセルは洗うことができません。
検査を受ける患者さんの全員が水槽のようにきれいな水を保てる状態の体になっていただかない限り、カプセルが行くいたるところに支障が生じます。そうならないための前処置の方法が必要であり、その前処置をどう行えば一番いいのか、様々な薬を用いて、どういう方法が最適なのかを現在研究している最中です。
また、人体の構造上、胃は水を溜めやすくできていますが、小腸は溜めにくい性質を持っています。そのため、小腸の写真撮影がスムーズにいかない可能性があります。そのような場合は、最悪カプセルを飲んだまま小腸の蠕動の流れに任せてしまいますが、すべての箇所で滞りなく撮影が進むような工夫をすることが必要になってきます。
さらには、カプセルは片方がカメラでもう片方が尾びれになっているため、向きがひっくり返ったときにまたひっくり返せるかという問題が生じます。現在ではまだあまり症例がないため、これを深く研究できていないのが現状です。もちろん後ろ向きに撮れてもいけないわけではありませんが、撮影する限りは見落としのないようにしなければいけませんし、そのあたりの担保をとっていかなければいけないでしょう。
いずれにせよ、まだ症例数は少なく、大阪医大のみで行われている試験です。今後はもっと試験を重ね、確実なものに固めていく必要があります。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
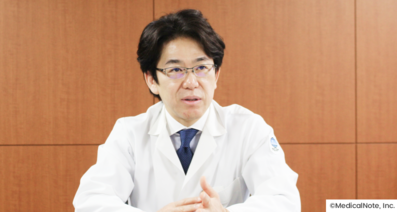
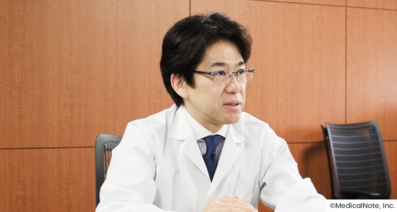
逆流性食道炎を調べる検査――どんなときに受診すればよい?

逆流性食道炎の治療――薬の種類や生活習慣のポイント
関連の医療相談が54件あります
なかなか痛み吐き気が治らない
9月1日から胃痛がおき、レパミピドとコリオパンとピロリ菌に効果ある薬(名前忘れてしまいました。)を飲んでいたのですがあまり回復せず、9月16日に内視鏡することにし、その時にピロリ菌の検査も致しました。 その日からエソメプラゾールとレバミピドを飲み始め19日に痛みが強く再度受診した際に、CTと採血をしました。 CT採血ともに異常はありませんでした。 ここ数日朝方4時か5時ごろくらいから胃痛が始まり起きてしまいます。 その旨も医師に相談したら、寝る前にロキソニンを飲むことを推奨され昨日寝る前に飲んでみたのですが今日も痛みで起こされてしまい、吐き気と痛みが強いです。 精神的なものから来てるのか、ただ逆流性食道炎によるものが強いのか分かりません… 仕事に行けないなどの支障があるので、どうにかしたいのですがこのまま同じクリニックで診てもらったほうがいいのか、または別の大きな病院行った方がいいのか心療内科にかかったほうがいいのか分かりません。 どうかご参考までにご意見聞かせて頂けましたら幸いです。
逆流性食道炎について
今年になって、生まれて初めて逆流性食道炎になりました。 原因は不明ですが、仕事や対人関係のストレスかもしれません。 ですが、月日を追う毎にメンタルも強くなっていってるのが自分でも分かります。 ただ、逆流性食道炎の症状(悪心・嘔吐)が治りません。 薬を服用すれば治りますが、飲むのをやめると症状が出てしまいます。 逆流性食道炎って完治するのですか?? どうやったら完治するのでしょうか??
まだ治らないです。
3月下旬から体調崩していて、ただの風邪かと思ったら逆流性食道炎ってことがわかったのですが、今、コロナ状況のため診察してもらおうと思ったらどこの病院断られたりして、胃ガメラ検査してもらえません。薬もらったりしてるのですが、なかなか治らないのですが、どうしたらいいですか?
逆流性食道炎と腹部膨満感
逆流性食道炎持ちなのですが、 お腹が常に張ってる感覚があります。 逆流性食道炎と腹部膨満感は関係性はありますか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「逆流性食道炎」を登録すると、新着の情報をお知らせします