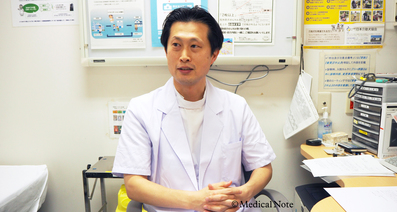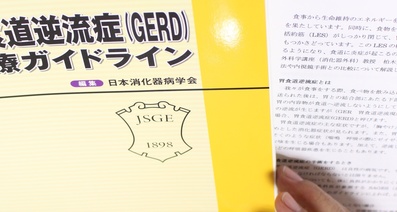摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)の検査には大きく分けて嚥下造影検査(VF:Videofluoroscopic examination of swallowing)と嚥下内視鏡検査(VE:VideoEndoscopic examination of swallowing)の2つがあります。検査結果に基づいて行われる治療や手術の適応などについて、東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 老化制御学系口腔老化制御学講座 高齢者歯科学分野 准教授の戸原玄先生にお話をうかがいました。
嚥下造影検査(VF)
嚥下造影(えんげぞうえい)といって、造影剤を使う検査があります。これはバリウムを飲んでいただき、その様子を横と正面から撮影して、飲んだものがどのように通過していくのか、またその際にどこがどのように動いているのかを見る検査です。
嚥下内視鏡検査(VE)
嚥下造影検査よりも多く行われているのが経鼻的(鼻を経由する)嚥下内視鏡検査(VE)です。検査に使用する機器が比較的安価であることに加え、私の場合は往診が非常に多いので、往診に持って行けるという点が大変便利です。
鼻から内視鏡を入れるので多少の不快感はあるかもしれませんが、痛みはそれほどありません。検査の際に暴れられてしまうような方以外であれば、ほとんどの方に検査が可能です。

舌接触補助床(Palatal Augmentation Prosthesis:PAP)
歯科的な治療のひとつにPAP(Palatal Augmentation Prosthesis:舌接触補助床)というものがあります。舌が萎縮するなど動きが極端に悪くなると、舌が上顎に触れることができなくなり、食べ物や飲み物を送り込むことができなくなることがあります。
このような場合、厚みのある入れ歯状のものを入れることで上顎の天井を低くし、舌が届くようにするというのがPAPです。保険適用になっていますので、保険診療の範囲内で作ることができます。進行性の疾患がある方でも関係なく使うことができますし、特別な訓練も必要ありません。私も時々患者さんに使いますが、かなり効果が期待できる方法です。


手術の適応
手術の場合は元に戻すことができないので、私はあまり積極的に手術を依頼することはありません
病気の種類でいえば、著しい球麻痺(きゅうまひ)症状(延髄の障害による舌・咽頭・喉頭などの麻痺)が手術の適応ということになりますが、球麻痺といっても軽いものであれば手術をする必要はありません。
たとえば唾液の誤嚥(ごえん・誤って気管に入ること)が非常に多く昼夜を問わず吸引が必要であるなど、介護するご家族の疲弊が限界に達しているような場合には、誤嚥を防止する手術を検討します。ただしその場合も、患者さんが1年以内にお亡くなりになるような状況ではなく、その手術をすることによって5年ぐらいは安全に過ごせるであろうという見通しでなければ、なかなか手術に踏み切ることはできません。
嚥下障害の手術はその目的によって大きく2種類に分かれます。ひとつは先に述べた誤嚥の防止で、もうひとつは飲み込みやすくするために喉の形状を変えるものです。
飲み込めるように喉の形を変える手術の場合、体はある程度元気で喉だけが麻痺しているという方に対して行うことが多くなります。一方、誤嚥の防止のみを目的に手術を行う場合は、体もあまり動かず寝たきりで、唾液の誤嚥も多いために在宅で介護するには吸引が欠かせないという方が対象になります。
薬剤の影響について
抗けいれん剤を服用していると、基本的に力が抜けて頭がぼんやりする傾向があります。もちろん必要があって処方されている薬ではあるのですが、食べる機能を考えれば決して良いものではありません。また、抗精神病薬や吐き気止めの薬の中には、パーキンソン症状を引き起こすものがあり、副作用によって飲み込めなくなってしまっている方も少なくありません。
このような薬の使用を減らすことによって嚥下機能が改善することがあります。これも条件を整え、良くない条件を取り除くという意味では、ひとつの環境調整といえるのかもしれません。
胃ろうの患者さんにも口から食べられるようになる方はいる
胃ろう(口から十分な栄養がとれない患者さんのために、内視鏡を使ってお腹と胃に作った小さな穴のこと)の患者さんの嚥下機能を調べたところ、77%の方は誤嚥なく食べることができたという結果が出ています。(※近藤和泉:在宅療養中の胃瘻患者に対する摂食・嚥下リハビリテーションに関する総合的研究報告書,平成23-25年度厚生労働科学研究費補助金長寿科学総合研究事業)もちろん、その77%の方たち全員がすぐに食事ができるというわけではありませんが、食べる訓練をすることは可能でした。
残念ながらその方たちに訓練を継続していただき、食べられるようになった期間や人数のデータを取ることはできていませんが、感覚としては半分には満たないものの、おそらく2〜3割の方は誤嚥なく食べられるようになるのではないかという感触を得ています。意識障害や重度の廃用(使わないために体の機能が低下すること)がなければ、多少なりとも誤嚥なく食べることができる方は多いのではないでしょうか。
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 老化制御学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科 科長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 老化制御学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科 科長
戸原 玄 先生日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士日本老年歯科医学会 認定医・老年歯科専門医・指導医・摂食機能療法専門歯科医師
高齢者を中心とする摂食嚥下障害の治療、リハビリテーションに取り組み、往診による在宅診療や地域連携を積極的に行っている。厚生労働科学研究委託費長寿・障害総合研究事業“高齢者の摂食嚥下・栄養に関する地域包括的ケアについての研究”の業務主任者を務めている。ウェブサイト“摂食嚥下関連医療資源マップ”やその他のインターネットメディア・講演活動などを通して、摂食嚥下障害に関する情報発信も行っている。
戸原 玄 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
8歳の子どもに行うオルソケラトロジーについて
近視の為、眼科でオルソケラトロジーを勧められています。行っても視力は現状維持で、良くはならないと説明を受けました。費用も高額で、毎晩親が装着し、朝は外すという事を続けなければならず、試しにつけた際、痛がったこともあり、やるべきかどうか悩んでいます。何もせず、そのままにしておけばもっと悪くなる恐れがありますし、近視は将来別の病気のリスクが高くなると言いますので、高い費用を払って、毎日の手間をかけてでもせめて現状維持し、将来のリスクを少しでも回避できるよう、やるべきとも思いますが、オルソケラトロジーの眼への悪影響もわからず不安なこともあり、悩んでいます。また、行うとなった場合、最近は行っている病院も増えており、その中から実績があり、信頼のおける病院を探す方法がわからず、そちらも合わせてご教示いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。
鼻炎で鼻汁が気管に下りて痰になり咳が出る
子どもの頃に副鼻腔炎を患ったことがあり、その影響が多分あるのだろうと思いますが、風邪を引くと鼻炎になりやすく、ひどくなると鼻汁が黄色みを帯びてきます。今月になって風邪で発熱し、熱が治った20日位前から、鼻汁が気管に下りてきて痰ができ、それを出すために咳が続いています。今回は鼻汁の色は無色透明です。咳は夜間にひどく出ます。 現在、漢方薬の麦門冬を服用していますが、このまま続けて快方を期待した方が良いでしょうか? また、他に何か効能のある薬やサプリ、食べ物とかを紹介していただけるとありがたいです。
転々と関節炎になる。
11/28に股関節炎(水が溜まっていた)の診断で、2週間の入院を経て、自宅で治療してます。入院した病院から紹介状を頂き、リウマチ科を受診しましたが、検査を2度実施してますが、正式な病名が不明です。関節の違和感や痛み、指先の痺れは継続してます。処方された薬はステロイド系の物、ロキソニン、胃薬です。この状況を察して、どんな病気が考えられますか? リウマチ科の先生は、血管炎とも言ってましたが検査後い特に断言しませんでした。
憩室炎、通院治療の際の推奨される食事内容と別の食事の質問
5日前の夜に右下腹部の違和感があり、4日前から痛みが出ている状況です。 同じような症状は3ヶ月ほど前にもありその際は抗生物質で治った経験があります。 3日前に内科受診、抗生物質を処方される(最寄りの消化器内科が休みのため内科受診) 2日前の夜に痛みがかなり増す。 昨日の朝に痛みがピークになったため消化器内科受診。そこで点滴治療を受けたのと外科の紹介状を書いてもらう。 本日外科を受診して検査の結果、憩室炎と言われました。 入院を強く勧められましたが通院治療を選択しております。 点滴治療を昨日から受けており今後も(少なくとも明日以降3日間も)毎日通院で受ける予定です。 前置きが長くなりましたが、このような状況で推奨される食事内容はどういったものでしょうか? また別の質問で、痛みがかなり酷くなった2日前の昼にバイキングで普段より食べすぎていたのですが、これは痛みが酷くなったのと関係ありますでしょうか? 以上となりますがよろしくお願いいたします。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「嚥下障害」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。