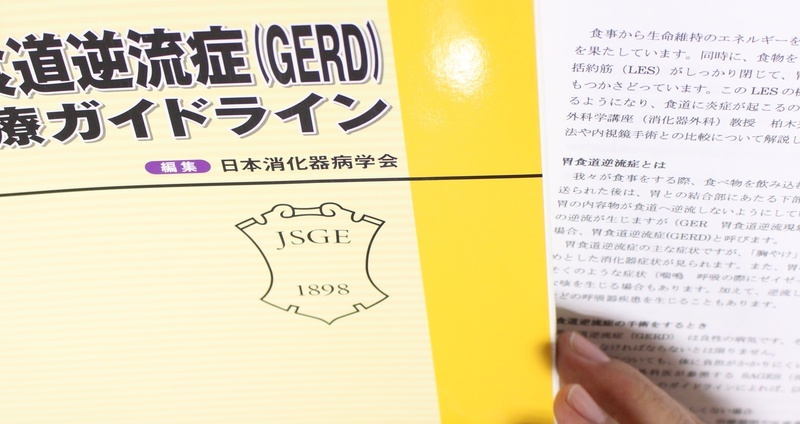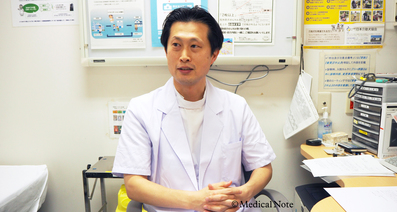食道自体または、食道と胃の結合部が正常に機能しなくなると、食事や水分の摂取困難や、胃液や胃の内容物の食道への逆流による胸焼けなどの逆流症状をひき起こすことがあります。これらの症状が見られる患者さんに対して、まず注意すべき病気は食道癌や胃癌ですが、癌がない場合には、胃食道逆流症、食道アカラシア、食道裂孔ヘルニアなどの食道の良性疾患を疑わなければなりません。
ここでは富士市立中央病院院長・東京慈恵会医科大学客員教授の柏木秀幸先生に、食道の良性疾患(非腫瘍性疾患)にはどのような病気があるのか解説していただきます。
食道と食道胃接合部の異常による症状には、どのようなものがある? その原因は?
食道は約30cm前後の筒状の臓器で、口から入れた食物や水分を胃へ運びます。そして消化吸収が行われ、栄養を摂取することにより、体の維持が行われているのです。食道と胃の境を食道胃接合部と呼びますが、これは食道の重層扁平上皮から胃の腺上皮に移行するところです。そして、同部は下部食道括約部(Lower esophageal sphincter:LES)とも呼ばれ、開閉を行うことにより胃への流れと逆流防止に関わっています。最近では、ヘリコバクター・ピロリ感染率の低下により胃癌が減少していると言われていますが、一方でこの領域の癌の増加が懸念されています。また、これからお話をする食道の良性疾患にとっても、この場所は非常に重要な関わりのある場所です。
下部食道活約部は、胃の内容物や消化液が食道へ逆流しないように働いています。この逆流防止機構が障害されると胃液の食道への逆流が繰り返されるようになります。これまで、年を取るとともに胃の老化により、胃酸が減ると考えられていました。しかし、胃酸が減少する原因は、ヘリコバクターの感染による胃の萎縮(胃の老化)が重要であることが分かってきました。ヘリコバクター感染のない胃では、胃の老化が少ないため、年をとっても、胃酸が多く、逆流防止機構に障害があれば、食道粘膜に傷害を起こしてきます。その結果、逆流性食道炎を生じ、胸焼けや呑酸のような逆流症状が出現します。
ただし、逆流により逆流症状だけを引き起こすことがあります。以前は、内視鏡検査で異常がないと、病気ではなく、心因的なもの、精神的なものとして取り扱われていました。実際には、食道炎がないにも関わらず、胃食道逆流が症状に関与しており、逆流に対する治療が有効な例も少なくありません。そのため、食道炎の有無に関係なく、慢性的な食道への逆流により生じる異常を胃食道逆流症(Gastroesophageal reflux disease:GERD)と呼び、病気として扱うようになりました。胃食道逆流の原因としては、食道胃接合部の一時的な緩みが関係していますが、重症化する要因としては食道裂孔ヘルニアの存在が重要です。(下図参照)

胸とお腹は、横隔膜という筋肉の膜で分けられていますが、食道は胸腔(縦隔内)から腹腔内に入る時に横隔膜にある食道裂孔という穴を通ります。食道の下部は横隔食道膜という丈夫な膜組織により食道裂孔に固定されているのですが、この固定が緩くなるか、または食道裂孔自体が大きくなることにより、食道胃接合部や胃が胸腔側(縦隔内)へ入り込んできます。この状態を食道裂孔ヘルニアと呼びます(図1-2参照)。食道胃接合部が胸腔側へ移動してヘルニアを起こす場合には滑脱型と呼ばれ、食道裂孔ヘルニアの中では最も頻度の高いグループです。
胃食道逆流を防ぐためには、下部食道活約部と食道裂孔の横隔膜脚の協調的の動きが重要です。滑脱型食道裂孔ヘルニアでは、この機構が損なわれて、下部食道活約部も常時開いていますから、胃食道逆流が生じやすくなります。一方、食道胃接合部は固定されたままで、胃が縦隔内に入り込んでくる状態は傍食道型と呼ばれ、ヘルニアによる胃の圧迫による胃痛やつかえが生じてきます。両者の要素が加わった場合、混合型と呼ばれますが、胃がすべて胸腔内に入り込んだり、大腸や他の臓器が入り込んだ場合には複合型と呼ばれます。

食道から胃へ食べ物が入るときには、食道胃接合部が開いてスムーズに食べ物が胃へ流れ込みます。癌の場合も、ここの開きが悪くなりつかえが生じますが、癌などの腫瘍疾患がないにもかかわらず開かなくなることがあります。食道の通過障害などの症状を呈する疾患を含め、食道の動きの異常により症状が出る病気を食道運動機能障害と呼びますが、その代表的なものに食道アカラシアがあります。これは胃食道逆流症とは対極にある病気です。まれな病気ではありますが、食道胃接合部が開かなくなるだけでなく、食道自体の運動もなく、非常に特殊な病気です。また、この病気は胸の痛みを伴うことが多く、最初は胸痛のみの場合もあるので、狭心症と間違えられることもあります。
食物を口に取り込み、食道を通って胃に入るまでの摂取と嚥下の過程は次の5期に分けられています。①先行期、②準備期、③口腔期、④咽頭期、⑤食道期です。先行期は、これから摂取する食物を認識して、食事摂取前の段階で、認知期とも呼ばれます。準備期は、口の中に食物が入って、咀嚼している時期で、嚥下の準備をしている時期です。いわゆる嚥下は③口腔期から始まり、嚥下の第1期とも呼ばれます。食物を舌により、次の咽頭へ送り込みます。
普段我々が呼吸をしているとき、鼻や口から入った空気は、咽頭から気管に入ったり出てきたりしています。嚥下の第2期の咽頭期では、口腔から咽頭へ食物が降りてくるときに鼻腔への交通が閉じられ、気管への入り口を閉じ、食道の入り口を開き、食べ物を食道へ送り込みます。これを嚥下反射と呼びます。高齢者の嚥下障害ではこれが問題となり、中枢神経障害の患者さんなどにも見られます。食道に食物が入ってくると、蠕動運動(食物を肛門側へ送り出す動き)が発生し、食物が急速に胃へ送り出されていきます。食物が食道に入ると、食道の入り口にある輪状咽頭筋が収縮して、咽頭へ逆流しないように働きます。食物が食道を降りてくると下部食道活約部が開き、胃へ食物を押し出します。この時期を嚥下の第3期と呼びます。食べ物がつかえる現象を嚥下困難と呼びますが、実際には嚥下困難の起こる時期(部位)として、3つの時期があるわけです。
高齢者や中枢神経障害などで見られる嚥下障害は、第2期の嚥下反射の障害で、飲み込みも難しいのですが、むしろ食事摂取に伴う咳嗽や誤嚥性肺炎の症状が見られます。一方、食道期の嚥下困難は前胸部のつまった感じを訴えます。食道での停滞が強いと、咽頭嚥下自体も損なわれますので、飲み込みができないため、咽頭期の嚥下困難と食道期の嚥下困難は症状だけでは鑑別できなくなります。
次の記事「食道の良性疾患の診断―内視鏡検査をはじめさまざまな検査がある」では、これらの病気の診断についてご説明します。
富士市立中央病院 院長、東京慈恵会医科大学 客員教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
富士市立中央病院 院長、東京慈恵会医科大学 客員教授
柏木 秀幸 先生日本外科学会 外科専門医・指導医日本消化器外科学会 消化器外科専門医・消化器外科指導医・消化器がん外科治療認定医日本消化器病学会 消化器病専門医・消化器病指導医日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡専門医・消化器内視鏡指導医日本内視鏡外科学会 技術認定取得者(消化器・一般外科領域)日本消化管学会 胃腸科専門医・胃腸科指導医日本腹部救急医学会 腹部救急認定医・腹部救急教育医日本食道学会 食道科認定医
1978年東京慈恵会医科大学卒業。1982年東京慈恵会医科大学大学院卒業。1982年より東京慈恵会医科大学第二外科学教室医員を経て1992年東京慈恵会医科大学第二外科学教授講師。附属病院消化管外科診療部長、外科学講座教授を得て、現在富士市立中央病院院長。食道の良性疾患(食道アカラシア、胃食道逆流症、食道裂孔ヘルニアなどの非がん疾患)のスペシャリストとして臨床に携わる。
柏木 秀幸 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
8歳の子どもに行うオルソケラトロジーについて
近視の為、眼科でオルソケラトロジーを勧められています。行っても視力は現状維持で、良くはならないと説明を受けました。費用も高額で、毎晩親が装着し、朝は外すという事を続けなければならず、試しにつけた際、痛がったこともあり、やるべきかどうか悩んでいます。何もせず、そのままにしておけばもっと悪くなる恐れがありますし、近視は将来別の病気のリスクが高くなると言いますので、高い費用を払って、毎日の手間をかけてでもせめて現状維持し、将来のリスクを少しでも回避できるよう、やるべきとも思いますが、オルソケラトロジーの眼への悪影響もわからず不安なこともあり、悩んでいます。また、行うとなった場合、最近は行っている病院も増えており、その中から実績があり、信頼のおける病院を探す方法がわからず、そちらも合わせてご教示いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。
鼻炎で鼻汁が気管に下りて痰になり咳が出る
子どもの頃に副鼻腔炎を患ったことがあり、その影響が多分あるのだろうと思いますが、風邪を引くと鼻炎になりやすく、ひどくなると鼻汁が黄色みを帯びてきます。今月になって風邪で発熱し、熱が治った20日位前から、鼻汁が気管に下りてきて痰ができ、それを出すために咳が続いています。今回は鼻汁の色は無色透明です。咳は夜間にひどく出ます。 現在、漢方薬の麦門冬を服用していますが、このまま続けて快方を期待した方が良いでしょうか? また、他に何か効能のある薬やサプリ、食べ物とかを紹介していただけるとありがたいです。
転々と関節炎になる。
11/28に股関節炎(水が溜まっていた)の診断で、2週間の入院を経て、自宅で治療してます。入院した病院から紹介状を頂き、リウマチ科を受診しましたが、検査を2度実施してますが、正式な病名が不明です。関節の違和感や痛み、指先の痺れは継続してます。処方された薬はステロイド系の物、ロキソニン、胃薬です。この状況を察して、どんな病気が考えられますか? リウマチ科の先生は、血管炎とも言ってましたが検査後い特に断言しませんでした。
憩室炎、通院治療の際の推奨される食事内容と別の食事の質問
5日前の夜に右下腹部の違和感があり、4日前から痛みが出ている状況です。 同じような症状は3ヶ月ほど前にもありその際は抗生物質で治った経験があります。 3日前に内科受診、抗生物質を処方される(最寄りの消化器内科が休みのため内科受診) 2日前の夜に痛みがかなり増す。 昨日の朝に痛みがピークになったため消化器内科受診。そこで点滴治療を受けたのと外科の紹介状を書いてもらう。 本日外科を受診して検査の結果、憩室炎と言われました。 入院を強く勧められましたが通院治療を選択しております。 点滴治療を昨日から受けており今後も(少なくとも明日以降3日間も)毎日通院で受ける予定です。 前置きが長くなりましたが、このような状況で推奨される食事内容はどういったものでしょうか? また別の質問で、痛みがかなり酷くなった2日前の昼にバイキングで普段より食べすぎていたのですが、これは痛みが酷くなったのと関係ありますでしょうか? 以上となりますがよろしくお願いいたします。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「嚥下障害」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。