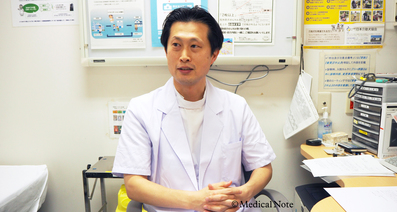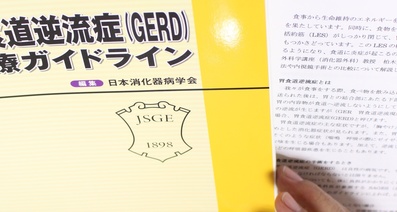摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)とは、口から食べたり飲んだりすることに障害があることをいいます。社会全体の高齢化が進む中で、摂食嚥下に対する関心が高まっています。東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 老化制御学系口腔老化制御学講座 高齢者歯科学分野 准教授の戸原玄先生にお話をうかがいました。
加齢に伴う摂食嚥下障害
軽い摂食嚥下障害の場合、特に何の病気もない方であっても、老化だけで嚥下の力が落ちるということが増えています。これにはいわゆるサルコペニア(加齢によって筋肉量が著しく落ちること)も関係していると考えられます。
特に、のどぼとけを持ち上げる舌骨上筋(ぜっこつじょうきん)という筋肉は嚥下に大きく関わっています。最近の研究報告でも、舌の筋肉や舌骨上筋が加齢で落ちてくるというデータが出ています。

何も病気がない方でも、たとえば以前よりもちょっとむせるようになった、ちょっと喉に何かが引っかかる感じがするといったことから、嚥下機能の低下が始まることがあります。そのことだけでは直ちに悪影響はないのですが、そのために食事の量が減ったりすると、今度は筋力も低下してさらに状態を悪化させることがありえます。
摂食嚥下障害の誘引となる疾患、きっかけ
何らかの疾患がきっかけで摂食嚥下障害が起こるケースとしては、やはり脳卒中の後に起こることが多いです
他にはパーキンソン病などの神経疾患がきっかけとなることも比較的多く見られます。
また、直接的には関係がないように思われますが、たとえば骨折で入院したご高齢の方が入院中に肺炎を起こして、その後食べられなくなるということがあります。つまり、入院で安静にしている間に急に弱って、廃用(使わないでいることで体の機能が衰えること)が進んでしまうのです。入院して帰ってきたら歩けなくなったなどという話はよく耳にするところですが、そういったことのひとつとして摂食嚥下障害が起こることもあるのです。
また、ご高齢の方の場合には認知症の影響もあります。アルツハイマー型認知症などが進むと体の筋肉も落ちてしまいますので、そのため嚥下も悪くなるということがあります。
歯と嚥下の関係
歯が悪いことから嚥下困難になるケースもないわけではありません
しかし、多少歯が悪くて噛めないとしても、それは食事に気をつけることである程度カバーすることができます。嚥下障害が多少進んだ症例の場合は、歯の状態にあまりこだわらず、どうすれば栄養が摂れるか、痩せないようにしていくにはどうすればよいかということを考えることがとても大事です。
たとえば、体の状態が悪い方から普通の方まで幅がある中で、普通の方の場合は歯が悪ければごく普通に治療をすればいいのですが、患者さんの状態が非常に悪い場合には、歯にこだわって普通の食事をしようとすると栄養状態が下がってしまいます。したがって、状態が悪ければ悪いほど、普通の食事をとれるようにすることよりも、何とかして栄養をとっていただかなくてはなりません。
その方の体状態がどの程度悪いのかによって、「普通の食事」にこだわるかどうかが変わってきますし、そのバリエーションはさまざまです。
むせる・むせないではなく「むせる原因」が重要
ひと口に「むせる」といっても、その原因がどこにあるかということは重要です
たとえば意識障害や体がまったく動かせないなどの理由で嚥下が本当に悪くなっている方は別として、それ以外では口や喉に問題があってむせる方もいます。また口や喉はそれほど状態が悪くなくても、姿勢が悪くてむせるという方もいます。あるいはその方の状況に合わない物を食べているということもありますし、要介護の方の場合は食事の方法がよろしくないということもあります。
嚥下障害が「ある・ない」ではなく、その方の嚥下障害を引き起こしているのはどこなのかを見ていくと、改善の方法はいろいろと考えられます。たとえば、ベッドの上でのけぞるような姿勢になっているとうまく飲み込めないので、頭の後ろに枕をあてがうだけでむせなくなることがあります。そのようなちょっとしたことから改善できることは少なくありません。
体の状態に合わせた食事の気づかい
私が過去に担当した患者さんの例で、退院後ミキサー食になったという90代の女性がいました。元々入院前は普通の食事をしていたので様子を見てほしいということで往診したところ、年齢相応に耳も遠くなっておられるし、歩き方も少しおぼつかないながら、その年齢としては普通といえる状態でした。
お話をうかがったところ、気管支拡張症で入院されて約2週間絶食の後、食事を再開するときに炒飯が出て、その炒飯でむせてからミキサー食(普通の食事または軟らかい食事をミキサーにかけたもの)になったというのです。
まずはおかゆなどを食べて、体を慣らしていくというようなことをしないまま、結局普通の食事できなくなっているケースが意外に多いのです。
病院などで嚥下機能の評価ができるようになってきているのは悪いことではありませんが、少し誤嚥(ごえん・食物や唾液が誤って気管に入ること)があるとすぐに胃ろう(腹部に入口を作り、栄養分などを胃に直接送りこむこと)をつくるようなケースもあります。
うまく食べられなさそうであれば、まず少し食事に気を使って工夫をしてみる。それでだめなら嚥下機能の検査をするという順序があってしかるべきだと考えます。それをせずにいきなり検査をするというのは、手順が抜けているのではないでしょうか。
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 老化制御学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科 科長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 老化制御学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授、東京科学大学病院 摂食嚥下リハビリテーション科 科長
戸原 玄 先生日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士日本老年歯科医学会 認定医・老年歯科専門医・指導医・摂食機能療法専門歯科医師
高齢者を中心とする摂食嚥下障害の治療、リハビリテーションに取り組み、往診による在宅診療や地域連携を積極的に行っている。厚生労働科学研究委託費長寿・障害総合研究事業“高齢者の摂食嚥下・栄養に関する地域包括的ケアについての研究”の業務主任者を務めている。ウェブサイト“摂食嚥下関連医療資源マップ”やその他のインターネットメディア・講演活動などを通して、摂食嚥下障害に関する情報発信も行っている。
戸原 玄 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
8歳の子どもに行うオルソケラトロジーについて
近視の為、眼科でオルソケラトロジーを勧められています。行っても視力は現状維持で、良くはならないと説明を受けました。費用も高額で、毎晩親が装着し、朝は外すという事を続けなければならず、試しにつけた際、痛がったこともあり、やるべきかどうか悩んでいます。何もせず、そのままにしておけばもっと悪くなる恐れがありますし、近視は将来別の病気のリスクが高くなると言いますので、高い費用を払って、毎日の手間をかけてでもせめて現状維持し、将来のリスクを少しでも回避できるよう、やるべきとも思いますが、オルソケラトロジーの眼への悪影響もわからず不安なこともあり、悩んでいます。また、行うとなった場合、最近は行っている病院も増えており、その中から実績があり、信頼のおける病院を探す方法がわからず、そちらも合わせてご教示いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。
鼻炎で鼻汁が気管に下りて痰になり咳が出る
子どもの頃に副鼻腔炎を患ったことがあり、その影響が多分あるのだろうと思いますが、風邪を引くと鼻炎になりやすく、ひどくなると鼻汁が黄色みを帯びてきます。今月になって風邪で発熱し、熱が治った20日位前から、鼻汁が気管に下りてきて痰ができ、それを出すために咳が続いています。今回は鼻汁の色は無色透明です。咳は夜間にひどく出ます。 現在、漢方薬の麦門冬を服用していますが、このまま続けて快方を期待した方が良いでしょうか? また、他に何か効能のある薬やサプリ、食べ物とかを紹介していただけるとありがたいです。
転々と関節炎になる。
11/28に股関節炎(水が溜まっていた)の診断で、2週間の入院を経て、自宅で治療してます。入院した病院から紹介状を頂き、リウマチ科を受診しましたが、検査を2度実施してますが、正式な病名が不明です。関節の違和感や痛み、指先の痺れは継続してます。処方された薬はステロイド系の物、ロキソニン、胃薬です。この状況を察して、どんな病気が考えられますか? リウマチ科の先生は、血管炎とも言ってましたが検査後い特に断言しませんでした。
憩室炎、通院治療の際の推奨される食事内容と別の食事の質問
5日前の夜に右下腹部の違和感があり、4日前から痛みが出ている状況です。 同じような症状は3ヶ月ほど前にもありその際は抗生物質で治った経験があります。 3日前に内科受診、抗生物質を処方される(最寄りの消化器内科が休みのため内科受診) 2日前の夜に痛みがかなり増す。 昨日の朝に痛みがピークになったため消化器内科受診。そこで点滴治療を受けたのと外科の紹介状を書いてもらう。 本日外科を受診して検査の結果、憩室炎と言われました。 入院を強く勧められましたが通院治療を選択しております。 点滴治療を昨日から受けており今後も(少なくとも明日以降3日間も)毎日通院で受ける予定です。 前置きが長くなりましたが、このような状況で推奨される食事内容はどういったものでしょうか? また別の質問で、痛みがかなり酷くなった2日前の昼にバイキングで普段より食べすぎていたのですが、これは痛みが酷くなったのと関係ありますでしょうか? 以上となりますがよろしくお願いいたします。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「嚥下障害」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。