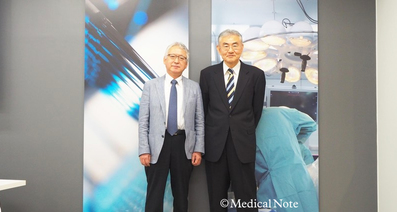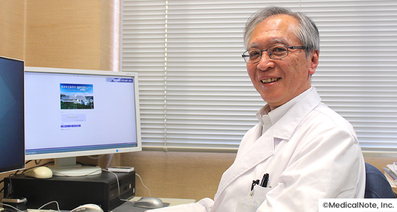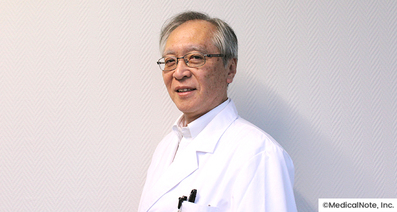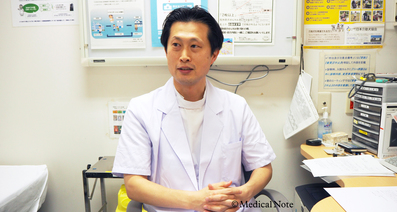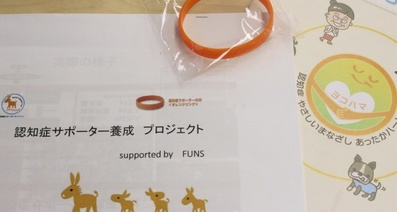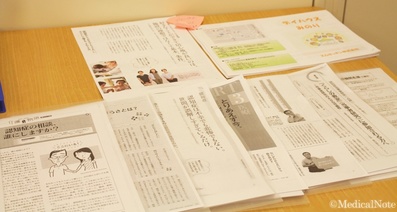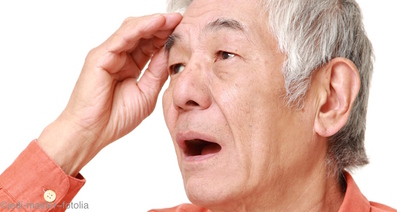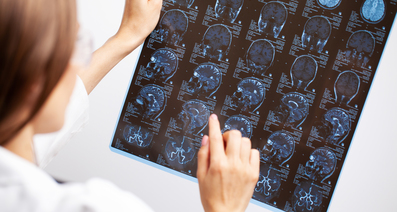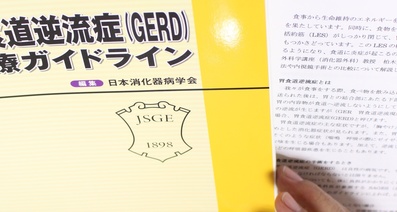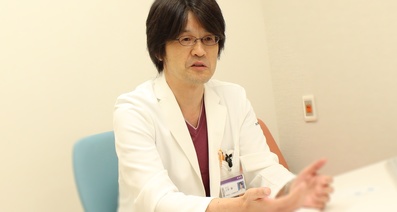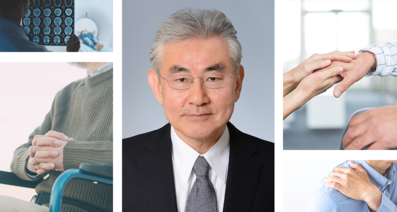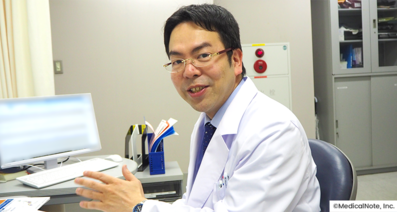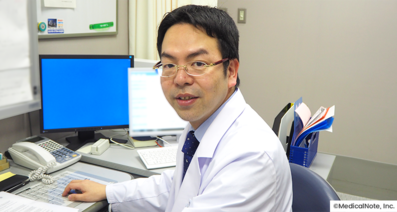認知症には、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などの種類があり、それぞれに異なる症状が現れることで知られています。食べ物や水分のとり込みがうまくいかず、むせてしまったり肺炎を引き起こすこともある「摂食嚥下障害」もそのひとつで、誤嚥(飲み込みの障害)が現れる認知症と現れにくい認知症が存在します。本記事では、認知症の種類ごとにみる症状の特徴について、大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室准教授の野原幹司先生に解説していただきました。
摂食嚥下障害とは
食物や水分を認識して口の中に取り込み、これらを咽頭から食道、そして胃へと送り込むことを「摂食嚥下(せっしょくえんげ)」または「嚥下」といいます。「(摂食)嚥下障害」とは、食べ物を認識してからゴクリと飲み込むまでの一連の機能が、何らかの原因により正常に機能しなくなってしまった状態を指します。たとえば、食事中にたびたびむせて水分をうまく摂れなくなったり、食べ物が食道ではなく気管に入ってしまい肺炎を起こすことなどが、摂食嚥下障害の代表的な症状として挙げられます。
これまでの摂食嚥下障害の捉え方の問題点-全てが「治る」わけではない
これまで日本では、摂食嚥下障害といえば主に「脳卒中後の回復期」にみられるものとして取り扱われており、訓練することで改善が見込めるものと考えられてきました。
しかし、本記事で取り上げる「認知症に伴う摂食嚥下障害」は、訓練により機能回復を目指す性質のものではなく、機能低下に応じたケアを要するものです。
認知症患者さんの摂食嚥下障害に関する認識は、医療者間においてもあまり広がっておらず、実際に介護施設の看護師さんやセラピストさんからも、「なぜ教科書通りの訓練を行ったのによくならないのだろうか」という疑問の声を耳にすることがあります。
しかし、参考にしている摂食嚥下障害の本をよくみると、それは「脳卒中の回復期」を対象にかかれていたものでした。つまり摂食嚥下障害とは、それほどまでに脳卒中の回復期と強く結び付きすぎているということです。しかしながら、脳卒中の回復期における摂食嚥下障害とは、「食べたいのに、うまく食べられない」といったものであり、意思疎通が難しく、回復の兆しもみられない認知症の摂食嚥下障害とは病態が異なります。ですから、適切な治療や支援のためには、病態別に摂食嚥下障害を考えていかねばなりません。また、認知症にはアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症などの種類があり、摂食嚥下障害の有無は認知症のタイプによっても変わります。
では、原因疾患別の摂食嚥下障害の特徴についてみていきましょう。
アルツハイマー型認知症は、誤嚥しない認知症
誤嚥とは、食べたものや唾液などが気管に入りむせてしまうことで、誤嚥性肺炎の原因となることもあります。本項で解説する「アルツハイマー型認知症」は、全ての認知症のうち約50%を占める認知症で、「誤嚥」しないという特徴があります。
これはアルツハイマー型認知症が、物忘れや記憶力の低下など認知機能の低下は起こるものの、身体機能はほとんど低下しない病態であるからです。身体機能が維持される理由は、アルツハイマー型認知症では大脳皮質はダメージを受けるものの、脳幹を構成する延髄には障害が及ばないからです。
このような病態であるため、たとえば「食事場面が認識できず、食事を始めることができない」、「喉へと食べ物を送り込むことはうまくできない」、「しかし、喉は正常に機能している」ということがあります。
ですから、認知症患者さんで誤嚥をしていない場合はアルツハイマー型認知症なのではないか、誤嚥をしているのであれば別の認知症なのではないかと推察することができます。
また、アルツハイマー型認知症の患者さんが肺炎を起こしたとき、誤嚥性肺炎と誤診されて禁食となるケースも往々にしてありますが、実際には市中肺炎に感染しただけということも考えられます。こういった誤診を防ぐためにも、アルツハイマー型認知症は基本的に誤嚥をしないというポイントを押さえておくことが重要なのです。
もちろん、脳卒中を合併した場合や、本当の終末期は、アルツハイマー型認知症でも誤嚥が目立つようになってきます。
レビー小体型認知症は、誤嚥する認知症
アルツハイマー型認知症以外の認知症のひとつ、「レビー小体型認知症」が世界的に認められたのは2000年代に入ってからのことです。そのため、ごく最近まで医療の世界でも「認知症=アルツハイマー型認知症」という捉え方が浸透しており、医療書籍などでも「認知症は誤嚥をしない」という記述がなされているものがありました。
しかし、本項で解説する「レビー小体型認知症」は、誤嚥をする認知症です。というのも、レビー小体型認知症は、摂食嚥下障害だけでなく歩行障害などの身体症状が出る認知症だからです。(※レビー小体が溜まる部位によっては身体症状が出ないこともあります。)
レビー小体型認知症の摂食嚥下障害の症状の中でも特に多いのは「食事中にむせこむこと」であり、実際に患者さんの介護に携わる方は、食事中に特に注意が必要であることを知っておくことが大切です。
ところが実際に施設を訪問すると、カルテに「認知症」としか書かれていない患者さんが多くいらっしゃり、どのようなフォローが適切なのか迷ってしまうこともあります。
もちろんご家族が近くにいらっしゃる場合は、初期症状などを聞き、アルツハイマー型認知症なのかレビー小体型認知症なのかを推察して誤嚥のリスクの高低を考えることも可能です。たとえば、初期に「(患者さんが)幻視がみえると言っていた」「手足が小刻みに震えていた」「血圧が不安定だった」といった情報が得られれば、レビー小体型認知症の可能性を考え、誤嚥のリスクと食事の際のフォローの必要性について共有することができます。
このように、誤嚥の有無がアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の鑑別に役立つということは、認知症を中心的に診ている先生にもまだあまり知られていません。ですから、摂食嚥下障害を専門的にみる我々歯科から情報を発信していくことが重要であると考えます。
(関連記事:https://medicalnote.jp/contents/150429-000005-GUYOPY 『レビー小体型認知症が世界中で認められるまで』 小阪憲司先生)
血管性認知症-誤嚥のリスクは損傷を受けた部位で変わる
脳血管が障害された結果として認知機能に障害が出るものの総称を「血管性認知症」といいますが、実際にはダメージを受けた部位により捉え方は大きく変わります。たとえば、大脳皮質がダメージを受けることで高次脳機能障害が起こることがありますが、これには脳卒中後の失語症などが含まれており、認知症とはいえないという考え方が主流です。
血管性認知症の主な病態とは大脳基底核の障害であり、具体的には白質病変やラクナ梗塞などを含みます。大脳基底核がダメージを受けると、摂食嚥下障害が現れるので食事の際には注意が必要です。
このような病態であることから、私は血管性認知症もしくは脳卒中により摂食嚥下障害が生じたという患者さんの診察においては、「大脳皮質と基底核のどちらが大きく損傷されているか」を考えるようにしています。
たとえば手足が硬直する痙性麻痺(けいせいまひ)がみられる場合は、大脳皮質が主ダメージを受けているケースが多いため、摂食嚥下障害のリスクは低いと判断します。
これとは逆に、手足の麻痺はなく、歩行障害やバランス障害などが現れている場合は、基底核が損傷されている可能性が高いと考え、誤嚥のリスクが高いと臨床推論します。
前頭側頭型認知症-ALSを合併すると強い摂食嚥下障害が生じることも
前頭側頭型認知症とは、様々な疾患が重複する認知症であり、摂食嚥下障害についても一概に言い表すことはできません。たとえば、前頭側頭型認知症のひとつであるピック病では、食べるペースが異常に速かったり、食の嗜好などに偏りは出てきたりするものの、誤嚥はしにくいという特徴があります。
ところが、進行性非流暢性失語や前頭側頭型認知症に運動ニューロン病を合併すると、摂食嚥下障害が非常に強く現れることもあります。
認知症患者さんのケアの質を向上させるために

以上のような特徴から、摂食嚥下障害の有無が鑑別の際の補助として役立つ認知症は、アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の2つであるといえます。また、実際の高齢者医療の現場では、この2つの認知症が大半を占めています。
認知症の確定診断は、より詳細かつ専門的な検査が必要であり、一部の専門医にしかできません。しかし、臨床所見から「この患者さんはレビー小体型認知症の可能性がある」「この患者さんは典型的なアルツハイマー型認知症だ」と推測し、より適切なケアを考えることは、看護師さんやセラピストさんなど、患者さんをとりまくあらゆる医療者にできることです。また、誤嚥のリスクの高低をご家族にお話ししておくことも、ケアの質の向上に繋がることと考えます。
このように、それぞれの認知症における摂食嚥下障害の特徴を知り、ケアに活かすことが、今後の認知症患者さんの介護において重要であると考えます。
大阪大学 大学院歯学研究科 高次脳口腔機能学講座 顎口腔機能治療学教室 准教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
野原 幹司 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が10件あります
8歳の子どもに行うオルソケラトロジーについて
近視の為、眼科でオルソケラトロジーを勧められています。行っても視力は現状維持で、良くはならないと説明を受けました。費用も高額で、毎晩親が装着し、朝は外すという事を続けなければならず、試しにつけた際、痛がったこともあり、やるべきかどうか悩んでいます。何もせず、そのままにしておけばもっと悪くなる恐れがありますし、近視は将来別の病気のリスクが高くなると言いますので、高い費用を払って、毎日の手間をかけてでもせめて現状維持し、将来のリスクを少しでも回避できるよう、やるべきとも思いますが、オルソケラトロジーの眼への悪影響もわからず不安なこともあり、悩んでいます。また、行うとなった場合、最近は行っている病院も増えており、その中から実績があり、信頼のおける病院を探す方法がわからず、そちらも合わせてご教示いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。
鼻炎で鼻汁が気管に下りて痰になり咳が出る
子どもの頃に副鼻腔炎を患ったことがあり、その影響が多分あるのだろうと思いますが、風邪を引くと鼻炎になりやすく、ひどくなると鼻汁が黄色みを帯びてきます。今月になって風邪で発熱し、熱が治った20日位前から、鼻汁が気管に下りてきて痰ができ、それを出すために咳が続いています。今回は鼻汁の色は無色透明です。咳は夜間にひどく出ます。 現在、漢方薬の麦門冬を服用していますが、このまま続けて快方を期待した方が良いでしょうか? また、他に何か効能のある薬やサプリ、食べ物とかを紹介していただけるとありがたいです。
転々と関節炎になる。
11/28に股関節炎(水が溜まっていた)の診断で、2週間の入院を経て、自宅で治療してます。入院した病院から紹介状を頂き、リウマチ科を受診しましたが、検査を2度実施してますが、正式な病名が不明です。関節の違和感や痛み、指先の痺れは継続してます。処方された薬はステロイド系の物、ロキソニン、胃薬です。この状況を察して、どんな病気が考えられますか? リウマチ科の先生は、血管炎とも言ってましたが検査後い特に断言しませんでした。
憩室炎、通院治療の際の推奨される食事内容と別の食事の質問
5日前の夜に右下腹部の違和感があり、4日前から痛みが出ている状況です。 同じような症状は3ヶ月ほど前にもありその際は抗生物質で治った経験があります。 3日前に内科受診、抗生物質を処方される(最寄りの消化器内科が休みのため内科受診) 2日前の夜に痛みがかなり増す。 昨日の朝に痛みがピークになったため消化器内科受診。そこで点滴治療を受けたのと外科の紹介状を書いてもらう。 本日外科を受診して検査の結果、憩室炎と言われました。 入院を強く勧められましたが通院治療を選択しております。 点滴治療を昨日から受けており今後も(少なくとも明日以降3日間も)毎日通院で受ける予定です。 前置きが長くなりましたが、このような状況で推奨される食事内容はどういったものでしょうか? また別の質問で、痛みがかなり酷くなった2日前の昼にバイキングで普段より食べすぎていたのですが、これは痛みが酷くなったのと関係ありますでしょうか? 以上となりますがよろしくお願いいたします。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「嚥下障害」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。