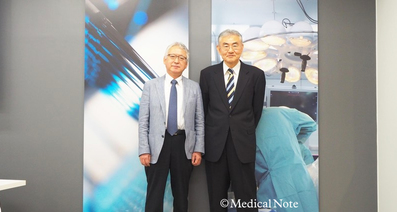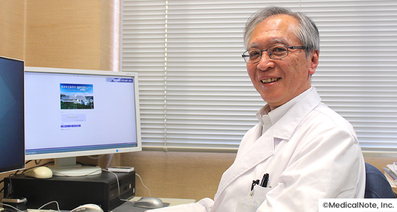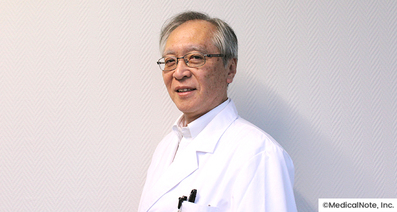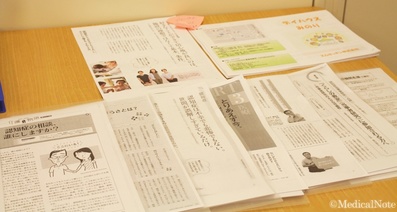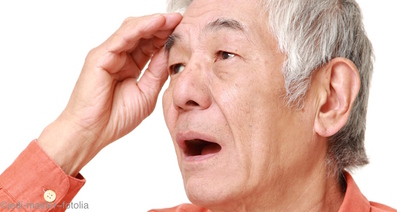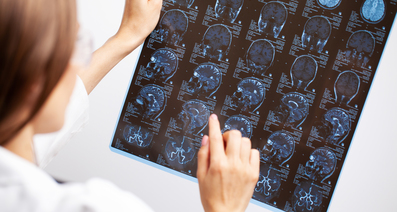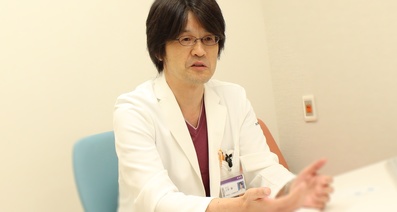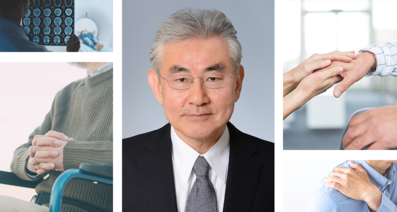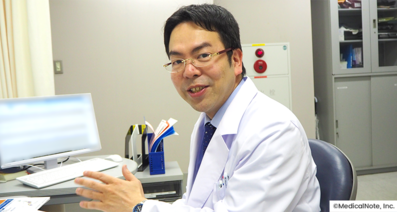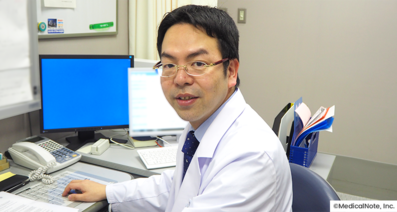認知症の患者さんを支えるために - 認知症サポーター養成プロジェクト

2016年6月、横浜国際ホテルにて「認知症サポーター養成プロジェクト」が開催されました。
この会は権利擁護などの面から認知症患者の生活支援を行っているLTRコンサルティングパートナーズ・加藤博明氏と、認知症サポーターを育成する「認知症キャラバン・メイト」ボランティアによる司会のもと、全国で活躍する認知症サポーターの理念や活動内容、そして今後さらなる高齢社会が進む日本で認知症サポーターに求められる使命について再認識すると同時に、若年性認知症と診断された方の気持ちや日常生活について直接語っていただきました。
認知症サポーターキャラバンとは? 社会で認知症患者さんを支えるために
認知症を完治させることはできません。ですが適切な治療と周囲の方の理解により、症状の進行を遅らせることは可能です。
認知症が進行すると、日常生活を送るうえで不都合が生じることが多くなります。「認知症サポーター」とは、認知症がどのようなものか正しく理解し、認知症と診断された方やその家族をサポート、温かく応援する支援者のことです。そしてこの認知症サポーターを全国各地で養成し、たとえ認知症になっても安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組んでいるのが「認知症サポーターキャラバン」です。
認知症サポーターキャラバンでは認知症サポーターを養成するため、所定のキャラバン・メイト研修を修了した「キャラバン・メイト」と自治体が協働し「認知症サポーター養成講座」を定期的に開催しています。2016年3月末の段階で間に全国で7,503,883名の認知症サポーターと125,179名のキャラバン・メイトを排出、各地で認知症の方やその家族を見守っています。
※認知症サポーターや認知症サポーターキャラバンについて、公式サイトはこちらから
横浜市では増加する認知症患者を支えるため認知症サポーター養成が課題のひとつとされている
横浜市内の開催ということもあり、会場には横浜市内を中心に活躍する認知症サポーター、介護の現場で多くの認知症患者のケアにいそしむ介護職従事者、認知症の診断や進行を食い止めようと日夜努力を続ける医師など多くの医療関係者が集結し、認知症の症状や原因、複数ある認知症との差異などについて認識を改めました。
認知症サポート養成講座が開催された横浜市は、2015年の段階で65歳以上の方の人口が約80万人、2025年には約97万人に増加すると予測されています。この数字は横浜に住む方の比率が2015年現在5人に1人、2025年には4人に1人になると計算することができます。
認知症に対する認識は以前よりも浸透しつつありますが、いまだ完全なものとはいい難い状況です。今回行われた認知症サポーター養成プロジェクトでは、認知症医療における現状の課題についても焦点が当てられました。数ある課題のなかでも特に
・認知症の人が住み慣れた地域で可能な限り生活を続けていくための介護サービスが量、質の両面から不足している
・地域で認知症とその家族を支援する体制が不十分
という部分が、問題視されていると強調されました。
高齢化の進展につれ認知症の方が増えることも予想されている状況を鑑み、横浜市では認知症に対する理解を広げるとともに、認知症と診断された方が安心して生活をできる環境を整える取り組みをしています。
『今が一番幸せです』周囲の理解が癒す患者さんの苦しみ

この日は8年ほど前から若年性認知症の症状がでてきた近藤英男氏に登壇いただき、認知症になってから日常生活にどのような変化が生じたのか、実際に体験したことや感じたことなどについてお伺いしました。
若年性認知症では特定の物事に対する能力が低下します。ゴミ出しや買い物など、認知症が原因で日常生活のなかで生じやすいトラブルに対しどのように対応したらいいのかをまとめたDVDが上映されました。
「内容には心当たりがあるものが多く、まるで自分の行動を見ているようだ。周囲から見ると違和感がある行動に思えるが、認知症により自分もこうした行動をとることがある。」
という旨のコメントをされました。
当日は同じ認知症を患う患者さんたちと行ったソフトボール大会、そしてご自身が通われていた高校にかつての同級生達と訪問したときのことや、自身が所属していたラグビー部に所属している後輩たちと交流したときの様子も伺うことができました。
友人たちによると、近藤氏は昔から明るく朗らかで人を引き付ける性格で、周囲には常に友人たちがいる方だったそうです。
非常に明るく常にニコニコされている点も特徴的で、今回の登壇でも終始ニコニコされていました。また、今回、たくさんの写真が紹介されましたが、どの写真でも例外なくニコニコされていました。近藤氏の診療を長年行われている、湘南いなほクリニック院長内門大丈(うちかど・ひろたけ)先生によると『認知症になると気持ちが滅入り、消極的になる人が多い。中にはうつ状態になる方もいる』とのことです。しかし、この患者さんは「毎日がホリデー。昨日よりも今日を楽しく、人生で今が一番楽しい。」とおっしゃいます。
近藤氏は発病から既にずいぶんと時間が経過していますが、毎日、明るく生活を送られているようです。その秘訣は一体何なのでしょうか?
もちろん、近藤氏個人の性格による部分が大きいと思います。しかし、お話をうかがっていると、やはりそれだけではありません。周囲の方々に恵まれていること、周囲の方々の認知症への理解が進んでいることも大きな理由のように感じられます。
繰り返しになりますが、認知症になると心の病の部分が患者さんを蝕んでしまうことも多くあります。しかし、認知症は、それになったからと言ってふさぎ込む病気ではありません。患者さんの周りにいる方々が認知症のことをよく理解することで、患者さんの毎日が楽しく変わることだってあるのです。近藤氏とその周囲の方々のあり方は、そのことを教えてくれる好例ではないでしょうか。
認知症の基礎知識
認知症はタイプによって自覚、もしくは周囲の方が認識する症状に差がみられることがあります。いずれのタイプも脳内の神経細胞が死滅することにより、情報の伝達が悪くなります。そのため
・物忘れ(ヒントをもらっても思い出すことができない)
・時間や場所の感覚が分からなくなる
・考え事に時間がかかるようになる
・一度に複数のことをこなせなくなる
というように、行動に変化が生じるようになります。
ほかにも脳の機能が衰えることが原因で
・認知能力の低下を悲観し元気が出ない、もしくは無気力などうつ状態になる
・大声を出す・怒りやすくなる。暴力をふるうなど、行動が荒くなる
・財布を盗まれた・食事を食べさせてもらえないなど、妄想を抱くようになる
というように、性格や感情に変化を生じさせます。
このように行動面・心理面での変化が生じ、生活に支障がみられることを認知症と呼びます。
認知症では脳がどのようにしてはたらきが悪くなったのかによって、いくつかの種類に分けることができます。
認知症①アルツハイマー型認知症
2011年の報告によると、認知症と診断された方のうち約67%の方がこのアルツハイマー型認知症が原因と診断されています。このアルツハイマー型認知症は女性に確認されることが多く、患者数も年々増加傾向にあります。アミロイドβやタウなど特殊なタンパク質が脳内に蓄積し、神経細胞が徐々に破壊され脳が萎縮していくことが原因とされています。アルツハイマー型認知症は20~30年かけてゆっくり進行、脳全体が萎縮していきます。
認知症②脳血管性認知症(VD)
脳疾患(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)により、脳内で生じた出血が血管に詰まることが原因です。脳全体が萎縮して能力が低下していくアルツハイマー型認知症と対照的に、脳血管性認知症では出血が生じた部位に障害が起こるので、できること・できないことに差があるのが特徴とされています。
血管性認知症(VD)の治療は?―生活習慣病の予防がカギ。地域連携をうまく活用した総合的な治療を
認知症③レビー小体型認知症(DLB)
男性に多く発症することが確認されている認知症のタイプです。神経細胞に「レビー小体」と呼ばれる特定のタンパク質が蓄積することで神経細胞が破壊、脳の活動が低下していきます。レビー小体が蓄積したのが大脳皮質であれば物忘れや幻視などの症状を呈し、脳幹に蓄積すれば歩行困難や震えなどに代表されるパーキンソン症状を呈するようになります。
認知症④前頭側頭葉型認知症(FTD)
若年性認知症の原因となることが多いタイプです。前頭葉は感情のコントロールや理性的な行動、状況を把握する機能を持っています。これに対し側頭葉では言語理解・記憶・嗅覚や聴覚をつかさどっている部位です。この部分に萎縮が生じることにより、同じ行動を何度も繰り返す・集中力や自発性の低下が生じるようになります。また理性をつかさどる分野が萎縮するため、異常な食行動や反社会的な行動を起こしやすくなる特徴があります。一般的な認知症として認識されている物忘れなどはあまり見られません。
医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 理事長・院長、横浜市立大学医学部 臨床教授、日本精神神経科診療所協会 理事、神奈川県精神神経科診療所協会 副会長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医療法人社団彰耀会 メモリーケアクリニック湘南 理事長・院長、横浜市立大学医学部 臨床教授、日本精神神経科診療所協会 理事、神奈川県精神神経科診療所協会 副会長
内門 大丈 先生日本精神神経学会 精神科専門医・精神科指導医
1996年横浜市立大学医学部卒業。2004年横浜市立大学大学院博士課程(精神医学専攻)修了。大学院在学中に東京都精神医学総合研究所(現東京都医学総合研究所)で神経病理学の研究を行い、2004年より2年間、米国ジャクソンビルのメイヨークリニックに研究留学。2006年医療法人積愛会 横浜舞岡病院を経て、2008年横浜南共済病院神経科部長に就任。2011年湘南いなほクリニック院長を経て、2022年4月より現職。湘南いなほクリニック在籍中は認知症の人の在宅医療を推進。日本認知症予防学会 神奈川県支部支部長、湘南健康大学代表、N-Pネットワーク研究会代表世話人、SHIGETAハウスプロジェクト副代表、一般社団法人日本音楽医療福祉協会副理事長、レビー小体型認知症研究会事務局長などを通じて、認知症に関する啓発活動・地域コミュニティの活性化に取り組んでいる。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が28件あります
若年性認知症
本日脳神経外科にてMRI検査にて脳の萎縮を数値化したものより若年性認知症との診断を受けました。会社では鬱の悪化、大人の発達障害等考えられることを確認しました。その上での診断でした。今後、気をつけて行かなくてはいけないことはなんでしょうか。
認知症 怒りの対応の仕方について
義父の嫁です。 昨年末から体調を崩し、検査の結果様々な部位に病気が見つかり、治療、手術(肝細胞がん等)をしました。その結果、入院中にせん妄になり、術後1週間で退院させられ、自宅生活になりましたが、認知症が急に進み、家族は皆振り回されています。 特に困るのは、自分の身体に心配が出来ると、家族にあちらこちらの病院や薬屋さんに連れていけと言います。自分が気になった物が見つからないと、買い物にも連れて行けと言います。 何とか話をそらそうとしても、自分の欲求が満たされないと、癇癪を起こし、最後には自転車で出かける!と言い出します。 もちろんそんなことはさせられないので、どうしたものか?と悩んで、家族は疲弊しています。 今は脳神経内科を受診していますが、このままで良いのでしょうか?よろしくお願いします。
認知症について、
今年に入ってから時々 母が幻覚を見てるのか誰かがのぞいてるとか俺には見えない誰かと口喧嘩したりしています、これって認知症ですか?。 どうしたらいいのか解らずその時たまに喧嘩してしまいます。 ここ数年 俺と住んで居ますが家にひとりで居るのがいけないのでしょうか? 認知症の検査うけよかって言うとまだボケてない!! って言って受けようとしませんどしたらいいですか?
どんどん症状が悪化
認知症の症状がどんどん悪化していて心配です。治りますか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「認知症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。