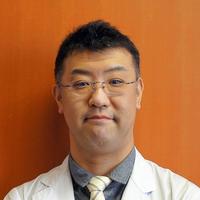1895年のレントゲンによるX線撮影の発明によって、医療の世界に「見えないものを見る」という最先端技術がもたらされました。放射線診断学は医療においてどのような役割を担っているのでしょうか。済生会宇都宮病院放射線科で診断部に所属する薄井広樹先生にお話をうかがいました。
診断医は各科の専門医に何を提供しているのか
レントゲンがX線撮影を発明したことによって、それまで主治医に見えなかったものが放射線診断学を通して見えるようになりました。我々診断医の大きな役割のひとつは、見えないものを見る、その「目」を提供するということです。
そしてもうひとつ、「知識」を提供しているという部分があります。内科・外科・整形外科など、さまざまな領域の医師はそれぞれ専門的な知識を持っていますが、専門外の部分についてはそこまでよく知っているわけではありません。ですから我々放射線診断医は、画像に映るものはすべて知っているべきです。もちろんそれはあくまでも理想ですが、我々はできるだけその理想に近づけるよう日々研鑽を重ねています。
主治医が注目している病変以外にも、実は思わぬところに何か別のものが写っているということもありますし、いま画像に写っている病変が原因となって、全身で他の問題が起こる可能性があるなど、さまざまな指摘ができる場合もあります。専門医の知識の外にあることを、我々診断医が知識として提供すること―つまり「目」と「知恵」、このふたつを提供するのが診断医であると考えます。
放射線診断専門医になるには
公益社団法人日本医学放射線学会(http://www.radiology.jp)では、専門医制度として「放射線診断専門医」というものを設けています。そこに至るまでに試験が2回あり、受験資格を得るためにはどのような画像を何件読まなければならないといった決まりがあります。つまり、ある程度経験を積んだということが客観的に担保されるような状態で試験を受けることになります。ですから、試験に受かれば一人前として認められることにはなりますが、実際にはそこからが勝負といってもいいでしょう。
放射線検査・診断が必要な病気とは
今やあらゆる病気で我々診断医による検査・診断が必要な場面があります。たとえば脳卒中で倒れた方の場合、それが脳出血なのか脳梗塞なのか、あるいは出血であればどこからの出血なのかということは、外側から見ていては絶対にわかりません。しかしそれはCT(コンピューター断層撮影)やMRI(核磁気共鳴画像)で見れば間違いなくわかることです。
胸部であれば、たとえば肺がんなども画像診断でわかる病気のひとつです。しかし肺炎でも細菌感染による肺炎だけではなく、ウイルスや真菌(カビの一種)による感染もあります。あるいは薬にともなう薬剤性肺炎や、そのほかの特殊な原因による肺炎などもあります。それらはある程度パターン化されているので、画像からどのような原因が疑われるかという判断ができます。
その他にも動脈瘤(どうみゃくりゅう)という破裂する危険性がある血管病変、あるいは腫瘍性の病変、尿管結石などあらゆる病気で放射線検査は欠かせないものとなっています。
術前シミュレーションのための画像診断
特に外科系を中心に、他科からは手術のシミュレーションのための画像を撮るというオーダーがあります。その画像から3Dイメージを構築したり、あるいはCTで非常に薄くスライスした画像を作り、そこから実際の術野に合わせて事前の検討を行ったりすることが多くなっています。
現在のCTでは1mm以下というような非常に細かい間隔でのスライスができます。その0コンマ数ミリを1辺とした立方体のドットをアイソボクセルといいますが、このデータを持つことができるようなったということが、現在の画像診断技術の根幹となっています。すべての辺が等しいこの微小なドットを積み重ねることによって、縦切り・横切り、そして立体でのシミュレーションが自由自在にできるようになったのです。
また、ソフトウェアの技術も非常に発達しています。縦切り・横切りの従来の断層撮影だけでなく立体的なイメージを得るためには、膨大な計算を行う必要があります。その点ではコンピューターのスペックやソフトウェアの性能の向上が大きく寄与しています。
放射線診断学においては、1895年にレントゲンがX線撮影を発明したその時から、医療にもたらされた最先端の技術を100年以上にわたって追い求めてきたという歴史があります。この技術の進歩には終わりがありません。我々もまたそれを永遠に追い続けることが使命であると考えています。
薄井 広樹 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。