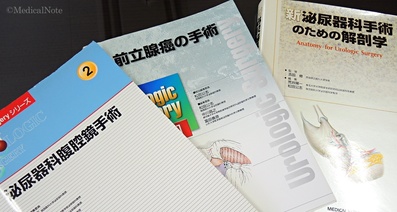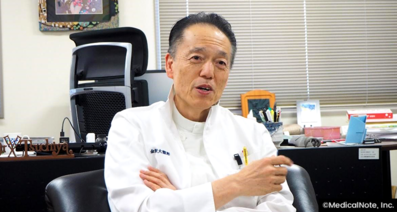

腎臓がんとは、早期段階で手術を行うことができれば、治すこともできるがんです。切除方法には、腎臓の一部を取る部分切除術と、全てを取る全摘出術の2種類があります。また、これらの手術は、腹腔鏡を用いて行われることもあれば、開腹して行われることもあります。腫瘍の大きさごとの手術方法について、秋田大学医学部附属病院泌尿器科科長の羽渕友則先生にお伺いしました。
腎臓がんの治療――標準治療は手術によるがんの切除
転移がみられない腎臓がんの場合、基本的に手術により病巣を切除します。薬物療法や放射線治療で腎臓がんの根治を目指すことは難しく、特に後者の放射線治療は原発巣である腎臓のがんには効きません。そのため、放射線治療は転移がある場合にのみ、転移巣を狙って行います。たとえば、骨転移がみられるときは、骨折の予防や疼痛緩和を目的として放射線治療を取り入れます。
転移がある場合、腎臓に対する手術を行うか?
肺転移や骨転移がある場合は、原発巣である腎臓のがん以上に、転移巣により命が左右されるケースが多くなります。そのため、腎臓を切除するかどうかは、患者さんの状態など、さまざまな要素をみて判断する必要があります。
ある報告では、転移のある進行腎臓がんでも、腎臓を切除することによりその後の治療成績がよくなるとされています。ただし、病状が悪化しており呼吸困難などの重い症状がみられる場合は、無理に手術を行わず薬物療法を選択します。
腎臓がんの切除手術――部分切除術と全摘出術
腫瘍の直径が4cm以下ならば部分切除

腎臓がんの手術方法には、部分切除術と全摘出術があります。当院では、腫瘍が4cm以下の場合、基本的には部分切除を選択し、4cmを越える場合に全摘出術を選択します。
部分切除にも、腹腔鏡手術と開放手術の2種類があります。また、全摘出術も、腫瘍の大きさにより腹腔鏡手術と開放手術に分けられます。
腎臓がんの部分切除術――腹腔鏡手術と開放手術の違い
腹腔鏡手術とは、腹部の小さな創部から内視鏡と器具を挿入し、モニターで腹腔内(お腹の中)の様子をみながら病巣にアプローチする手術方法です。当院では、ほとんどの腹腔鏡下の腎部分切除術を、手術支援ロボット・ダヴィンチを使って実施しています。
ダヴィンチを使用しない通常の腹腔鏡手術もありますが、ダヴィンチのほうがより繊細な縫合や処置を行うことが可能です。傷の大きさは約3cmです。
開放手術とは、腹部をやや大きく(20~30cmほど)切開し、術者の手で直接腎臓の切除を行う手術です。
腎臓がんの大きさと術式――秋田大学医学部附属病院の場合
当院では、腫瘍の大きさにより、以下のように術式を選択しています。
- 腫瘍の直径が4cm以下のとき
ダヴィンチ®を用いた腹腔鏡下腎部分切除術、もしくは開放手術による腎部分切除術
- 腫瘍の直径が4cm~10cmのとき
腹腔鏡手術による全摘出術
- 腫瘍の直径が10cm以上のとき
開放手術による全摘出術
開放手術は全体の約1割程度と減っている
腫瘍が腸や肝臓など周辺臓器に密着してしまっていたり、大血管内に入っていたりしているときには開放手術を選択します。
ただし、早期発見例が増えたことなど、さまざまな理由から開放手術は減っており、現在では全手術の約1割程度にまで低下しています。
腎臓を全摘出した後の生活の質(QOL)は比較的良好

大半の腎臓がんは、片側の腎臓のみに生じます。そのため、全摘出術といっても、両腎を取るわけではありません。記事1『腎臓がんの原因と症状とは?3大リスク因子や遺伝との関係について』でも述べたように、片方の腎臓を摘出したとしても、その後の生活に特別な制限はかかりません。これは、左右の腎臓が50%ずつ同様のはたらきをしているためです。実際には、腎臓の約25%の機能が残っていれば通常の生活に支障はないともいわれており、当院で全摘術を受けた患者さんの中にも、その後マラソンなどのスポーツを楽しまれている方や、糖尿病などに注意しつつ妊娠・出産された女性の方もいらっしゃいます。ほかに持病がなければ、塩分制限をする必要もありません。
ただし、ラグビーなど、残した腎臓に外傷を与える危険のある行為には気を付けていただく必要があります。また、腎臓は再生する臓器ではなく、予備もありませんので、部分切除で済むようであれば、やはり部分切除術を選択すべきであると考えます。
両腎にがんが生じる場合とは?
腎臓がんのうち約5%は両方の腎臓にがんが生じます。同時に発見されるケースもあれば、片方の腎臓を摘出した後、時間が経過してから残した腎臓にがんが生じるというケースもあります。
また、遺伝疾患のフォル・ヒッペル・リンドウ病のうち半数は腎臓がんになるといわれていますが、この場合は両腎にがんが生じます。
転移がある進行腎臓がんには分子標的治療を行う
腎臓がんが進行しており、肺や骨に転移がみつかっている場合は、一般的に分子標的薬(スニチニブ、アキシチニブ、パゾパニブ)を用いた分子標的治療や新規の免疫療法薬(ニボルマブ)を選択します。
このとき分子標的治療のターゲットとなるのは、主に転移巣です。というのも、肺や骨への転移は、腎臓を摘出したのち歳月が経過してから生じることも多く、既に腎臓自体がないことも少なくはないからです。
ニボルマブは第一選択ではない
現在、ニボルマブが進行腎臓がんにも有用であると話題を呼んでいます。しかし、現在では保険の問題もあり、ニボルマブはあくまで分子標的薬が効かなかった場合に選択される治療薬です。
分子標的薬は治療成績が安定しており、保険適用で第一選択として使用できるため、こちらが第一選択となるのです。
2次療法以降はニボルマブの使用により、劇的な効果を得られる人がいることも事実です。
転移巣が少ない場合は手術を行うこともある
分子標的薬により転移のある進行腎臓がんの根治を目指せるかというと、困難な例も少なくはないといわざるを得ません。
そのため、肺転移や骨転移などの転移巣が1つだけという場合は、より確実性の高い効果を狙い、転移巣を切除する手術を選択することもあります。
腎臓がんの手術後の再発率
腎臓がんの再発率は5~10%
腫瘍が4cm以下で部分切除術を行った患者さんの再発率は5%以下、腫瘍が4cm~10cmで、腹腔鏡手術により腎全摘出術を行った患者さんの再発率は10%ほどです。この数値から、もとの腫瘍が大きいほうが再発しやすくなる傾向があるといえます。
また、腫瘍が小さい場合でも、10年後など、非常に長い歳月を経て再発することがあります。再発がんは肺や骨に生じるため、腎臓に生じたがん以上に注意が必要です。
腹腔鏡手術による腎全摘出術の手術時間と入院期間
ダヴィンチを用いた腹腔鏡手術により腎臓の全摘出術を行なう場合の手術時間は、3時間~3時間半です。腫瘍が小さく、術者が技術と経験を積んでいる場合は、2時間以内で終わることも多々あります。
部分切除の場合は全摘出術のケースとは異なり、出血のリスクがあることから、必ず1週間入院していただいています。
安全に腎臓がんの手術を受けるために――病院選びのアドバイス
前の項目で、秋田大学では腹腔鏡下腎部分切除術のほとんどを手術支援ロボット・ダヴィンチを使い行っていると述べました。この理由は、医師の手で鉗子を操作する通常の腹腔鏡手術に比べ、ダヴィンチを用いたほうがより繊細な処置ができるからです。腎部分切除の場合は、がんをよりしっかりと取り除くことができます。また、縫合も精緻に行えるため、出血量など、患者さんの体にかかる負担も少なくなります。このような理由から、お住まいの地域にダヴィンチを導入している施設があれば、その病院を選ぶことをおすすめします。
腹腔鏡手術の技術認定医がいるか確認することも安心材料になる

ダヴィンチを使わない腹腔鏡手術は、術者の技術がある程度問われる手術方法です。その施設に1名以上、泌尿器腹腔鏡の技術認定者がいるかどうかを確認することも、安心材料の1つになるかもしれません。
認定要件はやや厳しく、一定の症例数を持っており技術を証明するビデオを提出した医師の中から、認定を受けられる医師は毎年5割ほどです。
現在日本には、約1,500人の泌尿器腹腔鏡技術認定医がいます。日本泌尿器科学会や日本泌尿器内視鏡学会のWEBサイトに名前を掲載している医師も多いため、病院選びに迷われたときには一度“ 「泌尿器腹腔鏡技術認定制度」審査による認定者一覧”という項目を確認してみるのもよいのではないかと考えます。
・日本泌尿器科学会 http://www.urol.or.jp/index.html
・日本泌尿器内視鏡学会 http://www.jsee.jp/
秋田大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学 教授、秋田大学医学部附属病院 前病院長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
羽渕 友則 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
頻尿治療について教えてください
一週間ほど頻繁に尿意と微熱があり 近くの泌尿器科で見てもらいました (前立腺肥大の持病はあります) そのときのデータ ・白血球50-99/HPE 赤血球5-9/HPF 細菌3+ 細胞質内封入対1-9/LPF ・左右腎臓には結石を認められるも 今回の症状とは関係なし ・膀胱の残尿量も多くはなし 結果 臓器に細侵入侵入している ということで ・レボフロキサシン500mg 1錠/夕食後 7日分 処方していただき服用して4日経過しましたが 微熱は収まりましたが尿意は当初の状態と変わりません (尿意は尿道出口でムズムズ痛かゆい感じ) 質問 ①このまま7日間抗生物質を飲み終えるまで我慢し 様子を見るしかないでしょうか?
一月ほど前から喉の違和感が続いています。
一ヶ月半ほど前から、右側耳の下辺りに違和感があり、ゲップをすると小骨が刺さった様な違和感があります。 耳鼻咽喉科を受診し、逆流症の疑いありとのことで薬を処方されていますが、痛みは治らず、三日ほど前から、右側舌の付け根が痛み始め、声のかすれや痰が絡む症状が出ています。 咽頭がんや舌癌が不安なので、精密検査を受けたいのですが、どの病院に行けば良いのでしょうか?
クレアチ二ンの数字の件
前立腺PSA検査と並行して、血液の他の項目の値でクレアチニン1.06、赤血球数590、Ht52.6、尿素窒素15.6、アミラ-ゼ65、Hb17.4などから脱水かなと言われました。今まで糖尿病外来の毎月の検査でも10年程、クレアチニンは高くても0.95程度でした。急に腎臓が悪くなったのかと心配です。夏程水分はとってなかったのですが、夜中にトイレの回数も減り、水分不足かなと思うところもあります。右の腎臓は萎縮してます。実際に一時的な脱水でこのようなクレアチニンの値になるのでしょうか、また1.06という数値はどの程度なのでしょうか。よろしくお願いします。
肺炎について今後の治療方針や転院について相談
現在89歳である父が肺炎と診断され、現在、近くの病院に3週間入院しています。現在の症状は 1. 熱が38度近くになったり、平熱になったりを繰り返している 2.本人は息苦しさを今も感じており、酸素吸入器をつけている。血中酸素飽和度は70代くらいの数値 3.医師からは、色々な薬を試しているが、なかなか適したのが見つからないとの事で、三日前にステロイド剤を使用したところ、副作用から本人は起き上がる事もできなくなり、ぐったりしてし始めた。トイレも自力で行けなくなり、体力も相当消耗している様子で 腎臓が悪くなり、病院からはステロイド剤を変えてみるとの事。 尚、何の種類の肺炎かについては、医師からの明確な説明は無く、少し前は誤嚥性肺炎の可能性もあると話しをしていたが、明確な肺炎の種類が分からないように見える。 4.食欲は今のところ有り、意識もしっかりしている。既存症は無い。 この病院がまだ色々な薬を試している一方で父の体力がどこまで持つのか心配しています。 今の病院の治療方針は正しいのか、他の病院に転院した方が良いのかアドバイスを頂けないでしょうか。 病院からは、今は安静にして動かさず、体力の温存に努めるべきとの説明を受けています。 よろしくお願いします。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「腎臓がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。